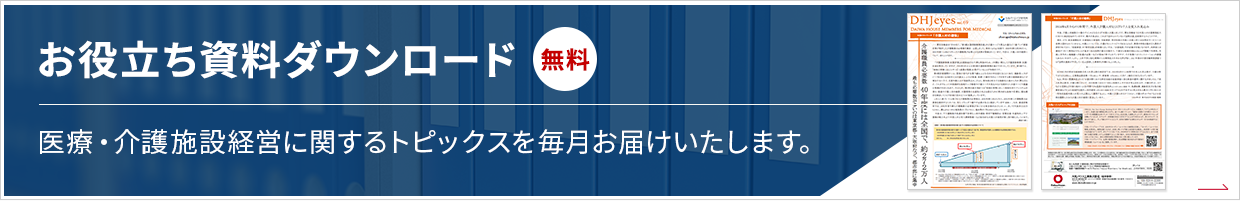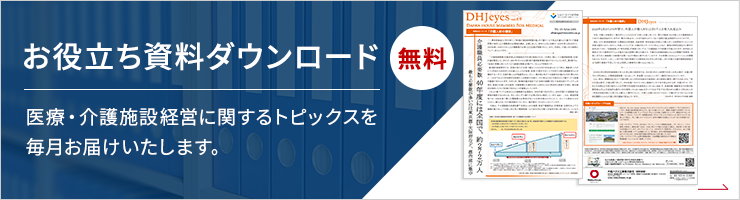業界最新ニュース
2025年09月29日
厚労省が具体案提示
人口20〜30万人に1カ所を目安に急性期拠点機能を確保
2040年頃を見据えた新たな地域医療構想で、厚生労働省は急性期拠点機能を担う医療機関を人口20〜30万人ごとに1カ所を目安に確保していくことを8月27日の「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」に提案した。
地域医療構想の構想区域はこれまで、医療計画と同じ二次医療圏単位での設定が原則とされてきた。だが、人口の減少によって今後、圏域内での医療の完結が困難になる二次医療圏は増加する。そのため厚労省は都道府県が新たな構想を策定する際に、現行の構想区域が40年やその先の医療提供体制を検討する区域として適切かどうかを点検し、必要に応じて広域化などを検討する案を提示した。
その際、人口の少ない地域(人口30万人まで)については、急性期拠点機能を1つ確保・維持できるかどうかという観点からの点検を求める考えを示した。こうした地域では大学病院本院が急性期拠点機能を担うことも考えられるが、当該大学病院が三次医療圏などを対象にした広域な診療を主に提供している場合は、「地域に1つ」というルールに縛られず、別に急性期拠点機能を確保することを容認する案も示した。
東京などの超大都市は医療資源の偏在などに留意しつつ、構想区域を複数設定
これに対して大都市型(人口100万人以上)と地方都市型(同50万人程度)の構想区域は、人口20~30万人ごとに1カ所を目安に急性期拠点機能を確保する。これらの地域類型とは別枠で整理するとしていた東京などの人口が極めて多い都市部は、構想区域を多くしすぎたことによる患者の流出や広くしすぎたことによる医療資源の偏在などが生じることのないよう留意しつつ、適切な単位で構想区域を複数設定すると整理した。
ところで急性期拠点機能を担う病院への医療の集約化にあたっては、集約化して区域内での提供体制を維持すべき医療と、診療体制を縮小して他の区域との連携を模索すべき医療を地域での協議を通じて選別していく必要がある。このため、例えば国が緊急手術の件数や全身麻酔手術件数などのデータを順次都道府県に提供し、構想区域の点検に早期から取り組めるよう支援する案も併せて示した。
2025年8月27日時点の情報に基づき作成