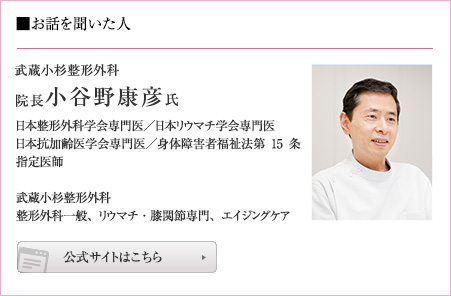- PREMIST Life TOP
- > きちんと向き合う、 私のカラダ
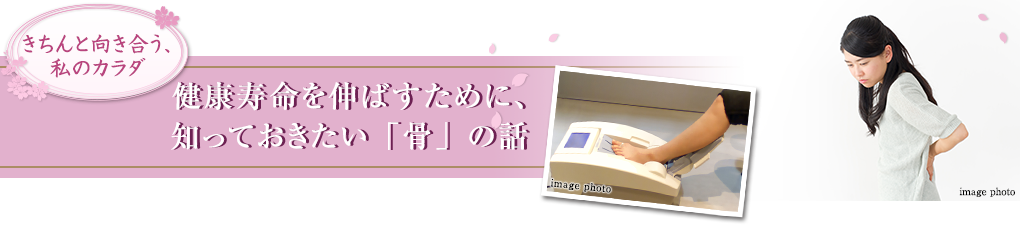
私たちのカラダを支えてくれる大切な骨。年齢を重ねても元気に暮らすためには、骨の健康が不可欠です。女性に圧倒的に多い「骨粗しょう症」、そして骨のために気をつけたい習慣について、専門家に伺いました。
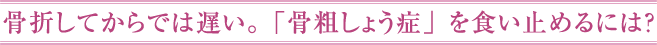
国民の10人に1人が「骨粗しょう症」
「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年」によると、日本国内の患者数は推定1280万人。国民の約10人に1人が骨粗しょう症といわれています。また、女性が980万人、男性が300万人と、女性患者が圧倒的に多いのも特徴。超高齢化社会のわが国において、女性の健康寿命に多大な影響を及ぼすと予測される骨粗しょう症は、社会的にも重要課題として位置づけられています。
骨は骨芽細胞による「骨形成」と、破骨細胞による「骨吸収」の2つの働きで新陳代謝をくり返しています。しかしこの2つのバランスが崩れると骨形成よりも骨吸収のスピードが増すことで、骨量がしだいに減少。さらに進行すると骨は中身がスカスカになり、もろく骨折しやすい状態になります。これが「骨粗しょう症」と呼ばれる病気の本体。痛みなどの自覚症状が全くないため、知らないうちに進行してしまうことが多いのが現状です。
日常の動作で簡単に骨折
骨粗しょう症が進行すると、ちょっと手をつく、体をねじるといったささいな日常動作で、信じられないほど簡単に骨折します。日常の診療においても、ゴミを捨てる動作をした、旅行先でスーツケースを持ち上げた、庭の植木鉢を移動したなど、驚くような理由で生じた腰痛や背中の痛みで来院される患者さんがたくさんいらっしゃいます。これらの方々の痛みの原因は、背骨が潰れる「圧迫骨折」。通常ですと軽い「ぎっくり腰」程度で、安静と治療により数日で元の生活に戻れるはずが、骨折ですから痛みが1か月以上続くことも稀ではありません。腰椎や胸椎(肋骨と繋がる背骨)の骨折が多く、背中や腰の痛み、背骨が曲がる、身長の低下などが見られます。骨粗しょう症の方はひとたび圧迫骨折を起こすと連続して骨折することも多く、長期にわたって苦痛を強いられることになります。また、中には痛みを全く伴わない「いつの間にか骨折」も。痛みはなくても背骨が曲がり見た目にも辛いばかりでなく、胸の圧迫により胸焼け(逆流性食道炎)や息切れ(心肺機能の低下)など様々な機能障害を招く可能性があることも忘れてはいけません。
「寝たきり」になる危険性も増える
骨折は直接的な苦痛だけでなく、間接的に要介護のリスクを高める危険性があります。若い方は2~3週間ほど安静が続いてもすぐに日常生活に復帰できますが、老年期に1週間ほど動かない状態が続くと、心身の様々な機能が衰弱します。よく取り上げられるロコモティブシンドローム(体を動かす運動器の部位が衰えること)もその1つ。一度の骨折から日常生活の自立度が低下し、寝たきりになってしまう方も少なくありません。
閉経後の女性はリスクが急増
骨粗しょう症の要因には、加齢、食習慣の乱れ(偏食、喫煙、飲酒)、運動不足、他の疾患(糖尿病、甲状腺機能亢進症、リウマチ、高カルシウム尿症、腎不全)など様々なものがありますが、何といっても「女性に起こる可能性が極めて高い」ということにつきます。その理由は女性ホルモンにあります。女性ホルモンのひとつであるエストロゲンには、骨形成を助け骨吸収を抑える働きがありますが、更年期・閉経を迎えるとエストロゲンの分泌量が急激に減少するため、骨の代謝バランスが崩れ、骨量が急激に低下していくのです。また、若年齢でも過激なダイエットやスポーツにより無月経や生理不順の状態が続くと、エストロゲンの分泌量が低下し、骨粗しょう症が進行することがあります。女性ホルモンの減少とともに、女性の骨量は必ず低下するもの。そう心得ておきましょう。
また、以下の方は骨粗しょう症による骨折を起こすリスクが高いので、より一層の注意が必要です。
・身長が2cm以上低下
・胃手術歴、乳がん、バセドウ病(甲状腺機能亢進症)
・早期閉経(45歳未満)
更年期になったら、定期的な骨密度検診を
こんなにも日常生活を脅かすことになる骨粗しょう症ですが、「診察してほしい」と外来を訪れる患者さんの数は極めて少ないのが現状。なぜなら骨粗しょう症自体には自覚症状がないため、近親者の骨折などで怖さに気づかない限り検査の必要性を実感しにくいのです。知らないうちに進行し骨折する前に骨粗しょう症の程度を知り、早めに進行を抑える対策をすることが大切です。
女性を対象にした骨密度検診は多くの自治体が実施しており、40~70歳まで5年毎に受診できるケースが一般的です。ただし、基本健診や特定健診のように通知が届くものではないため、自主的に居住地区の各自治体に確認して骨密度検診を受けましょう。閉経までは5年毎の検診でも大丈夫ですが、閉経後は一気にリスクが上がりますので、少なくとも年に1回は整形外科などの専門医院か、人間ドッグなどで検診することをおすすめします。
骨密度検査には、X線で各部位の骨密度を測定するDEXA(デキサ)法、かかとに超音波をあてて測定する超音波法などがありますが、DEXA法の方がより正確な結果が得られます。特に腰椎や大腿骨近位部の骨密度を測定できる全身型骨密度測定装置のある医療機関での検査をおすすめします。骨密度の結果から骨粗しょう症を評価するには、20~44歳の健康な成人の骨密度を100%として、現在の自分の骨密度が何%であるかを比較した数値YAM(若年成人平均値)を診ます。
骨量の減少を早めに発見できれば、薬の投与で骨粗しょう症の進行と骨折のリスクを防ぐことができます。人生を最後まで健康に生きる、すなわち健康寿命を伸ばすためにも、時期を逃さずに骨と向き合い、しっかりとチェックしていきましょう。
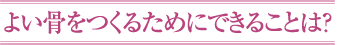
骨の質を保つためには、生涯を通してバランスのよい食事と適度な運動が必要。毎日コツコツ取り組むことが大切です。
1日3食、バランスを考えた食事を
骨をつくるためには、カルシウムだけでなく様々な栄養素が必要です。1日3回、規則正しく偏りのない食事を摂り、栄養素が不足しないように心がけましょう。
骨の形成には、以下のような栄養素が必要です。
●カルシウム/骨の主成分となります
◎乳製品:牛乳、チーズ、ヨーグルト、スキムミルクなど 野菜・海藻類・種実類:小松菜、わかめ、いりごまなど ◎大豆製品:とうふ、納豆など ◎魚介類:いわし、ししゃもなど
●マグネシウム/骨の形成に必要です。
◎海藻類:あおさ、わかめ、こんぶなど ◎種実類:ごま、アーモンドなど
●リン/骨の形成に必要です
◎魚介類:いわし、さくらえび、しらすなど ◎穀類:米ぬか、小麦胚芽など
●ビタミンD/カルシウムの吸収を促進して、骨を丈夫にします
◎魚介類:いわし、さんま、さけなど ◎きのこ類:干ししいたけ、きくらげなど
●ビタミンK/カルシウムを骨にとりこみ、骨を強くします
◎野菜類:小松菜、ほうれん草、ブロッコリーなど ◎その他:納豆、鶏もも肉、ワカメ など
ただし、リンは摂り過ぎると逆に骨形成を阻害します。リンが多く含まれるインスタント食品やスナック菓子、炭酸飲料の摂り過ぎには気をつけましょう。塩分も摂り過ぎは骨によくありません。また、喫煙や過度のアルコール摂取も避けましょう。
骨を刺激する、日常的な運動を
骨に歩行やジョギングなどによる力学的負荷が加わると骨芽細胞が活性化して骨形成が亢進されますが、長期間の寝たきりや宇宙空間(無重力)での滞在は十分な力学的負荷が骨にかからなくなることで骨吸収が亢進する一方、骨形成が抑制され、骨粗しょう症が進行します。骨を維持するために、ウォーキングやジョギングなど力学的負荷がかかる運動を日常的に行いましょう。また、スクワットや軽いダンベルをつかった筋力トレーニングも効果があります。適度な運動は、体力、筋力、心肺機能を高め、骨折の原因となる転倒を防ぐこともできますので、ぜひ続けてください。
※運動前には骨密度測定を。また、腰痛などの不安がある場合は専門医にご相談ください。
成長期の子どもには、骨を増やす食・生活習慣を
骨量がもっとも増えるのは、女性が11~15歳、男性は13~17歳。そして、女性は18歳頃、男性は18~20歳頃に骨量が最大になります。この時期に骨量を増やす「貯金」をしておくと、将来、骨量が減っても骨粗しょう症にならない確率が高くなります。
成長期のお子さんがいらっしゃる場合は、
・骨をつくる栄養素を充分に摂る
・運動などでしっかり体を動かす
・外に出て日光を浴びる(ビタミンDの合成を促す)
・充分な睡眠をとる(成長ホルモンの分泌を促す)
といった生活を促し、骨量を増やしてあげるようにしましょう。