

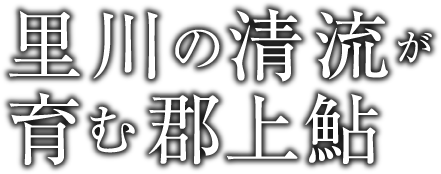
全国清流めぐり利き鮎大会でグランプリもとったブランド「郡上鮎」。木箱で出荷される。
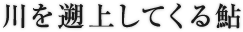
6月5日、郡上八幡は鮎漁の解禁日を迎えた。それを待ちわびていた県内外の釣り師たちは長良川やその支流に繰り出し、長さ9メートル前後にも及ぶ郡上竿を垂らす。おとり鮎を使い、縄張り意識の強い鮎の特性をいかして釣る友釣りという漁法だ。郡上市は、釣り師の中でも特に人気の高いメッカ。鮎で職漁師が成り立つほど、多くの鮎が川を遡上する。「この辺りでは5月中旬くらいになると、鮎が黒い帯になってさーっとのぼってくる。今年もたんと来てくれたなあと橋の上から見ています」と話すのは、郡上漁業協同組合の村瀬和典さん。
鮎は年魚だ。海で産卵するために河川を下るウナギなどの降下魚や、産卵のために海から溯上するサケやマス類などの溯上魚とは違う両側洄游魚(りょうそくかいゆうぎょ)と呼ばれる。10月から11月にかけて長良川の忠節橋付近で産卵し、産まれた仔魚は川の流れにのって伊勢湾まで降り、冬の間は海中のプランクトンを食べ、3月頃から成長のために河川へ溯上する。母川回帰するサケやマス類とは違い、生まれた河川に必ず戻ってくるわけではない。
郡上市内の長良川水系で漁獲された鮎は「郡上鮎」と呼ばれ、今や日本を代表するブランド鮎。河川産淡水魚で唯一の地域団体ブランド商標登録されている。
郡上市には、いくつか鮎の出荷所がある。郡上漁業協同組合もその一つで、料亭や岐阜市の中央市場に出荷する。岐阜市の中央市場は、全国で唯一鮎専門の競り台があるという。午後3時に持ち込まれた鮎を氷や電気でしめて、翌日の午前5時に始まる競りに間に合わせる。

吉田川で鮎釣りをする様子。携帯するタモに鮎をさっと入れる時にもふわんとスイカの香りが漂う。
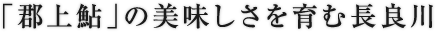
「郡上鮎」には3つの味わい方がある。解禁直後の若鮎の時は、スイカのような匂いが香り、身が柔らかくて少し水っぽさのある味。梅雨があけた夏の季節は、脂がのった芳醇な匂いと美味しさ。そしてお腹に卵をもった落ち鮎の時は、色は少し悪くなるがさくっとした香ばしい味。鮎はお腹に内臓が入った状態で頭から丸ごと食べるのが醍醐味だ。内臓のほろ苦さが食した時のアクセントになる。
鮎は釣り師が石垢と呼ぶ川の石についた藻を食べる。藻そのものに臭みや汚れがないため鮎の内臓が食べられるのだ。それはつまり、川の水質がよいということでもある。さらに村瀬さんは「長良川は流れの急な瀬があって、休むことができる淵があっての繰り返し。よい川層があるおかげで、身の締まりがよいのだと思う」と言う。
郡上市には長良川や吉田川、亀尾島(きびしま)川など一級河川が24本もある。中でも長良川は高鷲(たかす)町の大日ヶ岳を源流として、柿田川、四万十川と並ぶ日本三大清流の一つとして名を馳せてきた。大日ヶ岳は8世紀に泰澄禅師によって開かれ、古くから信仰されてきた山だ。郡上市をはじめとした長良川流域には多くの人が暮らしているが、里川でありながら清流として美しい水資源を保つ。それを評価され、2015年に世界農業遺産「清流長良川の鮎」として認定された。「鮎を中心として、よい水環境、人の生活、漁業資源が相互に関連しているシステムがあります。そのシンボルが長良川の鮎なんです」と村瀬さんが言うように、長良川と鮎が織りなす自然の循環サイクルは地域の経済や文化と密接に関わってきた。

「だるまや」の出荷所で見せてもらった「郡上鮎」。色が美しいのも鮎ならではの魅力だ。
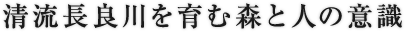
水は山から染み出す。よい水が流れる川をつくるためにはよい山をつくることが必要だ。郡上市は約9割が森林だ。しかし戦後の政策でもともと自然にはなかった杉林が増えた。手入れされなくなった針葉樹林は草も生えず腐葉土もない。そのため昔に比べると山の保水力が弱まり、水に溶けこむミネラル分も減ってしまったという。そこで郡上漁業協同組合では、少しでも水源をよくしようと年に一度、高鷲町など長良川源流近い山奥で、トチ、ナラ、ナナカマド、ヤマグリ、ヤマザクラなど地域の植生にあった広葉樹を植樹している。
郡上市の子ども達にとって、川はとても身近だ。川に飛び込み、川で泳ぎ、川に棲む生き物と遊ぶ。新橋では13メートル下への吉田川への飛び込みが小学生の通過儀礼になっている。それが普通なのだと村瀬さんは子どもの頃の話をしてくれた。それができるのも「地域住民に、川を大事にしよう、汚さないようにしようという意識があるからだと思います」と村瀬さんが言う通りなのだろう。町中で見られる水舟の清掃や管理は、自主的に地域住民の手で行われる。他にも目に見えない水に関してはさまざまな目に見えないルールが培われてきた。
郡上八幡は、透明度の高い湧水と郡上鮎を育む豊かな清流が暮らしの中に息づく。「天然の力はすごい。この辺りの地点で河口から約100キロ。それを小さな鮎がのぼってくるんですよ」という村瀬さんの言葉がとても印象的だった。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.