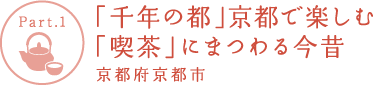




京都のシンボル、京都タワー。JR京都駅に訪れた人がまず目にする光景

石畳と黒塀・黒壁の細い道…まるでタイムスリップしたかのような気分になれる祇園の街並み

川沿いに料亭が立ち並ぶ祇園白川。数々のドラマのロケ地としても有名な場所だ
京都は西暦794年の桓武天皇の遷都より、
1000年以上にわたって都でありつづけた場所。
これまでの日本の歴史において、
ここまで長い間首都であった都市は
世界的にも珍しい場所だという。
今や日本を代表する観光地であり、
多くの人が世界中から
足を運ぶ場所となった京都。
いくつかは世界遺産にも
登録されている多くの寺社仏閣、
伝統を守り続ける工芸品や料理、
古き良き"遊び"の文化を
未だ残す祇園などの花街、
昔ながらの建物を大切に残し、
かつ人々の"生活"の息吹が
鮮やかに見えてくる
街並みの風景……。
多くの人が惹かれる京都の"魅力"は、
全て1000年の時間が培ったもの。

抹茶、煎茶、ほうじ茶などの番茶、玉露…日本茶の栽培が盛んになることで、日本茶の種類もさまざまなに細分化してゆく

16世紀後半、宇治で「覆い下栽培」と呼ばれる栽培法が開発され、鮮やかで濃緑色のあるうまみの強い茶が生まれた。これが抹茶を生み、「茶の湯」文化を花開かせることとなる

高級品として知られる「玉露」が生まれたのも江戸時代後期の宇治からという
そんな京都の生活において、
欠かせないのが「お茶」……
つまり、日本茶。
日常的に飲むものから
"おもてなし用"のものまで
その用途は幅広く、
気軽に飲むものもあれば、
「茶道」という芸道に
使用されるのもまた日本茶だ。
その歴史は古く、
もともとは奈良・平安時代に、
遣唐使や留学僧によって
もたらされたものだと言われている。
しかしこの頃の茶は
国外から持ち帰った希少なものであり、
特権階級だけが楽しめるものであった。
やがて、12〜13世紀に中国より
種子を持ち帰った僧が
佐賀県で栽培を開始。
その後、京都の僧が種子を譲り受け、
京都・栂尾の高山寺に茶を植え、茶園を開く。
その後、宇治地方を中心に栽培が広がり、
ここで「宇治茶」の基礎ができたことで、
やがて日本茶は全国に
広まっていったという。
つまり京都は、
「日本茶発祥の礎」となった土地なのだ。
今や京都といえば
「抹茶」をイメージする人も
多いのではないだろうか。
京都・宇治地方はまた、日照時間や
土壌、
気温や降水量などの条件が
お茶の生育に適した土地でもあった。
京都周辺が今なお、
日本を代表する茶葉の産地であるのは
歴史的な背景と気象条件、
その両方が重なった結果と言えるだろう。

趣を感じさせる店内。現在の店舗は幕末の時代、1864年の「禁門の変」で以前の店舗が焼けてしまったため再建されたものとのこと

店内には茶葉を入れておく茶櫃(ちゃびつ)がズラリ。古くから使われてきたものを使い続けている様子に、老舗の風格が感じられる

日常的に飲めるお手頃価格のものから贈答用まで、商品は幅広いラインナップ

抹茶といえば「茶道」が思い浮かぶ人も多いかもしれないが、日常的に家庭で点てて楽しむのもおすすめ

長い歴史を持つだけに、
数多くの茶舗が店を構える京都。
一保堂茶舗は創業1717年、
およそ300年もの歴史を持つ
老舗茶舗の一つだ。
農産物であるお茶は、
産地や製法によってその味は千差万別。
木津川、宇治川両水系の気候で栽培され、
穏やかな香りと上品な甘み、
まろやかな味わいが特徴の一保堂の京銘茶は、
京都に暮らす多くの人々に愛されている。
しかし、農作物であるがゆえに当然、
同じ産地であっても
その年の気候によって
茶葉の風味も変わってしまう。
しかし、お客様には毎年同じ味筋の
お茶をお届けする、
それが専門店の役目。
そのため、あえて特定の
契約農家を持たず、
1年を通じて味が変わらぬよう
ブレンドを行う。
「合組(ごうぐみ)」と呼ばれる
このブレンドの妙技は、
長い経験を培ってこそ身につくもの。
1年に何度も収穫できるものではない
日本茶の世界で
このクオリティを
保つことができるのは、
老舗茶舗の伝統ならではといえるだろう。

売り場に併設されたスペースでは、一保堂が販売する茶葉が試飲できる

日本茶の種類や味わいの違いなどを、わかりやすく具体的に知ることができる。海外観光客の方の利用も多いとか

一保堂茶舗の京都本店には、店舗の横に試飲もできるスペースが併設されている。
茶葉の味わいはやはり、
実際に淹れてみないとわからないもの。
また、海外観光客など日本茶自体に
馴染みがない人も来店するため、
日本茶の種類や
味わいを知ってもらったり、
淹れ方などを簡単に
レクチャーすることができる
場所ともなっている。
実際のところ、若い世代を中心に
「日本茶離れ」が進んでいる現在。
「茶葉を急須で淹れて飲む」という経験を
したことがない人も増えている中で、
「日本茶の魅力を
多くの人に知ってもらう」ために
手がけているさまざまな取組の一つだ。

気に入ったお茶をお買い上げ。取材時は年末、贈答用・年始用のお茶を買い求めるお客がひっきりなしに訪れていた

一保堂の代表的な銘柄「嘉木」は、煎茶ならではの甘みと渋みのバランスを楽しむお茶。しっかりとした甘み、はなやかな香りとじんわり広がるうまみを楽しむことができる。小缶108g3240円

可愛いイラストが付いたテイクアウト用カップで、店頭で淹れてもらったお茶をテイクアウトできる。煎茶、玉露など4種411円〜
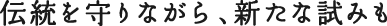
淹れるときの温度、使用する茶器、
抽出する時間……
日本茶はこれらによって、
その味わいが変わってしまう
非常に繊細なもの。
だからこそ一保堂のお茶は、
「販売しているときはまだ、
製品として半分しか完成していないもの。
お客様の手で淹れられて初めて、
製品として完成する」という
考え方だという。
抽出時間長めで
しっかり目に淹れた味が
好みの人もいれば、
あえて高い温度で出した
お茶が好みの人もいる。
そんな自由度の高さも、
日本茶の面白さの一つ。
そんな一保堂にとって、
「テイクアウトのお茶」の提供は
新たなトライだったという。
お客様に淹れ方を委ねるのではなく、
店舗で"淹れたものを提供する"、
という形になるからだ。
しかしそれも、日本茶の美味しさを
より手軽に、多くの人に
体験して欲しいという想いからこそ。
動物たちがお茶を淹れる
可愛いイラストには、茶舗ならではの
想いが込められている。
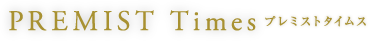
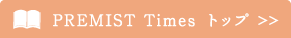
![[Part.1]老舗茶舗で知る、古都が育んだ日本茶の味わい](images/side_part1_ov.gif)
![[Part.2]京都で根付いた「喫茶」文化](images/side_part2.gif)
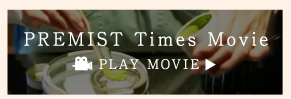
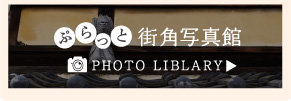




![一保堂茶舗 京都本店[いっぽどうちゃほ きょうとほんてん]](images/part1/02_tenpo_pc.png)
![[Part.2]京都で根付いた「喫茶」文化](images/part1/btn_next.png)
![[Part.2]京都で根付いた「喫茶」文化](images/part1/btn_next_sp.png)
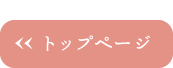

![[Part.1]老舗茶舗で知る、古都が育んだ日本茶の味わい](images/p_ftr_part1.jpg)
![[Part.1]老舗茶舗で知る、古都が育んだ日本茶の味わい](images/index/btn_part1_sp.png)
![[Part.2]京都で根付いた「喫茶」文化](images/p_ftr_part2.jpg)
![[Part.2]京都で根付いた「喫茶」文化](images/index/btn_part2_sp.png)




