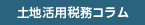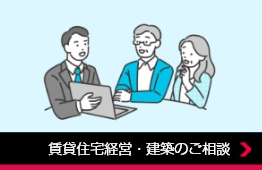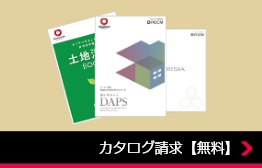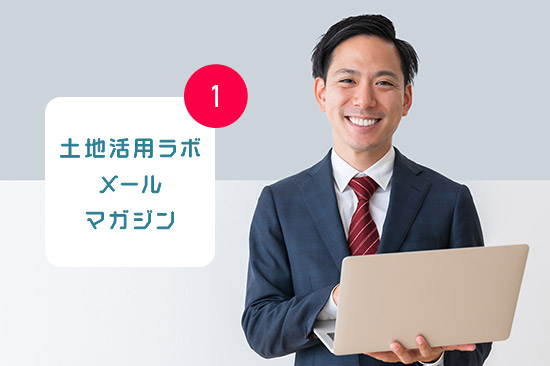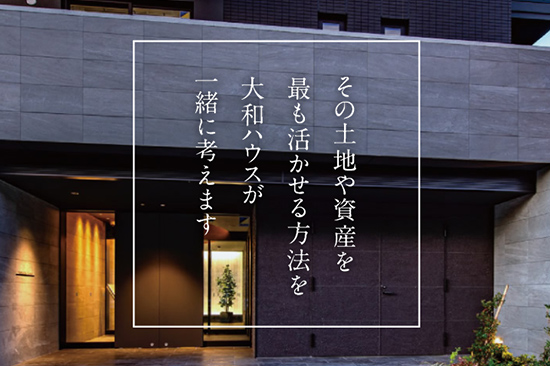コラム vol.531
コラム vol.531郊外賃貸住宅の都心部への買換えによる相続対策と注意点
公開日:2024/12/26
都心部の地価は上昇している一方で、地方ではいまだに地価が下落しているところも多いようです。
そこで最近注目されているのが、郊外の所有賃貸住宅から都心の優良賃貸住宅への買換えです。
所有している不動産(賃貸住宅)の収益性が下がってしまうと、将来への不安から、持ち続けるべきかどうかを検討する人も多いでしょう。そこで、検討したいのが、「不動産資産の組み換え」という手法です。「不動産資産の組み換え」によって、不動産の収益性を改善するだけではなく、相続対策としても活用するケースもあるようです。
ひと言で「不動産資産の組み換え」と言っても、さまざまなケースがあり、目的によって採るべき方法は異なりますが、保有資産の将来的な価値を上げたり、やがて訪れる相続対策として、戦略的に不動産資産組み換えを検討することも必要ではないでしょうか。
上昇基調の地価、東京都区部の人口増加
令和6年版土地白書によれば、地価公示は、全国全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇し、上昇率が拡大しています。特に、三大都市圏や地方4市(札幌、仙台、広島、福岡)では上昇率が拡大しており、地方圏でも上昇率が拡大傾向となっています。
図1:全国の地価動向
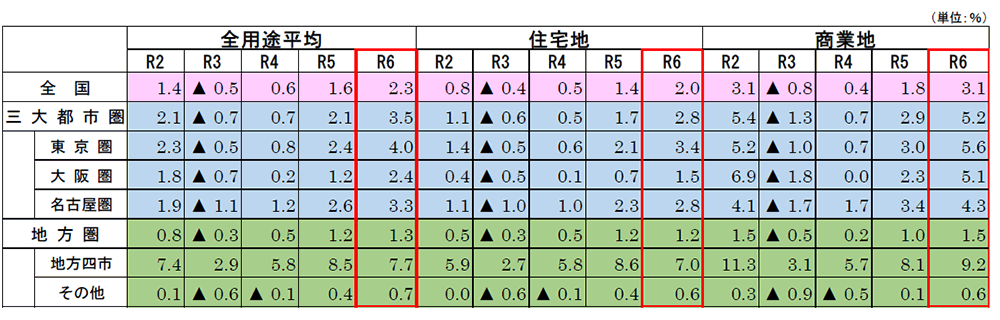
出典:国土交通省「地価公示」
また、東京都区部の人口は1997年に増加に転じてからは、2020年まで増加を続けてきました。2021年からは、新型コロナウイルス感染症拡大によって、テレワークやリモートワークが普及し、郊外への人口流出が起こりましたが、2022年には再び増加に転じ、令和6年10月1日現在の東京都の人口は、推計で14,192,184人となりました。都心回帰と呼ばれる現象となっています。
人口の都心回帰によって、まず考えられるのは、都心部の人口増加による住宅需要の拡大でしょう。今後もさらに都心の人口増加が続くとなれば、不動産価格がさらに上昇することも考えられます。一方、郊外や地方においては、転出増加による人口減少という問題が起こってきます。
郊外の不動産を譲渡して都心の収益物件を取得
郊外に所有している収益性の悪い不動産を売却し、都心の物件に買い換えることも相続対策につながる場合があります。収益性が良くなり相続対策にもなりますから、買い換えるのに必要なコストの負担がどの程度かが問題となります。
次ページの例で検討します。郊外の青空駐車場を所有していますが、満車状態ではないため年間駐車場収入が500万円、この土地にかかる固定資産税が200万円で差引手取り額が300万円です。この土地は2億円で売ることができますので、時価で見た時の実質利回りは1.5%です。これを売却して、都心の中古ワンルームマンションの建物1億円、土地1億円の合計2億円のものに買い換えたとします。年間収入1,500万円、建物にかかる固定資産税100万円、土地にかかる固定資産税125万円、諸経費90万円、差引手取り額1,185万円で、利回り5.9%です。実際の例ですが、なかなかこのような物件を探すことは難しいのが現実です。
図2:郊外賃貸物件の都心部への買換え
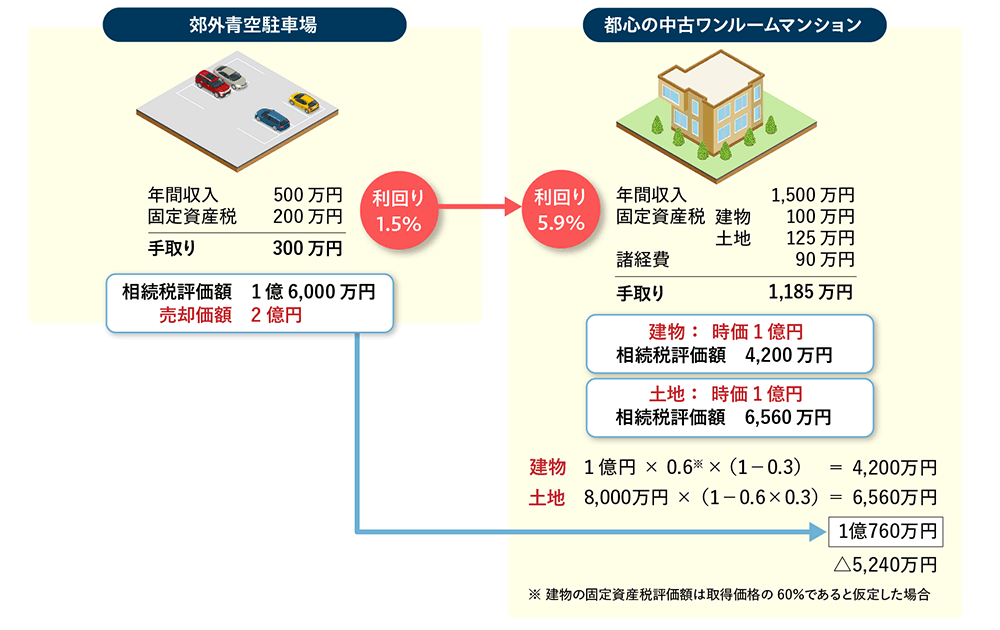
相続対策の効果
郊外の青空駐車場の相続税評価額は時価の80%として1億6,000万円です。買い換えた場合の中古ワンルームマンションの評価額は合計1億760万円ですから、評価額は5,240万円下がりました。このように、中古の賃貸住宅を取得した場合には相続税評価額が結果的に下がることも多く見受けられます。
買換えにかかるコスト
買換えには、譲渡にかかる譲渡所得税・住民税、仲介手数料、購入物件にかかる仲介手数料、登記費用、登録免許税などのコストがかかります。譲渡して手にした2億円全額を物件取得資金に充当できません。特に大きいのが譲渡所得税・住民税です。郊外賃貸物件が先祖からの相続財産だとすると、取得費は譲渡収入の5%の1,000万円です。仲介手数料等の諸費用が5%で1,000万円あったとしても、2億円からこれらを差し引いた1億8,000万円に20%(復興特別所得税を除く、以下同じ)の税率を乗じた3,600万円を所得税・住民税として納付しなければなりません。
事業用資産の買換え特例
その年1月1日現在、所有期間10年超の農地や貸地、賃貸住宅用地、駐車場などの事業用不動産を、例えば、2億円で売却して、別の事業用物件を取得し、事業用資産の買換え特例を適用した場合には、次の算式のように本来の譲渡所得金額の20%(一定の地域への買換えは10%、25%、30%又は40%)相当額が譲渡所得の金額とされます。
図3
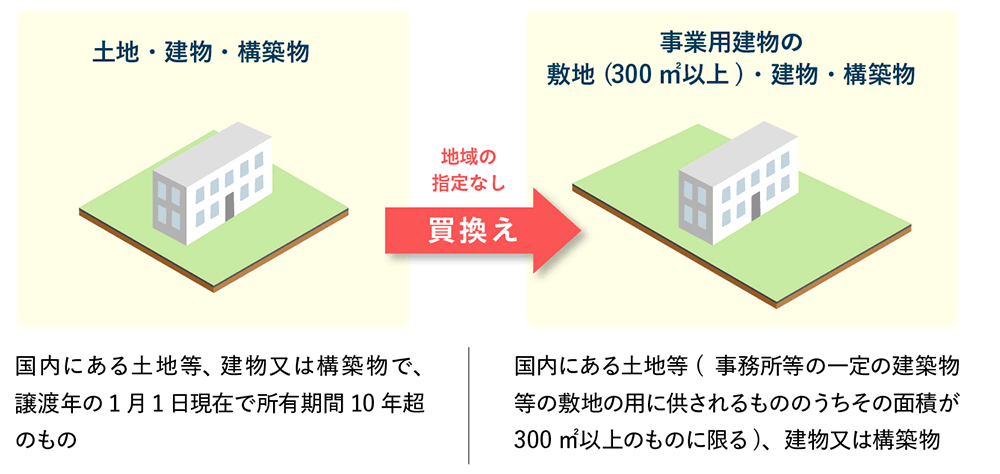
買換え特例適用の譲渡所得の計算式一例
①「譲渡資産の譲渡価額≦買換資産の取得価額」(同額又は増額買換え)の場合
図4
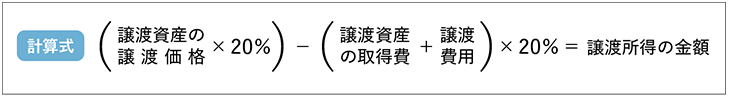
②「譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額」(低額買換え)の場合
図5
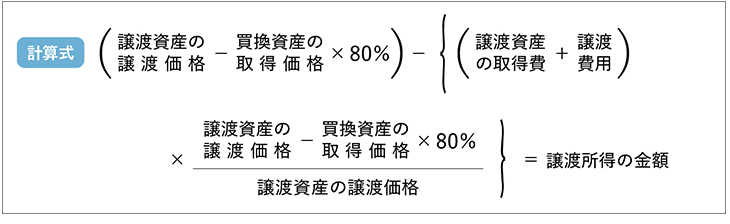
本来払うべき税金の20%の税金でよい
「買換えにかかるコスト」が「東京23区を除く首都圏既成市街地、首都圏近郊整備地帯、近畿圏既成都市区域、名古屋市の一部」の区域内での買換えですと、2億円の20%の4,000万円が課税対象の収入金額となり、取得費及び譲渡費用等の合計2,000万円の20%の400万円を控除した3,600万円の20%が譲渡所得税・住民税となり、720万円ですむことになります。この特例の適用を受けなければ3,600万円ですから、差引き2,880万円の税務対策になります。
図6
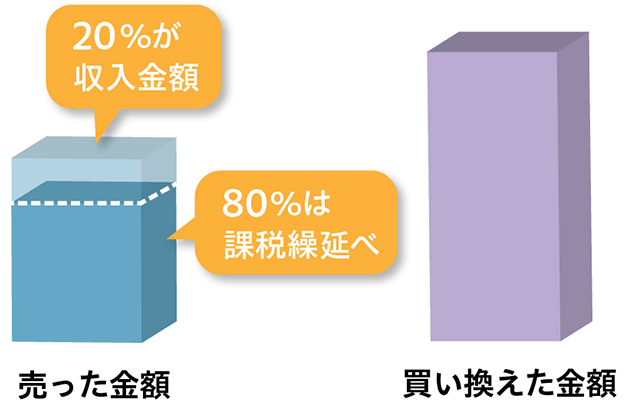
図7
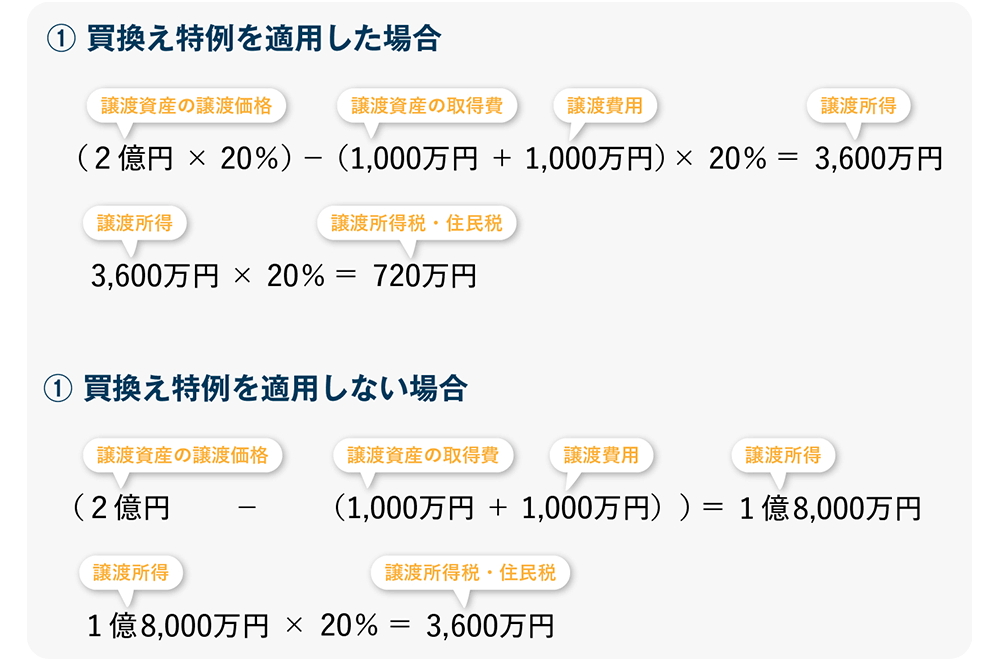
買換え特例の適用期限など
特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例制度(法人は「特定資産の買換えの場合等の課税の特例」)は国内にある長期保有の土地等、建物又は構築物である事業用資産を譲渡し、国内にある土地等、建物、構築物である一定の事業用資産に買い換えた場合に適用があります。適用期限は令和8年3月31日までの譲渡とされています。なお、課税繰延べの割合が次のとおり、地域によって異なりますのでご注意ください。
令和6年4月1日以後の譲渡又は先行取得から、これらのあった日の属する三月期間の末日の翌日から2か月以内に所轄税務署長に対して届出書を提出しなければ適用できなくなっていますので注意してください。
「三月期間」とは個人の場合、1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月までのそれぞれの期間をいいます。法人の場合は事業年度開始の日から3か月ごとの期間をいいます。
表:事業用資産の3号買換えの課税繰延べ割合等
| 譲渡資産の地域 | 買換資産の地域 | 課税繰延べ割合 |
|---|---|---|
| 地域再生法の集中地域以外の地域の本店又は主たる事務所の所在地 | 東京23区への本店又は主たる事務所の所在地 | 60% |
| 地域再生法の集中地域以外の地域 | 東京23区 | 70% |
| 東京23区を除く地域再生法の集中地域 | 75% | |
| 東京23区の本店又は主たる事務所の所在地 | 地域再生法の集中地域以外の地域の本店又は主たる事務所の所在地 | 90% |
| 上記を除くすべて | 80% | |
(注)地域再生法の集中地域とは、東京23区及び首都圏既成市街地、首都圏近郊整備地帯、近畿圏既成都市区域、名古屋市の一部を除く地域をいいます。
譲渡資産の範囲:譲渡の日の属する年の1月1日において、所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等、建物、構築物
買換資産の範囲:国内にある土地等(特定施設の敷地の用に供される300㎡以上のもの)、建物、構築物
買換資産の適用対象
事業用資産の買換え特例は、「事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもの」以外の土地等への買換えには適用されません。また、分譲マンションの一室や戸建て分譲住宅を取得して賃貸する場合、1棟売り投資物件などを取得する場合の建物や構築物については適用できますが、敷地が300m2未満の場合の土地等については適用できません。したがって、敷地面積300m2以上の賃貸物件であれば土地部分も含めて事業用資産の買換え特例の対象となります。駐車場の用に供されるものは原則不可ですが、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて、やむを得ない事情※があるものに限って適用できます。
※やむを得ない事情とは、次の手続その他の行為が進行中であることについて、一定の書類により明らかにされた事情をいいます。
- ①開発許可手続
- ②建築確認手統
- ③文化財保護法の発掘調査
- ④建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続
注意点
事業用資産の買換え特例は、譲渡所得税・住民税の課税の繰延べです。譲渡して取得した買換資産の取得価額は、譲渡資産の取得価額を基礎として計算することとされています。土地のように減価償却資産でなければ、将来の譲渡時まで課税が繰り延べられますが、賃貸建物や構築物などのような減価償却資産に買い換えると、その償却費の計算のもととなる金額は実際の取得金額より大幅に少なくなってしまいます。
個人の場合には超過累進税率が適用されますので、高額所得者の場合は譲渡にかかる所得税・住民税の合計税率20%を適用するほうが長期的にみると有利になることもあります。このような点も考慮して建物については適用するかどうかを考える必要があります。
資産の組み換えはむやみに行えばよいわけではありません。不動産投資という観点から見れば、資産の組み換えを行うための理由は大きく分けて、収益性の向上とリスク分散の二つです。
保有している空き地や遊休地は、何も活用しなければ、収入を生み出すことはありません。むしろ税金などのコストが発生します。保有している空き地や遊休地が、不動産賃貸需要が少ないと判断できるのであれば、それらの不動産を売却して、不動産賃貸需要が高い地域の不動産に資産の組み換えを行うことで、収益性を高めることにつながるわけです。
この収益性という目的に加えてもうひとつの理由は、リスクの分散です。仮に資産が1カ所に集まっていると、何か大きな要因が起きた場合に、資産価値の維持という点でリスクが高くなってしまいます。1カ所ではなく分散して保有することで、リスクも分散することにつながります。
また、資産が分散していることで、相続が発生した場合でも、遺産の分割がしやすくなるというメリットもあります。