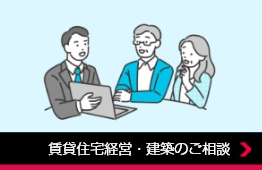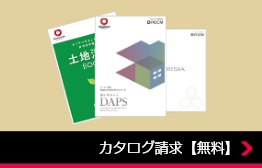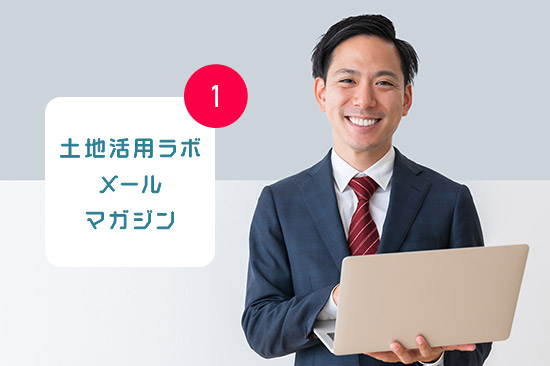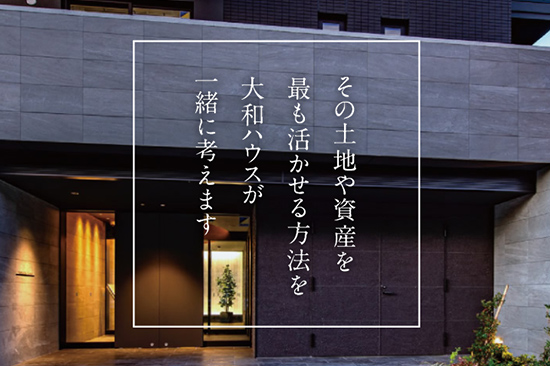コラム vol.543
コラム vol.543個人事業の賃貸住宅経営者は、事業承継制度を活用できるか?
公開日:2025/04/10
相続発生後も後継者が以前と変わらない状態で不動産賃貸業を継続するには、事業としての継承として、事前に対策をとっておく必要があります。不動産賃貸業とは事業であり、賃貸住宅を相続するということは、事業承継を行うことでもあります。
2019年度の税制改正で、個人版事業承継税制が創設されました。この制度は、2018年度税制改正で創設された法人版事業承継税制(特例措置)に準じた内容となっており、個人事業主の事業承継も行いやすくなりました。個人事業主が事業承継時に、大きな手間がかからないように、また、自由に事業が行えるように制度がつくられました。
個人版事業承継税制とは、個人事業の後継者が、贈与又は相続等により取得した特例受贈事業用資産または特例事業用資産にかかわる贈与税・相続税の納税を猶予し、後継者がさらに次世代の後継者にその特例事業用資産等を承継した場合等に、その猶予された税額が免除される制度です。後継者の死亡や事業を継続できないやむを得ない事由が生じた際等には、猶予されている贈与税や相続税の納付は免除されます。
法人版事業承継税制に比べて手続きは簡素になっており、法人版事業承継税制のような従業員要件もありませんが、この制度の適用を受けるためには、「その事業に係る特例事業用資産等のすべてを贈与または相続により取得していること」「青色申告を行い、帳簿書類を備え付け一切の取引を詳細に記録していたこと」等の要件を満たしている必要があります。また、2026年(令和8年)3月31日までに「個人事業承継計画」(「先代事業者が後継者に事業承継するまでの期間における経営の計画」や「後継者が事業承継をした後の経営計画」)を都道府県庁に提出し、2028年(令和10年)12月末までに特例事業用資産等の承継を行う必要があります。
制度を受けることができる要件
他にも、個人版事業承継税制の適用を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
表
| 後継者の要件 |
|
|---|---|
| 事業用資産の要件 | 先代事業者(贈与者・被相続人)の事業の用に供されていた次の資産で、贈与又は相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。
|
参考:「国税庁 個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし」
個人事業で不動産賃貸経営を行っている場合は?
租税特別措置法「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」によれば、特定事業用資産とは、贈与者の事業は「不動産貸付業その他政令で定めるものを除く」事業の用に供されている資産とされており、受贈者の条件としては「特定事業用資産に係る事業が資産管理事業(※)」に該当しないことが条件となるため、原則として、この制度の対象となる事業からは不動産貸付事業等は除かれます。
※「資産管理事業」とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定の資産の保有割合が特定事業用資産の事業に係る総資産の総額の70%以上となる事業(資産保有型事業)やこれらの特定の資産からの運用収入が特定事業用資産に係る事業の総収入金額の75%以上となる事業(資産運用型事業)をいいます。
しかし、複数の事業を行っている場合、「資産管理事業」以外の事業に関しては、条件を満たせば、適用が認められることになりますので、詳しい内容については、税理士に相談してください。
個人版事業承継税制を活用する際の注意点
個人版事業承継税制の適用にあたっては、次の点に注意する必要があります。
すべての特例事業用資産等を一括して贈与する必要がある
先代事業者は、本税制の対象となる資産を一括して贈与する必要があります。例えば、土地は先代事業者が保有したままにし、建物や設備だけを贈与することは認められていません。
相続時には、一定の要件のもと納税猶予制度を受けることができる
贈与税の納税猶予制度の適用を受けたあと、その贈与者が亡くなった場合、その贈与された特例事業用資産等は相続税の課税対象となりますが、相続発生時において一定の要件を満たしていれば、引き続き相続税の納税猶予制度を受けることができます。
登録免許税・不動産取得税が発生する
土地や建物を後継者に贈与した場合、登録免許税や不動産取得税も課税されます。
小規模宅地等の特例とは選択適用となる
個人版事業承継税制と小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)とは選択適用となっており、どちららかを選択することになります。小規模宅地等の特例を選択した場合には、後継者以外の相続人の相続対策にもなりますので、後継者のみならず、他の相続人も含めてメリット・デメリットを正確に理解し、他の相続手法と比較検討したうえで判断するようにしてください。また、検討する際は、必ず税理士に相談しながら進めてください。