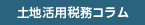コラム vol.555
コラム vol.555不動産オーナーの相続対策暦年課税と相続時精算課税制度を比較する
公開日:2025/06/30
相続税と贈与税
適切な額を繰返し贈与する、評価を下げて贈与するなどを実施すれば、贈与はシンプルで有効な相続税対策といえます。ただし、贈与税の累進税率は相続税の累進税率よりはるかに高く、また、贈与税の基礎控除額(年間110万円)は、相続税の遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)とは比較にならないほど小さな金額になっています。
家族に財産を生前に贈与して贈与税を納めるか、または相続が発生してから相続税を納めるか、どちらのほうが税金の負担が軽くて済むかはケースによって異なります。例えば、一時に全財産を移転する場合は、実効税率の低い相続税の方が有利といえるでしょう。しかし、贈与は贈与者が選んだ時に、選んだ人に自由にできますから、相続税の実効税率よりも低い税率の範囲内で贈与するならば、贈与のほうが税法上有利といえるでしょう。
注目したいことは、贈与税には年間110万円の基礎控除額があることです。この基礎控除額を利用して生前贈与を行うことは、相続税対策として効果のある方法でしょう。相続財産を減少させることができる上、年間110万円以下の贈与額ならば贈与税はゼロだからです。しかし、あまり少額な贈与では相続財産を減少させる効果はほとんどありませんし、高額すぎる贈与は、相続対策の効果は大きくても贈与税の負担が非常に重くなるので、結果的にはマイナスになることも考えられます。
7年以内の贈与財産は相続財産に加算
相続開始前7年(令和5年末までの贈与の場合は3年)以内の贈与は持ち戻されて相続税が課税されます。贈与によって不当に相続税を免れないように、被相続人から相続等によって財産を取得した人については、被相続人が死亡した日から遡って7年(令和5年末までの贈与の場合は3年)以内に被相続人から贈与された財産を相続財産に加算し、その代わりに、納税した贈与税については相続税から控除するという制度が設けられています。この場合、控除しきれない贈与税については還付されません。よって、原則として、相続開始前7年以内の相続等により財産を取得した人への贈与は、相続税対策としては効果がないのです。
生前に贈与できれば財産の移転という意味では成功ですが、税務対策の観点では、相続財産に持ち戻されることになり効果がありません。したがって、税務対策も兼ねて生前贈与をするときには、相続人に対しては計画的に贈与を行い、持ち戻されることのないように行うのがよいでしょう。令和6年1月1日以後の贈与から、相続開始前加算対象期間が3年から7年に延長されましたので、相当早くから贈与を行わないと税務効果がありません。
また、加算対象者は相続等により財産を取得した相続人等に限られますので、遺産等を取得しない人に対する贈与の場合は加算対象外となっています。例えば、相続人の配偶者(嫁や婿)や孫などの相続人でない人たちへの贈与です。これらの人への贈与ならば、相続の直前であっても持ち戻されることなく贈与税のみで完結します。ただし、遺言で財産をもらった人、死亡保険金を受け取った人等の場合には、相続税の納税義務者となりますので、生前贈与加算を受ける対象者になることに注意してください。
居宅の持分贈与は要注意
贈与税を安くしようと、数多くの親族に少しずつ分散して贈与する人がいます。この場合、簡単に分けることのできる現預金については問題ありませんが、不動産の持分贈与については要注意です。不動産について贈与により共有になると、収入や諸費用を分けたりする手間や、売却や増改築する際に意見が食い違うなど困った状態になるからです。
特に居宅の贈与の場合、居住者以外の人がもらっても使うことのできない財産となりますので、固定資産税の負担の問題もあり、相続後居住者である相続人が兄弟等から持分の買い取りを請求されるケースが増えてきています。居住者である相続人が収益性や換金性のない居宅を買い取らなければならなくなった場合、資金もなく非常に困ってしまうことにもなりかねません。居宅やその敷地を居住している人以外に贈与するのは避けたほうがよいでしょう。
相続時精算課税制度を効果的に活用する
相続時精算課税制度であっても、上手に活用すれば相続税の税額が減少していることもあります。
今後の資産価値を予測することは非常に困難ですが、収益性の高い不動産や値上がりが予想される土地、収用が予想される不動産は有利な贈与財産といえるでしょう。例えば、ここ数年のうちに市街化区域に編入されることが予想される調整区域内の土地や再開発が決まり変身する地域、収用予定地などがあります。
このように、現在は利用制限や環境不良により評価額が低いにもかかわらず、将来その利用価値や環境が改善されることが予想され、評価額の上昇が望めるものについては、これらを評価の低いうちに贈与することは大事な視点です。
賃料収入が確実に入ってくる不動産を贈与すると、低い評価額で贈与でき、安定収入がそのまま後継者に移転できるというメリットがあります。
ただし、なるべく高収益な不動産でないと費用倒れになることも考えられますのでご注意ください。特に典型的なのがロードサイド店舗や貸倉庫ですが、借入金や建設協力金がある場合が多く、慎重な贈与が求められます。また、老朽化した建物等は修繕費などの負担により、もらった人にとっては、かえって経済的には持ち出しが多くなることも考えられますので、修繕してから贈与するなどの考慮が必要です。
評価が下がっているものを贈与する
現金に比べると、建物やゴルフ会員権などの評価額は実際の取引価格よりも低くなっています。例えば、建物の相続税評価額は、国税庁の定める評価方法によると、固定資産税評価額(建築価額の約60%程度)で評価することができます。なお、賃貸している場合は借家権割合を控除することになっており、借家権割合は全国一律30%となっています。新築の貸家の場合には、その相続税評価額は投資金額の40~50%程度と大幅に下落します。
相続時精算課税制度により贈与する場合には、このように評価が下がっているものを贈与するとよいでしょう。相続時に精算されることを想定すると、この収益物件の贈与は相続時精算課税制度を選択する場合の切り札ともいえます。現金と比較して非常に低い評価であり、毎年安定した収益が入ってきますので、デフレやインフレによる将来のリスクにも備えることができます。
居住用財産の譲渡特例を活用するための贈与
親又は祖父母が所有している子や孫の自宅の敷地を売却した場合、親又は祖父母にとっては居住用財産に該当せず、居住用財産の譲渡所得の特例等は使えませんので、譲渡益がある場合には税金を払わなくてはなりません。このようなことが将来想定できるケースでは、親又は祖父母から自宅の敷地を贈与してもらえば、子や孫にとっては土地も家屋もどちらも居住用となるので、3000万円の特別控除や軽減税率をしっかりと活用できることになり、売却に対する税金は減少することになります。
相続税のかからない家族ならば、相続という後顧の憂いもなく、適切な方法といえるでしょう。
相続時精算課税制度の選択は慎重に
贈与された財産について「相続時精算課税制度」を選択しますと、相続発生まで財産の評価額が一定だと仮定した場合、令和6年以後の贈与から控除できる基礎控除額110万円部分を除き、贈与で取得しても相続で取得しても負担すべき税額は一緒です。しかし、贈与するものや贈与の時期、相続の発生時期によって、贈与財産の贈与時の評価額と相続時の評価額は大きく変動します。
相続時精算課税制度は値上がりするものの贈与や、相続税の申告の時に持ち戻す必要がない基礎控除部分の贈与については、暦年課税に比較すると有利です。しかし、相続税の税率より低い贈与税率の範囲で生前贈与加算期間の7年を超えて長期にわたり贈与を繰り返す、または相続時に持ち戻しのない相手に贈与するなら、暦年課税のほうが有利です。相続税のかかる方は暦年課税か相続時精算課税を選択するのか、慎重に検討する必要があります。