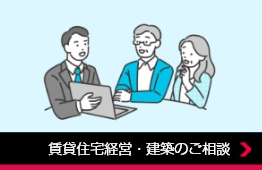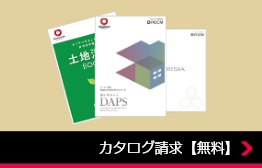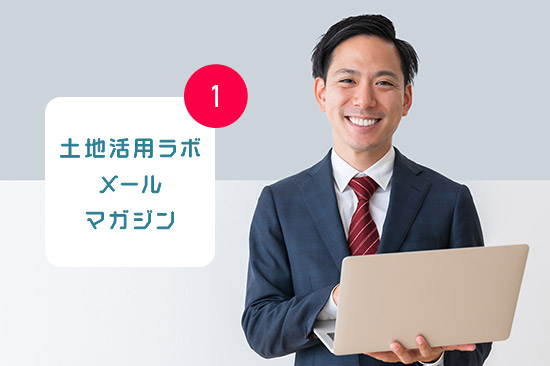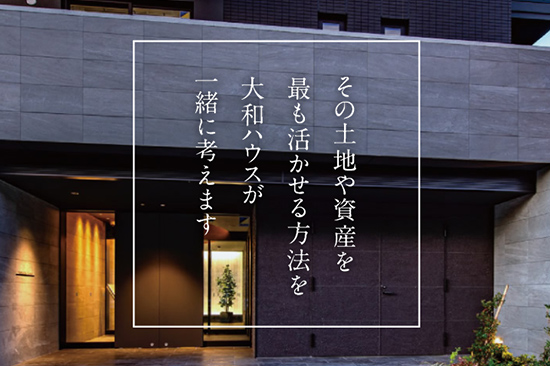コラム vol.561
コラム vol.561事業承継対策は、遺言書の作成から始める
公開日:2025/07/31
現在、多くの中小企業経営者が高齢化し、事業承継に課題を抱える経営者も少なくないでしょう。長年事業を経営してきた中小企業オーナーは、会社に対する愛着や築き上げてきた有形無形の財産に対する思いも格別なものであることでしょう。
事業承継を考えるにあたっては、そうした会社、残された後継者たち、そして家族への思いをまとめた遺言書の作成からスタートしてみるのもひとつの方法です。
相続税等の税金が発生してしまうことを気にする経営者も多いとは思いますが、事業をどうするかで、家族、きょうだいが仲たがいしてしまっては、せっかく事業を継続してきた意味すら薄れてしまうでしょう。
もっとも大切なことは、残された家族が幸せに、事業が後継者にスムーズに引き継がれ、順調に継続していくことのはずです。
遺言書作成の効果
自社株の分散リスクの回避
会社経営に関係する複数の相続人がいる場合、先代経営者は遺言書を作成しておくことで、現金、株式、不動産等、事業のための資産が、相続人に分散することを防止することができます。先代経営者が後継人を決めていたとしても、遺言がなければ法定相続分で分けることになり、株式が分散してしまう可能性があります。そうなると、後継者の議決権がないまま、会社を経営していくことになりますので、スムーズに進まないことが出てくる可能性があります。
分散を防ぎ、会社の後継者に株式などの事業のための資産を集約することができれば、議決権が分散することもなく、事業承継後の経営がやりやすくなるでしょう。
また、相続財産を後継者や他の相続人にどのように引き継がせるのか決めることができれば、相続税の納税資金を確保したり、遺留分侵害額請求対策の金銭を確保したりすることもできるでしょう。
経営空白期間の回避
相続発生時に遺言がない場合、相続財産に含まれる自社株は遺産分割協議で複数の相続人に分散してしまう可能性が高くなりますが、その際、遺産分割会議は時間も手間もかかり、会社の経営に影響を与えてしまうこともあります。何より、その間、重要な意思決定や判断ができなくなる可能性がありますので、こうした経営の空白期間はできるだけ避けたいものです。
親族外の人にも財産を遺贈できる
遺言がなく、相続となってしまった場合、相続人になれるのは、原則、配偶者と子ども(代襲相続人含む)のみになります(子どもがいなければ、両親やきょうだいまで順位が及ぶこともあります)。
後継者にしたい人が、優先順位の低い血族者や外部の人の場合、遺言書を作成することで、遺贈の意思を明らかにすることができます。
また、後継者に資産を集約した結果、他の相続人が遺留分侵害額請求を起こしそうな場合でも、遺言書に「相続人に対して、事業の必要性を理解して遺留分侵害額請求をしないように求める」ことを付言事項として残すことで対処することができる場合もあります。付言事項に法的な効力はありませんが、遺言者の思いを伝えられるからです。
遺言による事業承継が適したケース
相続人の複数が会社の経営に関係している
前述したように、経営者の相続人となる親族が複数人いて会社の経営に関係している場合、それぞれが法定相続分の相続を主張し、株式が分散してしまう可能性がありますので、こうした相続人の状態のときは、先代経営者は遺言書を作成すべきでしょう。
また、相続する財産の大半が株式の場合、財産ごとに分割することができなくなるため、どうしても株式を分散して相続することになり、同様のことが起こりえます。
個人事業主または一人会社の場合
個人事業主の場合は、事業承継というよりも相続の側面が大きくなりますので、相続時にもめることのないように、遺言の重要性が高くなるでしょう。また、2006年に成立した「新会社法」によって会社を設立するための条件が緩和され、いわゆる一人会社として、事業を行っている経営者も少なくないでしょう。この場合も、事業用の資産も個人名義になっているケースもあるでしょうから、事業用の資産は後継者へ渡るように遺言書に明記し、ほかの相続人は事業に悪影響を与えないような資産配分を行う等の対策が必要となるでしょう。
遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」2種類がありますが、どちらも法律上認められていますので、どちらでも問題ありませんが、法的な効力が認められないことがないように、注意が必要です。
いざ事業承継のことを考えてみても、何から始めればよいか、わからないという人も多いでしょう。そうした場合こそ、遺言書の作成から始めるのもひとつの方法です。財産分与のことだけではなく、会社の将来について、家族のこれからの暮らしについて、考えを整理するところから始めれば、自ずと、財産分与についても、考えがまとまっていくのではないでしょうか。
会社には、長年の間築いてきた、貴重な資産がたくさんあります。これらをどのように活かし、さらに有効な資産へと築いていくのか。当然、自分一人では解決できないことも出てくるかもしれません。そうしたときは、後継者や家族だけではなく、これまで一緒にやってきた仕事上のパートナー等にも相談し、周囲のニーズにも耳を傾けることも大切なことです。
経営者が資産と事業をバランス良くスムーズに承継するためには、遺言は必要な対策のひとつでしょう。