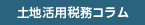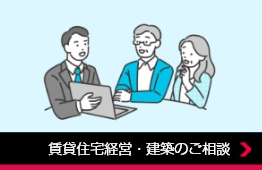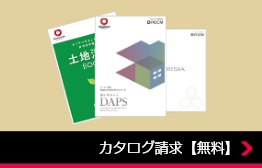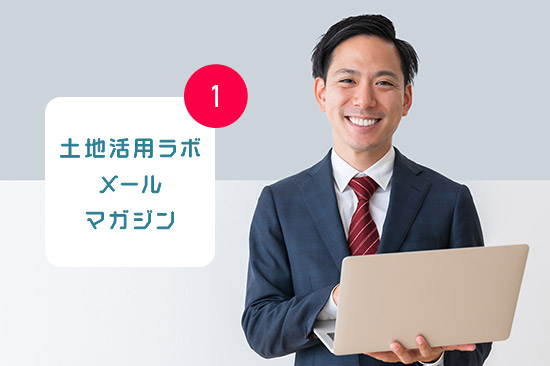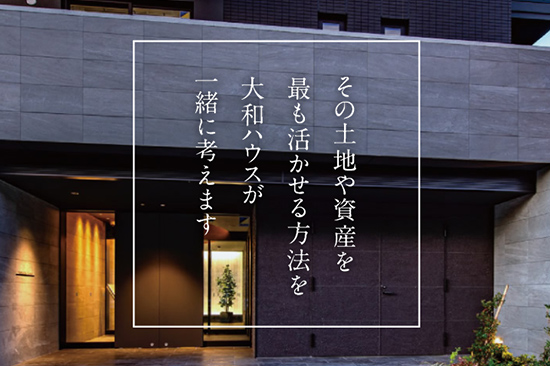コラム vol.563
コラム vol.563相続対策は、むしろ二次相続に注意が必要
公開日:2025/08/29
相続人(子ども)に両親がいて、最初に父が亡くなり、母と子どもが相続をした後、今度は母が亡くなると、子どもからすれば、二度目の相続をすることになります。これを二次相続といいますが、一次相続よりも、むしろこの二次相続のほうがより注意すべき点がありますので紹介します。
子どもからすれば、多くの財産を持つ父が亡くなったときにさまざまな相続手続きを終えることができれば、ようやく終わったと安心するのも無理はありませんが、二次相続には、相続税などの観点からさまざまな注意点があります。
二次相続で相続税が増える場合がある
一次相続で、さまざまな特例や制度を利用し、相続税がほとんどかからなかった場合でも、二次相続の際は、母からすべての財産を子どもだけが相続することになりますので、思いがけず相続税が高額になってしまうことがあります。
配偶者控除が使えなくなる
亡くなった父の配偶者の母が亡くなったわけですから、配偶者控除という特例を使うことができません。配偶者控除とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が相続した財産のうち、課税対象となる額が、「1億6000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからないというものですが、二次相続では、この特例を使うことはできません。
配偶者が所有していた財産が父の財産に合算される
財産を持つ母親は少なくありません。高齢になるまでずっと働いていたり、祖父母からの遺産を相続していたり、父親よりも多い財産を持つ人もいるかもしれません。その場合の二次相続では、一時相続で引き継いだ財産と母自身が持っていた財産が合算されますので、遺産額が多くなり、相続税額が大きく増える可能性があります。
法定相続人が減り、基礎控除額が減少する
相続税額を算定する際には、基礎控除や債務や葬儀費用などを差し引いて計算します。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で算出しますので、法定相続人の数が多いほど、基礎控除額は大きくなり、相続税額を減らすことができます。二次相続では、法定相続人が減りますので、基礎控除額が減少します。
死亡保険金と死亡退職金の非課税限度額が減る
基礎控除額の計算と同じ根拠ですが、死亡保険金と死亡退職金についても、法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額が設けられていますので、二次相続では相続人数が減少し、相続税の上昇につながることになります。
小規模宅地等の特例が活用できないケースがある
居住用の宅地が相続財産の大きなウエートを占めるケースは多く、小規模宅地等の特例を活用して一次相続を行った人も多いでしょう。
小規模宅地等の特例は、相続開始の直前において、被相続人や、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が、事業用または居住用に使っていた宅地等を、最大で80%評価減できるというものですが、配偶者以外の親族が相続した場合は、相続開始前から相続税の申告期限まで、引き続きその家に居住し、所有している必要があります。
昨今、二人世帯、単独世帯が増加しており、何世代も継続して同じ居住地に住むケースは少なく、子どもがすでに独立していたり、相続した親族がすでに自己所有の家に住んでいたりする場合など、二次相続では小規模宅地等の特例を使えないケースが多くなります。
二次相続の対策
一次相続、二次相続の問題は、誰にでも起こりうることです。一次相続が起こる前から、二次相続までを見据えた計画、相続方法を考えておく必要があります。
生前贈与の活用
親の意思で、子どもに財産をどのように遺すかを決めているのであれば、積極的に生前贈与を行うのが良いでしょう。金額によっては贈与税がかかりますが、その分、相続税の対象額は減少することになります。また、年間110万円までの生前贈与は非課税となります。相続までに時間があるのであれば、年間110万円の範囲で贈与を続けておけば、贈与税の負担なく、財産を引き継ぐことができます(ただし、相続開始前7年以内の贈与に関しては相続税の課税価格に加算する必要があります)。
一次相続の段階で子どもに相続する
多くの場合、二次相続で子どもに財産がいくわけですから、一次相続の際に、相続税がかからないからといって、すべての財産を配偶者に相続するのではなく、一次相続の時点で、子どもにある程度の財産を相続しておくことも、有効なひとつの方法です。
たとえば、遺言書を作成し、配偶者には、今後の生活に必要な財産を相続させて、それ以外の財産については、あらかじめ子どもに相続させるようにしておけば、二次相続での負担を減らすことにもつながります。賃貸住宅など、将来価値を生み出す財産については、時間の経過とともに財産が増えていきますので、早めに相続することも、相続対策としては効果的です。
いずれにしても、残された配偶者や子どもたちの人生設計を考慮したうえで、慎重に検討することが望まれます。