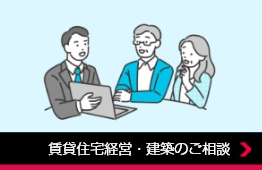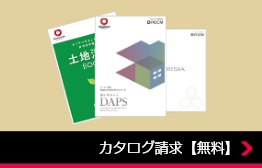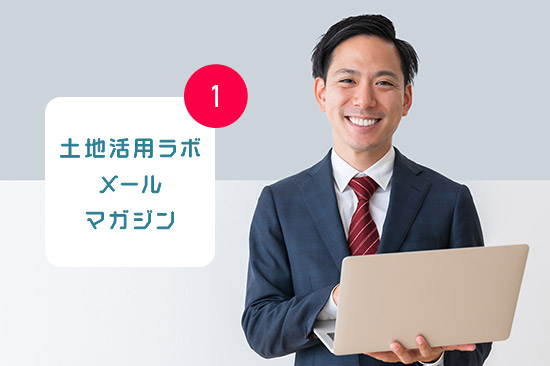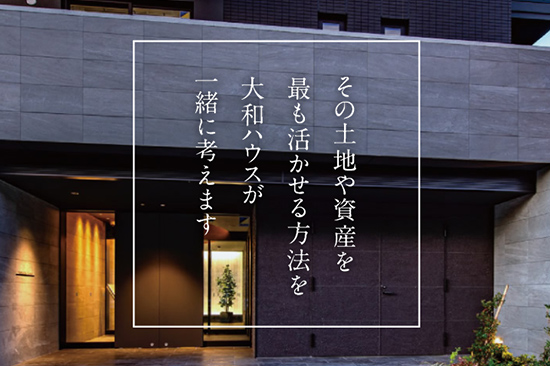コラム vol.568
コラム vol.568「住宅市場動向調査」に見る、賃貸住宅ご入居者のニーズの変化
公開日:2025/09/30
2025年6月に公表された「令和6年 住宅市場動向調査報告書」では、住み替え・建て替え・リフォームに関するさまざまなアンケート調査が紹介されています。ここ数年、物価上昇や建築費の高騰が顕著となっており、令和5年と比較しても、住み替えの動機やニーズ、意識、そして世帯の状況に多少の変化が起きているようです。今回は、この中から、「民間賃貸住宅」に関する内容をピックアップして紹介します。
住宅の選択理由
「なぜその賃貸住宅を選んだのか」という、民間賃貸住宅入居世帯における住宅の選択理由についてのアンケートでは、「家賃が適切だったから」が55.5%で最も多く、次いで「住宅の立地環境が良かったから」が31.0%、「交通の利便性が良かったから」が29.8%、「住宅のデザイン・広さ・設備等が良かったから」が27.2%となっています。
令和5年と比較すると、「家賃」については4.4%上昇しており、「立地環境」「交通利便性」「デザイン、設備」は逆に減少しています。やはり、賃料の上昇傾向は賃貸住宅の選択基準に少なからず影響しており、1年前と比較しても、より賃料に敏感になっていると思われます。賃料上昇と実質賃金のバランスによる家賃の見極めが大きな施設選択の理由となっているようです。
この傾向は「その賃貸住宅を選ぶにあたって妥協したもの」についても顕著に表れています。「家賃(予定より高くなった)」が最も多く、27.2%となっているものの令和5年よりは1%減少しており、逆に、職場からの距離が10.2%(令和5年)から14.7%(令和6年)、利便性の高い立地が11.1%(令和5年)から14.2%(令和6年)、交通の利便性が10.2%(令和5年)から13.4%(令和6年)と、家賃に影響を与える要素のほうに、変化が起きています。家賃の上昇への対策として、さまざまな条件を我慢せざるを得ない人が表れているといえます。
住宅を探した方法
民間賃貸住宅入居世帯が住宅を探した方法は「インターネット」が55.8%で最も多く、次いで「不動産業者」が44.7%となっており、Webサイトでの検討が半数を超えていますが、興味深いのは、令和5年と比較すると、インターネットはマイナス4.3%、不動産業者はプラス1.3%と増加している点です。地域に強いイメージがある不動産業者で少しでもより良い住まいを探そうという意識なのかもしれません。
建築時期
民間賃貸住宅の建築時期は「平成27年以降」が26.2%と令和5年(34.0%)と比較すると大きく減少し、「昭和60年~平成6年」が18.7%と令和5年(15.4%)と築30年以上の賃貸住宅に入居する人が増加しています。平均築後年数は令和5年の17.5年から、令和6年は19.9年と大きくなっています。貸家の新設住宅着工戸数の推移(国土交通省)を見ると、令和3年33.6万戸、令和4年35.3万戸、令和5年34.6万戸と同じような水準を保っていますので、築古の賃貸住宅への入居が増加している背景としては、住居選択の際に、家賃が影響を与えていそうです。
図1:建築時期
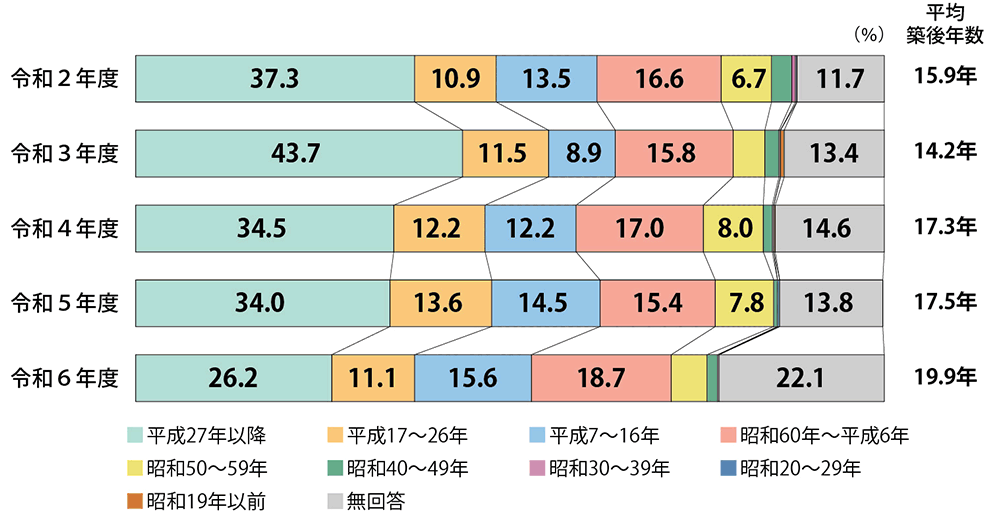
国土交通省 令和6年度「住宅市場動向調査報告書」より作成
在宅勤務等の個室スペース
コロナ禍においては、在宅勤務が急激に増加し、個室スペースを求める声が多かったようですが、令和6年では、その必要性が少なくなってきたのか、半数近くは、「在宅勤務に専念できる個室やスペースはない」と答えています。
「在宅勤務に専念できる個室がある」世帯は、令和4年が33.3%、令和5年が25.0%、令和6年は19.9%と大きく減少しています。
図2:在宅勤務等の個室スペース
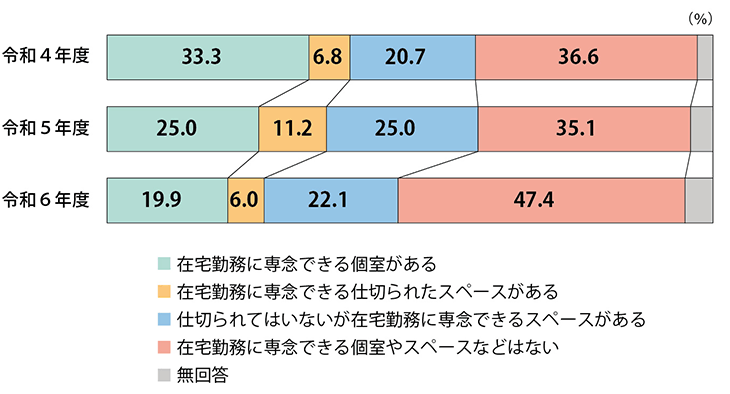
国土交通省 令和6年度「住宅市場動向調査報告書」より作成
世帯主の年齢
ここからは、賃貸住宅に住む人の世帯状況について紹介します。
民間賃貸住宅入居世帯の世帯主の年齢は、「30歳未満」が34.6%で最も多くなっており、これは晩婚化による単身者の増加が起因しているのかもしれません。平均年齢は38.9歳、ここ5年間の数値を見ても、大きな変動はありません。
居住人数
民間賃貸住宅入居世帯の居住人数は「1人」が41.1%で最も多く、令和5年と比較しても増加しています。次いで「2人」が35.6%と、1人と2人で86.7%と増加傾向にあります。その分、「3人以上」の世帯は大きく減少しています。
図3:居住人数
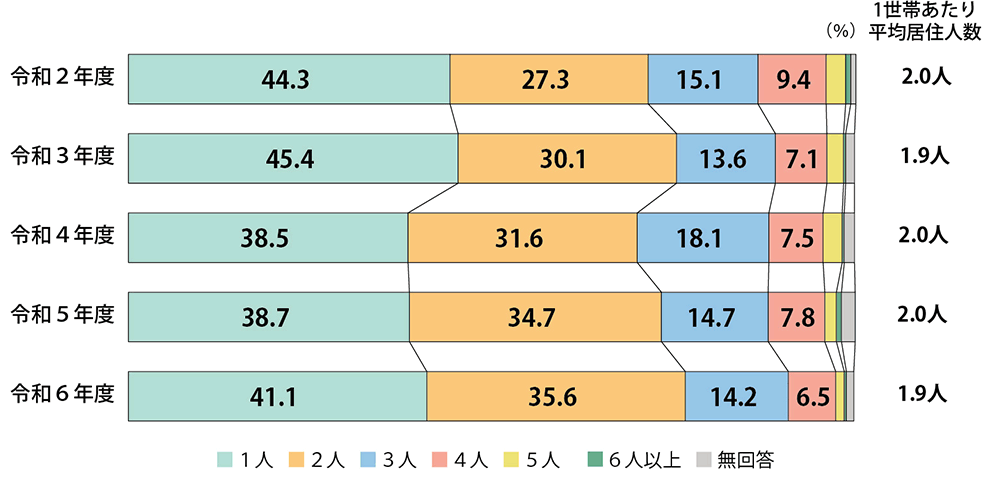
国土交通省 令和6年度「住宅市場動向調査報告書」より作成
高齢者のいる世帯
民間賃貸住宅入居世帯のうち高齢者がいる世帯は11.3%と増加傾向にあります。また、高齢者がいる世帯のうち、高齢者のみの世帯は60.6%、令和5年の51.6%から9%も増加したことになり、民間賃貸住宅全体の約6.8%が単身の高齢者世帯であるといえます。この傾向は、今後さらに増加すると思われます。
図4:高齢者がいる世帯の内訳
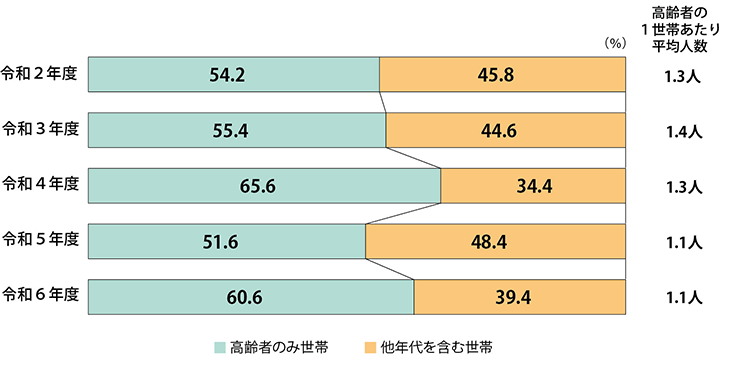
国土交通省 令和6年度「住宅市場動向調査報告書」より作成
世帯年収
民間賃貸住宅入居世帯の世帯年収(税込み)は「400万円未満」が33.9%で最も多く、令和2年から増加傾向にあります。「400万円以上600万円未満」は23.6%と、世帯年収600万円以下の総数はあまり変化がありません。年収600万円~800万円世帯が増加しているのは、住まいの選択肢として、あえて賃貸住宅を選ぶ人たちが増加しているといえるかもしれません。
図5:世帯年収
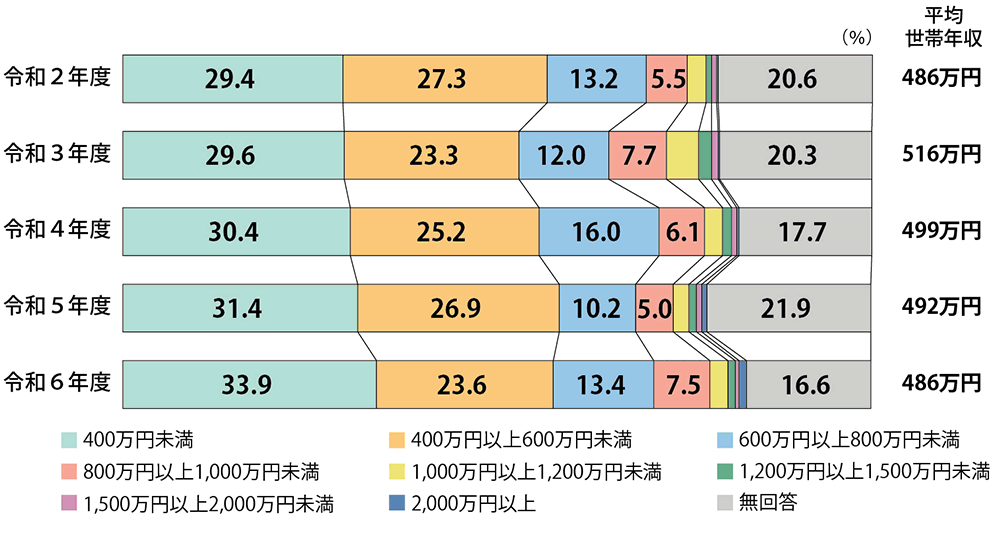
国土交通省 令和6年度「住宅市場動向調査報告書」より作成
勤務先からの住宅手当
昨今の福利厚生の実情を表しているといえそうなのが、勤務先からの住宅手当ですが、令和6年は、住宅手当を受けている世帯は令和5年度の28.3%から令和6年は23.8%と減少しています。昨今、企業において住宅手当は減少しているといわれていますが、その背景にあるのは、テレワーク含めた働き方が多様化しており、住宅だけではなく、働き方全体に対するサポートが必要とされていることが挙げられます。
また、働き方改革が進むことで、正社員だけに手当を支給することは、同一労働同一賃金の観点からも難しくなっていることも一因となっているようです。社員にとっては、手当よりも社宅のほうがより魅力的なケースもあり、福利厚生のあり方にも変化が起きているといえます。
図6:勤務席からの手当
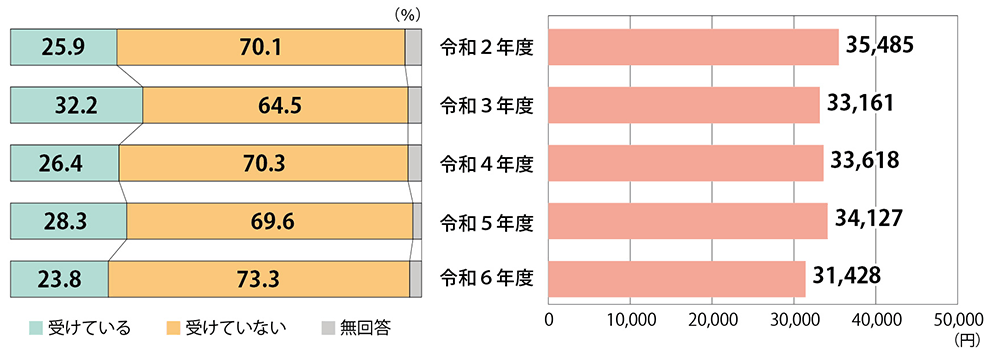
国土交通省 令和6年度「住宅市場動向調査報告書」より作成
月額家賃
入居した住宅の家賃の平均は月額77,677円となっており、家賃相場が上昇しているにもかかわらず、令和5年の78,737円よりも令和6年は下がっています。高齢者の単身者が増加し、世帯年収の低下と比例する結果となっています。家賃10万円以上の人は、あまり変わらない割合となっており、少しずつ両極化している傾向といえそうです。
図7:月間家賃
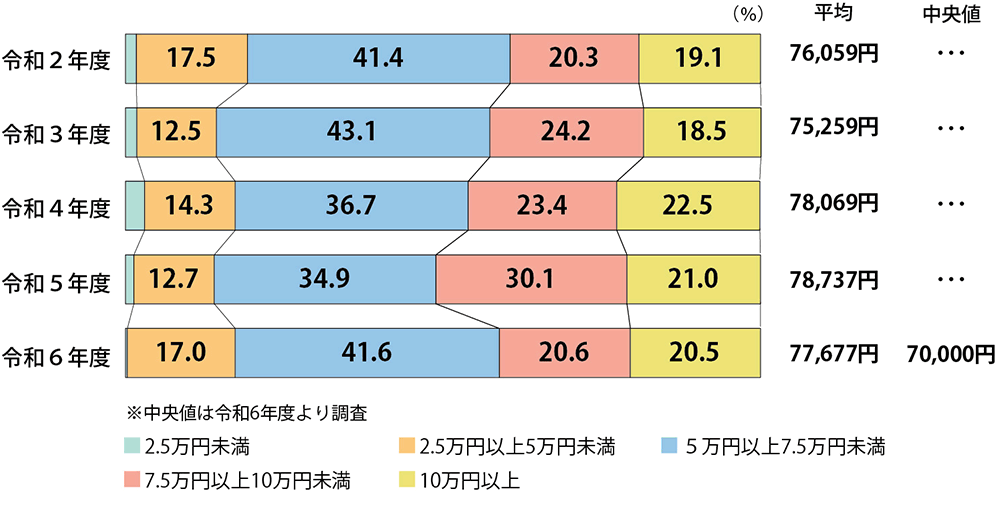
国土交通省 令和6年度「住宅市場動向調査報告書」より作成
礼金に関しては、令和6年は大きく変わっています。1か月未満という人が、令和5年の5%から、19.5%と大きく増加しました。礼金という制度そのものに変化が起きている状況のようです。更新手数料についても、令和5年から1か月未満が大きく増加しました。空室対策の一環として行われているケースもあり、築古の賃貸住宅などで増加しているものと思われます。
図8:敷金の月数・更新手数料の月数
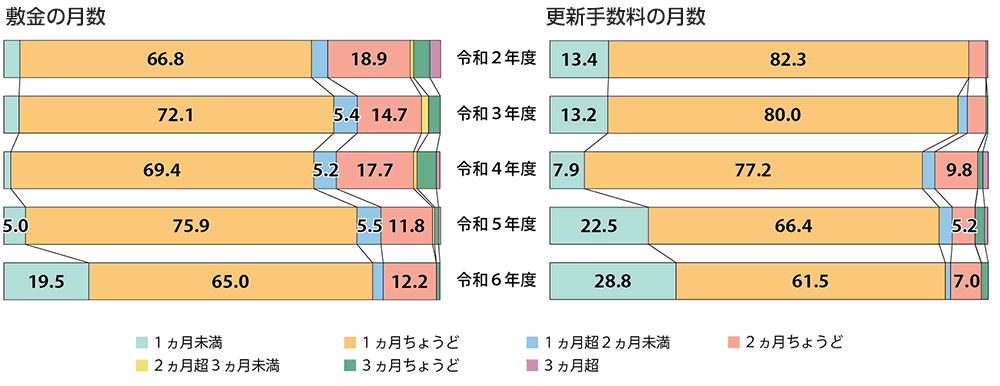
国土交通省 令和6年度「住宅市場動向調査報告書」より作成
賃貸住宅に関して困った経験
賃貸住宅に入居し困った経験として、契約時は「敷金・礼金などの金銭負担」が56.1%で最も多く、次いで「連帯保証人の確保」が23.6%。入居時は「近隣住民の迷惑行為」が39.0%で最も多く、次いで「家主・管理会社の対応」が24.4%。退去時は「修繕費用の不明朗な請求」が22.0%で最も多く、次いで「家賃、敷金の清算」が13.8%となっています。
賃貸住宅経営や管理の立場から見れば、このような問題を解決することで、「ご入居者に選ばれる賃貸住宅」につながる可能性が出てきますので、対応策を講じたいものです。
子育て世帯、若者夫婦世帯の割合
令和6年からの新しい項目として、「若者夫婦世帯」のウエート調査があります。民間賃貸住宅入居世帯における子育て世帯の割合は17.6%に対して、若者夫婦世帯の割合は12.3%となっており、一定層の若者2人以上の賃貸住宅入居者がいます。今後、こうした層への訴求も必要となりそうです。
賃貸住宅に入居する世帯の実情は、世帯自体の変化に加えて、ニーズや動機も変化しています。賃貸住宅オーナーとしては、こうした変化を敏感に感じ取り、これからの賃貸住宅経営に活かしていくことが求められています。