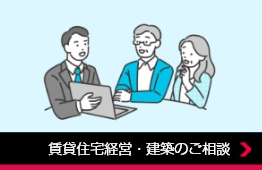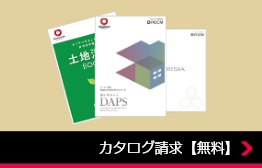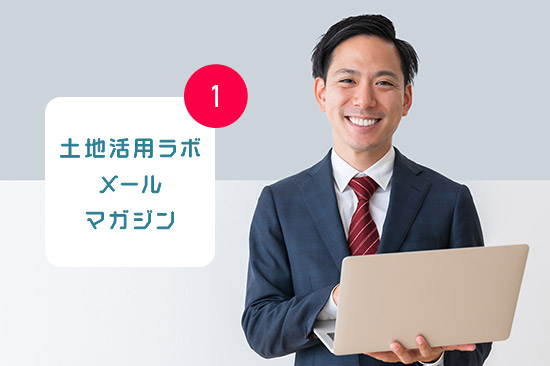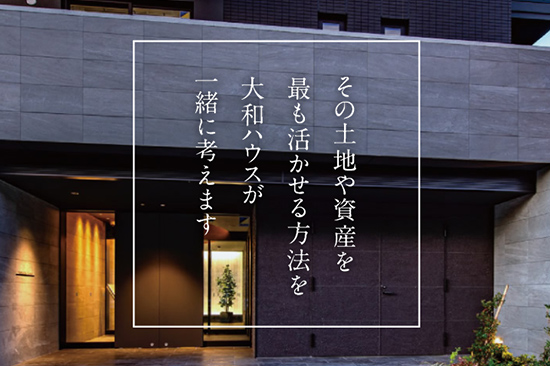コラム vol.573
コラム vol.573地方圏の地価上昇がいっそう鮮明に!2025年都道府県地価(基準地価)を読み解く
公開日:2025/09/30
2025年都道府県地価調査の概要が国土交通省より9月16日に公表されました。毎年9月に公表される都道府県地価調査は、都道府県が主体となって全国規模で行われる地価調査で、都道府県からの発表に合わせて国土交通省から全国の状況を取りまとめて公表されます。都道府県地価調査は7月1日を価格時点として、全国2万1441地点の「基準地」の地価を調査します。この調査結果により公表される地価は、「基準値」の地価ということで「基準地価」とも呼ばれます。
都道府県地価調査は、用途別では住宅地、商業地、工業地、宅地見込み地、に分けて調査されます。3月に公表される地価公示(国土交通省土地鑑定委員会:価格時点1月1日)と調査時期(中間点=半年)、調査地点において相互に補完的な地価調査となりますが、調査地は地価公示に比べて市街地以外も含めて満遍なく行われるのが特徴です。今回のレポートでは、初めて工業地地価についても触れます。
(本文、図表とも、データは全て国土交通省「令和7年都道府県地価調査」より作成)
2025年都道府県地価調査の全国平均の状況
2025年都道府県地価調査では、全国平均で、全用途平均・住宅地・商業地、工業地のいずれも4年連続で上昇、すべて昨年を上回る上昇幅となりました。
全用途の平均は1.5%の上昇(昨年は+1.4%、一昨年は+1.0%)で4年連続での上昇です。住宅地は1.0%の上昇(昨年は+0.9%一昨年は+0.7%)で4年連続の上昇となりました。商業地は2.8%の上昇(昨年は+2.4%、一昨年は+1.5%)となりました。
2017年から2019年まで3年連続の上昇のあと、新型コロナウイルスの影響を受けて、マイナスに転じましたが、2022年以降4年連続してプラス、上昇幅も4年連続で拡大となっています。
3大都市圏の住宅地地価の状況
3大都市圏(東京圏・大阪圏・名古屋圏)では、東京圏、大阪圏では全用途平均、住宅地、商業地、工業地いずれも上昇幅が拡大しましたが、名古屋圏では全用途平均、住宅地、商業地、工業地のいずれも上昇しているものの伸びは鈍化しました。
3大都市圏全体では、全用途平均は5年連続して上昇、住宅地は5年連続、商業地は13年連続して上昇しました。3大都市圏では、名古屋圏だけが上昇の勢いがやや止まってきている状況で、差が付き始めています。名古屋圏では人口流出が続き、インバウンド需要においても東京圏や大阪圏に比べて、勢いがないことが要因でしょう。
全国的な傾向としては、物価の上昇が続き、株式市場も好調で、人流も活発な状況で、好景気が続いており、それに連動する形で地価も上昇しています。地域や用途で多少差があるもの、とくに東京圏や大阪圏では上昇幅の拡大が目立っています。
引き続き住宅需要が堅調で、加えて金利上昇傾向にあるものの実質金利でみれば、依然金融緩和政策が継続しています。また、住宅ローンも低金利が続いていることなどが需要の下支えとなっています。とくに東京圏や大阪圏の中心部では住宅地地価が高い上昇を示しています。
また、三大都市圏における主要地域の商業地においては、店舗やホテル需要が堅調で、加えてマンション需要が旺盛な中でマンション適地が少ないことから競合となっており、それも商業地地価上昇の要因と考えられます。
住宅地の上昇幅を圏域別でみれば、東京圏では+3.9%(昨年は+3.6%、一昨年は+2.6%)、大阪圏では、プラス2.2%(昨年は+1.7%、一昨年は+1.1%)、名古屋圏ではプラス1.7%(昨年は+2.5%、一昨年は+2.2%)となっています。昨年までは3大都市圏すべてで、上昇幅が拡大していましたが、名古屋圏だけが上昇幅が鈍化しました。
図1:圏域別 基準地価対前年平均変動率(住宅地)
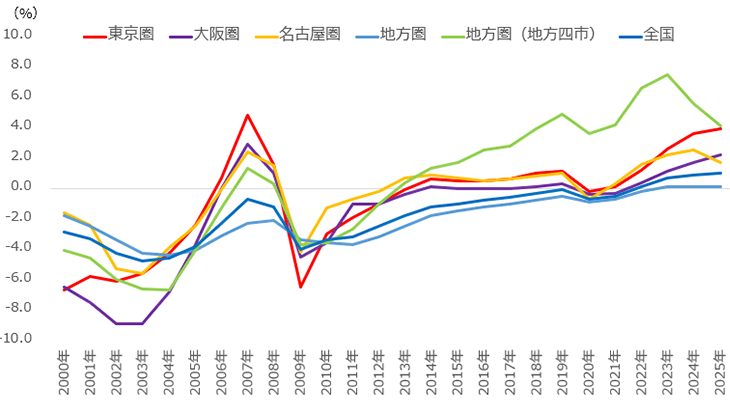
国土交通省「都道府県地価調査」より作成
地方圏の住宅地の状況:30年ぶりに「その他地方圏」はマイナス圏を脱出!
地方圏も昨年に引き続き、上昇が続いています。
地方圏全体の住宅地ではプラス0.1%(昨年、一昨年と同じ)でした。これを地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)だけで見れば、+4.1%(昨年は5.6%、一昨年は+7.5%となっており、長く上昇幅拡大が続いていましたが、さすがに2年連続して伸びが鈍化しました。
その一方で、地方四市を除く、「その他地方圏」では、±0.0%となり、30年ぶりにマイナス圏を脱しました。ちなみに、過去5年をみれば、2024年は-0.1%、2023年は-0.2%、2022年は-0.5%、2021年は-0.8%で順調に回復した足取りが伺えます。
住宅地地価、地方もプラスへ。都道府県別の住宅地の状況
住宅地地価を都道府県別にみれば、地方都市にも地価上昇の波が及んでいます。
変動率がプラスとなった都道府県は、前年の17から20へと増加しました。過去5年をみれば、7→14→18→17→20となっており、2000年以降では最多となりました。
一方、変動率がマイナスとなった都道府県は、前年の29から26となり3つ減りました。過去5年をみれば、38→32→28→29→26となっており、住宅地地価上昇の波が地方に及んでいることがわかります。昨年プラスから唯一マイナスとなったのが北海道で、昨年まで4年連続してプラスが続いましたが2025年はマイナス0.2%となりました。富良野など、リゾート地での上昇幅は大きい一方で、過疎化が進む地域の住宅地地価下落が続き、また長く上昇幅が大きかった札幌市の上昇率は昨年の+3.6%から+1.4%と下落していることも大きな要因と思われます。
昨年変動率マイナスあるいは横ばいだったのがプラスとなったのは4県あり、2024年年初に地震のあった石川県と長野県、滋賀県、宮崎県です。マイナスの26道県をみれば、マイナス幅の縮小した県は11県あります。このように、変動率がマイナスの県においても、マイナス幅が小さくなっています。プラスからマイナスになったのは、前述の北海道のみです。また、最もマイナス幅が大きかったのは、人口減少が続く、鹿児島県と徳島県で、昨年まで4年連続してマイナスが最も大きかった愛媛県は―1.0%(昨年は―1.2%)でした。長年地価下落が続いた地方都市においても地価回復基調にあることがわかります。
図2:都道府県別 基準地価対前年平均変動率(住宅地)
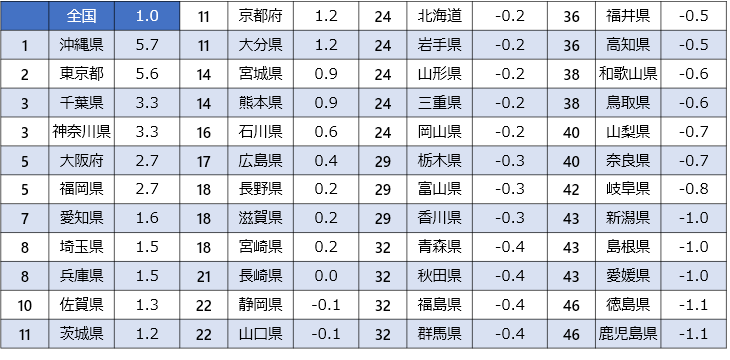
国土交通省「都道府県地価調査」より作成
図2は、都道府県別の住宅地地価を対前年変動率の高い順に並べたものです。最も上昇したのは沖縄県で5.7%の上昇(昨年は+5.8%、一昨年は+4.9%)でした。沖縄県は、2016年以降10年連続で上昇幅トップを維持しています。各観光地の上昇が著しく、地点別でみれば、住宅地地価上昇の上位には7位には宮古島市下地島(宮古島と橋でつながる、空港もあり)の地点で+19.8%、9位に宮古島市の池間島(宮古島と橋でつながる)の地点で+18.6%、8位には恩納村の真栄田の地点(ダイビングスポットで有名)では18.7%の上昇となっています。昨年は上昇率ベスト10に宮古島市の地点が6つランクインしていましたが今年は2地点でした。
県庁所在地の那覇市は+4.9%(昨年は4.3%)でしたので、中心部(=県庁所在地)よりも沖縄県全体の方が高い上昇率を示しています。本島の観光地や離島の観光地近くの住宅地上昇が顕著な事が伺えます。
2位は昨年と同じく東京都で+5.6%(昨年は4.6%)、3位は千葉県と神奈川県で+3.3%(両県とも昨年は4位で+3.2%)5位は大阪府で+2.7%でした。
全般的には、人口減少県の基準地価マイナスが目立ちますが、エリアで明暗が分かれている状況です。九州では鹿児島県以外ではプラス(長崎県は±0%)となっており、とくに福岡県は+2.7%(上昇率5位)で、福岡県に隣接している佐賀県は+1.3%(同10位)、大分県は+1.2%(同11位)、熊本県は+0.9%(同14位)、となっています。また宮崎県は26年ぶりの上昇(+0.2%(同18位))となり、エリア全体での住宅地地価上昇が目立っています。
活気が続く福岡県が牽引する経済状況に加えて、半導体企業TSMCの熊本進出の影響、そして宮崎県の観光地としての再脚光の影響が出ているものと思われます。
また、2025年の基準地価でも、半導体工場進出の影響で千歳市の基準点が住宅地地価上昇率ベスト10内に2地点ランクインしました(ちなみに、商業地のベスト10では1位~3位は千歳市の地点)。
大型工場の開業により、従業員やその家族の為の住宅需要が高まります。家族で転居する方々、単身で転居する方々が急増し、会社・工場周辺地域に一気に住宅需要が起こります。そのため、持ち家、賃貸住宅ともニーズが高まり、住宅地地価上昇につながっている状況が鮮明となっています。
図3:2020年~2025年 基準地価対前年平均変動率(住宅地)
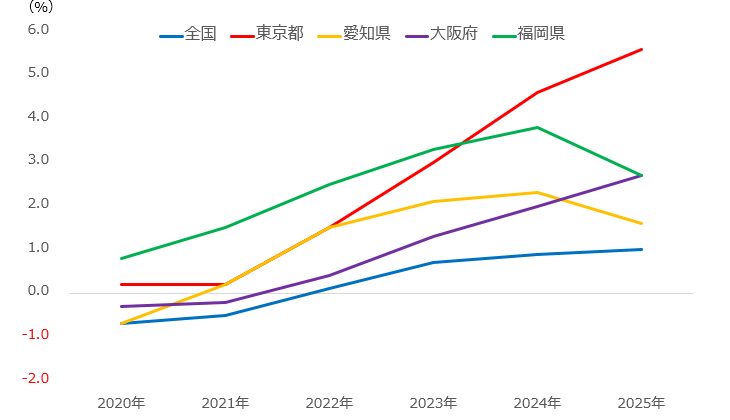
国土交通省「都道府県地価調査」より作成
直近6年(20年のコロナ禍以降)の4大都府県(東京都・大阪府・愛知県・福岡県)にフォーカスしてみると、図3のようになります。主要都市の住宅地地価上昇率は、東京都・大阪府は上昇率が拡大していますが、その一方で長く上昇率拡大が続いた福岡県は上昇率一服感が出ており、また愛知県は過去4年上昇率拡大しましたが、伸びが鈍化しており、明暗が分かれた格好となりました。
大都市圏で大きな伸び:商業地の状況
ここからは、商業地を見てみます。三大都市圏を域別にみれば、東京圏は+8.7%となりました。昨年は+7.0%、一昨年は+4.3%ですので、上昇幅は年々大きくなっています。大阪圏は+6.4%(昨年は6.0%、一昨年は3.6%)となり、東京圏ほどではないものの上昇幅は拡大しています。その一方で、名古屋圏は+2.8%となり、昨年は+3.8%、でしたので、上昇率が鈍化しました。不動産市況好調が続く中での、名古屋圏の上昇率鈍化が目立ちます。
首都圏主要都市、大阪圏主要都市では、再開発が各所で進んでおり、複合商業施設とオフィス一体開発が広まり、利便性の期待が高まっており、空室率低下・賃料増により収益性が高まる傾向にあり、地価上昇につながっています。
商業地は住宅地以上に、地方圏の上昇が顕著となっています。地方圏全体では+1.0%(昨年は+0.9%、一昨年は+0.5%)、地方四市では+7.3%(昨年は8.7%、一昨年は9.0%)と13年連続して上昇しているものの、上昇率の鈍化は2年連続です。それでも7%を超える上昇ですので、勢いは続いています。地方四市を除く地方圏の「その他地方」は+0.6%(昨年は+0.5%、一昨年は+0.1%)と3年連続プラスとなりました。
図4:圏域別 基準地価対前年平均変動率(商業地)
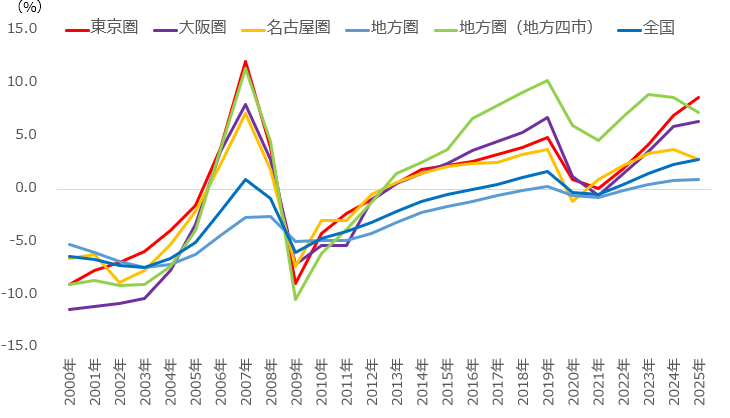
図5:2020年~2025年 基準地価対前年平均変動率(商業地)
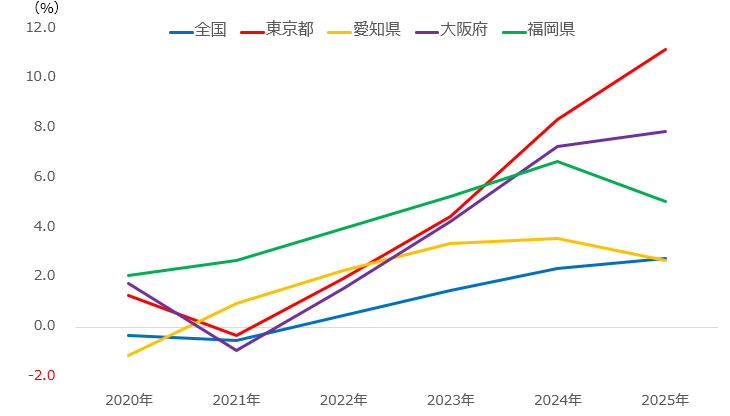
国土交通省「都道府県地価調査」より作成
直近6年の4大都市(東京都・大阪府・愛知県・福岡県)の商業地地価の変動率をみると、図5のようになります。
グラフをみれば、東京都の上昇率は11.2%となり上昇の勢いに弾みがついていることが伺えます。愛知県や福岡圏では、上昇しているもののやや勢いに陰りが見えてきた感があります。
商業地地価は30の都道府県で上昇
商業地地価を都道府県別にみれば、変動率がプラスとなった都道府県は、前年の28から2つ増え30となりました(3年分では18→22→28→30)。一方、マイナスとなった都道府県は、前年の17から2つ減り15となりました(3年分では27→23→17→15)。商業地地価は住宅地地価と比べてボラティリティが大きくなる傾向にありますが、近年の上昇幅を見ていてもその傾向にあり、住宅地地価よりも商業地地価の方が上昇の都道府県が多く、また上昇率も大きくなっています。そして地方への地価上昇の波及は、商業地の方が大きいようです。
図6:都道府県別 基準地価対前年平均変動率(商業地)
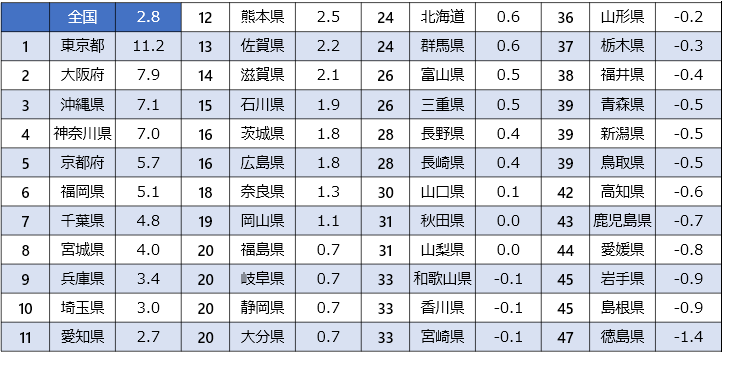
国土交通省「都道府県地価調査」より作成
図6は、都道府県別の商業地地価を、対前年変動率の高い順に並べたものです。
上昇率のトップは東京都で+11.2%(昨年は+8.4%)で2年連続の1位です。インバウンド観光客、国内観光客、ビジネス等、人流が活発でホテル・店舗、オフィスとも好調です。また、引き続き都心各地で再開発が進んでいることなどが要因と思われます。
2位は大阪府で+7.9%(昨年は7.3%)。万博開催などを契機にインバウンド観光客と国内観光客が大幅に増加、またJR大阪駅北側の「グラングリーン大阪」がオープンと、梅田エリアの再開発が進んでいます。3位は沖縄県で+7.1%(昨年は+6.1%)、4位は神奈川県でプラス7.0%(昨年は+6.2%)、5位は京都府でプラ+ス5.7%(昨年もつ5.7%)となりました。沖縄と京都は引き続き観光需要が活況であることが大きな要因となっていると思われます。
県庁所在地の商業地地価をみれば、47つのうちマイナスは、昨年と同様に唯一鳥取市だけで、-0.6%(昨年は-1.4%)でした。最も上昇したのは東京23区で+13.2%、昨年は+9.7%でしたので、上昇幅は大きく拡大しました。
商業地の変動率上位の地点を見てみると、ベスト1~3位は、半導体工場進出に沸く千歳市の地点で、いずれも30%前後の上昇率です。また、昨年同様、白馬村の地点や飛騨の高山市の地点もベスト10にランクインしています。
工業地の状況
工業地は、約2万1000の地点のうち863地点と、多くはありませんが、工業地の状況も見ておきましょう。本レポートでは初めての記載ですが、工業地の状況をお伝えしている記事は少ないので、参考にしてください。工業地の全国平均の変動率は、+3.4%で、変動率は昨年と同値です。
域別では、東京圏は+6.7%(昨年は6.6%)、大阪圏は+6.8%(昨年は6.3%)、名古屋圏は+2.5%(昨年は3.5%)となっており、工業地地価でも名古屋圏だけが上昇率鈍化となっています。地方圏では地方四市は+10.7%(昨年は+14.1%)、その他地方圏は+2.2%(昨年も同じ)となっています。
2026年の地価見通し
昨年の本レポートでは「2025年の9月に公表される基準地価は、3大都市圏はとくに商業地で上昇が2024年以上に顕著になると思われます」と書きましたが、地価上昇の傾向は概ね予想通りの結果となりました。
一方で、「これからの1年間(2024年後半~2025年前半)の間に金融政策の変更があり、金利上昇が複数回行われるようなことになれば、多少失速する可能性もあるかもしれません」とも予想しましたが、結局、政策金利は2025年1月末に0.5%となった以降は上がっていません。長期金利はこの1年間で1.6%程度まで上がりましたが、不動産市況は依然活況が続いています。
三大都市圏、地方四市は、ここ10年の間、再開発などを契機に不動産好景気が続き、地価は大きく上昇しました。そうした中、「さすがに上がりすぎ」との声も聞かれ、大都市圏の中でも一部地域においては上昇率の鈍化が鮮明になってきました。その一方で、人口流入が続き、国内外からの訪問客を集める東京圏(≒首都圏)や大阪圏(≒関西圏)は、上昇率は拡大しています。2026年の基準地価は、こうした二極化傾向が、より鮮明になるものと思われます。また、リゾート地への資金流入は続いており、また国内・国外問わずリゾート観光需要はまだまだ活況と見込まれるため、2026年もリゾート地の地価大幅上昇は継続するでしょう。