

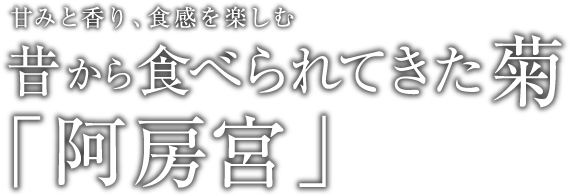
南部町の霊峰名久井岳と菊畑の光景は、まるで美しい日本の原風景を見るかのよう。(撮影:村井ユリ)

霊峰名久井岳をはるかに望む青森県三戸郡南部町。1日の寒暖の差が大きく、雨も少ない山間の気候をもち、水も豊富に湧くところだ。ここでは、サクランボやリンゴ、梨など果物がたくさんとれる。その中でも自然の豊かさが育んだ特産品に、食用菊がある。菊の王様といわれる「阿房宮」を筆頭に、南部町では菊を食べる文化が古くからある。
「八戸」駅から青い森鉄道に乗り継いで、「剣吉(けんよし)」駅で降りて車で約5分、南部町産の果物に特化して扱う村井青果がある。昭和20年頃から行商で関東や関西地方に干し菊を卸してきた青果卸業の会社だ。干し菊とは菊を蒸して乾燥させたものだ。今ではサクランボ、梅、プラム、洋梨なども扱う。営業課長である村井ユリさんは「阿房宮は他の菊に比べて、色がレモン色できれいですし、香りも神々しい。この地域ではとても身近な食材です。それを干し菊にすることで、長期保存が可能になっていつでも食べられるようになりました。菊は秋にとれるものです。でも季節の物を長く食べたい、さらに冬場の野菜が不足するといった点から、先人たちの知恵として進化した形が干し菊になったんだと思います」という。
そこで、阿房宮の生産現場を見せてもらうために、村井青果の契約農家を紹介してもらった。

菊花の束ごと鎌で刈り取っていく木村利子さん。そのスピードは早い。
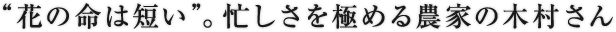
「うちはサクランボ、リンゴ、梨などが主で、秋に菊を育てています」というのは、阿房宮を生産する木村裕一・利子さんご夫妻。阿房宮の栽培は次のような流れだ。春先に芽が出、畑とは違う別の場所で苗を育てる。6月半ばに、長くなった根を寝かせながら畑に植える。10月に入ると花のつぼみがつき始める。朝晩が寒くなり、寒暖の差が大きくなると花が開いてくる。その花を束にして鎌で刈り取って収穫する。収穫した後は、すぐにほかす作業に入る。ほかすとは、花びらをがくから離していく作業のことだ。
阿房宮の作業は忙しい。例えばリンゴなら翌日に作業を回すことができても、阿房宮は成長しすぎると、花の黄色が抜けて茶褐色になってしまう。しかも刈ったらすぐにほかす作業に入らなければ、花がしなってきてしまう。また、天候によって収量が大きく左右される。とくに大敵なのが霜だ。10月下旬にもなると南部町では霜が下りる。そのまま放っておくと、菊の花がやけて茶色に変色してしまう。そのため、シートや藁でできた菰をかぶせて霜よけをする。そのタイミングもまた難しい。「このキレイな色をもっとよくしたいんです。でもあまり早く菰をかぶせると、太陽が当たらない分黄緑っぽい色の花になってしまう。そういう点でも霜は早く下りてほしくないですね」と木村さん。去年は夕方の町内放送で霜が下りる予報が出た。そのため夜冷え込みが増す中、月明かりの下で菰をかぶせる作業をしたという。「阿房宮の作業はゆっくりやっていられない。花の命は短いよ」と木村さんは笑いながら話してくれた。

取材時には3人のおばあちゃんがほかす作業をしていた。一番若い人でも15年はやっているという。
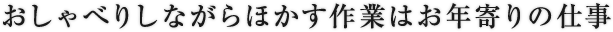
木村利子さんの案内で、自宅の一角でほかしている作業を見せてもらった。ケース一つで4キロ分の花びらがとれる。普段は8人ぐらいで作業する。昔は多くの家で干し菊をつくっていたが、今は高齢化で少なくなってきているという。取材時は、3人のおばあちゃんがイス代わりのケースに腰かけ、ちょうど刈り取ったばかりの阿房宮を膝と膝の間に乗せ、花びらを一輪ずつほかしていた。その中の一人、村木セリさんは83歳。30年もの間、ほかす作業一筋にやってきた。「ほかすにもコツがいります。大変なのは、霜に当たって茶色くなった花びらをとることです。最初のうちは霜に当たってない花ばかりだから楽ですけれど、傷んだものが多くなってくると大変です」と村木さんはいう。取材時も、少し茶色になった花びらをとり除きながら作業していた。この作業に同じ姿勢で8時間、それが収穫の盛んな時期になると10時間にもなる。それでも苦にならないのは、昔から年寄りの仕事であり、皆でおしゃべりして笑ったり、お茶を飲んだりしながら作業しているからだという。
ほかす作業の後は、蒸す作業に入る。この時は釜の準備ができていなかったため見られなかったが、蒸す作業になると一晩中立ち仕事となる。午後に刈り取り、ほかしに約8時間、その後すぐに蒸す作業に入り、乾燥機に入れるまでがひと続きの仕事だ。木村利子さんのいう、「花の命は短い」という言葉がまさに真に迫ってくるようだった。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.