

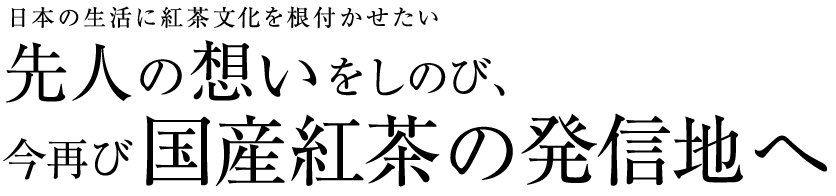
多田元吉が眠る墓地への階段。周辺に糸魚川静岡構造線という断層があるためか、
このあたりの水は硬度が高く紅茶に適している。それは、紅茶の国イギリスにも匹敵するという。
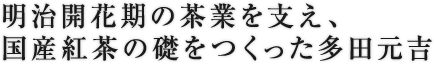
慶応から明治へと改元された1868年、朝敵として謹慎生活を送る元徳川15代将軍慶喜は、移封された駿府(今の静岡市)に移住。続く版籍奉還で、禄そのものを失うことになる旧幕臣たちの生活は困窮を深めていった。
一方、開国した明治新政府は富国の策として茶の輸出に注目し、茶業振興を後押しした。駿府から静岡へと地名が変わった明治二年、自活の道を模索していた旧幕臣たちは、静岡県中西部の牧之原台地で茶園の開墾に着手。だが、慶喜の側に仕える旧幕臣多田元吉は、静岡に近い長田村(現丸子)赤目ヶ谷の官林、約5haの払い下げを受けて、茶園の開墾をはじめた。こうした土地は荒れた地であったが、開墾から5年後に茶園を約10倍にしたという逸話が残っている。元吉の茶づくりの知識と技量は、時の明治政府にも認められるところとなった。
やがて世界市場では、緑茶に代わり紅茶人気が高まりを見せる。すると明治政府は国産紅茶産業育成のためとして、元吉を内務省勧業寮に配属し海外派遣を命じた。明治8年に中国、9年には通訳・エンジニア3名を同行してインドへと赴き、日本人として初めてダージリン、アッサムなどの紅茶プランテーションを巡察。貴重な茶樹の種子を持ち帰り、製茶生産技術を日本に紹介した。その後も丸子の地から、製茶の研究・振興に尽力を続けた彼は、明治29年67歳で没し、今は丸子の茶畑を見渡せる丘の上で眠っている。

村松二六さんと妻の時枝さん。今年で結婚50年、金婚式を迎える。
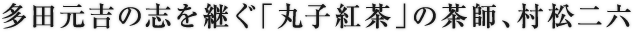
丸子で生まれ育った村松二六さんは昭和15年生まれで今年(2015年)75歳。二六さんが幼い頃、多田元吉の墓地の周りは木が鬱蒼と生い茂る格好の遊び場だった。多田元吉の偉業は周囲の大人たちから度々聞かされ、「偉い人がいたなあ」と思っていたそうだ。
二六さんの実家は蜜柑やお茶を栽培する農家だったが、20代の昭和28年から3年間、静岡県茶業試験場で行われた実習に参加した。その実習には紅茶製造技術のカリキュラムもあり熱心に学んだ。ところが皮肉にも、実習が終わる昭和30年頃から、年間8千トンあった国内紅茶生産は輸入自由化により衰退の一途をたどる。しかしこの時、紅茶製造の基本的な知識をしっかりと身に着けたことが、後に大いに役立つことになる。
それから数十年後の昭和60年、丸子地区に持ち上がった開発計画で多田元吉の旧家が取り払われることになった。敷地にはインドから持ち帰った種から育った茶の原木がある。二六さんはこの原木が多田元吉の功績を伝える証だ、どうしても残したいと思い奔走する。「やはり“発祥の地“という重みが大きかったね」と語る二六さん。幸い周囲の協力を得、原木の移植保存が叶った。そしてこの原木が多田元吉との縁をつなぎ、二六さんは紅茶づくりをはじめる。

二六さんが「悪い紅茶は時間が経つと色が緑っぽくなる」と教えてくれた。
それならと、試しに数時間置いたミルクティー。百聞は一見に如かず。
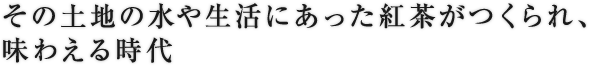
紅茶づくりに情熱を傾ける二六さん。本場の紅茶製造法を知りたいと思い立ってから、スリランカへは8回も通った。そうして長い時間をかけて紅茶製造の技術を自身の血肉としていった。しかし自身が培った紅茶づくりのノウハウをまったく隠そうとしない。そんな二六さんのもとには、全国から紅茶製造を志す人が押し掛ける。
“地ビール”ならぬ“地紅茶”が話題になっているのもブームの原因の一つだ。二六さんはその地紅茶にも一役買っている。JTB主催の「第7回 日本おみやげグランプリ」で農産加工部門金賞を受賞した「湯けむり温泉紅茶『飛騨紅茶』」。その紅茶は二六さんの畑で育った茶葉「紅富貴」であり、温泉水を使った発酵機も二六さんが特許を持つ発酵機を応用したものだ。「スリランカのバイヤー達は、みんなその土地の水に合わせて紅茶をつくっている。その土地それぞれの水と、それに合った紅茶がある。そういう意味では地紅茶というのも納得です」と、二六さんは言う。そして国産紅茶に人々の関心が集まっている今こそ、日本の紅茶のレベルを上げるチャンスだと考えている。
また、地元丸子の有志で運営している「丸子ティーファクトリー」は、一般の人たちも紅茶づくりが実習できる施設だ。今年6年目を迎え、全国から年間200人ものひとが紅茶を学びに訪れる。国産紅茶への熱い想いが、丸子から日本各地に広がっている。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.