

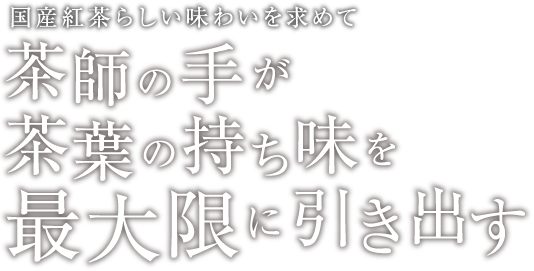
「紅富貴」の場合は、萎凋(いちょう)で42、3%の水分を抜く。
水分の抜け具合を確認する二六さん。
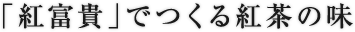
「丸子紅茶」では毎年5月20日前後に「紅富貴」のファーストフラッシュ(初摘みの茶葉)をつかった紅茶づくりがはじまる。茶葉の香りが良い時期は3日ほど。そのため、畑ごとに新芽がでるタイミングを微妙にずらし、すべての葉を最高の状態で摘めるようにしている。
「紅富貴」は二六さんにとって特に思い入れのある茶樹だ。日本で初めての半発酵茶・紅茶兼用品種で、じつは多田元吉がインドから持ち帰ったアッサム系の品種が母親の木だ。平成8年に苗木1500本を導入したが、民間では初めての栽培だった。お茶は寒さには弱い。とくにアッサム系は寒さに弱く静岡での栽培は無理といわれた。それでも諦めきれず、秋に樹皮の糖度を上げる肥料を施したり、剪定法を変えたりと、苦労の末やっと栽培に成功した。
摘みとった「紅富貴」は、すぐに萎凋槽(いちょうそう)に入れられる。この萎凋で紅茶の出来が8割方決まるという大事な作業。「丸子紅茶」には1.8×7メートルの萎凋機が2台ある。木枠の底がネットになっており、そこから風を送り込むことで、むら無く水分が抜ける。この時期は刈り取り後14時間ほど萎凋を行うが、冷える夜間はカーテンで覆い、ガスで5時間ほど温風を送る。二六さんは「『芯(茎)の水』まで抜かなきゃダメ」といいながら、萎凋された茎を自分でグニャッと曲げて見せてくれた。

揉捻機の釜の上の分銅で、茶葉へ圧力をかける。
かけすぎは渋みの原因となるので、葉の香りや色を見ながら調節する。
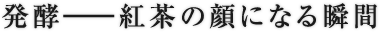
一晩、萎凋槽で水分を抜いたら、いよいよ発酵工程に入る。お茶は緑茶もウーロン茶、紅茶も樹木としては同じもので、発酵度合いによりその違いがでる。緑茶は不完全発酵茶で、葉そのものの旨味が尊ばれるが。完全発酵茶である紅茶の場合、旨味の素であるアミノ酸が紅茶の発酵を阻害してしまう。「紅富貴」は酵素の働きが活発なのでよく発酵し、紅茶に向いている品種だが、二六さんは「やぶきた」など本来緑茶用の茶葉も紅茶にする。茶葉それぞれの特性を見極めながら行う発酵で紅茶の渋み甘みが決まる。
まず揉捻機という機械で葉を揉んでゆく。釜の中に茶葉を入れ、分銅で圧力をかけながら65分程度揉んでゆく。こうして葉の細胞を適度に傷つけ、まんべんなく葉に酵素をいきわたらせ発酵を促す。揉捻が進み濡れた茶葉からは、かすかに青葉アルコールの香りがする。すでにゆっくりと発酵がはじまっている証拠だ。
揉捻を終えた茶葉は発酵機へ移される。この発酵機は二六さんが特許をとった自家製の加水分解発酵機。内部にはたえずお湯が流れ、機内の温度を30度前後、湿度は90%に保っている。日本では発酵に必要な湿度が足りないことから考案した機械だ。また加水分解発酵は「カテキン」の苦みも軽減できる。およそ60分後、発酵機の扉を開けると、紅茶特有のレンガ色に染まった茶葉が、芳醇な甘い香りをまといながら顔をだす。

「時間、熱、水分、の三拍子が決め手」と、二六さん。ガスの火力調節に余念がない。
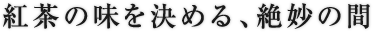
発酵がすんだ茶葉をドラム型の乾燥機に入れ回転させながら高温で煎る。これで酵素が働くのを止め、味を定着させる。ドラム内の温度は最高100度まで上げる。極限まで温度を上げることで、紅茶の甘みが最大限引きだされるという。普通は焦がすのを恐れてあまり温度を上げないが、二六さんはドラムにあたる茶葉の音や匂いなどで焦げる寸前のタイミングを見極める。これを周りの人は「二六マジック」と呼んでいるそうだ。
仕上げは茶葉と茎を峻別する作業。ここは二六さんの奥さん、時枝さんが行う。回転する容器に茶葉を入れると、細かい茶葉や茎が静電気で勝手にベルトに吸い寄せられていく。「面白いでしょ」と時枝さん。工房ではいつもご夫婦が阿吽の呼吸で働いている。
取材中、たまたま機械のトラブルがあり、二六さんが時枝さんに何か問いただそうとした。しばらくしてその原因が二六さん自身にあると気づき、「アア俺がやったあ」と朗らかに言った。それを聞いた時枝さんは、茶葉を優しくなでながら「そうでしょ」と小さい声でつぶやいた。その様子がとても微笑ましかった。
国産紅茶の味について、二六さんは「日本でダージリンはつくれない。我々はやはり旨味を求める。プロは渋みにこだわるが、一般の人の口に合うには、やはり旨味がなくてはと思っています」と、答えられた。お二人の様子を見ながら頂いた紅茶は、心なしか旨味が増したようだった。
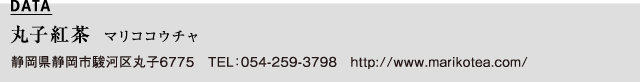
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.