

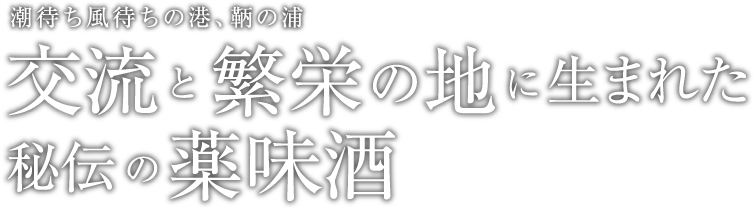
鞆の浦の全景。島々に守られた小さな港町である。
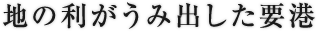
広島県では、広島市に次いで人口の多い福山市は、晴れの日が多い穏やかな気候と海の幸に恵まれたところだ。岡山の県境に近く、重工業が盛んな福山市にあって、風光明媚な景勝の地が、鞆の浦だ。福山駅より南に約14km、バスで約30分ほどの沼隈半島の東南端に位置する。目の前の瀬戸の海には、弁天島や仙酔島などの島々が浮かぶ。よく知られた箏曲『春の海』は、鞆の浦で育った宮城道雄が小さな頃に見た鞆の海を思い出しながら作った名曲だ。
ここはかつて多くの人々が行き交い、万葉集の大伴旅人の歌「吾妹子が見し鞆の浦のむろの木は 常世にあれど見し人ぞなき」でも知られる、古くから栄えてきた港町だった。この周辺の海は、潮の流れがとても複雑だ。東は紀伊水道、西は豊後水道からの満ち潮が鞆の沖合でぶつかる。かつて風や人力で動いていた船は潮にのって動くのが基本だった。瀬戸内には潮を待つための港が多くあったが、この鞆の浦もそう。満ち潮で港へ入り、引き潮で再び船出するという自然のサイクルに従って動いていたのだ。さらに鞆の浦は、沖合の島々が防波堤となる天然の良港であり、ちょうど瀬戸内海の中心にあった。そのため平安時代末期にはすでに港としての機能をもち、後には船の修理、物資の補給が行える要港にまで発展した。

太田家住宅の前に佇む鞆酒造の岡山純夫さん。
太田家住宅や鞆皿山焼など保命酒文化を守り伝えている一人だ。
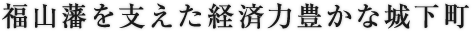
鞆の浦には西国の大名や長崎からの海外の使節など、多くの要人が訪れている。それが如実に分かるのが、国の史跡「対潮楼」だ。鞆港の終点であるバス停の近くに、福禅寺という寺院がある。対潮楼は、岩の上に組まれた石垣の上にそそり立つ、福禅寺の客殿だ。朝鮮通信使の迎賓館であり、その客殿から一望できる瀬戸内海の美しさに、朝鮮からの人々は「日東第一形勝」と称賛したという。儒学者の頼山陽が滞在して「山紫水明」の言葉をうみ出したといわれる「対仙酔楼」も、今日なお残っている史跡の一つだ。
鞆の浦は、歴史の宝庫だ。「足利氏は鞆に興り、鞆に亡ぶ」といわれたように、室町幕府を興した足利氏にとっても鞆の浦は重要な地だった。織田信長に京を追われ、鞆に下っていた室町幕府最後の将軍、足利義昭は、あるいは鞆幕府を打ち立てていたかもしれない。幕末には、坂本龍馬も足跡を残している。
実際に町を歩くと、各時代の遺構や建物が多く残されていることに驚く。「鞆の町は、福島正則公が鞆城を作った時の町割りと変わっていません。鞆の浦は、もともと譜代大名の福山藩のお膝元。姫路藩に匹敵したのではないかといわれるほどの豊かな藩の城下町です。大坂(現大阪)堺の港と同じように福山藩を支えた商人の町なんです」と話してくれたのは、鞆酒造の岡本純夫さんだ。その代表的な商家が太田家住宅であり、保命酒の造り酒屋だった旧中村家である。

保命酒屋を屋号とする「鞆酒造」では、保命酒一筋。
徳利入りのものもある。
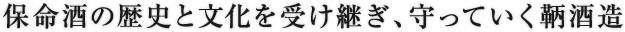
「世にならす鞆の湊の竹の葉をかくて嘗むるもめずらしの世や」とは、幕末、尊王攘夷をおしていた三条実美が保命酒を詠ったものだ。三条実美ら七卿が京都から落ち延びた先が、当時、保命酒を作っていた中村家(現太田家住宅)の主屋だった。もともと保命酒は、大坂の漢方医中村吉兵衛が知人を頼って鞆の浦に移住し、万治2年(1659)に藩の許可を得て大名や公家などを相手に販売を始めたものだ。
「広島は西条のような名酒の町もありますが、鞆は気候があたたかすぎて清酒づくりには向いていないんですね。保命酒は味醂と焼酎を使っていますから、春や秋、糖化の管理をすればよく、鞆には適している酒でした」と鞆酒造の岡本純夫さんは言う。
清酒と違って腐りにくい保命酒は長期保存に向いている。中村家は門外不出と言われた保命酒づくりの秘密を独占し、「御用命酒屋」として福山藩と密接な関係を結び、その藩の力を利用して北前船で全国に流通させた。幕府の買い上げも始まり、最後は筆頭老中にもなった阿部正弘公によって伊豆でペリーにも供されるほど、名声を高めるようになった。しかし明治に入ると中村家は衰退し、保命酒づくりは現在では4軒の酒屋が守るだけになってしまった。その1軒を継いだ岡本さんは、「中村家文書を解読して中村家の手法で保命酒を再現しました。保命酒は忘れ去られた商品です。それぞれ4軒とも個性がありますが、うちは基本に忠実に、もともとの保命酒を伝えるという筋を通しておきたいという想いがあるんです」という。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.