

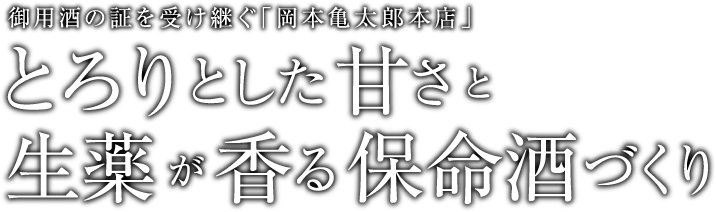
鞆の浦の町には、蔵が多く残されている。モダンな装飾が施されたナマコ壁。
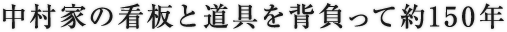
鞆の浦を歩いていると、福山城の長屋門を利用した店があった。その奥には、「保命酒」と書かれた大きな龍の看板がかかっている。店の前を通る子どもが龍に怖がって逃げると笑うのは、この店の主、岡本亀太郎本店の岡本良知さんだ。岡本亀太郎本店は、もともと清酒業を営んでいたが、明治に入って中村家の設備を譲り受け、味醂や甘酒をつくる中でじょじょに保命酒づくりを手がけるようになった。
「龍の看板は、中村家が掲げていた御用酒の証です。中村家が保命酒づくりをやめる時に、看板と道具一式を譲っていただきました。もともと中村家は、保命酒が一番知名度があったんですが、実は梅酒など9品目ほどを作っていたんです。だからうちは保命酒だけでなく中村家の得意とするところを受け継いでいると考えています」と岡本さんは話す。たしかに岡本亀太郎本店の商品の品揃えは、保命酒だけではない。純米仕込本味醂や梅酒、杏酒、保命酒の飴なども扱っている。
「漢方の臭みを抑えて飲みやすくしようと保命酒を磨き上げていく中で、味醂そのものに着目することが大事だと気づきました。麹にしっかり仕事をさせながら、利用していく方向を探ったんです。それでできたのが保命酒仕込みの梅酒「梅太郎」です。杏酒は梅酒を見た地元の方から鞆特産の杏を使ったらいいのではないかという声でつくらせていただきました」と岡本さんは話す。

岡本亀太郎本店の4代目である岡本良知さん。
保命酒の全盛期を象徴する見事な装飾彫刻が施されている中村家の看板が威容を放つ。
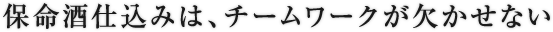
保命酒の仕込みは、まず味醂に始まる。気温の高い春先から夏にかけて、約3ヶ月。それから地黄を中心に16種類の生薬を約1〜2ヶ月じっくり漬け込む。これがおおまかな保命酒づくりの流れだ。4軒4様の配合レシピを元にしているが、時代によっても流行の漢方などがあったという。
岡本亀太郎本店では、基礎となる味醂づくりに力を入れている。岡本さん曰く、「清酒づくりと味醂づくりは明らかに違う。味醂は、酵母は一切使いません。麹による糖化作用だけ。清酒の場合は、糖化によって得られた米本来の旨味や甘みを酵母が餌にしてしまう。味醂はそれがないので、米のおいしさを最大限引き出した味の濃厚なものが作れるんです」
そのためには撹拌も大事だ。味醂のもろみは、清酒より粘度が高くとても重い。動力も使うが、様子を見ながらの撹拌作業は重労働だ。しかしこの作業なくして旨い味醂はできない。そこで忘れてはならないのは、“和を以て貴しと為す”ことだという。「お酒づくりはコミュニケーションが重要な世界です。私は青森県八戸で味醂の仕込みの修行をしました。杜氏を頂点とした組織に初めて入り、寒い気候の中、そこで人のぬくもりを強く感じたんです。今でこそ醸造環境が進歩して機械でできることも多いですが、やはり職人のチームワークで一致団結してこそ、満足のいく保命酒ができると思っています」という。

岡本亀太郎本店で、保命酒を磨き上げていく中でできた梅酒の「梅太郎」。

全盛期には、保命酒をつくる酒屋は、鞆の浦だけでも10軒はあった。しかし現在は4軒に減り、さらに保命酒といっても一般的には知られていないのが実情だ。鞆酒造の岡本純夫さんと同様、岡本良知さんもまた保命酒の認知度は低いという。岡本亀太郎本店では、梅酒などもあるが、これは薬臭さや甘さを調整しながら味醂を磨き上げていった結果できたものだ。また海外向けには香草系リキュールとして40度の保命酒もつくっている。他にも保命酒の味醂は、臭みを消すなどジビエ料理にも使われるようになってきている。だからこそ現在の状態を保ちながら、認知度をあげていきたいという想いは強い。「中村家の看板つまり伝統を引き継ぐ老舗の一つとして、その重みはいつも感じています。でも毎日同じ材料で保命酒をつくっても、全く同じ物はできないんです。6代目として五感の中で理想としている味があるので、そこに近づく楽しみもありますが、同時に次の世代に繋げていかなくてはならないと思っています」と岡本さんは話す。
現代は地産地消のかけ声のもと、地域資源の活用が模索されるようになってきた。現在、生薬の主産地は中国だ。しかし広島大学や岡山大学には薬草園があるので、いずれ鞆の浦でも生薬をつくれるようになったらいいという。そういった伝統を受け継ぎながらも新しい技術や試みを取り入れていく姿勢は、まさに岡本亀太郎本店が理念とする温故知新そのものといえるだろう。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.