

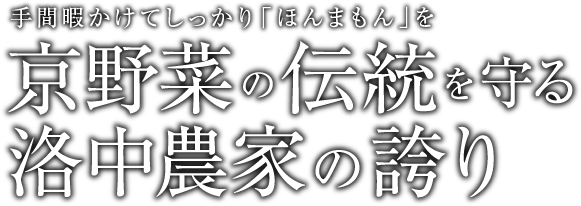
軒先の床几に所狭しと並んだ京野菜たち。みな色が濃く個性的です。

京都御所からまっすぐ西へ、約2㎞のところに位置する京都市上京区西上之町。付近には北野天満宮や方位除けで有名な大将軍八神社があるが、普段は観光客もあまり訪れることのない下町的な生活感あふれる町だ。ここで長年お店を営むのが、市内の畑で露地栽培の京野菜を育てて販売している「京やさい 佐伯」のご主人佐伯昌和さんだ。自宅を兼ねた間口二間のお店には、土のついた採れたて野菜が並んでいる。
佐伯さんは1955年生まれで、2015年に還暦を迎えた。京都の中心部である洛中では数少なくなった農家のひとりで、また、京都府の外郭団体が選出する「京野菜マイスター」の上京区ではただひとりの認定者でもある。
佐伯さんがつくる野菜の種類は年間を通じておよそ70種類。その中心となるのが「京の伝統野菜」だ。京都でつくられる野菜は総じて京野菜と呼ばれるが、なかでも「京の伝統野菜」とされるのは37種類。うち二つはすでに絶滅しており、今も栽培されているのは35種類となっている。春の京たけのこ、夏の賀茂なす、伏見とうがらし、鹿ケ谷かぼちゃ、秋から冬にかけては九条ねぎ、聖護院だいこん、聖護院かぶ、みず菜、壬生菜などがその代表的なものだ。
「京の伝統野菜」をはじめとする京野菜は、長い歴史の中で培われてきた京都の食文化の象徴として知られている。しかし京都市内の町中でこうした野菜がつくられているのを意外に感じたので佐伯さんに伺うと、「京野菜の伝統を守り続けているのは、京都市内の農家ですよ」との答えが返ってきた。

「町中の畑には、緑地としての価値も感じてほしい」と佐伯さん。
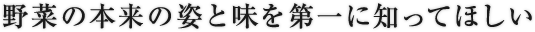
京都市内の農家の5代目として生まれた佐伯さん。現在は中京区西ノ京、右京区花園・太秦安井など市内4か所の畑と亀岡市河原林に1か所、合わせて79アールの畑で野菜をつくっている。そのうちの一つ右京区花園の畑を見せていただいた。
軽トラックの助手席に乗せてもらい走ることおよそ3分。市街地らしく一反ほどの畑のまわりには住宅が並び、その抜けた空の下で九条ねぎ、金時にんじん、聖護院だいこん、みず菜などが元気よく育っていた。
佐伯さんの野菜は生産と販売が直結しており、市場には出さないので、同じ時期に同じ大きさの野菜を出荷する必要がない。そのため多少大きさや形の違いがあっても良いし、出荷のタイミングも店頭での売れ行き次第で調整できる。その分、野菜本来の姿や味を第一に考えた野菜づくりに注力できるという。
九条ねぎの苗が植えてある畝に、春菊が一つ、顔を出しているのに気がついた。よく見ると他にも同じように、きちんと植えてある野菜の畝に、別の野菜がポツンポツンと顔を出している。その訳を聞くと「ああ、種がまじってしもたんや」という。種取りする筵(むしろ)が同じなのでまぎれてしまうらしい。佐伯さんは九条ねぎ、鹿ケ谷かぼちゃなど15~16種類の野菜の種を自分で取って栽培している。通常売っている種は一世代しか収穫できない。佐伯さんのように苦労をして種から育て、その遺伝子を次代へ継承していくことは、伝統の野菜を守ることはもちろん、私たちの食生活にとっても重要な意味を持つ行為だ。
佐伯さんは、一時のブームや生産性のみが問われる野菜づくりに対して、ここ京都の洛中で、家業としての農業のあり方を考え続けている。

店先に立つのは奥さんの孝子さん、息子さんも農家を継いで、もうすぐ10年になるという。
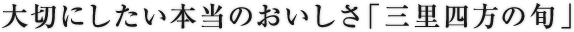
佐伯さんの畑を通りがかった人が、季節の野菜を眺めている様子や、親子連れが「あれがほうれん草で、あれが…」などと子どもに教えているのを見ると、野菜をつくって売るという行為だけではない別の意義が見えてくるという。住宅、商店、駐車場などがモザイク状に混在した町にとって「農地は共有財産で自分一代のものではない」と話す佐伯さんは、農業を先代の父から継いだ当初から無農薬で野菜を育てている。それは畑が人々の生活の場に近く、住宅に近接した場所で野菜を栽培していることとも関係しているだろう。
そして「三里四方の旬」が大切だと佐伯さん。これは文字通り自分が住んでいる場所で、その折々の旬の作物をいただくということ。食物には初物といわれる<はしり><旬>そして<しまい>があるが、<はしり>ものばかりがもてはやされ、旬がおろそかになっているという。
だれもがもっと農業を身近に感じて、旬のおいしさ、ありがたさを感じてほしいと佐伯さんは願っている。
近頃ではお膝元の京都市内でも京野菜の旬を知り、きちんと食べる人が減っていると顔を曇らす佐伯さん。しかし、おいしい京野菜ということで遠方から買いに来るお客さんも多く、さらに和食以外にも中華やフレンチ、イタリアンのシェフがそのおいしさに目をつけ、京野菜をメニューに加えることが増えているという。京野菜の旬の味は、三里四方を越えて広がっているようだ。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.