

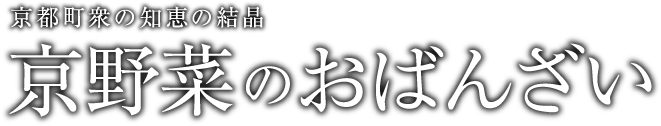
「京やさい 佐伯」から持ち込んだ京野菜。九条ねぎ、聖護院だいこん、えびいもなど。
昆布と椎茸は出汁用。「出汁をしっかりとるのが基本」と藤田さん。
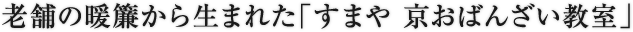
京都のグルメとして人気のおばんざい。「おばんざいには『出会いもん』という言葉があります。これは相性のいい食材どうしが出会うことで、1+1が3にも4にもなって一層おいしくなるという考え方です。京都の人はそういう組み合わせを考えるのが、もう天才的なんです!」こう話すのは四条烏丸で「すまや 京おばんざい教室」を主宰する藤田博子さん。「このあたりは室町筋と呼ばれていて、祖父の頃は『京都の着倒れ』というほど呉服、繊維問屋が軒をつらね、すごい賑わいを見せていたらしいですよ」と往時の京都の町の様子を教えてくれた。
藤田さんは昭和の初めから70年続いた京会席の料理屋に生まれ、平成元年の1989年から4代目女将として店を切り盛りしていた。しかし長年一緒に働き、店の味をつくってきた板場さんが病に倒れたのをきっかけにいったん休業する。
「京都の家庭には『始末をする』という言葉が根づいています。たとえば、大根一本でも皮を厚めに切ってきんぴらにする。葉っぱは菜飯に、まんなかは煮物。食材のすべてを使い尽くして、栄養のあるものをおいしく食べる文化です。そんな知恵や工夫が詰まった豊かな食文化を伝えていきたいですね」と藤田さん。
長い歴史の中で洗練されてきた京料理。一方つつましくも、生活の知恵に溢れた京都の町衆の日常食。その両方を知る藤田さんは、食に関わりながら、一人でもできることはないかと考え、2007年、「すまや 京おばんざい教室」をはじめた。

出汁の香りとねぎの甘さでご飯もすすむ「九条ねぎと厚揚げ、竹輪の炊いたん」。
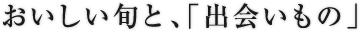
「京都は昔から各地の品物が集まり、そのなかから良いものだけを残してきた。その代表的なものが京野菜でしょうね。おばんざいには旬の野菜を使ったものがたくさんあります」と藤田さん。そこで前章の「京やさい 佐伯」から、冬の京野菜を持ち込んでお料理をつくっていただくことにした。
一品目は「九条ねぎと厚揚げ、竹輪の炊いたん」。霜がふるたびに甘さを増した九条ねぎを余すところなく堪能できる一皿だ。作り方は簡単で、厚揚げと竹輪を出汁がしみこむまで7、8分炊き、やや大きめに切った九条ねぎを入れさらに炊くだけ。ねぎの青味が残るよう炊きすぎないのがポイント。ねぎのとろみには風邪予防の効果があるそうで、佐伯さんたち農家ではこのとろみを「はなたれ」と呼ぶ。「はなたれ」で風邪予防というのが面白い。食べるとネギのとろみが出汁とからまり、とても滋味深い味になる。
もう一品は、聖護院かぶらを使った「かぶら蒸し」。すりおろした聖護院かぶらに卵白と酒、塩を入れて混ぜ、そこににんじん、きくらげなどを加えてあえる。これを器のなかで一度蒸した鯛にかけ、ぎんなんをのせて彩りを入れもう一度蒸す。色が真っ白くなったら蒸しあがり。そこにさらに銀餡をかけ、最後に山葵をのせて出来上がり。鯛の代わりに平目やグジ(アマダイ)などの白身魚を使うことも。どちらかというとおもてなし料理だという。魚のアクを淡白なかぶらが取り込んでうま味に変えている。まさにこれが、食材を組み合わせてさらにおいしくする京都の食の知恵が詰まった「出会いもの」料理だ。

2017年に10周年を迎える「すまや 京おばんざい教室」。それを機に本を出版する予定だ。
「普通のレシピ本じゃつまらない」と内容は現在思案中。
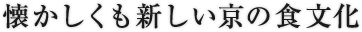
商家が多い京都の家庭では、「おきまり食」というものがあり、月初めはニシンと昆布を炊いた「渋こぶ」を食べる。「月初めだからしぶく節約していけ」という意味だそうだ。月末にはおからを食べる。おからは包丁で切らなくて済むから「きらず」。つまり、月末に「客足が途切れないよう」「財布の中身が切れないように」と食べるものらしい。
最近京都ではおばんざいを食べさせてくれるお店が増え、たくさんの観光客が訪れている。藤田さんのもとには食生活を見直したいという30代の女性の相談が増えているそうで、料理教室では、おばんざいを料理のレパートリーに加えたいという人から、包丁を持つ手もおぼつかない人まで経験を問わず幅広く受け入れている。また、一日体験コースやビジターコースがあるので日本各地や遠く海外からの旅行者も参加しているという。2015年には東京で出張料理教室を開催したところ好評で、今年も行う予定だという。
「千年続いた都は、これからの千年も続いていく」。京都の町中で野菜をつくる人、食文化を守り伝える人など、それぞれが悠久の歴史の中にある自分を当然のように受け止めていることに驚きつつも、節約しながら旬の野菜を煮炊きして食卓を満たしてきた京都の家庭料理が、今のこの時代にぴったり合っていることに気付かされた。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.