

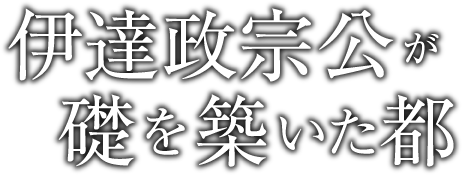
伊達政宗公の御木像。『瑞鳳殿特別御開帳』の期間(2018年1月1日〜2日、5月24日、8月15日)のみ見られる。
また政宗公は肖像をつくる際には両目を具えるよう申し渡したといわれ、そのため御木像には両目が具えてあるという。

広瀬川や七夕祭りなどが歌われ、今なお仙台をイメージさせる歌として広く歌い継がれている『青葉城恋唄』。歌詞の中で繰り返される“杜の都”とは、古くからある仙台市の別称だ。宮城県仙台市は中部にあり、東に仙台湾、西に奥羽山脈を擁する東北地方最大の都市だ。大都市の景観の中に濃い緑と深い歴史を併せもち、多くの人々を魅了してきた。
この礎を築いたのが、後世に独眼竜と呼ばれた伊達政宗公だ。慶長6年(1601年)、青葉山に仙台城(青葉城)を築城し、千代という地名を仙台に改めて、その後400年以上続く都市の歴史が始まった。政宗公は城下町を整備して豊かな国づくりに力を注ぐ一方で、書や茶をたしなむ文化人でもあった。その功績の一つは、仙台の地に上方の桃山文化を取り入れた絢爛で新しい文化を花開かせたことで、“伊達”な文化として今も受け継がれる。
それを象徴する史蹟の一つが、70歳で生涯を閉じた政宗公の遺命により造営された霊屋(おたまや)「瑞鳳殿」。藩祖政宗公が眠る霊廟だ。国宝に指定されていたが1945年の戦災で焼失し、1979年に再建された。極彩色の彫刻や紋様が豪華な桃山文化の影響を受けた廟建築は、創建当時の仙台藩のきらびやかな文化を想起させるよすがとなっている。

もち米が実る水田風景。加美町の辺りで見られる。
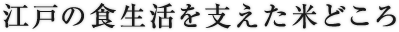
仙台藩は、加賀藩、島津藩に次いで62万石もの石高を誇り、18世紀には実質100万石を超えていたといわれる。北上川や阿武隈川などが流れる仙台平野は、水田に適した低湿地帯だった。政宗公は新田開発、舟運や港の整備を進めて石高の増加を図り、江戸で不足していた米を供給することにも成功する。江戸市中に出回る米の約3分の1は仙台産だったという。
「昔は本石米(ほんこくまい)と呼ばれて、江戸の人々の食生活を支えていたんです」と話すのは、JA全農みやぎの遠山さん。宮城県の米づくりについて聞いた。「作付面積では全国6位、うるち米では「ひとめぼれ」や「ササニシキ」が多くつくられます。もち米は4、5品種つくられますが、昭和33年に出た「みやこがねもち」がいまだに生産の9割を占めますね」
「みやこがねもち」は、“もち米の王様”といわれる新潟生まれの「こがねもち」を宮城県で栽培したものだ。宮城県の寒さが厳しく乾燥する冬と高温にはならない夏の気候に適しており、とくに奥羽山脈など山からの雪解け水が水田を潤す加美町などでつくられてきた。白くて滑らかで粘りやコシが強いとされ、餅や赤飯はもちろん、和菓子やあられの原材料としても使われてきた。
「ハレの日には家庭でよく餅が食べられていたんです」と遠山さんがいうように、宮城では折にふれて餅が食べられ、その種類は100近くもあるとか。あんこやきな粉といったポピュラーなものから、あめ餅やふすべ餅、そしてずんだ餅まで餅を味わう文化が深く根づいている。

もち米でできたあられと「あおばた」のきな粉を混ぜて練る。練りすぎるとお菓子ができあがった時にかたくなるので注意が必要だ。
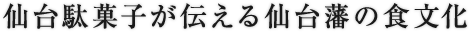
「料理心なきはつたなき心なり」という政宗公の言葉がある。政宗公は三代将軍徳川家光を自ら考えた献立で接待したほど、料理にこだわりをもっていた。仙台藩の米づくりという素地があったから、米の転作作物である大豆生産が今では全国で作付面積2位に位置するほど、さまざまな穀物づくりが盛んだ。
そのことを象徴するような和菓子がある。仙台駄菓子と呼ばれるものだ。「米や大豆といった穀物を使って江戸時代からつくられてきたもので、種類が豊富にあります。政宗公が茶の湯を好んだために菓子づくりが盛んになって庶民に広まったこと、戦の常備食だった糒(ほしい)が余った時にそれを菓子に転用したことで、たくさんの駄菓子がつくられたようです」と教えてくれたのは、「仙台駄がし本舗日立家本店」の森さん。見せてもらった仙台駄菓子の一つ「若草ねじり」は米のおこし種と、「あおばた」と呼ばれる青大豆のきな粉を原材料とする。
政宗公の料理への関心は兵糧の研究から始まったとされるが、後年の太平の世では幅広く食を追求してホヤ、鮭、蒲鉾など郷土の食材を創意工夫して食していたというから、そのグルメぶりは推して知るべし。多芸多才だった政宗公の存在こそが、今も残る郷土色豊かな仙台の食文化を発展させてきたといえるかもしれない。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.