

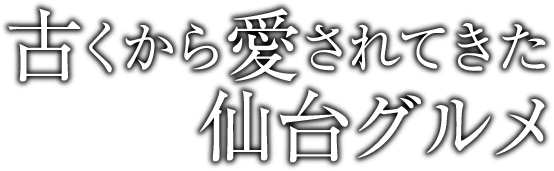
熟練した焼き手によって炭焼きされる牛たん。
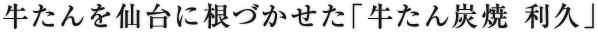
もともと洋食で使われていた牛たんが焼き料理として登場したのは戦後まもなくのこと。今では約100軒もの専門店があるほど仙台名物として定着した。中でも人気を誇るのが「牛たん炭焼 利久」だ。厚切りの牛たんと、それに加え店舗ごとに特徴を出した創作料理で客の心をつかんできた。
牛たんは焼きに適さない部位を切り落とし、柔らかい部分を切り分け、塩を振って味つけし、冷蔵室で2、3日熟成させてから焼く。麦飯とテールスープ、青唐辛子の南蛮味噌漬けとお新香がついた牛たん定食が定番だ。「炭火で表面はパリッと焼き上げてあるが、中はピンク色の完全に火は通らない状態。そうすると柔らかく噛み切れる。この絶妙な焼き加減がうちの心臓部ですね」と泉本店店長の長岐さんは話す。全国に支店が増えた今でも、包丁一本で職人が手作業で仕込んでいくスタイルを守る。
創業店として1987年に誕生した泉本店は、その頃からの常連客も多い一方で、全国から多くの観光客が訪れる。創作料理は洋食和食取り揃え、季節には宮城の海産物や旬の野菜を使ったメニューも並ぶ。東日本大震災で建て替えざるを得なくなったが、それ以前は客同士が肩を寄せ合って食べるような店だったという泉本店は、客とスタッフとの距離が今でも近いという。人間味のある店づくりを大事にしながら、長岐さんは牛たん焼きを「仕事で毎日見ていても何度食べても、また食べたくなる食材。自信をもって県外に紹介できるものです」と答えてくれた。

仙台駄菓子は店舗によってさまざまな味や形がある。「日立家本店」では、写真のようなラインナップ。
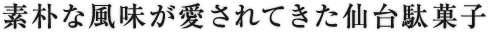
「仙台では昔、“小さい”ことを“ちゃっこい”、“休憩しよう”というのを“おちゃっこすっぺ”といっていたんです」と、仙台駄菓子の小ぶりな詰め合わせ「chacco」を説明してくれたのは「仙台駄がし本舗 日立家本店」の森さん。年配の女性には昔なじみの味だが、「chacco」をつくってからは20〜30代の女性にも新鮮さと可愛らしさで人気が高まっている。
創業当時は飴菓子が中心だったが、今では17種類ほどの仙台駄菓子をつくる。機械による練りではなかなか良い食感が得られないため、職人による昔ながらの手仕事でつくっている。県内ではもう手に入らない材料もあるが、もともとは大豆(きな粉)、餅米、麦粉など仙台の産物を材料としてきた。名前が個性を表す「だるま飴」「しおがま」「かつお節」「月の輪」などがあり、保存料を使わない素朴な風味が口にも身体にも優しい。懐かしさを感じさせながら、若い方には目新しく映るのが仙台駄菓子の魅力だ。
「仙台駄菓子はジャズのようなもの。受け継がれた伝統を残しながら、決まりにとらわれず今の時代のいいものを味に加えて広げていきたい」と森さんが話すように、「日立家本店」では、野菜の自然な色と味が生きるあんこ玉やおこしなども新しく展開している。どれも地元宮城の産物を使ったもので、伝統の仙台駄菓子をさらに発展させたもの。古い形を残しながら新しい風を常にとりいれるその様は、まさに伊達な食文化を象徴するものといえるのかもしれない。

「阿部酒店」が蔵元に特別醸造してもらったオリジナル「亀岡」を始め「宮寒梅」や「日輪田」など酒どころ宮城を代表する蔵元の酒が揃う。

米どころである宮城県は酒どころ。有名な「浦霞」や「一ノ蔵」を筆頭に、「伯楽星」や「日高見」など人気銘柄も多い。今では2軒しか残っていないが、昔は仙台市内にも伊達家に関わりある蔵元が多く存在していたという。「宮城県は20数年前に“純米酒の県”宣言を行って、量は少ないけれどいい純米酒をつくろうと努めてきたんですよ」と教えてくれたのは、100年以上の歴史をもつ「阿部酒店」の阿部さん。宮城県の蔵元は「みやぎ酵母」を使って、酒造好適米「蔵の華」や、「ひとめぼれ」「ササニシキ」などで蔵元独自の特徴ある酒づくりを進めてきた。
宮城県の蔵元は新潟など他県に比べて規模が小さいところが多く、数も少ない。だからこそ蔵元との交流を大事にする特約店「阿部酒店」では、一般の流通にはのらない地酒や限定ものを多く揃える。微発泡している「日輪田 山廃純米うすにごり生」など夏のお酒もあれば、荻野酒造につくってもらった「阿部酒店」オリジナル「亀岡」といった定番商品もある。
「同じ銘柄でも使用したお米、精米歩合、使用酵母、仕込み時期などさまざま。造りで比べることで、より日本酒の世界が広がる。それを認識するきっかけを作ってあげて、興味を示してもらうのがオレの役割」というように、店に並ぶ地酒の話は尽きない。蔵元との交流、そして客へのきめ細かな提案で、宮城の地酒をより楽しんでもらおうとする姿勢には、老舗酒店としての貫禄がにじみ出ていた。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.