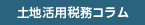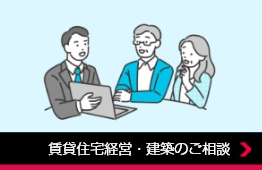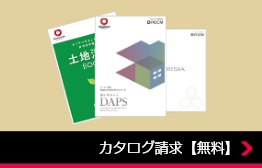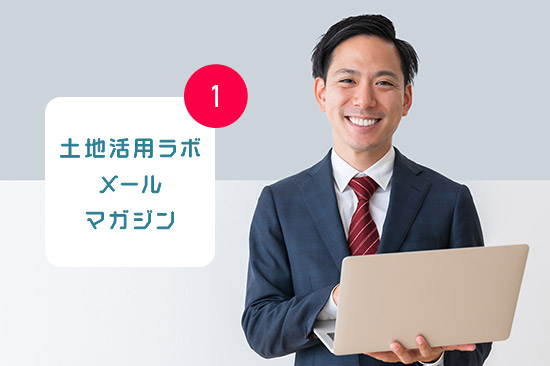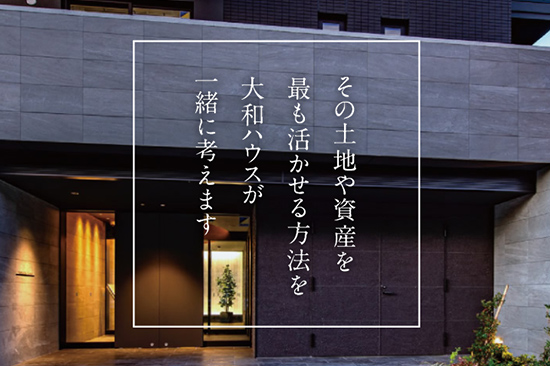コラム vol.471-18
コラム vol.471-18CASE18孫に相続させたい
公開日:2025/06/30
相続を考える年齢になってきましたが、長男は海外生活が長く、いつ戻ってくるかもわからず、長女は結婚後、順調に生活できているようなので、日本に住んでずっと私を支えてくれている孫(長男の子ども)に遺産を相続させたいと考えています。
知人に相談すると、孫は法定相続人ではないから、よく検討するほうが良いとアドバイスをくれました。具体的にはどういう方法があるのでしょうか。

さまざまな理由があって、「孫に相続させたい」と考える人は少なくないでしょう。しかし、このケースでは、長男の子(=孫)にも財産を残したいと考えていても、法定相続人は妻と長男、長女の3名となるため、何もしなければ、孫は財産を取得することができません。
孫に財産を渡すためには、どのような方法が必要なのでしょうか。
生前贈与を行う
まず、考えられるのは、生きている間に孫に財産を渡すことです。つまり生前贈与を行うということです。目の前で本人に渡すことができるので、本人に意思を直接伝えることができ、安心感もあります。また、生前贈与には贈与税がかかる可能性がありますが、1年に1人あたり110万円までなら基礎控除があるため、贈与税はかかりません。生前に毎年110万円ずつの財産を孫に贈与することで、課税されることなく財産を渡すことができます。 生前に教育資金として贈与する方法もあります。1,500万円までは非課税で贈与することが可能です。教育費には、学校に関わる費用(入学金、授業料のほか、学校の寮費、通学交通費、修学旅行代や給食費)、また塾や教材の費用が含まれます。ただし塾や教材などの教育資金は、非課税として認められるのは500万円までとなっています。
相続で孫に財産を渡すには
生前に財産を渡す以外に、相続時に孫に遺すこともできます。
- ・遺言書によって孫に相続する
遺言書の内容は、何よりも優先されますので、遺言書を作成することで、法定相続人ではない人を財産の相続人として指定することができます。
「孫に〇〇と○○を譲る」などと遺言書に記載しておくことで、被相続人の思う通りに相続が実現するでしょう。 - ・養子縁組により親子関係になる
子は相続順位が第一のために、親や兄弟姉妹に優先して相続人となります。つまり、孫を養子にすることで相続人にすることができます。
また、相続人の数が増える分、相続税の控除額が増えるため、全体の相続税が抑えられるという利点もあります。
ただし、ほかの相続人が納得しないままに、養子縁組を結んだ場合は、後々、トラブルが起こる可能性が高くなりますので、十分に調整したうえで行うことが大切です。 - ・生命保険の受取人を孫にする
生命保険に加入して受取人を孫に指定しておけば、間接的にはなりますが、孫に財産を渡すことができます。死亡保険金は、受取人(契約時に死亡保険金受取人として指定されていた人)の固有財産ですから、原則として遺産分割協議の対象外とみなされます。
死亡保険金は、現金で受け取ることができますので、仮に、相続後に相続税の納税(現金で支払う必要があります)が発生した場合でも、納税資金として利用することができます。
遺言作成や養子縁組よりも、手順も簡単で、保険に新規に加入するか、受取人を変更することで手続きが完了しますので、簡単に実行することができます。
ただし、死亡保険金は「みなし相続財産」とされるため、相続税の課税対象となります。さらに、相続人に該当しない場合は、「死亡保険金の非課税枠が適用されない」「相続税の2割加算の対象となる」といったことに注意してください。 - ・家族信託の受託者を孫にする
家族信託とは、財産管理方法の一つで、あらかじめ不動産や金銭などの財産を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せることができる仕組みです。
所有権を受益者(財産から利益を受ける権利を持つ)と受託者(財産を管理運用処分できる権利を持つ)を設定すること(この場合は、受益者を祖父母に、受託者を孫に設定)で、生前に、孫に財産を渡すことができます。
孫に資産を遺す際の注意点
孫に渡す財産が多すぎる場合は、ほかの相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。ほかの相続人に相談することなく、孫に財産の大半を渡すようなことがあれば、法定相続人として保証された最低限の相続分を当然の権利として、主張することは十分にありえます。
孫に財産を渡す場合は、遺留分に注意しながら、生前に家族の同意を得ることがなにより大切なことです。
また、生前贈与加算の対象になる期間が相続発生前の3年間から7年間に変更されました(順次延長)。ですから、生前の贈与時に、110万円を超えていなくても7年以内であれば生前贈与加算の対象となります。
そうなると、孫への相続の場合、相続税は相続税額の2割に相当する金額が加算されることに加え、生前贈与加算の対象になれば、孫が負担する相続税がさらに高くなってしまうことになります。
なお、2024年からは相続時精算課税制度に基礎控除(110万円)が導入されたため、相続時に加算される金額は基礎控除を控除した後の残額となります。ですから、年110万円以内の贈与であれば相続時に課税されることはありません。
孫へ財産を渡す方法はいくつかありますが、トラブルにならないように、ほかの相続人にも十分に配慮した財産の分割や相続方法を選択する必要があります。弁護士や税理士などの専門家に相談しながら進めるようにしてください。