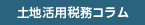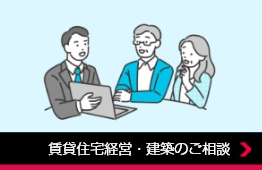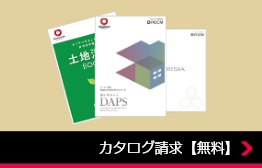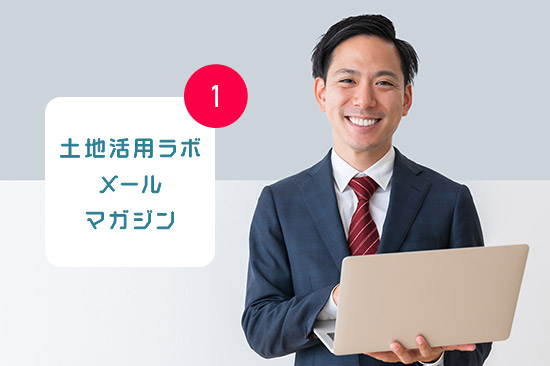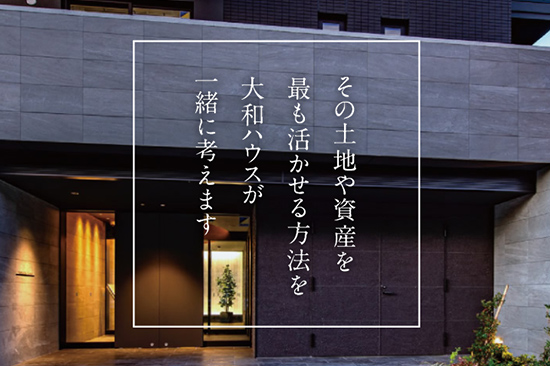コラム vol.471-21
コラム vol.471-21CASE21財産の大半を慈善団体に寄付したいが、遺留分侵害額請求されることが心配
公開日:2025/09/30
ある程度の資産を築き、相続の対策をしたいと考えています。資産は私一人で築いたものだし、老後にたずさわってきた慈善団体に資産の大半を寄付したいと考えていますが、相続人から遺留分侵害額請求をされるのではないかと心配です。

「相続でのもめごとを避けたい」「世の中のために資産を遺したい」と考え、法定相続人以外の第三者に寄付や遺贈を検討し、そのことが逆に、もめごとの原因になってしまうというケースです。慈善団体への寄付の他にも、ある相続人に資産の大半を相続させたい、あるいは、ある相続人には相続させたくないというケースもあるかもしれません。しかし、きょうだい以外の法定相続人には法律上取得することが保証されている最低限の取り分がありますので、注意が必要です。
遺留分とは
相続が発生した際、一定範囲の相続人には、「遺留分」というものが発生します。これは、遺言の内容とは関係なく、被相続人(死亡した方)の財産から特定の相続人が法律上取得することが保証されている最低限の取り分です。
本来、遺言とは相続のトラブルを防止したり、被相続人の思いを実現したりするために用いられるものですが、場合によっては、遺言自体がトラブルの元になることがあります。例えば、本来は被相続人の配偶者や子どもに相続されるべき資産が、事前の相談や説明もなく、遺言によって慈善団体やある組織などに遺贈されることになれば、配偶者や子どもが完全に納得することは難しいでしょう。
このような、本来相続されるべき財産が権利を侵害された状態を「遺留分の侵害」といいます。このとき、遺留分を侵害された配偶者や子どもは、遺産を多くもらい過ぎている人に対して、侵害された部分を返還請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
また、遺留分の返還方法は、以前の法律では、不動産の現物と現金での返還が可能でしたが、2019年の法改正後は、原則として現金でしか返還できなくなりました。土地などの不動産を渡した場合でも、遺留分の請求を受けて認められた場合は、現金を用意する必要があります。
基本的に、遺留分は法定相続分の2分の1です。例外として、直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人である場合には、法定相続分の3分の1になります。例えば、相続人が配偶者と子どの場合、遺留分は法定相続分2分の1ずつの2分の1となりますので、4分の1ずつということになります。
遺言書を適切に活用する
遺留分の制度には、相続人の生活を守るという側面があるため、たとえ、遺言書に「遺留分の請求を認めない」と記載しても、原則として、相続人の遺留分請求を防ぐことはできません。ですから、遺言書を作成するときには、遺留分が請求されることも想定したうえで、財産のどのように渡すかを考えておく必要があります。
ただし、遺留分を侵害するような内容が書かれた遺言書であったとしても、「署名や押印」「遺言能力」など、民法で定められている要件を満たせば、遺言書は有効です。遺言書は形式的に問題がない限り、遺留分を侵害するような内容が書かれている遺言書も法的には有効になります。
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。その中でも推奨されているのは公正証書遺言ですが、日本公証人連合会によれば、令和6年の公正証書遺言は12万8,378件でした(自筆証書遺言は2万件弱)。遺言書の作成件数は、徐々に増加傾向にはありますが、まだまだ遺言が一般的になったとはいえないようです。
「考えている相続のかたちを遺言書に書いても、遺留分を請求されたら何もならない」といった考えがあるのかもしれませんが、遺言書自体は有効であり、自分の思いを遺言に記すのは、大切なことではないでしょうか。
遺言書の「付言事項」で相続人に想いを伝える
遺言書の「付言事項」とは、遺言者が相続人への思い、気持ちを書いた部分のことです。遺言書には、遺産配分をどうするかを書くものと考えがちですが、自分の気持ちを自由に書くことができます。たとえば、財産を慈善団体へ寄付するならば、その理由や思い、残された相続人への配慮、お世話になった人への礼など、ここで書かれた内容によって、被相続人の思いを理解し、相続人の気持ちが変化することがあるかもしれません。ただし、付言事項には法的な効力はありません。
生前に相続人と十分に話し合う
何よりも、相続人と生前に十分に話し合いを重ねることが望ましいといえます。多くの場合、遺言書の内容は被相続人が亡くなったあとに、相続人が知ることになりますが、その場合、内容はともかく、「事前の相談が何もなかった」との思いが先行し、もめる原因になる場合もあるでしょう。事前の相談さえあれば、問題なかったケースもあるかもしれません。被相続人の真摯な思いを伝え、その時点で調整することで全員が納得できれば、相続後にもめることも少なくなるでしょう。
いずれにしても、法的な問題を含んでいますので、弁護士などの専門家に相談しながら、相続への準備をすることが必要です。