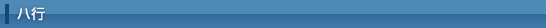
■バーコード 【バーコード(Bar-Code)】
何本かのバー(棒)で商品名、製造会社名、品目などの商品情報を表すシンボル。
■バース 【バース(berth)】
船舶を停泊させるために所定の施設をもった停泊場所。この言葉の引用で、トラックターミナルなどでトラックをとめて荷積み、荷降ろしを行うスペースもバースと呼ぶ
■配送 【ハイソウ】
貨物(商品)を物流拠点から荷受人に送り届けること。特に近距離の域内輸送を指します。
近年は少量多品種、無在庫化が進み、必要なときに必要なだけ納品するという要望が強くなっています。そのためには配送回数が増え効率が悪くなりますので、計画配送や共同配送、一括納品の必要性が高まっています。
■バックヤード 【バックヤード(back yard)】
店舗において陳列する前の商品を一時的に保管しておく倉庫で、一般に店舗の裏側に設けられる。最近は店舗の在庫を極小にするため、バックヤードは縮小化の傾向にあり、配送センターからタイムリーに陳列場へ直接供給するシステムが主流となりつつある
■ハブ&スポーク 【ハブアンドスポーク(Hub & Spoke)】
大都市を拠点として、各地の都市に乗り入れる航空会社の路線運行方式で、アメリカのFedEx社が開発したシステム。“Hub System(車輪の輪)”を意味する。FedEx社の輸送の中心ターミナルはアメリカのメンフィスにあり、アメリカ国内の主要都市で集配荷→メンフィスで集中仕分け→アメリカ国内の主要都市で集配荷を行うことで効率的な輸配送を行う。
■配送料 【ハイソウリョウ】
主に荷物の輸配送について発生する費用。各項目は別途詳細に説明。(1)チャーター料金(1車あたり)、(2)混載料金(1個あたり)、(3)宅配料金(1個あたり)、(4)時間指定料金(トップ便など)、(5)特定荷物料金(クール便、ゴルフ便、スキー便など)
■販売物流 【ハンバイブツリュウ】
物的流通はもともと企業の立場から、販売活動の行われている流通システムの物的な側面を意味する用語で、物流と省略された。ところが物の流れを示す物流という言葉と混同されて、誤解を招くようになった。そこで物流は調達物流、生産物流、販売物流、廃棄・回収物流などとその分野の名称を物流の前につけて物の流れを限定する習慣がついた。消費者物流、ビル内物流、地下物流などはそれである。
■物流 【ブツリュウ(Phisical-Distribution)】
アメリカのマーケティング関係者によって、流通の物理的側面の管理について主張された"Phisical-Distribution"の直訳語である「物的流通」の省略語。商品の供給者から需要者、消費者への供給についての組織とその管理方法およびそのために必要な包装、保管、荷役、輸配送と流通加工、ならびに情報の諸機能を統合した機能をいう。
■物流技術管理士 【ブツリュウギジュツカンリシ】
(社)日本ロジスティクスシステム協会が発行する資格。「物流技術管理士資格認定講座」を修了し、所定の試験に合格した方に「物流技術管理士」の称号が授与される。(前身として「物流士」「物流管理士」の資格がある。) 物流管理者および物流技術者として必要な物流の全領域にわたる専門知識とマネジメント技術を、ロジスティクスのコンセプトに基づき、総合的かつ体系的に把握できるロジスティクス・スペシャリストとしてのスキルが取得できる。
■物流業務委託契約 【ブツリュウギョウムイタクケイヤク】
荷主から物流企業へ物流業務を委託する際に取り交わす契約とその書面をさす。従来、物流業務については見積書を根拠に料金を設定し、電話や直接訪問による口頭指示で業務を進めていたケースが多かった。しかし(1)委託内容が広範になり、責任が重くなったこと、(2)要求する業務水準が高度になり、口頭だけでは伝えきれなかったり、実行できた場合、出来なかった場合の判断基準があいまいになること、3)市場の動向に応じて料金がどちらかの都合でスポット的に上下するなどの不具合が出てきてから、明確にお互いの役割と責任の所在を取り決める目的で作成されるようになってきている。部分的な委託も、全面的な委託も基本契約を交わした上で、覚書で詳細を取り決めることが一般的である。
■フォワーダー 【フォワーダー(Forwarder)】
荷主と輸送会社を結び付けて、ドアツードア輸送を行う業者。輸送機関の経路(リンク)で活動するのがキャリア(船会社や航空会社)であり、リンクの結節部分(ノード)を基盤として活躍するのが運送取扱等を行う業者でフォワーダーと称し、欧米のフレートフォワーダーに相当する。わが国ではこのようなフォワーダー業としては運送取次業、利用運送事業、航空代理店業、海運代理店業、海運仲立業、港湾運送業、倉庫業などがある。
■ベンダー 【ベンダー(Vendor)】
言葉の意味は「売り主」を指しており、消費者から見た小売店、小売店から見た卸、卸から見た仕入先・メーカーとなる。
■保管料 【ホカンリョウ】
荷物を特定の場所に保管しておくことについて発生する費用。保管料には契約方法により多数の計算方法があり、主に次のような項目になる。(1)保管場所を借りる(賃借料)、(2)保管管理をお願いする(保管料)単位:坪(3.3・あたり)、パレットあたり(1.1×1.1m)、立米あたり(1m3)1ユニットスペースあたり(1棚など)、重量あたり(kg・t)、商品1個あたりなど、(3)出し入れの作業をお願いする(入出庫料)、在庫管理をお願いする(在庫管理料)1回あたり、1個あたり、1作業あたり、定期的作業1式あたりなど
■保税蔵置所 【ホゼイゾウチジョ】
外国貨物の積卸し、運搬及び3ヶ月蔵置できる場所として税関長が許可したもの。輸出入貨物の税関手続きを簡易、迅速に処理するために設けられたもので公共的性格を有する指定保税地域の補完的役割を有する。その設置場所は屋内、屋外を問わず野積場、貯木場等露天施設も含まれる。
■保税地域 【ホゼイチイキ】
外国貨物に対する輸入税の賦課を猶予したままの状態で蔵置できる地域。我が国では外国貿易において貨物の輸出又は輸入をするに当たっては全て通関手続きを必要とし、従って貨物の国内への引き取り又は船舶・航空機への積み込みに当たっては、通関手続きを行う間貨物を蔵置しておく施設が必要となる。
■保管 【ホカン】
保管とは、商品を一定期間、倉庫においておくこと。生産と消費との間には時間的なズレが生じます。例えばお米などのように限定期間に作られたものが一年中かけて消費されるものや、メーカーが原材料の安い時期に大量生産しておくケースもあります。
■保管型倉庫 【ホカンガタソウコ】
保管機能を重視した倉庫。メーカー工場の生産倉庫や農水産物の保管に多く見られる。保管物の特性・目的に応じて、冷凍食品や水産物を保管する冷蔵倉庫や、コンピュータを駆使し保管効率・作業効率を高めた立体自動倉庫などもあります
■ボトルネック 【ボトルネック(Bottleneck)】
〔瓶の首の意〕生産活動や文化活動などで、全体の円滑な進行・発展の妨げとなるような要素。隘路(あいろ)。障害。ネック。

