

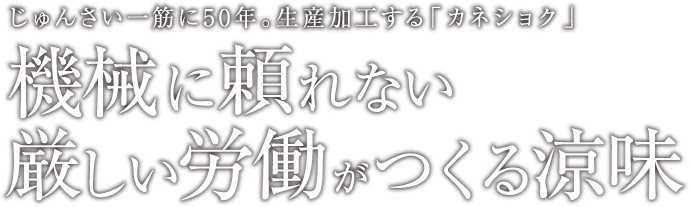
採り子の田村さん達が箱舟を操って収穫する。
箱舟の中は、自分に合うように自前の竿を使ったり、膝あてを作ったりと工夫がこらされている。
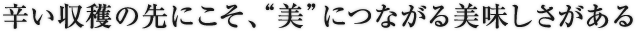
森岳じゅんさいの生産加工販売をしている農家数は、三種町だけで約230戸ある。ほとんどの農家が米づくりなどを兼業しており、じゅんさいのみを生産加工販売している農家は少ない。じゅんさい専業農家として生産から加工販売まで一貫して行う「カネショク」を訪ね、社長の金山松男さんにじゅんさい沼に案内してもらった。水田を改良した4面の沼があり、沼1つにつき、じゅんさいを摘み採る「採り子」と呼ばれる摘み手が2人、箱舟を浮かべている。沼はだいたい30〜40cmで浅い。そこで6尺(約180cm)の箱舟を左手の竿で操って、右手で一つ一つ若芽を摘み採る。水中で爪を使い茎を切りとるのだ。昔は生爪でやっていたが、今では爪を保護する器具を使う。「採り子」の佐々木さんに話を聞くと、「一つ一つ手作業でしかできない仕事なので大変です。7年もやっていると爪が変形してくるんですよ。それに足や腰、膝に負担がかかって辛いですね。でもやっぱり多く採れると嬉しいんです」と笑顔でいう。
沼にいた採り子の中でも一番長く「採り子」をやっているという60代の田村さんは、じゅんさいの採り方について「始めた頃はベテランのおじいさんから、目で見て判断するのではなく、“指で見れ(ろ)”と教えられました。今では手を水中に入れて触っただけでどんなじゅんさいか分かります。ゼリー状のものを私たちは専門用語でノリと呼んでいますが、これがたっぷりついているものを採るんです」。4年ほどやれば、水中の若芽を指先の感覚で察知できるようになるそうだ。すると収穫量が違ってくる。素人では2時間で500gがやっとだが、ベテランの採り子だと2時間で約3kgも収穫できる。
このじゅんさいをどういう風に食べるのか、皆さんに聞いたところ、夏に鶏鍋にして、生じゅんさいをたっぷり入れる料理がいいと口を揃えたように言う。先の田村さんは、じゅんさいは“美”だという。目で見ても風情があって美しい。食べて美味。そして美容にもいい。採り子歴が長いためなのか、その料理法も多岐に渡っていた。和風スパゲティに入れたり、わさび醤油につけていただけば冷酒とぴったり合うと鍋に限らない調理法に、身も心もじゅんさいに尽くしている姿を見た思いだった。

じゅんさいを選別する手つきはためらいがなく、どんどんざるの中にじゅんさいが溜まっていく。
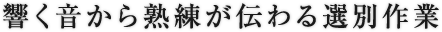
摘み採ったじゅんさいは、工場に運ばれて選別作業に入る。工場の中では、小気味良いタン、タン、タンという音が響いている。5名の女性がじゅんさいの余分な茎をステンレスの小刀で一つ一つ切り落としながら選り分けていた。同時に小さなゴミや絡みついている雑草を取り除いていく。ベテランになればなるほど、そのスピードは早く、リズミカルにこなしていく。生じゅんさいの選別作業では、サイズが特選、M、無選別とわかれる。特選は若芽の中でも新芽で揃っており、Mサイズは新芽からさらに育って芽が大きくなっているものだ。無選別はそれが混じった状態のもの。この選別作業は、昔から変わらない手法で行われてきた。機械化できればよいが、それが難しいのがじゅんさいの生産加工だ。沼1つにつき8人の採り子がほしいというが、高齢化や農家数の減少といった問題に直面していると金山社長は語る。
ひたすら小刀で茎を落とし、次にサイズの選別作業に休まず入った一人の女性職人に苦労を訪ねてみた。「1日中同じ姿勢で座っているから、夜は足がパンパンにむくんでしまいます。それが辛いけれど、やっていると楽しい。無心になりますよ」と手を休めず話をしてくれた。

森岳じゅんさいは、ツルンとした喉越しを楽しむもの。
淡白な味わいが、さまざまな料理に涼味を添えてくれる。
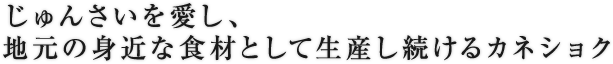
じゅんさいはとても繊細な水草だ。大半が水分で構成されている以上、沼の水質は大きく影響する。いい沼はメダカやドジョウ、タニシなどさまざまな生物が生息している。清らかな水でしか生長しないため、水質汚濁、雑草繁茂、高温、農薬の流れ込みなどで簡単に枯れてしまう。そのため森岳じゅんさいは、環境指標のバロメーターでもある。自身も小さな頃からじゅんさいを採っていたというカネショクの社長金山さんのじゅんさい沼では、白神山地の水をパイプラインで引いている。沼の管理について聞くと「大変なのは、沼に生える雑草です。沼底まで太陽の光が入らないとじゅんさいは育たないけれど、同時に雑草も育つ。じゅんさいの方が弱いので、雑草が混むとお天道様が届かなくなってじゅんさいが育たない」と、金山社長はじゅんさいの栽培の難しさを語る。
さらに、単に水を引けば良いというわけではなく、やはり自然に降る雨も必要なのだという。かの与謝蕪村もじゅんさいを「ぬなわ生ふ 池の水(み)かさや 春の雨」と俳句で詠んでいる。「親父の頃は神主を呼んで雨乞いをしたりしていましたよ。今年(2015年)はこの異常気象で雨が降らない。普通は雨は嫌がられるもんですが、私らは雨を呼ぶ黒い雲が出てくると嬉しいもんです。天然の雨には、酸素が含まれているんですね。だから入梅の長く降る雨がある年は豊作です。ただこればかりは、自然が相手ですから祈るばかりです」。
カネショクはじゅんさい一筋でやってきた。地元では高級食材という意識はない。そこかしこの沼に自生して存在していたので、本当に身近な食材なのだ。その土地で育つ食材と、その食文化を、普段の食卓にのぼらせ続けている。森岳じゅんさいは、生活の一部として、この森岳という風土そのものをその風情と食感で表しているのかもしれない。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.