

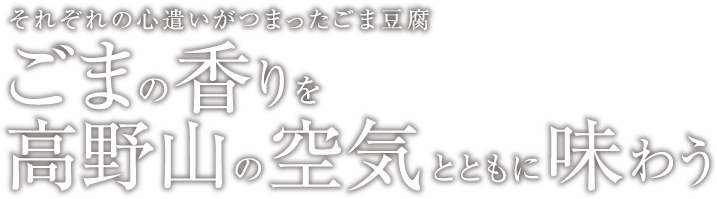
夕食に出される本膳形式の精進料理。食べきれないほどの品数がある。
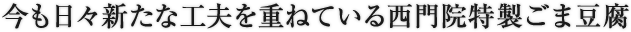
「ここは旅館ではなく宿坊のお寺です。お大師様が今も生きておわして、今もわたくしどもを救ってくださる仏教の場所。いらっしゃる方は信心の方や観光客の方などいろいろですが、旅館に比べて不便な宿坊に泊まり、その雰囲気、またお寺の料理を召し上がられることから何かを感じていただきたい。ごま豆腐もその一つなんです。だから西門院で手づくりしています」というのは住職の奥さん智祐さんだ。西門院の賄いを一手に引き受けて精進料理をつくる。朝食も夕食も、振舞料理にのっとった季節感あふれる精進料理がいただける。しかし、これでも本来の振舞料理の品数や量には及んでいないという。
もともとごまはエジプトには3000年前に、葛は中国に2000年前にはあった食材。両方とも主に薬として食されてきた。そこから今のごま豆腐になるまで、様々な偶然と長い時間が必要だった。西門院のごま豆腐もまた試行の上に工夫を重ねて作っている。「今回のごま豆腐は、黒ごまと白ごまの2つを使っています。醤油と山葵が一般的ですが、黒味噌のタレを使っています。味・タレともに何が一番よいのかを試していると、まだまだ広がる可能性のある料理だと感じます」という。いただいてみると、濃厚な黒ごまの味わいが舌の上に広がり、それに黒味噌ダレが甘く絡む。ごま豆腐とひと口にいっても、さまざまな味わいがあると感じさせられる逸品だ。

歴史を感じさせる「かさ國」の店構え。生菓子の製造風景を見られるようになっている。
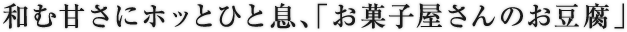
和菓子屋さんが作るごまの豆腐と聞いて、珍しさに「御菓子司 かさ國」を訪ねた。江戸時代に僧侶の笠などを扱う行商人だった初代の名にちなんでおり、参拝客の増えた明治時代に和菓子屋となった。店内は、外国人から日本人まで大勢の客がひっきりなし。というのもお店の一角に喫茶コーナーがあり、そこで店頭の「やきもち」などの朝生菓子や、看板商品「みろく石」「高野通宝」などがいただけるからだ。その一つに、「お菓子屋さんのお豆腐(胡麻)」があった。
「昔はお土産のなかった高野山で時代の流れで、高野豆腐からごま豆腐がお土産として定着しました。うちでもその材料で、和菓子屋ならではのごま豆腐を作れないかと4代目が考案したんです」と教えてくれたのは、忙しい中迎えてくれた5代目となる小林章義さん。常連客に一番人気の商品で、ごま豆腐では使わない砂糖が入っている。「葛菓子に近い味わいですかね」と言われながらいただくと、優しい甘さの後にごまの風味が香ってくる上品な逸品だ。「このお豆腐も山内寺院の方々からご進物としてつかっていただいています。お大師さんのおかげで、お寺さんとのつきあいができ、皆さんにも買っていただける。だからお大師さんには感謝しかない」と話してくれたその心が、まさに地域で古くから愛されてきた所以かもしれない。

山葵あんがかかった「花菱」特製のごま豆腐。料理屋だからこそのひと工夫が凝らされている。
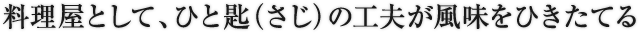
手のぬくもりを大事にしている高野山料理の「花菱」。精進料理だけでなく、魚介や肉を使った会席料理、人気のお好み弁当まで扱う日本料理は幅広い。近隣でとれる旬の食材を活かした数々の料理は、まさに目食で見た目にも華やかだ。それでもその本当の魅力は、都会では伝わりにくいという。「高野山の空気の中で心を洗われながら食べていただくことに意味があるのだと思います」と女将の育子さんは話す。
4代目には、基本的に王道を守り、その中で料理を進展させていくという信念がある。精進料理で出されたごま豆腐には、その工夫が凝らされている。通常、ごま豆腐は山葵と醤油で食す場合が多い。しかし「花菱」の「胡麻豆腐山葵あん掛け」は、ごま豆腐に下味を少しつけ、竹ベラで気長に25分ほど手練りすることで、粘り気を出す。さらに本来のごまの香り、舌にのった時の味わいを活かすため、だしと黒川本家の吉野葛を入れ、本山葵の葉で香りづけした山葵あんでいただいてもらうのだ。ひと口含んでみると、だしのきいたあんとごま豆腐の2つの優しい味わいに山葵の爽やかな風味が広がる。それはまさに、女将の「この高野山の地を踏んで、お腹を満たしに暖簾をくぐってくださった。心からようお参りくださいましたという気持ちです」というおもてなしの心に通じる美味しさだ。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.