

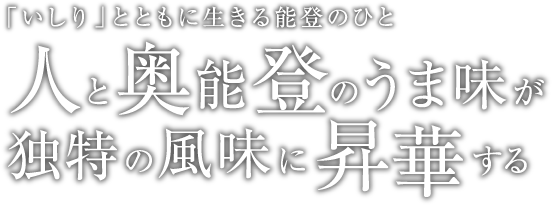
ベンジャミンさんは「能登は、水がおいしい。それにどの季節も山菜や魚、
新しい食材に出会えるからおもしろい」という。能登でしか味わえず、
能登らしい食文化を映した料理は、能登イタリアンと呼ぶ。
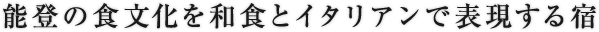
波の穏やかな日本海を見渡せる高台に、民宿「ふらっと」はある。「いしり」を使った料理をいただけるということで訪れた。
「ふらっと」は、オーストラリア人のシェフ、ベンジャミンさんと能登町に生まれ育った智香子さん夫妻が営む1日限定4組の民宿。能登の恵みをふんだんに使い、夕食は、ベンジャミンさんがその日手に入る食材で仕立てるコースのイタリアン、朝食は和食が用意される。訪れた日の夕食で自家製「いしり」が使われたのは、大根のスープ、タラのグリルなど。ひと口食べただけで、深いコクと素材そのものの味わいがまろやかに広がる。ベンジャミンさんは「「いしり」はうま味が濃い。隠し味に使うと他の食材そのもの味を引き出してくれる」という。
実は能登半島は農産物の南限・北限の地でもある。珠洲市のシイタケ、穴水町の栗。米もとれる。ワラビやフキなど山菜は山から調達できる。敷地の畑では柚子や野菜なども無農薬で育つ。智香子さん夫婦は、それらを余すところなく料理にいかす。柚子ならば調味料、塩、果汁、ジャム、種で化粧水までつくってしまう。「いしり」だけではない、糠でサバを漬けた「こんかさば」などの発酵食も豊か。「山も海も川も平地もある。環境が揃って、伝統や保存食、発酵文化が育ってきた。こういう場所はほかにない」と智香子さん。能登という地域の個性が皿の上の料理に結実している。

朝食に出る海餅(かいべ)。「いしり」で炊き込んだご飯を囲炉裏で焼き上げたもの。
イカのうま味とカリッとした香ばしさがたまらない逸品は、「さんなみ」から受け継いだ。
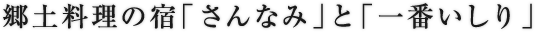
そもそも「ふらっと」が「いしり」を使う背景には、智香子さんの両親の存在が大きい。両親は、食通に知られた郷土料理の宿「さんなみ」を営んでいた。その宿があった場所は、現在の「ふらっと」が引き継いでいる。父親は、全国で唯一「いしりの匠」と石川県から認定され、母親も農林漁家民宿おかあさん100選の最初の10人に選ばれた。舟盛りなど豪華な食事が客へのもてなしだとされたバブルの頃に、早くから家庭の外には出なかった「いしり」の料理を郷土料理としてきちんと世の中に出し、能登の食文化の伝承に尽力してきた2人だ。
その一つの形が、「一番いしり」にある。通常「いしり」は、1年で3回しぼり、混ぜて使うことが多い。中には、一番は生醤油のように、二番は煮物、三番は漬け物にと使い分けする場合もある。しかし「いしり」の匠は、3年寝かせて1回しぼるのみ。うま味はもちろん一番しぼりに濃縮されている。この製法を智香子さん夫妻は忠実に受け継ぐ。しかし同じやり方をしても同じ味になるとは限らない。その時の気候などの微妙な変化を見極めていくのが、発酵技術の難しいところ。「自分たちの「一番いしり」を漬けてから4年を迎える。目指す味は分かっとる。父の助けを借りながら、そこにたどり着けるようにするだけ」という智香子さんからは、両親への敬愛の念がうかがえる。

あたたかく迎えてくれる「ふらっと」のベンジャミンさんと智香子さん。
取材期間中、雨があがったのは門に立ってもらったこの時のみ。
宿全体は、四季のうつろいが楽しめるように、落葉樹や常緑樹などが配されている和の趣。
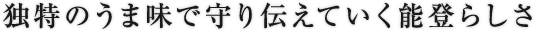
「スープが口に入ったとたん、皆わっと驚く。これが「いしり」のうま味なんやねって。「いしり鍋」のように伝統的な調理法だけでなく、イタリアンのように逆に違う方法で表現することで認識しやすくなる。ニューヨークでベンのスープを出したら、いつものスープの味が明らかに違うと感じて、これは何?っておっしゃられる。最初の「いしり」との出会い方によって印象が変わる。だから「いしり」の良さをどう伝えていくかが大事」そう言う智香子さん夫妻の郷土料理を求めて、国内や海外から食への意識が高いお客様が宿に通う。夏は半年先の予約でうまる時も。さらに、地元の能登に住むお客様も訪れ、「いしり」の使い方に驚いて改めて関心を持つ人も多いのだ。 「能登の気候、自然、産物でしかできないことがある。「一番いしり」がそう。この土地でしか味わえない。それが残ってきたし、地域の個性に繋がっていく。この能登らしさを次に残していくのも私らの役目です。ぜひ能登でしか味わえない郷土料理を食べに来てほしいですね」 夫妻の能登ならではの食文化を継承していく信念、そして手間と時間をかけたあたたかなもてなし。「さんなみ」の郷土の味を受け継ぎながら、2人なりの郷土料理へのアプローチは続く。そこで活躍する「いしり」は、まさに能登の風土と人となりが醸し出した名物なのである。
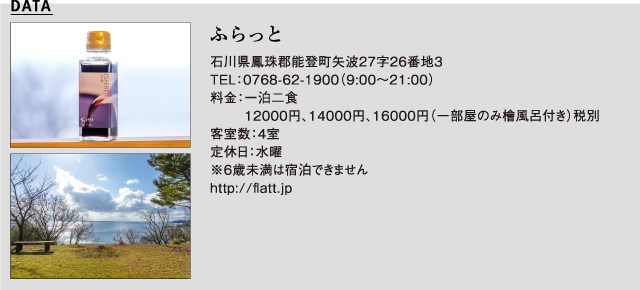
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.