

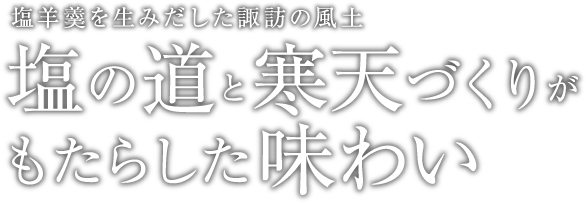
諏訪大社下社の神楽殿。古事記によれば、出雲の国譲りに反対した大国主神の息子、
建御名方神が諏訪にやってきたという。
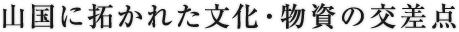
八ヶ岳や北・中央・南アルプスなど、神々しいまでの峰々が人々を魅了する長野県。その美しい風景ばかりではなく、644年の開山と伝えられる「善光寺」などの名所旧跡にもこと欠かない。ことに、今回訪れた諏訪地方は、出雲の国譲りに由来する「諏訪大社」を擁した神話の地。また、中山道と甲州街道が交差する五街道中でも珍しい宿場町でもあり、交通・物流の要衝としても大切な役割を果たしてきた。
諏訪湖の周辺に4つの境内地があるという形態もさることながら、「御柱祭」など全国に名を知られながらいまだ謎の多い神事を行う「諏訪大社」に代表されるように、諏訪の地にはその街道と風土が育んだ独自の文化がみられ、歴史や民俗を愛する者のロマンをかき立てる。また、諏訪や近隣の塩尻は、日本海と太平洋から暮らしに欠かせない塩を運ぶ、"塩の道"の拠点でもあった。
街道を通じて、信州の中央部、諏訪へと集まった物資や定着した技術、文化。「諏訪大社」下社春宮の門前で、人々に愛されて続けている塩羊羹も、実はそんな諏訪の歴史と風土から生みだされたものだった。

農閑期の畑地で寒気にさらし、凍結させたり、融解させたりを繰り返しながら、
2週間ほどかけて乾燥させる。冬の畑が、磯の香りに満たされる。
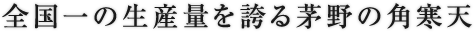
茅野市は寒天製造の中心地。生産量もさることながら、天保12(1841)年頃からの長い歴史がある。だが、テングサなどの海藻を原料とする寒天の製造が、なぜ信州で発展したのか。市を代表するメーカー・松木寒天産業の松木修治社長を訪ねた。「昔のこの辺は冬になると出稼ぎにいくか、行商に出るかしかなかった。行商で関西に行った小林粂左衛門という人が技術を持ち帰って始めたんです」
テングサを煮つめてろ過し、固めたのが生寒天。いわゆるトコロテンだ。それを寒気にさらし、凍結と融解を繰り返しながら乾燥させると寒天になる。寒さが厳しく、空気も乾燥した諏訪なら、もっといいものが作れる。粂左衛門にはそんな気持ちがあっただろうと松木社長は語る。
こうして作られる天然寒天は、角寒天と呼ばれ、棒のような形状も信州産の特徴になっている。関西では糸寒天が主流だったそうだ。しかし現在は、製品のほとんどが工業的に生産される粉寒天や糸寒天になり、天然の角寒天はわずかになった。粉寒天も角寒天も無味無臭で、成分を分析しても両者に大きな違いがあるわけではない。「それでも、下諏訪の老舗和菓子店、新鶴本店さんなどもずっと角寒天を使い続けています。分析しきれない違いがあるのでしょう」 天然の角寒天づくりは大切に受け継がれ続けている。

天保年間にはすでに塩を扱っていたという(株)丸多田中屋の現当主は百瀬博子さん。料理教室の主宰でもある。
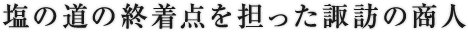
「敵に塩を送る」という言葉がある。上杉謙信が敵対関係する武田信玄に塩を送り、塩不足の窮地から救った。史実かどうかは諸説あるようだが、逸話からは内陸で塩を確保することの苦労がうかがえる。信州には沿岸部から塩を運ぶ"塩の道"があった。日本海と塩尻を結んだ千国街道、北国街道はよく知られる。そして、太平洋側のルートが目指したのは諏訪だった。諏訪で代々、塩や大豆の卸商を営んできた老舗・丸多田中屋の百瀬博子さんはいう。「昔は塩のことを鰍沢(かじかざわ)と呼んだそうです。山梨県の鰍沢まで大豆を運んで、塩と交換していたんですね」 富士川を船で運ばれてきた塩は、鰍沢で陸に上がり、馬で諏訪まで運ばれた。戦後、丸多田中屋は塩から手を引いたが、塩を扱う店は多い時で界隈に23軒ほどあったらしい。
現在、百瀬さんは料理教室を主宰する一方、敷地内にある蔵をリノベーションした完全予約制の手打ち蕎麦と会席料理のお店を切り盛りしている。その蔵にはかつて大豆や塩が積まれていた。また、お店で使用している器は、百瀬さんの曾祖父が収集し、蔵にしまっていた伊万里焼や九谷焼だ。「明治から戦前にかけて、ひいおじいさんやおじいさんの頃が一番栄えていたようです」百瀬さんの暮らしには、塩の道の終着点だった諏訪の栄華が今も息づいている。
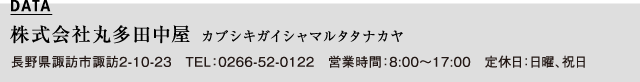
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.