

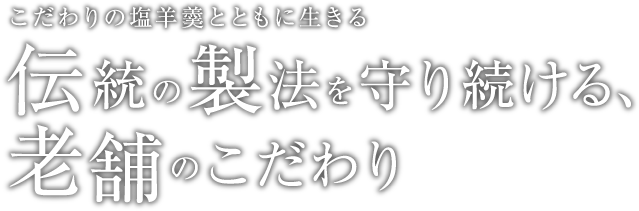
歴史を感じさせる新鶴本店。諏訪大社下社秋宮の門前をゆく観光客も、
その風情ある店構えについ足を止める。
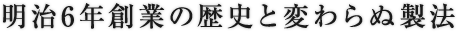
朝の下社秋宮門前。女性がお店の前を掃き、暖簾を掲げる。その光景は、風格ある店構えとあいまって、映画のワンシーンのようだ。新鶴本店は、明治6(1873)年創業の老舗和菓子店。諏訪地方の名物・塩羊羹の元祖といわれ、そのほのかな甘みと絶妙な塩加減は、全国の甘党を魅了する。
「一番は、小豆の風味を引き出すということだったと思います」 羊羹になぜ塩を使ったのかという質問に、5代目となるご主人、河西正一さんは穏やかに答えた。「お汁粉に塩を入れたり、甘いものに塩を使うことはそれほど珍しいことではない」としながらも「信州名物の漬物は塩が必要ですし、魚がくるといえば塩漬け。塩イカなんていうものもあります。塩がない山国だからこそ、思い入れも深く、いろいろな使い道があったのではないかと考えています」
塩を入れても、普通の羊羹と作り方に大きな違いはない。ただ、昔ながらの製法を守り続けている。現在の羊羹はアルミの包装材で包むことにより、格段に賞味期限が延びた。だが、新鶴本店の場合、その方法を導入しようとすると羊羹そのものが変わってしまうという。だから、昔ながらの製法で、賞味期限も夏場は5日間、他の季節は1週間。「おいしく召し上がっていただくためには、こうしてやっていくしかない」 透明感のある薄墨色の塩羊羹、その繊細な姿の内には頑固なこだわりが秘められている。

かまどで加熱しながらかき回す「練り」と呼ばれる作業を終え、
型に流し込まれる塩羊羹。型は「舟」と呼ばれる。
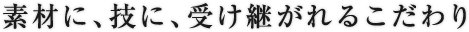
店の裏手にある工場では、職人さんが2人、大きな鍋に付きっきりで「練り」と呼ばれる作業に取り組んでいた。煮溶かした寒天を鍋に注ぎ、そこに粉状にした小豆と砂糖、そして少量の塩を入れ、加熱しながら、「えんま」と呼ばれる櫂で25分ほど、かき回す。原料の寒天は、昔ながらの配合で製造を依頼している。コシが強いという特徴があり、それをかき回し続けるのは容易なことではない。
時々、かまどには薪をくべる。この火加減も代々受け継がれてきた職人技のひとつだ。最初は白い鍋の中身が、加熱するにつれて小豆色に染まっていき、いい香りが立ち上る。小豆は、ゆでて皮をむき、あくをとってジャッキでしぼる。しっかりと皮をむくことで生まれる白さが、塩羊羹の独特の色味を醸している。温暖化の影響で全国的に小豆の色が濃くなってしまったときには、塩羊羹の色あいも変わってしまい困った。練り上がった羊羹は、「フネ」と呼ばれる型に流し込まれて、固まるまで1日置かれ、翌日店頭に並ぶ。その日に作ってすぐに売るというわけにはいかないのでたまに売り切れがでてしまうこともある。この日は鍋8つ分くらいを練るとのことだった。1つの鍋から80本ほどの羊羹ができるという。

水墨画を思わせる淡い色合いが塩羊羹の特徴。
その見た目は、そのまま繊細な味わいを表しているかのよう。
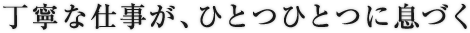
塩羊羹のほかにも、新鶴本店には売り切れ必至の人気商品がある。「新鶴もちまんじゅう」だ。職人さんが毎日、石の臼で撞く餅に、小豆の滋味豊かな餡がくるまれている。新鶴本店の開店は朝8時半だが、もちまんじゅうの販売は9時半から。それだけ、手間がかかるのだ。さらに、本当にもちと餡だけでできているので時間が経つと固くなってしまうこともあって、あまり数を作ることができず、午前中で売り切れることが多い。幻のまんじゅうとまでいわれるゆえんである。
店内には、このほかにも薄く焼いた皮で餡をくるんだ「千代皮」、地元の造り酒屋と協力して作った「万治のほろよい」といった多彩な生菓子が彩りも豊かに並ぶ。餡は、皮のむき加減によって3種類くらいを用意して使い分けているのだという。「羊羹にしろ、ほかの餡にしろ、うちの考え方というのは、小豆を美味しく食べるということ。小豆の風味を活かすことを大切にしています」
塩羊羹をはじめ、製品の作り方はこれからも変えるつもりはないという。「薪がずっと確保できるのかとか、気がかりはありますけど。寒天も職人さんが高齢化していますが、最近若い人が少し増えてきたようです。しばらくは大丈夫だよって仕入れ先からは聞いています」といって河西さんは笑った。
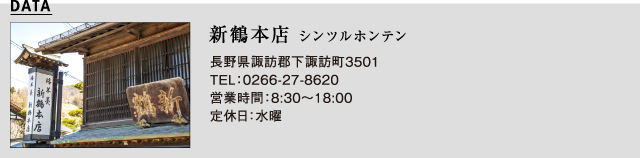
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.