


筑後川と合流する小石原川。希少なオヤニラミやゲンジボタルが生息する。
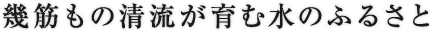
「博多」駅からJR鹿児島本線で、「基山」駅に。そこから甘木鉄道レールバスに揺られること約45分。ワンマン車両がレール上を走る通称「甘鉄」の車窓からは、のどかな田園風景が広がる。降り立った「甘木」駅が朝倉市の中心だ。
今回訪ねた朝倉市は、阿蘇山を水源として有明海に注ぐ九州地方最大の筑後川を境に、久留米市と隣接する地域。豊富な水が湧く広大な扇状地であり、上流に小石原焼の産地をもつ小石原川や佐田川など、筑後川に注ぐ多くの支流が市内を通る。
とくに佐田川は、市内でも11カ所がホタル大発生地として知られるほど水のきれいな川だ。6月も中旬を過ぎた蒸し暑い夜、佐田川支流の上流へ行くと、ホタルが渓流のせせらぎの音の中で、美しく乱舞していた。夜の帳が降りるにつれて舞うホタルが増えていく。その幻想的な光景に魅了され、車で毎年見に来る地元の人も多い。
そんな清らかな川の一つで採れるのが「川茸」だ。清流でしか育たない高級珍味として知られる食材の背景を訪ねた。

秋月城の本門として建っていた黒門。
移築されて、秋月藩祖黒田長興公を祀る垂裕神社の参道に建つ。

『朝倉や 木の丸殿にわかをれば 名のりをしつつ 行くは誰が子ぞ』
後の天智天皇である中大兄皇子の母斉明天皇が朝鮮半島の百済の国を助けるために、この地に仮の宮である朝倉宮を構えた後、崩御した。その喪に服して詠んだといわれる歌である。
朝倉市には、朝もやの濃い明け方の風景に古代の面影を追いたくなるような、歴史ロマンをかきたてるものが多く存在する。
邪馬台国があったといわれるのも朝倉や甘木のあたりだ。それは定かではないとはいえ、この一帯には弥生時代から人が暮らしを営んできた。国の史跡でもある平塚川添遺跡公園や、日本最古といわれる大己貴(おおなむち)神社、古墳、神社仏閣など、その痕跡はそこかしこにひっそりと息づく。
特筆すべきなのが、黒田官兵衛ゆかりといわれる秋月地区だ。「筑前の小京都」と呼ばれ、黒田官兵衛の孫にあたる黒田長興公が秋月藩として治めた。苔むした風情に包まれた秋月城跡や当時の暮らしぶりを伝える武家屋敷などが残された界隈は、桜と紅葉のシーズンに多くの人が訪れる。しかし初夏の青紅葉に彩られた黒門や杉の馬場通りもまた趣深く、この地で受け継がれてきた歴史を静かに伝えてくれる。

三連水車は、200年以上この地の田に水を供給してきた。
水を通す時には、きちんと神主による祈祷が捧げられるという。

朝倉市を歩いていると、ところどころで幹の太いクスノキに出会う。九州地方にはクスノキの巨樹がとても多い。安長寺や須賀神社にはそれぞれ女樟、男樟と呼ばれる縁結びの神木が見事な樹勢でそびえている。樹齢百年以上は軽くあろうかと思われるクスノキが豊かに枝葉を広げられるのも、地下水が豊富にあるためだ。清流を保つには、上流に深い山や森の存在が欠かせない。山の木々に水を一時貯めておく大事な役割があることを人々は知っており、大事にしてきた。
朝倉市の人々の暮らしの糧の一つに、田がある。この田は、山から湧き出る小川の水だけでなく、筑後川からも水をひいている。江戸時代前期に筑後川をせき止める水門の山田井堰が築かれ、岩盤をくりぬいてつくられた堀川用水が、そこから水を運んでいる。しかし一部の土地は筑後川や堀川より高い位置にあるため、水を容易にひけなかった。そのため自動回転式の水車がつくられた。それが国の史跡に指定された堀川の水車群である。江戸時代につくられてから、5年ごとに新調されているが、いまだに田の水は水車によって汲み上げられ、その水が樋を通り田に注がれる。6月中旬を過ぎると、そのために水車をまわす。取材時はまわっていなかったが、そろそろ水を通す時期。地元の人たちが暗きょを掃除してきれいにしていた。ゴットンゴットンと音をたててまわる水車は、田植を告げるこの地の風物詩だという。
長く受け継がれて来た暮らしに息づく古くからの人の知恵は、自然への敬意に基づいている。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.