

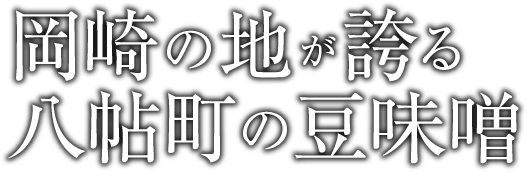
岡崎城と徳川家康公銅像。岡崎城は徳川家康の祖父である松平清康が本格的に築城した。
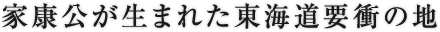
一級河川矢作(やはぎ)川の東側にある岡崎市は、豊田市とともに西三河地方の核をなす街だ。肥沃な平野部にあり、旧石器時代から人々が暮らしを営んできた。戦国時代に入ると松平氏の勢力下に置かれ、岡崎城の礎が築かれた。1542年、ここに幼名竹千代、後の徳川家康が生まれた。そのため江戸時代以降は、徳川家の重臣本多忠勝が治めるなど、家康公の生誕地として別格の扱いを受けることになる。
岡崎は城下町であり、徳川家康が定めた東海道五十三次の一つ、岡崎宿があった。岡崎宿は駿河国府中宿に次ぐ規模を誇っていた。それを表すのが、江戸時代に日本最長と称された矢作橋だ。矢作川にかかる橋で、通るのは東海道である。矢作橋は度々架け替えられており、現在は16代目といわれるが、往時の見事な姿は広重や北斎の浮世絵などで見ることができる。
この矢作橋にはおもしろいエピソードがある。後の豊臣秀吉となる少年、日吉丸が矢作橋の上で寝ていたところ、野武士の一団が通りかかり、頭領が日吉丸の頭を蹴った。これに怒った日吉丸は、詫びていけと物怖じしなかった。この時の頭領が小六正勝、後に秀吉の家臣となって活躍した蜂須賀正勝であり、秀吉と正勝との最初の出会いだったといわれる。後世のつくり話ともいわれているが、この逸話を伝えるために矢作橋の袂には「出合之像」が建てられている。

「カクキュー」のレトロモダンな外観。観光の記念写真にぴったり。
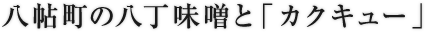
岡崎城に向かって矢作橋を渡ると、味噌の香ばしい香りが漂う。岡崎城西へ八丁(約870メートル)の距離にあることから八帖町(旧八丁村)と呼ばれる一帯は、八丁味噌の工場があるところだ。もともとこの地方では矢作大豆と呼ばれる良質の大豆の生産が盛んで、花崗岩質の地盤からは矢作川の伏流水がきれいな泉となって湧き出していた。また、矢作川の水運によって吉良地方の塩も入手しやすかったため、味噌づくりに適していた。その昔ながらの製法を伝えてきたのが、「カクキュー」と「まるや八丁味噌」の老舗だ。
今回取材したのは、1645年創業で19代続く「カクキュー」。1560年桶狭間の戦いで敗れた今川義元の家臣早川新六郎勝久は武士を止め久右衛門と改めた。(早川家には以前から豆味噌を造る技術があり、三河武士の兵糧にもなっていたという。)江戸時代には出荷量の約1/3が江戸へと送られ、みそ汁や焼き味噌などの料理に使われていた。明治時代には宮内省御用達にもなった。ほかにも著名人が自ら愛用し、あるいは贈答の品としたという貴重な資料が多く残る。例えば、三島由紀夫、志賀直哉、小津安二郎、藤田嗣治、北大路魯山人、山田耕筰、本多忠勝の子孫である本多家など、その名の枚挙には暇がない。

大豆の旨味がギュッとつまったコクと風味がクセになる味。
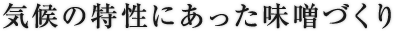
八帖町は矢作川、乙川などの川が入り組んでおり、夏はとくに高温多湿となる地域だ。そのため酸化が進みやすく、水分量の多い米味噌や麦味噌は製造に向かない。そこで水分を少なく仕込む豆味噌づくりが盛んとなった。中でも八丁味噌はより水分を減らして保存性を高めたことで、特有の味や香りが生まれた。
「カクキュー」企画室の早川昌吾さんが八丁味噌の製法を教えてくれた。まず形がよく丸い大豆を選別し、それらの大豆に適度に水分を吸わせる。この時、季節によって吸水率が微妙に変わるため、過去のデータをもとに職人の経験と勘によって管理される。水分を含ませた大豆を釜で蒸し、それを拳大に丸めて味噌玉をつくる。これに麹菌をつけて、麹室(こうじむろ)で繁殖させる。この時の塩梅も職人が厳しくチェックする。その味噌玉を塩、水とともに桶に入れて踏み固め、空気を抜いたら円錐状に重石を積み上げて二年以上寝かせる。自然の気候変化にあわせて熟成させる天然醸造だ。
こうしてつくられる「カクキュー」の八丁味噌は、加熱を行わない生味噌だ。長く仕込むため色も濃くかたいが、塩分控えめで、大豆の旨味あふれるコク、そして酸味と少しの渋味による独特の風味がある。一時途絶えた矢作大豆を復活させて仕込んだ八丁味噌や、有機大豆でつくられたものなどが揃う。また、八丁味噌の風味を生かした赤出し味噌(合わせ味噌)などもつくられている。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.