

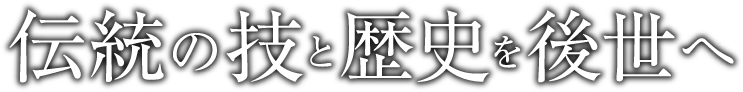
円錐状に積まれた杉桶の上の石。
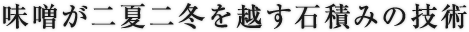
八丁味噌の味噌づくりで、重要な道具の一つが熟成の際に杉桶の上に積まれる石だ。もともとは矢作川の河原に転がっていたものだが、矢作川の上流から大豆を運んでくる際に、船を安定させるために重石として使っていたものだという。江戸時代から現在に至るまで大切に使われてきた。味噌の仕込み重量約6トンに対して、重石ひと山の重量は約3トン。重いもので一つ40〜50キログラムほどで、形もサイズもさまざまだ。
「私は30数年、石積みに携わってきました。大きさが違うので、それをどこに配置するか瞬時に見分けて円錐状に積み上げられるようになるまでには、10年はかかると思います」と話してくれたのは、元石積職人の竹内徹さん。この石積みには職人の経験と技術が生きる。大きな石は下に積み、上にいくにつれ小さい石を積み上げる。さらに難しいのが、一つ一つの重石を斜めにして全体の重心を中心に寄せながら、圧を全面均一にかけるようにしている。こうして積み上げられた石積みは、地震があっても崩れないというほどしっかりしたものだ。この石積みの下に二夏二冬を越してようやく、三河土産にも登場する半固形状の八丁味噌ができあがる。
専門家によると、この技術は、安土桃山時代から活躍した滋賀の石工の集団穴太(あのう)衆の積み方に近いとのことだ。

史料館では、人形を使って分かりやすく展示解説されている。
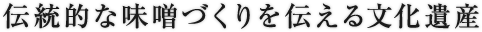
白いラインが強調されたハイカラな外観が目を惹きつける。「カクキュー」の本社は教会風の外観で、昭和初期に建てられた。一方で明治時代に建てられた味噌蔵は、木造の瓦葺で、梁には直径60センチにも達する太い材が使われた城のような巨大な姿。これらは国の登録有形文化財になっている。
味噌蔵に入ると、石の積まれた巨大な木桶が並び、圧巻の光景を見せる。補修を繰り返しながら古いものは江戸時代から使われているというから驚く。
味噌蔵の一部は「八丁味噌の郷・史料館」として一般公開され、明治時代半ばの味噌づくりの様子が、人形を用いて再現されている。当時の蒸し釜やその他の道具、岡崎城登城の際に着用した江戸時代の当主の衣装のほか、昔の看板やラベルデザイン、宮内省御用達に関する資料、八丁味噌を愛した文化人たちの資料などさまざまなものが展示されている。
「カクキュー」では、「八丁味噌の郷」として見学コースを設けており、本社事務所、史料館、熟成蔵を見て回ることができる。

テイクアウトできる味噌カツ。味噌のほろ苦さと豚肉の甘みがほどよくマッチして飽きない美味しさ。
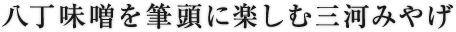
「カクキュー」の「八丁味噌の郷」には、直営売店がある。ここでは豆の産地が異なる八丁味噌をはじめ、赤出し味噌、八丁味噌を使ったお菓子、味噌カツのたれ、インスタントで手軽に味わえる八丁味噌のみそ汁、漬物、たまりや味噌煮込みうどんなど、八丁味噌に関わる商品がずらりと並ぶ。ほかにも地元三河の各種産品が揃っている、バラエティ豊かなお土産どころだ。試食コーナーもある。
テイクアウトコーナーでは、八丁味噌を使ったソフトクリームや味噌カツが購入できる。
早川昌吾さんは「現代の日本の食生活の中では、昔と違って味噌が必須なものじゃなくなってきています。だから味噌企業としては、もう一回家庭の味であるみそ汁の味などにかえって、日本的な食文化を大切にしていきたい。例えば、その入門編として、フリーズドライタイプの八丁味噌のみそ汁などを開発したりしています。もっと味噌食品の普及に努めていきたいですね」と話す。
毎朝みそ汁を飲む人には胃潰瘍や胃ガンが少ないともいわれている。海外ではマクロビオティックの食材や料理のコクだしなどに使われるようになり、注文も増えている。八丁味噌は、大豆と塩と水だけを原料とし、無添加で加熱処理もしていない生きた自然食品。旅を機会にシンプルでありながら奥の深い、八丁味噌という文化に触れてみてはいかがだろうか。
Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.