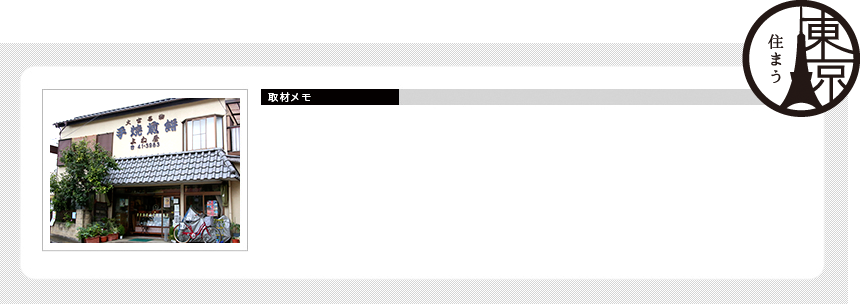独自の視点で、地域の魅力を紹介する“住まうTOKYO”。
交通の要所として50万人以上の人々が暮らす「さいたま市大宮区」。
JR「大宮」駅前を中心とした賑やかで活気のあるエリアから、商業都市のイメージをもたれる方も多いこの街。
一方で、中山道(なかせんどう)の宿場町として栄えた歴史が街の景観に深みを与え、独特の雰囲気を持っています。
さらに、駅の東側には「武蔵一宮氷川神社(むさしいちのみやひかわじんじゃ)」(※以下「氷川神社」)の参道、「氷川参道」が約2kmに渡って伸び、門前町としての歴史も継承されてきました。
参道周辺の「大宮・高鼻町」エリアには、豊かな緑や水辺も多く、どこか清々しい空気と静寂に包まれているのが印象的です。
今回は、「氷川神社」を中心とした心地良い空気の流れる「大宮・高鼻町」エリアをご紹介します。
|
大宮と聞くと、皆さんはどんなイメージをされますか?
JR「大宮」駅周辺の賑やかで活気ある街並みが、多くの方が想像する大宮の表情だとすれば、「氷川神社」周辺の凛とした佇まいは、大宮のもうひとつの魅力的な表情と言えます。 JR「大宮」駅東口から東へ徒歩7分ほど直進すると、両側に鮮やかな緑の参道が見えてきます。南北におよそ2kmに渡るこの参道、「氷川参道」は、右手へ向かえば参道の入り口である一の鳥居、左手へ進めば二の鳥居の大きな鳥居を抜けて「氷川神社」へと通じます。
緑豊かな並木道は、ケヤキ・スダジイ・クスノキ・エノキなどを中心に30種類以上の樹木によって構成されています。
現在も700本近くの大木が立ち並ぶさまは壮観で、一歩参道へ足を踏み入れると大都市とは思えないほど凛とした空気が流れています。 大宮という地名は「大いなる宮居(みやい)」として古来より人々に崇められてきた「氷川神社」に由来するといわれています。
関東各地に存在する氷川神社の総本社である大宮の「氷川神社」は2000年以上の歴史を持つ古い神社であり、大宮はその門前町としても栄えました。 聖武天皇に武蔵一宮と称えられた「氷川神社」は、武家社会となった後も源頼朝をはじめ、 北条家や足利家、徳川家といった時の権力者たちに敬われることになります。 その門前町である大宮はまた、江戸時代に中山道が整備されると、中山道六十九次(なかせんどうろくじゅうきゅうつぎ)と呼ばれた宿場町のひとつ「大宮宿」として大いに栄えました。
|
||||
|
||||
|

 |
 |
||
|
そもそも氷川神社とは、水の神、農耕の神を祀る場として営まれたのが起源とされます。
かつて神社の東側には見沼(みぬま)と呼ばれる無数の沼・湿地帯が広がり、豊かな土壌がありました。その見沼湿地のほとりに位置する「大宮台地」には、こんこんと水の湧き出る場所があり、 神聖な水をたたえるその場所が「氷川神社」となったのです。また、高鼻町周辺は、大宮台地の中でも鼻のように突き出た位置にあったことから、一帯が「高鼻」と呼称されるようになったと言われています。 「氷川神社」は今から2000年以上昔、第五代孝昭天皇の御代に創立されたとの伝えがあり、明治維新を迎えて一層の発展をみせることになります。1868年(明治元年)、明治天皇は御所を京都から現在の皇居の地に移しました。
同年10月28日、この地に行幸すると、天皇自ら祭儀を執り行い、さらに1870年(明治3年)11月1日、再び行幸。この時の行列は京都からの遷都と同様、非常に荘厳なものだったと伝わっています。現在でも60もの年中行事が行われ、初詣や 茅(ち)の輪くぐり、夏まつり、大湯祭(※)など季節の祭礼に大勢の人で賑わいをみせます。 また、「氷川神社」の周囲にひろがる広大な敷地は、明治政府により国有化され、1885年(明治18年)に現在の「大宮公園」が誕生しました。春には「日本さくら名所百選」に数えられる約1200本のサクラが咲き誇り、 樹齢100年を超える赤松林などに囲まれ、四季折々の変化を身近に感じることができます。
(※)12月10日の本祭に酉の市がたつため、十日市(とおかまち)・熊手市とも呼ばれる師走の風物詩。
|
|||
|
|||
|
|||

|

「NACK5スタジアム大宮」に隣接する「県営大宮公園野球場」は、今から80年以上も前、1934年(昭和9年)開業しました。同年秋に開催された「日米野球」では、“野球の神様”と呼ばれるベーブ・ルースや、その頑丈さから“鉄の馬”と称されたルー・ゲーリックもプレーしたという歴史を持ち、埼玉球児の聖地になっています。
現在でも、「全国高等学校野球選手権大会」の埼玉大会が開かれる球場として、周辺住民のみならず、県民にとっての特別な場所でもあります。
|
|||||||||

文明開化によって急速に近代化する明治以降、大宮には武蔵野の面影を求めて多くの文人たちが訪れました。まだ東京帝国大学の学生だった正岡子規は1891年(明治24年)秋に「大宮公園」を訪れた際、今は無き公園内の旅館「萬松楼(ばんしょうろう)」に滞在しました。この時、夏目漱石も松山から呼ばれて滞在。子規は「寒山落木」(1898年)の中でその時のことを詠んでいます。1913年(大正2年)の森鴎外の作品「青年」では、主人公と親友が「大宮公園」で人生論などを語り合う場面や、公園内の料理茶屋などが描かれています。また、樋口一葉や永井荷風が「大宮公園」を作中で表現し、寺田寅彦や田山花袋が随筆の中で称讃しました。太宰治は1948年(昭和23年)4月29日から2週間程この地に滞在し、「氷川参道」を散歩しつつ「人間失格」を書き上げたほか、自死する前日にこの地を訪れていたことが伝わっており、特別な場所だったことが分かります。
「大宮・高鼻町」エリアを歩いていると、
「氷川参道」の高木や巨大な鳥居から醸し出される荘厳な雰囲気に、
太古から連綿と続いてきた歴史が想起されます。
移ろい行く時代の中で、文人たちにも愛されたこの豊かな自然は、
地域住民の植林や保護運動によって形をかえながらも継承されてきました。
こうして育まれてきた自然や歴史が文化となり、
この地に暮らす人々にとってのかけがえのない環境資産として大切に守り育てられています。
いわば、このエリアそのものが後世へと伝え継がれた結晶と言えるのかもしれませんね。
大宮は、教育の街というイメージと、コンサートで度々訪れた「大宮ソニックシティ」がある、開けた商業都市というイメージがありました。
そうした印象を持って改めて街を歩いてみると、抱いていたイメージとは違った一面に気づかされました。
「氷川参道」に一歩足を踏み入れると訪れる静寂、木漏れ日に読書を楽しむ人々、参道沿いにひっそりと佇む老舗のお煎餅屋さんやお団子屋さん。そして時折聞こえてくる野鳥の声。そこには自然を畏れ敬い、未来へ繋ごうとする強くも温もりに溢れた意志を感じることができます。
きっと、時代に寄り添って暮らしてきた人々の歴史が脈々と受け継がれてきたからなのでしょう。