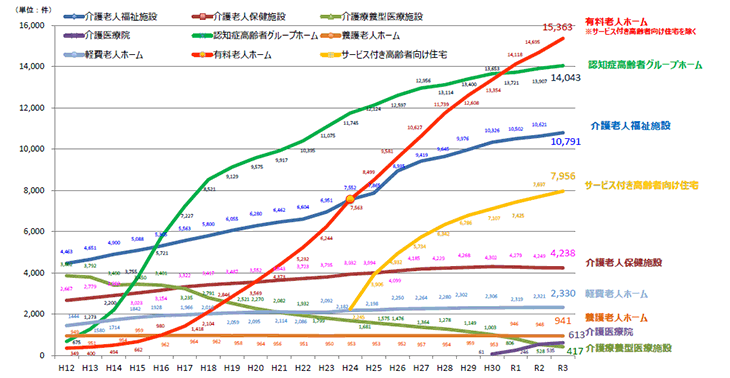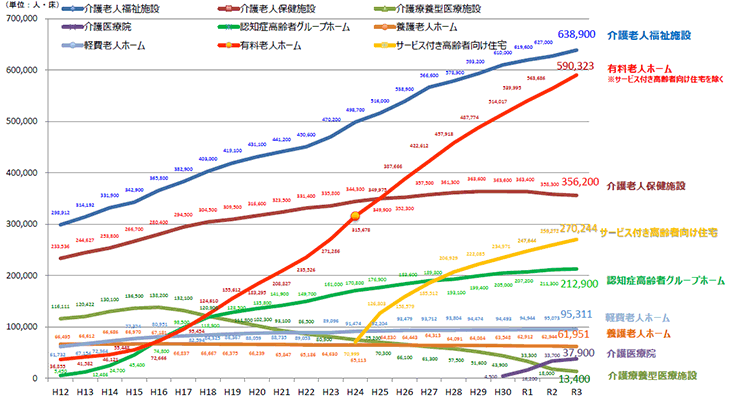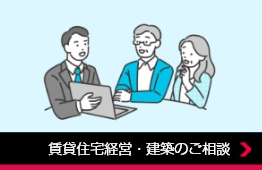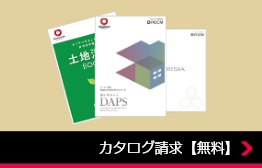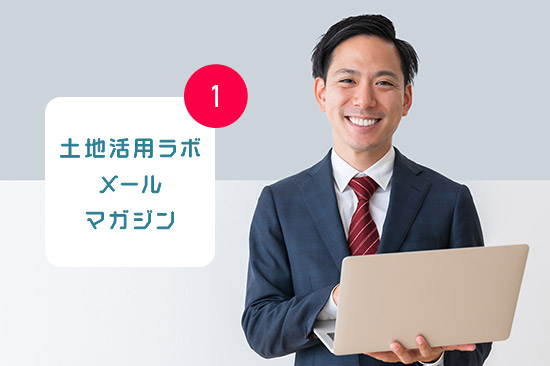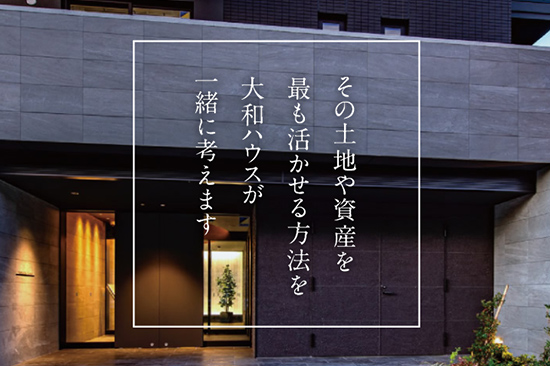コラム vol.556
コラム vol.556高齢者人口の増加とともに、高齢者向け施設の必要性が高まる
公開日:2025/06/30
高齢化が進む中、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など高齢者向けの介護施設や高齢者向け住宅、高齢者向け医療施設などの需要が高まっています。これらの施設は、少子高齢化社会を支えるインフラとして必要とされており、超高齢化社会における社会貢献性の高い不動産とも言えます。
高齢者人口の増加が続く
令和6年版高齢社会白書によれば、65歳以上人口は、「団塊の世代」が65歳以上となった2015(平成27)年に3379万人となり、「団塊の世代」が75歳以上となる2025(令和7)年には3653万人に達するとされています。その後も65歳以上人口は増加傾向が続き、2043(令和25)年に3953万人でピークを迎え、その後は減少に転じると推計されています。
65歳以上が増加する中、総人口は減少していきますので、当然、高齢者率は上昇を続け、2037(令和19)年には33.3%となり、国民の3人に1人が65歳以上となると推定されています。2043(令和25)年以降は65歳以上人口が減少に転じても、少子化が続くことで高齢者率は上昇を続け、2070(令和52)年には38.7%に達して、国民の2.6人に1人が65歳以上の社会が到来すると予測されています。また、総人口に占める75歳以上人口の割合は、2070(令和52)年には25.1%となり、約4人に1人が75歳以上となると予測されています。
人が高齢者になると、介護の問題が出てきます。公益財団法人 生命保険文化センターによれば、年代別の人口に占める要介護認定者の割合は、40歳~64歳では0.4%、65歳~69歳では2.9%ですが、加齢とともに高まり、80歳~84歳では26.2%、85歳以上では60.1%となっています。また、厚生労働省によれば、認知症となる高齢者は、2040年には高齢者のおよそ15%、6.7人に1人が認知症と推計されています。つまり、高齢者人口の増加とともに、高齢者向け施設のニーズが増していきます。
人口減少、高齢者の増加、要介護認定者の増加といった人口問題は避けることはできず、社会全体で対応していく必要があります。その解決策のひとつが、高齢者向けの住まいや介護施設、医療施設などであり、今後、ヘルスケア関連施設の社会的なニーズはさらに増加していくと考えられます。
高齢者向け施設の動向
高齢者人口の増加にともない、高齢者向け施設や住まいを利用する人数も増えています。厚生労働省 老健局の資料によれば、2011(平成23)年は約130万人超でしたが、2020(令和2)年に200万人を超えました。特に、「有料老人ホーム(介護付き、住宅型)」および2011年から制度化された「サービス付き高齢者住宅」を利用する人の増加が目立ちます。この両施設は介護度が比較的低い高齢者の入居が可能で、本格的な介護が必要となる前に、見守りサービスなどを活用しながら、ご入居者同士の交流を楽しむ生活を送る人たちが多いようです。
しかし、厚生労働省の調査によれば、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に入所を申し込んでいながら入所できない「特養入所待機者」は27.5万人(令和4年4月1日時点)いるとされており、平成31年と比較すると減少しているようですが、「有料老人ホーム(介護付き、住宅型)」や「サービス付き高齢者住宅」が受け皿のひとつになっている側面もあるようです。
図1:高齢者向け施設・住まいの件数
出典:厚生労働省「特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 高齢者向け施設・住まいの件数」
図2:高齢者向け施設・住まいの利用者数
出典:厚生労働省「特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 高齢者向け施設・住まいの利用者数」
2021年3月に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」では、「高齢者等が健康で安心して暮らせるコミュニティの形成とまちづくり」と題し、「コミュニティスペース等の生活支援や地域交流の拠点整備など、地域で高齢者世帯が暮らしやすい環境の整備」を実施するとして、次の成果指標を掲げています。
- 成果指標
- ・高齢者の居住する住宅のうち、一定のバリアフリー性能及び断熱性能を有する住宅の割合を、平成30年の17%から、令和12年には25%へ
- ・高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合を、平成30年の2.5%から令和12年には4%へ
政府は不動産へのESG投資を促進
国は、不動産投資におけるESG(Environment(環境)Social(社会)Governance(ガバナンス)の組み合わせ)やSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みを2019年2月から推進しており、ヘルスケア不動産への投資についても、Social(社会)へのインパクトとして、投資の増加を見込んでいます。
その中で、ヘルスケア不動産は、現時点では、投資対象としては広く認知されているとは言えない状況であるものの、超高齢社会の課題解決のための不動産であり、固定賃料の長期的賃貸契約を実現することもできるとしています。すでに、クラウドファンディング等を活用して集めた資金を保育所に投資する事例もあり、今後、ESG投資としての意識が高まり、不動産資産の多様化が起これば、投資家にも変化が生まれ、社会課題を解決する資金としての活用が図られることが期待されています。
図3:ヘルスケア不動産への投資
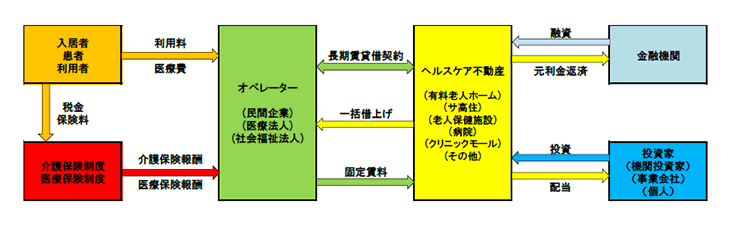
出典:国土交通省「ESG不動産投資のあり方検討会 中間取りまとめ(概要)」
ヘルスケア不動産は、地方創生の観点からも注目されており、いわゆる「ご当地ヘルスケアファンド」も登場しています。不動産の価値が都市部ほど高くない地域においても、医療施設や高齢者住宅などの事業としての価値が高ければ、収益を見込める投資として格付けされることもあり、地方創生のひとつのソリューションとなる可能性もありそうです。