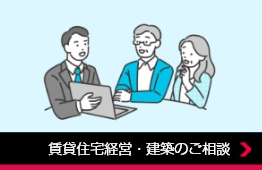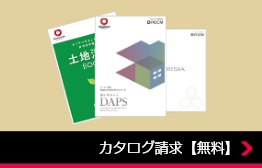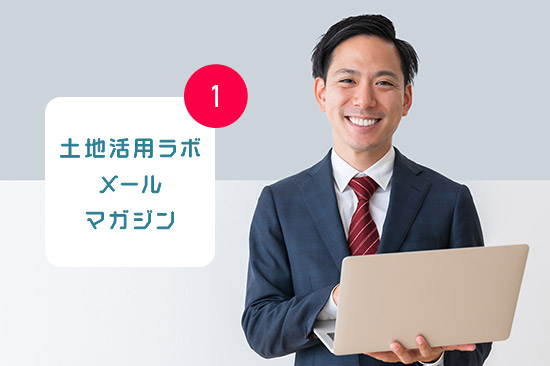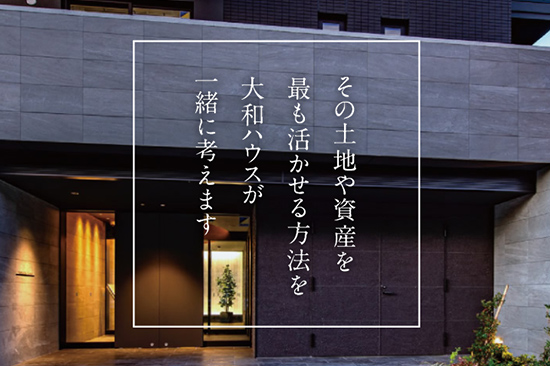コラム vol.550
コラム vol.550最新の人口移動の状況と賃貸住宅需要の展望
公開日:2025/04/30
3月下旬から4月上旬は、進学・就職・転職などの理由で、都道府県を跨ぐ人の移動が増える時期です。都道府県を跨ぐ移動では、多くの場合、住まいの移動をともないます。人口移動の動向をみながら、賃貸住宅需要を考察します。
人口移動の概要
2025年1月31日に総務省統計局より、「住民基本台帳人口移動報告 2024年(令和6年)結果」が公表されました。これによれば、2024年の1月~12月に都道府県を跨いで移動した方(住所を移した方)は、日本人+外国人合わせて252万3249人で、前年に比べて2万1390万人減りました(-0.8%)。2022年以降をみれば、2年連続して微減が続いています。また、都道府県内の移動は268万4497人で、1.3%の減少。市区町村間の移動は520万7746万人でこちらも1.1%の減少となっています。傾向としては、コロナ禍が治まって以降、人口移動数は減少しています。物価上昇、住宅価格上昇、賃料上昇、などから、「STAY」の状況を選択する方が増えているのでしょう。
一方で、2024年1年間で国外との移動(日本人+外国人)では、国外からの転入者は73万5883人で前年に比べて3万5745人の増加(+5.1%)となっています。
都道府県間の移動のあった252万3249人を年齢5歳階級別でみれば、20~24歳が最も多く、次いで25~29歳、30~34歳となっており、この3つの階級で6割近くとなります。
就職、転職、進学などのために移動するという状況が伺えます。
国内の都道府県別転入・転出の状況
転入者をみれば、東京都が最も多く46万1454人、次に神奈川県で23万4097人、次いで埼玉県、大阪府、千葉県、愛知県、福岡県とこの5府県が10万人台です。以上7都府県への転入者合計は145万5711人で、転入者総計の57.7%と半数を超えています。
前年からの増加分をみれば、実数では東京都が7321人(+1.6%)ですが、割合でみれば、福井県が最も増加しており+9.2%、次に大阪府で+3.1%、山梨県が+2.5%となっています。
転入・転出超過数
転入超過数(転入者-転出者)は、東京都が7万9285人と最も多く、最も増加(1万1000人)しています。次いで、神奈川県で2万6963人、埼玉県2万1736人、大阪府1万6848人となっており、転入超過となっているのは東京都、神奈川県、埼玉県など7都府県となっています。逆に転出超過は40道府県、山梨県は前年の転出超過から転入超過へ転じ、滋賀県は前年の転入超過から転出超過へ転じています。最も転出超過が多いのは広島県で-1万711人でした。昨年よりも転出超過数は少し減りましたが、昨年に続き最多となっています。
住まいは世帯で住むことが多いため単純には言えませんが、基本的には、転入超過の場合は、その分、住宅需要が増え、逆に転出超過の場合は、住宅需要が減ることになります。
三大都市圏の状況
東京圏(一都三県)では約13万6000人の転入超過、昨年より9328人転入超過数が増えました。一都三県すべてで転入超過となっており、東京都は3年連続で、すべての道府県との間で転入超過となっています。東京圏への流入は、過去10年を見ても、49万~54万人で推移、転入超過数は、11~14万人程度(コロナ禍期の2020~2022年は9万人前後)で推移しており、この10年で120万人以上増えています。また、東京圏の転入超過数は20~34歳が圧倒的に多く、この世代の転入超過数は拡大しています。首都圏への人口集中、とくに若年層にその傾向があるという状況がわかります。
その一方で、大阪圏(二府四県)合計では、2014年の外国人を含む集計を開始して以来、初めて転出超過から転入超過となりました。ただ、大阪府はプラスですが他はマイナスのため、大阪圏全体での転入超過数(プラス)は2679人と東京圏に比べると多くはありません。
大阪圏からの転出超過数は、圧倒的に東京都が多く、次いで神奈川・千葉・埼玉で、首都圏以外の転出超過はほぼなく、あっても僅かな数です。
名古屋圏では、そもそも中核の愛知県で大きくマイナスとなっており、名古屋圏全体では大幅なマイナスとなっています。
大都市圏では首都圏の一強化が進んでいることがわかります。関西圏では落ち込みは見られませんが、横ばいという状況です。その一方で、愛知を中心とする中京圏は、地価公示の圏域別の上昇率をみても上昇幅が縮まっており(地価公示では名古屋圏と表記されます)、三大都市圏から脱落しそうな様相です。将来、品川~名古屋間でリニア新幹線が開通すれば、時間距離が近くなり、より一層厳しさを増すことが予想されます。
人口移動と賃貸住宅需要
都道府県を跨いだ方を年齢別に見れば、例年通り20代が最も多くなっており、10代後半~20代後半での移動が全体の多数を占めている傾向は変わりません。就職や転職を機に移動する方が多いものと思われます。2023年と2024年の都道府県間移動者数を5歳階級別で比較すれば、15~19歳の移動者は若干減りましたが、逆に20~24歳、25~29歳、30~34歳は増えています。
進学、就職、転職を機に移動する大半の方は、新しい地での最初の住居は賃貸住宅です。今回取り上げた人口移動報告の最新データを見る限り、とくに都市部での賃貸住宅需要は底堅いものと思われます。