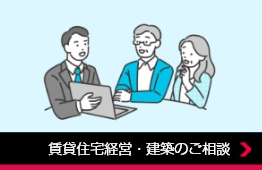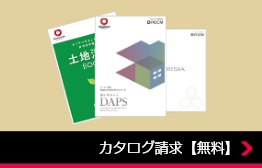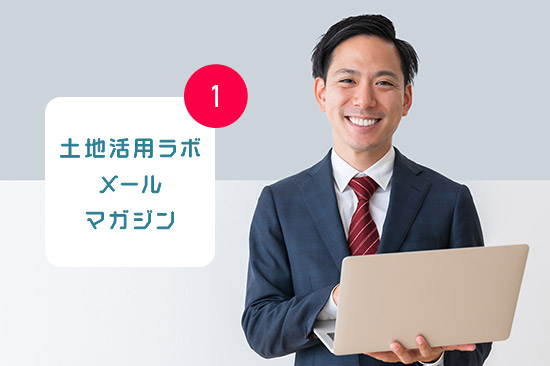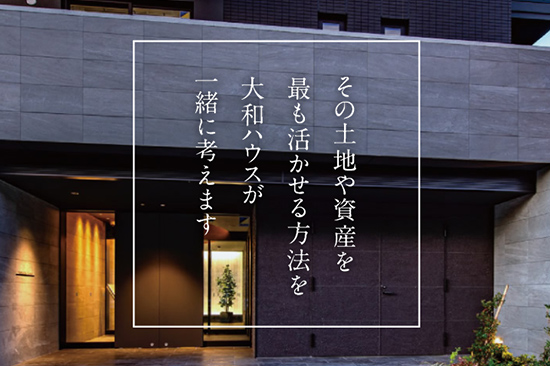コラム vol.559
コラム vol.559最新 2025年路線価を読み解く
公開日:2025/07/31
7月1日に2025年分の路線価が国税庁から公表されました。
土地価格(=地価)は「一物四価」とよばれるように、同じ土地でも評価方法や評価の目的により価格が変わります。4つの評価は、公示地価(地価公示)、基準地価(都道府県地価)、固定資産税評価額、そして今回公表された路線価です。加えて、実際の取引価格が異なることも多く、そのため「一物五価」とも言われます。
路線価は、相続税や贈与税の税額を算定に用いられる地価ですが、「主要道路に面する土地のm2あたりの価格」ということで「路線」価と名前がついています。価格時点は、地価公示地と同じ1月1日で、毎年7月1日に公表されます。2025年の路線価の動向について解説します。
※本文中のデータは全て国税庁より。路線価等の詳細はこちらのWebサイトで確認できます。
宅地の相続税評価額は、路線価または固定資産税評価額をもとに評価
路線価は、「相続税や贈与税における土地価格の算定基準として用いられる地価」ということで、税を扱う国税庁から公表されます。
相続税法では、原則として「相続税や贈与税における土地の価値算定は時価で行うこと」とされていますが、土地価格は時価での評価が難しいため、価額算定を容易にし、また公平に算定するために、財産評価基本通達で、宅地については路線価または固定資産税評価額をもとに評価すると定め、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率が公表されているわけです。
2025年の路線価全体俯瞰
路線価は公示地価(同じ1月1日が価格時点:3月公表)をベースに約80%が目安となります。そのため、変動率(増減率)の傾向は概ね似通うことになります。
全国約32万地点(民有地の宅地、田、畑、山林など:路線価等の評価における宅地とは、住宅地、商業地、工業地等の用途にかかわらず、建物の敷地となる土地のことを指します)の平均変動率は、前年プラス2.7%(前年はプラス2.3%、前々年は1.5%)となりました。4年連続の上昇、また連続して上昇率拡大となり、現行方式となった2010年以降で最高の伸び率となりました。コロナ禍以降続く不動産価格の全国的な上昇を反映した状況となっています。大都市圏の上昇はもとより、地方主要都市へも波及、そして国内外から注目を集める観光地における大幅な上昇も目立っています。
47都道府県のうち35の都道府県でプラスとなっており、全国的に上昇が顕著となっています。
都道府県別の状況
都道府県別の変動率でみれば、前年比で上昇した都道府県は35都道府県、マイナスは12県。また変動率が、マイナスからプラスになったのは4県となりました。
上昇率も拡大しており35の上昇都道府県のうち、31の都道府県で上昇率が拡大しました。
図:都道府県別の平均の路線価の増減率
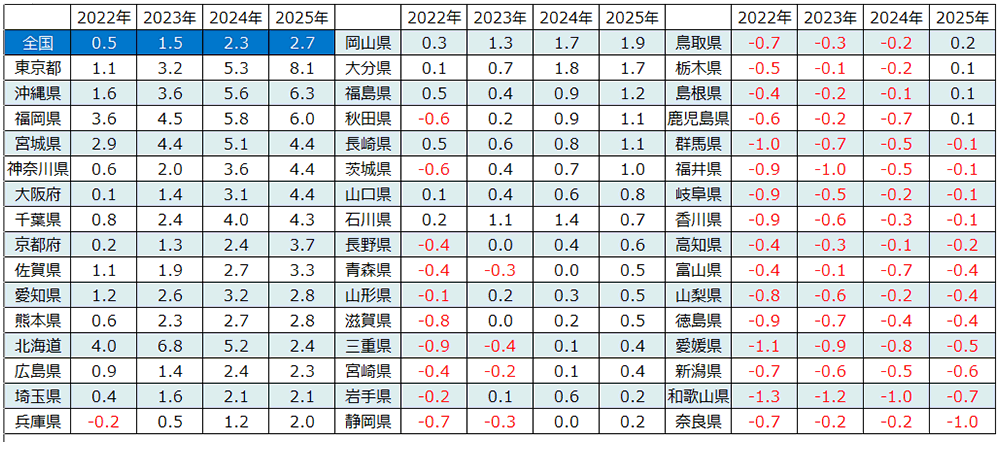
国税庁公表データより作成
表をみれば、上昇率がトップだったのは東京都で8.1%(前年は5.3%)、次が沖縄県で6.3%(前年は5.6%)、つづいて福岡県で6.0%(前年は58%)となっています。それまで高い伸びだった北海道は前年の+5.2%から+2.4%と上昇幅が縮まりました。同様に、宮城県も+5.1%から+4.4%となっています。約10年近く高い伸びを示していたこれらの地域では、上昇幅に一服感が出てきたようです。
新たにプラスとなった4県をみれば、鳥取、栃木、島根、鹿児島と人口が大きく減少している県ですが、中心市街地の再開発が進んでおり、周辺部からの流入が起こっていることが伺えます。これらの地域では賃貸住宅需要も伸びているものと思われます。
路線価方式と倍率方式
実際の路線価の算定は、以下のようになりますので、相続や贈与について関係のある方は参考にしてください。路線価が定められている地域(あるいはその周辺地域)では、「路線価方式」で評価額算定します。計算方法は以下の通りです。
- 1、ベースとなるのは、評価対象地が接する路線の路線価×面積(=地積)
- 2、画地調整率(=評価対象地の形状、たとえば奥行距離、不整形の度合い、角地など)に基づき、価額を補正する率)を掛けて補正する
また、上記以外の土地は、「倍率方式」を用いて価格評価を行います。倍率方式では、固定資産税評価額(3年ごとに評価替えが行われます)に地価事情の類似する地域ごとに定めた「評価倍率」を掛けて算出します。
路線価の上昇で納税額が増える
株価の全体的な上昇は、株を保有する方々にとっては、「喜ばしいこと」でしょう。しかし、「不動産保有者にとって路線価の上昇は喜ばしいことか」と言えば、「そうでもない」と答える方も多いことでしょう。
確かに、保有する(あるいは相続する)不動産(土地)の価値が上がることはうれしいことですが、「相続税や贈与税における不動産の算定の基準」となるのが路線価ですから、路線価の上昇は、基本的に納める税が増えることになります(控除額を超えている場合)。
特に相続の場合は、いつ起こるかを考えることはなかなか難しいものです。そのため、「急に多額の相続税が必要だが現金が不足している」とならないように、事前の準備を必要しておくべきでしょう。不動産資産の相続対策には様々な方法がありますので、不動産を相続する可能性のある方は、土地活用で実績のある大和ハウスなどの専門家に相談することをおすすめします。