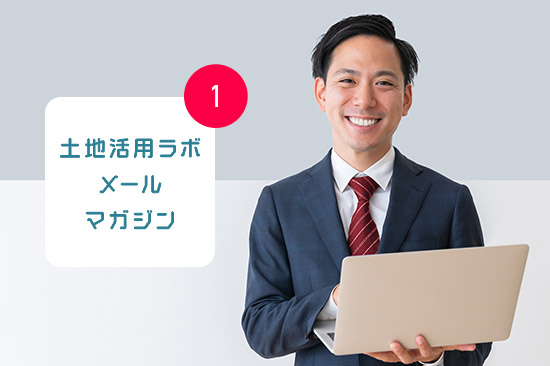コラム No.169
コラム No.169CRE戦略として、不動産を戦略的に活用し企業価値を向上させる「等価交換」
公開日:2025/08/29
企業として事業用不動産を保有しているものの、施設が老朽化したり、利活用されていなかったりする不動産をどう処理すればいいのか、悩みを抱えている企業も少なくないでしょう。
国土交通省の「令和5年法人土地・建物基本調査」を見ても、全国の法人のうち27.6%の企業が土地と建物両方を保有、建物は38.1%の企業が保有していますが、法人が所有している建物の建築時期をみると、最も多いのが1991年から2000年の10年間に建築されたもので21.5%、次いで1981年から1990年の20.6%。1981年から2000年に建築された建物が法人所有する建物の4割以上を占めています。
遊休不動産は当然のこと、老朽化し生産性が低下している事業用不動産は、管理・メンテナンスの費用や固定資産税などの負担が大きく、経営にマイナスになるケースもあります。さらに、単に解体するだけでも費用負担が大きいと思われる不動産を保有する企業もあるでしょう。
特に、都市部の老朽化した建物や未利活用の土地は、本来持つ不動産の価値が活かされていない可能性が高く、企業の収益性にも大きな影響を与えています。
しかし、不動産の利活用や建て替えなどは、大きな資金、費用がかかるため、安易に決断できることでもありません。そこで考えられるひとつの方法が、「等価交換」という手法です。不動産を単に売却するのではなく、資産として保有しながら、しかも資金負担を最小限に抑えながら、新たな価値を生む資産として生まれ変わることが可能になる仕組みです。
等価交換とは
不動産の等価交換とは、別のオーナーが保有する土地にデベロッパーが建物を建て、竣工後に土地の一部と建物の一部を等価で交換する方法のことです。下記の図のようになります。
図
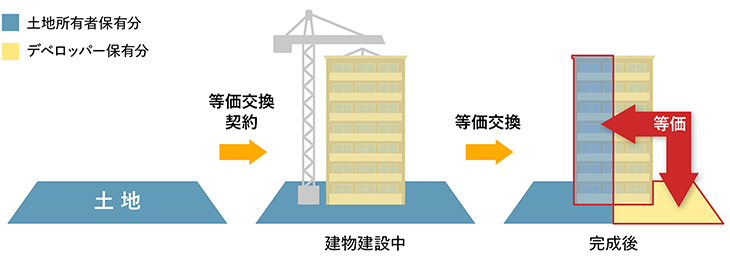
多くの等価交換のケースとしては、デベロッパーが建物資金を負担して建物を建築します。このとき、土地オーナーが土地を貸すだけだと借地事業となり、地代だけを得るだけのビジネスになりますが、等価交換では竣工後に建物の一部と土地の一部を等価で交換します(所有権の割合は、土地価格と建築費のバランスで決まります)。つまり、土地の価値の一部と建物の価値の一部を交換することで、土地オーナーとデベロッパーの両方が土地と建物の所有者になるわけです。
これを企業が保有する不動産にも応用することで、企業が抱える遊休不動産や収益性の低い事業用不動産の問題解決につながる可能性があります。
たとえば、使用していない建物が建つ土地や、老朽化し収益の出ない賃貸住宅を保有している場合など、等価交換の仕組みを使って新築マンションを建築し、マンションの一部所有権を取得することができれば、新たに賃貸収入を得ることができます。駅に近い利便性の高い土地であれば、ホテルや商業施設を建設することで、収益性の高い不動産へと変わる可能性もあります。また、郊外でも高速道路のインターに近い不動産であれば、昨今ニーズの高い物流施設へと用途転換することも可能でしょう。広大な土地でなくとも、隣接地との調整がつけば、大きな施設を建設することも考えられます。保有する土地に自社ビルを建てている場合も、等価交換の仕組みを活用することでより大きなオフィスビルを建て、自社で利用する分以外は賃貸オフィスにすることも考えられます。
少ない資金で不動産を活用可能
等価交換の最も大きなメリットのひとつは、資金が少ない場合でも資産価値を移転できることにあります。保有する土地の価値は変わらないかもしれませんが、デベロッパーが新たな施設をつくることで、将来価値を生み出す不動産に変わることになります。つまり、土地オーナーは、開発のリスクを負うことなく、不動産を活用できます。
等価交換を行うことで、土地オーナーは所有不動産の一部権利を失うことになりますが、建物の一部の権利を所有することができます。土地価格と建築費用の関係にもよりますが、これまでコストばかりかかっていた土地が収益を生む資産に変わることも可能となります。
何より、デベロッパーからの提案によって、自分たちだけでは出なかったアイデアが出てくる場合もありえますので、資産の有効活用という点でも有力な方法といえるでしょう。
合意形成には注意が必要
適切に進めば、メリットの多い等価交換の仕組みですが、必ず土地オーナーの希望通りには進むことが少ないことには注意が必要です。まず、どのような土地でも等価交換の仕組みが使えるわけではなく、土地オーナーが処理したい不動産とデベロッパーが望む土地では、乖離があることも少なくありません。土地の価値と完成後の権利を交換するわけですから、不動産の適正な価値の評価や等価交換時の権利の調整は時間がかかることが予想されます。また、実際に開発を進めるのはデベロッパーであるため、デベロッパーの開発意向が優先されることも多く、土地オーナーの希望通りに進まない可能性が高いことには注意が必要です。
等価交換は、少ない資金で土地を有効活用できる手段のひとつであることには間違いありませんが、等価交換をうまく進めるためには、保有する土地の特性や将来的な市場動向を吟味し、自社の戦略にマッチした選択肢を探す必要があります。
そして、不動産の等価交換の仕組みは簡単ではなく、専門的な知識も必要となりますので、信頼のおけるデベロッパーは当然として、第三者としての専門家や経営パートナーに相談しながら進めることも大切なことです。