土地活用ラボの記事を検索する
土地活用ラボの記事を検索する












































































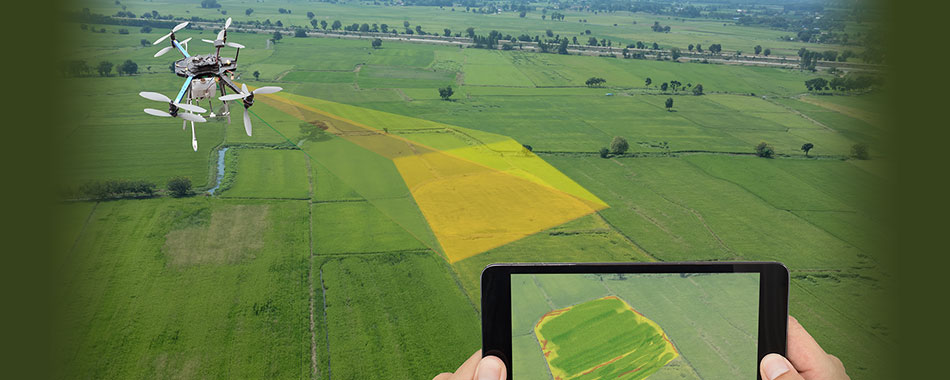







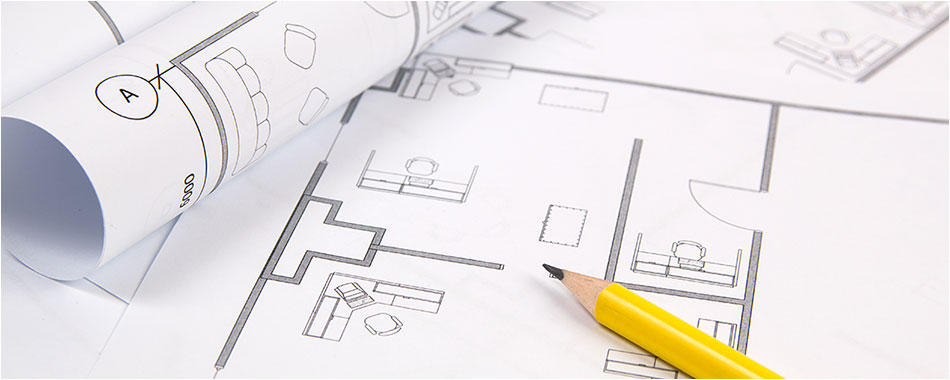

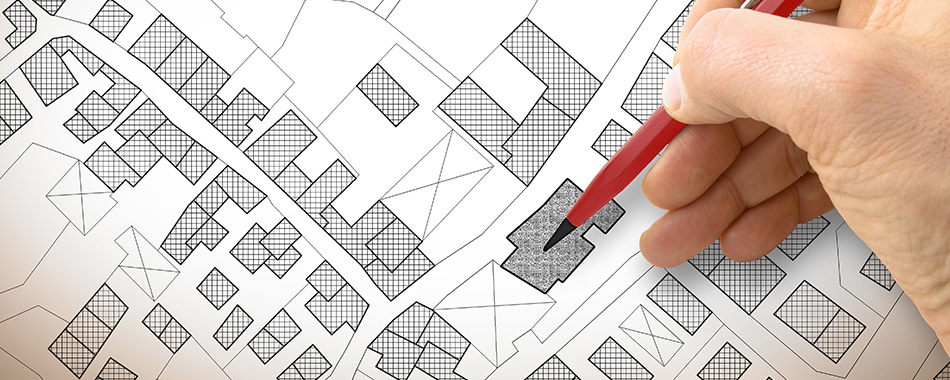



















注目
ランキング
注目ランキング


