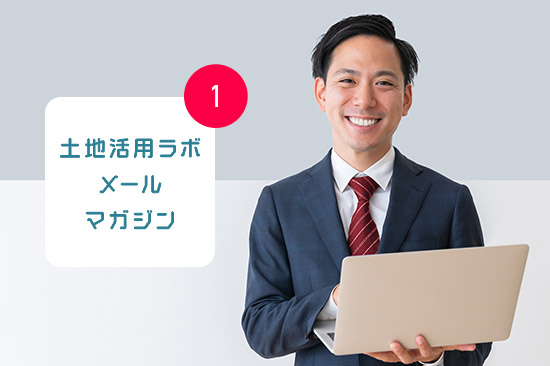コラム No.165
コラム No.165物流2024問題の現在地~環境改善でも課題直面
公開日:2025/05/02
昨年、産業界で最も注目された話題のひとつがいわゆる「物流2024問題」でした。その後の経過と現状が業界団体の調査結果で明らかになりました。最大の焦点だった運転手の労働時間の上限規制は対応が着実に進んでいる一方、ドライバー不足は依然として解消されておらず、課題に直面していることが浮き彫りになっています。
9割超が上限規制クリアの見通し
物流2024問題は、働き方改革法によるトラックドライバーなどの労働環境改善策で、年間の時間外労働時間の上限規制(960時間)を順守することによって労働力不足を引き起こすというものですが、全日本トラック協会は2025年3月末、全国のトラック運送事業者(2,973社)と荷主企業(3,601社)を対象に「物流2024問題」への対応状況の調査結果を公表しました。
この時間外労働時間の上限規制に対して、運送事業者の9割超が「全ドライバー」または「大多数のドライバー」が順守できる見通しと回答しており、対応が進んでいることがわかりました。
図1:時間外労働の上限規制(年960時間)の遵守の見通し(運送事業者)
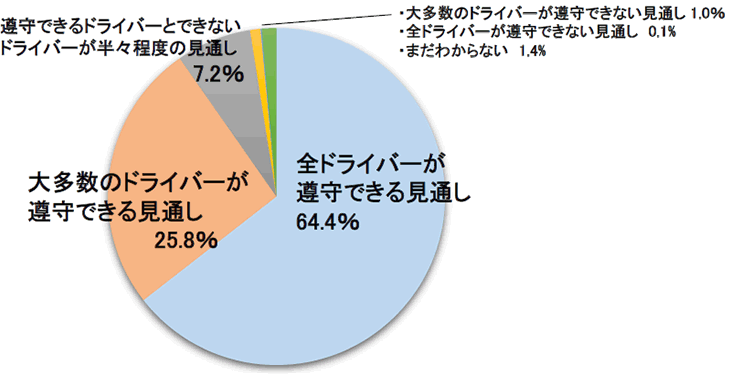
出典:公益社団法人全日本トラック協会「物流の2024年問題対応状況調査結果」(2025年3月)
厚生労働省がまとめた、自動車運転者の労働時間や休息時間の基準(拘束時間は原則1日13時間以内、上限15時間以内、14時間を超える日は週2回までなど)の順守状況は、7割が「守られている」と回答する一方、「守られていない基準がある」と答えた事業者が約3割ありました。守られていないのは1日の拘束時間が約6割と最も多く、次いで1日の休息時間が4割強となっています。
運賃・料金引き上げだがコスト増も
2024問題による運送事業者の好影響としては、①運賃・料金の引き上げができた(68.5%)②労働時間・拘束時間を縮減できた(45.8%)③処遇改善のきっかけになった(36.4%)などとなり、待機時間や荷役作業時間の縮減も27.9%と3割近くに達しています。ただ、ドライバーには朗報ですが、給与改善は事業者にとっては人件費増となります。給与が上がれば、予算上採用枠は削らざるを得ないことにもなりかねません。
図2:物流の2024年問題による「良い影響」(運送事業者/複数回答)
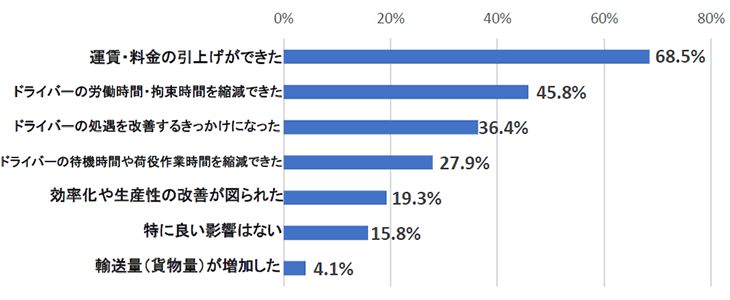
出典:公益社団法人全日本トラック協会「物流の2024年問題対応状況調査結果」(2025年3月)
法令順守のためドライバーの稼働時間を抑制すれば、実働日数は減少して車両の稼働状況は悪化します。調査では運送事業者からは「長距離運送ができにくくなり、輸送量が減少して売り上げにも悪影響を起こした」との回答が寄せられています。このため6割以上の事業者が荷主などと運賃や荷待ちに関する交渉を実施。また、高速道路の利用拡大や運行計画の見直しなどに着手したとの声が寄せられています。
新規制への完全対応は道半ば
一方、荷主企業から見た2024問題の具体的な影響は、「物流コストの増加」と回答した企業が8割近くに達しています。経営サイドから見ると、運送事業者も荷主企業もコスト増という実感は変わらないようです。荷主側では「納品リードタイムの延伸や配送スケジュールの変更」が45.7%、「荷物が運べない、配送遅延などによるリスクの発生」も33.8%と高くなっています。
図3:物流の2024年問題による具体的な影響(荷主企業/複数回答)
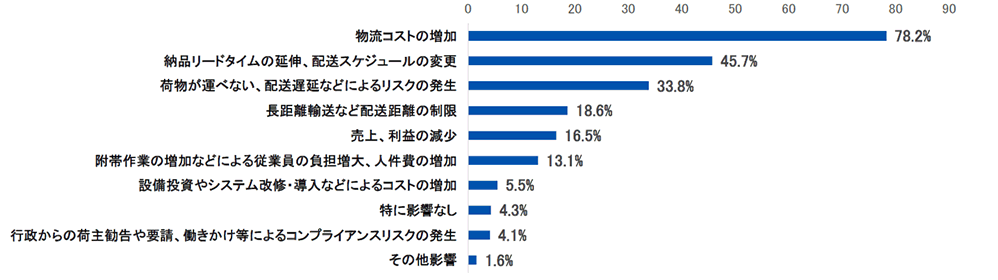
出典:公益社団法人全日本トラック協会「物流の2024年問題対応状況調査結果」(2025年3月)
トラックドライバーの労働環境改善に欠かせないのが、荷待ち・荷役時間の削減です。荷主企業の対応状況をみると、程度の差(「積極的に」15.7%、「ある程度」36.9%)はありますが、半数以上が取り組んでいます。しかし今後取り組むかどうかは、「わからない」も含めれば47.4%。時間削減に積極的な企業と消極的な企業の割合は拮抗しているのがわかります。
待ち時間の発生状況は、1時間未満が51.5%。ほぼ発生していないと答えた企業が38.9%あり、9割は1時間未満または発生していないということになります。前述した取り組み状況で時間削減の対応が二分している背景には、労使ともに1時間未満は許容範囲と考える現場の雰囲気があるのかもしれません。
全日本トラック協会は、2024年問題への対応として、適正運賃や労働環境改善など適正取引推進のための業界独自の自主行動計画を設けていますが、この計画を知らないと答えた荷主企業が6割を超えています。また荷待ち・荷役時間の短縮を掲げた「物流効率化法」に関しては、「知っている」との回答が6割を超えている反面、「公表されたことを知らない」が約4割となっています。法律があることは認識しているが、その内容にまで関心が向いていない、ということでしょうか。
図4
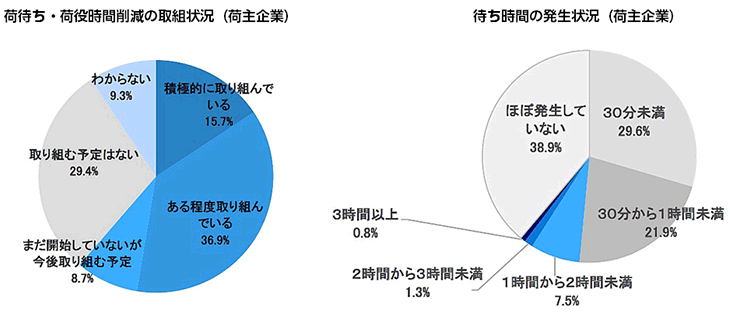
出典:公益社団法人全日本トラック協会「物流の2024年問題対応状況調査結果」(2025年3月)
3,600もの荷主企業となると、企業の規模間格差は相当大きなものがあると思われます。物流管理部門を設置している会社が約1割で、部門も担当者も設けていない企業は約6割にも達しています。こうした関連法令、ガイドラインに対する取組について、「取り組む予定はない」と回答した企業が実に3割を超えており、「何から取り組んだらよいかわからない」との声も9.5%あります。トラック運送は物流の大動脈。2024年問題は、1年で全ての課題が解消できるものではありません。従来からの慣習を改善していくのは容易ではないようです。