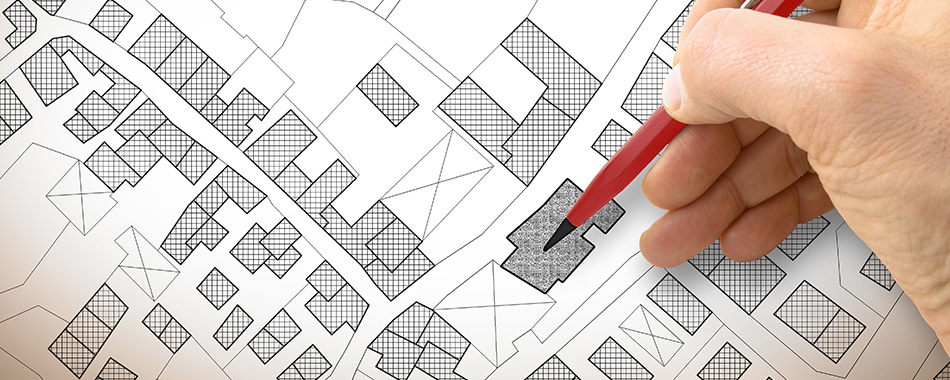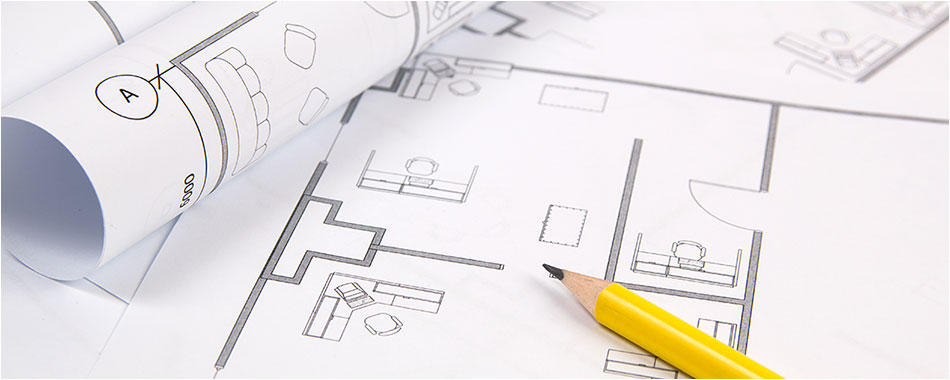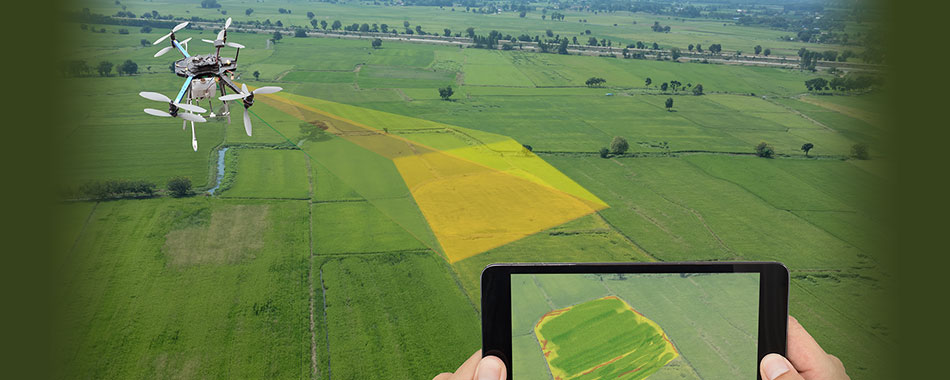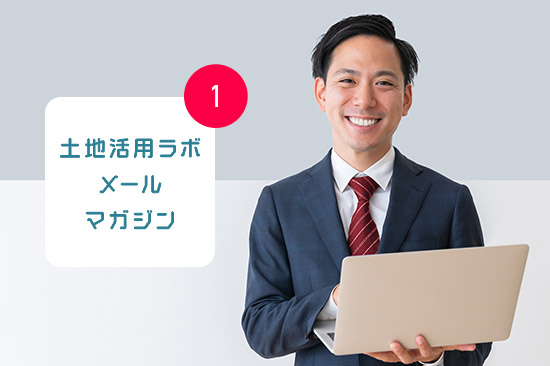コラム No.53-84
コラム No.53-84戦略的な地域活性化の取り組み(84)公民連携による国土強靭化の取り組み【46】人口減少、少子高齢化時代の都市再開発と団地再生等多極的な地方創生の取り組みについて
公開日:2025/05/02
国土交通省が2025年3月18日に公表した「令和7年地価公示」によれば、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇し、上昇率も拡大しています。今回は、人口減少、少子高齢化時代における地域開発の新たな方向性などについて考えてみます。
「令和7年地価公示」によれば、地域や用途により差があるものの、三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)・地方圏ともに地価上昇が継続しており、上昇率が拡大基調にあります。
主な傾向としては、コロナ禍以降活発化した市街地や駅前の再開発もあって、都市中心部など利便性・住環境に優れた地域では住宅需要が堅調であることから、地価上昇が継続しています。また、都市部を中心に、店舗需要も回復傾向が続いており、オフィス需要も底堅く推移しています。さらに、三大都市圏や地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)中心部における地価上昇に伴い、その周辺部においても上昇の範囲が拡大しています。
その他に、LRTが開通した栃木県宇都宮市事例のように、交通利便性の向上などを受けて、沿線部の上昇率が拡大した地点が見られます。また、外国人にも需要の高い北海道富良野市や長野県白馬村などリゾート地では、別荘やコンドミニアムなどの需要が増大し、住宅地の地価が高い上昇となった地点が見られるなど、インバウンドを含めた観光客が回復した観光地や、人流回復が進む繁華街では、地価の大幅な回復が見られます。
人口減少、少子高齢化時代における都市再開発の影響
都市部での地価上昇が堅調である一方、都市部より人口減少の進展が早い地方部を中心に、依然として地価が弱含んでいる地点が見られます。言い換えれば、都市部と地方部の地価格差が拡大してることを意味しており、人口減少時代の将来的な課題が顕在化しているとも言えます。もちろん、再開発によって都市の公共空間の整備が進むことは、地域の代謝を促進し、都市を高機能化することで国際化を強化するとともに、スポンジ化や空き家空き地問題に対するひとつの解決手段として有効であると思いますが、結果的には、高額所得者や資産家等の都市部への集約を誘発し、地域間格差を拡大させているようにも思えます。また、自治体によっては、再開発によって公共施設の統廃合や集約を進めた結果、公共施設が巨大化する、いわゆる官製再開発も散見され、将来的な需要を疑問視する声もあります。
他方で、少子高齢化対策を考えると、都市中心部への若者の流入を促進、賑わいを取り戻し、スタートアップ事業などを誘致することで新たな産業を創造し、周辺部へと普及させていくような多段的な施策も必要かもしれません。中心市街地や駅前再開発のみならず、都市内外の低未利用地を積極的に再生して、若い世代や地域住民が自主的にまちづくりに参画する共助的な 取り組みが求められるところです。
住宅団地再生への挑戦:住宅団地再生推進モデル事業(住宅市街地総合整備事業)
高度経済成長期以降、都市部への急激な人口集中に対応して、全国で多くの住宅団地の開発が進み、現在約3,000か所の住宅団地(5ha以上)が整備されています。住宅団地は、良好な住環境、道路等の都市基盤、長い年月をかけ育まれた豊かな自然環境等を有しているものが多く、地域の良質な社会資産ですが、近年では急激な高齢化や空き家の発生等が見込まれるため、再生が急務となっています。国土交通省は、2025(令和7)年より「住宅団地再生推進モデル事業(住宅市街地総合整備事業)」を開始し、将来にわたり持続可能なまちを形成するため、地域のまちづくり活動、既存ストックを活用した高齢者・子育て世代の生活支援施設等の整備及び若年世帯の住み替えを促進するリフォーム等について総合的に支援する計画です。
これ以前にも、住宅団地再生の 取り組みは都市圏を中心に各所で行われています。例えば、大阪府住宅供給公社は、1965年から開発が始まった西日本最大級の泉北ニュータウン内にある賃貸住宅「茶山台団地」をリーディングプロジェクト団地と位置付け、2014年より建物の老朽化対策、若年者・子育て世帯向け住戸リノベーション、買い物弱者のための移動販売事業者誘致、地元大学と連携した地域コミュニティ再生等の 取り組みを進めています。
また、民間企業による住宅団地再生も進んでいます。大和ハウス工業は、1960年代以降に全国61ヵ所で開発してきた郊外型戸建住宅団地「ネオポリス」を「再耕」(団地を元に戻すのではなく新たなまちの魅力を創出)する 取り組みである「リブネスタウンプロジェクト」を全国8か所で進めています。同社は、住宅の建設だけではなく、「人のつながりをつくりだすこと」をコンセプトに、高齢化や空き家が顕在化している団地内で、コンビニ併設型コミュニティ施設を設置したり、イベントを開催するなど交流を促す環境を整えるとともに、地域内高齢者のライフスタイルに合った住み替え支援や、空いた家をリフォーム/建て替えするなどで、若い世代に新たに入居してもらう施策などで、持続可能な地域再生の 取り組みを推進しています。
内閣府が2024(令和6)年12月24日に公表した「地方創生2.0の基本的な考え方」では、①一極集中をさらに進めるような政策の見直し、②地域の経済・社会、これらを支える人材の力を最大限に引き出す政策の強化、③若者や女性にも選ばれる職場や暮らしを実現する政策の強化、④都市と地方の新たな結びつき・人の往来を円滑化する政策の強化、などに取り組むとしています。
人口減少、少子高齢化時代にあっては、都市中心部の再開発に留まらず、様々なプレイヤーが地域の貴重な社会資本である既存ストックを再生し、都市や地域の活性化、世代間のコミュニティを再編する活動にも、目を向ける必要があると思います。