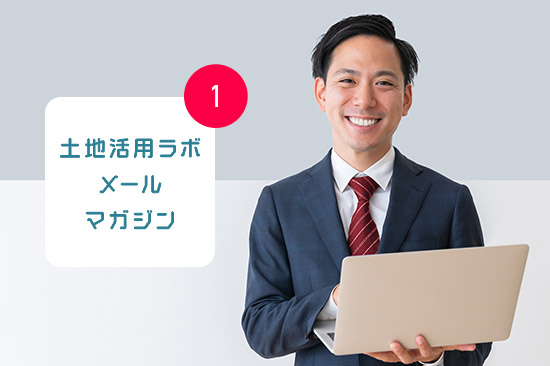コラム No.170
コラム No.170令和6年度の証券化対象不動産の資産総額は約66.6兆円に~令和6年度「不動産証券化の実態調査」の結果を公表~
公開日:2025/09/30
国土交通省は、不動産証券化の実態把握を目的とした「不動産証券化の実態調査」結果を公表しました。この調査は、各種スキームを対象に取得・譲渡実績を集計したもので、証券化市場の全体像を把握する基礎資料とされ、今後の政策立案や投資動向の分析にも活用されています。 2024年度末時点で、証券化の対象となった不動産と信託受益権の資産総額は約66.6兆円となり、前年度の59.8兆円から大きく増加しました。
不動産証券化とは
不動産証券化とは、一般社団法人 不動産証券化協会によれば「土地や建物などの不動産等を裏付けとした証券を投資家に向けて発行する仕組み」のことで、この仕組みを通じて、不動産所有者は資金調達の多様化や財務体質の改善、リスク分散が可能になります。また、投資家にとっては、少額から不動産に投資できる、投資先を分散できるといったメリットがあります。
具体的な仕組みとしては、不動産等の原資産所有者(オリジネーター)が、キャッシュフローを生みだす特定の不動産等(原資産)を自身のバランスシートから切り離して、倒産隔離(企業が倒産した場合でも、その影響を他の企業や資産に及ぼさないための法的・経済的な仕組み)された「特別目的事業媒体(Special Purpose Vehicle:SPV)」に売却し、当該不動産から生まれるキャッシュフロー(賃貸による収益など)を裏付けとした出資証券や組合出資持分、債券などの有価証券などを発行し、第三者の投資家に販売する仕組みです。
投資家はSPVが発行した証券(不動産証券化商品)を購入し、SPVはそこで得た資金をもとに、借入れの元利払い、投資家への配当などを行います。
SPVが発行する証券には、デット(債券などの負債)やエクイティ(株式・出資などの資本)、その中間の性質を有するメザニン(英語で中二階の意味)などの形態があります。
図1
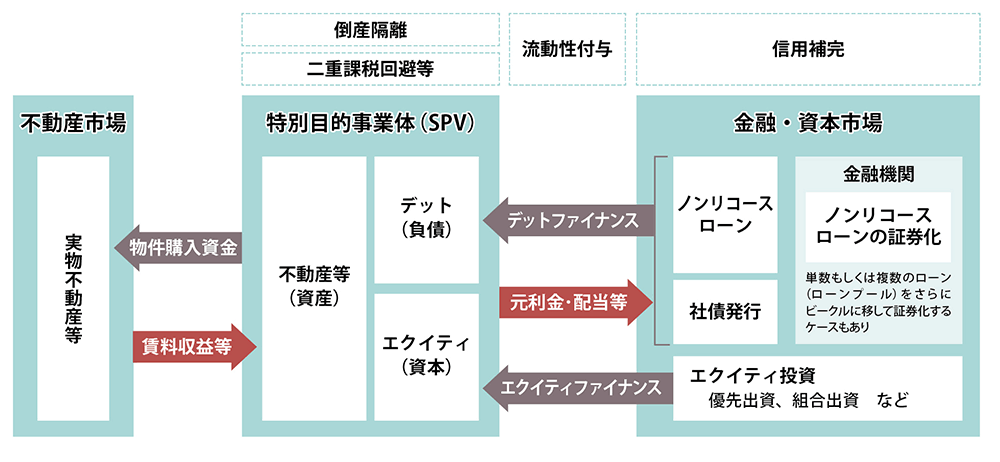
一般社団法人 不動産証券化協会ホームページを参考に作成
不動産証券化による各プレーヤーには次のようなメリットがあります。
| 原所有者(オリジネーター) |
|
|---|---|
| 不動産ファンド(ビークル) |
|
| 投資家 |
|
国土交通省も「不動産証券化を推進し、不動産投資市場の持続的な成長を実現することは、不動産取引の活性化を促し、優良な都市ストックの形成や、地域経済の活性化等に貢献する」として、不動産証券化を推し進めています。
不動産証券化の実態
国土交通省が公表した調査結果によれば、証券化の対象となった不動産と信託受益権の資産総額は約66.6兆円となり、前年度の59.8兆円から増加しました。下図が示すように、資産総額は2015年(平成27年)度の29.9兆円以降、着実に拡大を続けています。特にリートを中心とする証券化ビークルの活用が進み、私募リートやGK-TKスキームなど多様な方式が活用され、資産の流動化手法も広がっています。
図2:証券化の対象となった不動産の資産総額推移(全体)
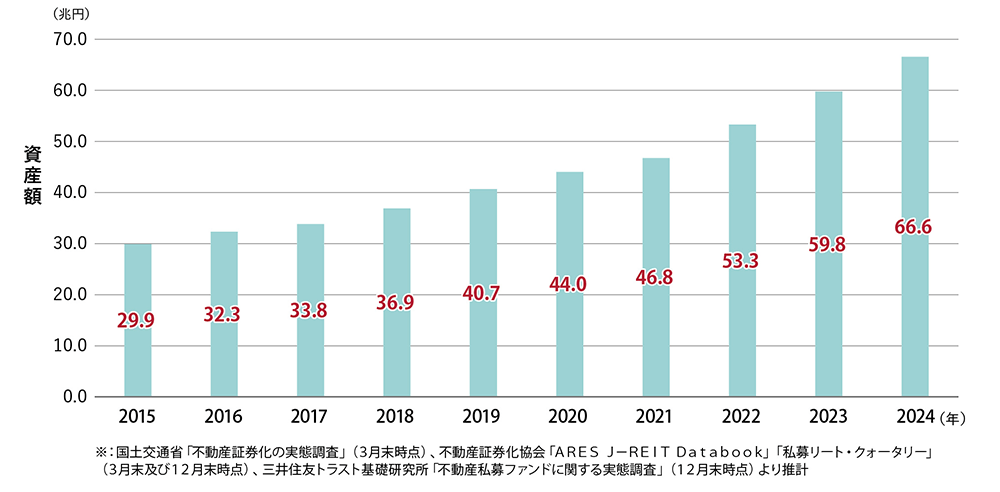
国土交通省「令和6年度 不動産証券化の実態調査」より作成
スキーム別の実績
令和6年度にリート及び不動産特定共同事業の対象として取得された不動産又は信託受益権の資産額は約2.7兆円でした(令和5年度と同額)。また、譲渡された資産額は約1.1兆円(令和5年度は約0.8兆円)でした。
令和6年度に取得された資産をスキーム別にみると、リートが約2.1兆円(令和5年は約2.3兆円)、不動産特定共同事業が約0.7兆円(令和5年は約0.4兆円)でした。また、令和6年度に譲渡された資産は、リートが約0.8兆円(令和5年は約0.6兆円)で、不動産特定共同事業が約0.3兆円(令和5年は約0.2兆円)でした。
不動産の用途別実績
リート(私募リートを含む)および不動産特定共同事業において、令和6年度に取得された資産額の割合を用途別にみると、住宅が23.0%、宿泊施設が21.7%、物流施設が17.6%の順でした。
令和5年と比較すると、オフィス関連が減少し、物流関連が倍増しています。
図3:用途別 証券化の対象となった不動産の取得実績の推移(資産額)
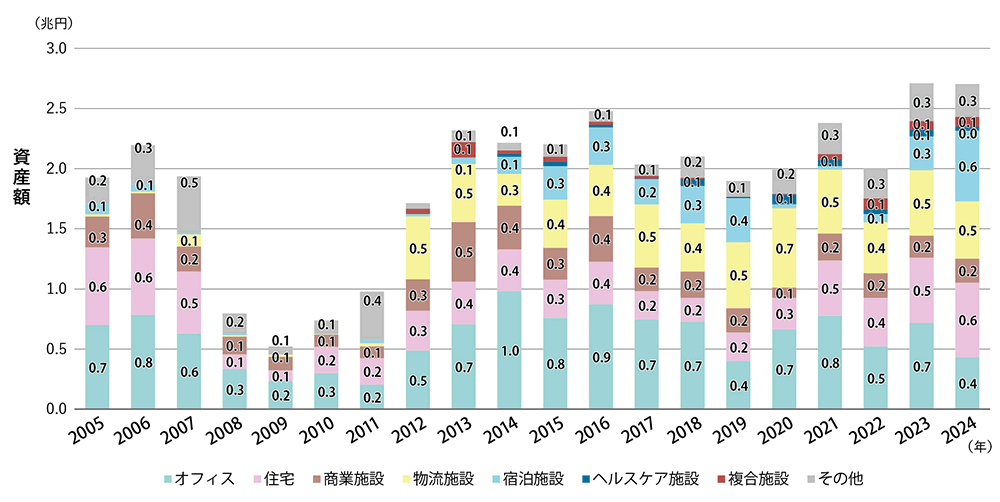
国土交通省「令和6年度 不動産証券化の実態調査」より作成
都道府県別の実績
リート(私募リートを含む)及び不動産特定共同事業において、令和6年度に取得された資産を所在地別にみると、東京都569件、大阪府147件、神奈川県117件、千葉県89件の順でした。東京都が全体をけん引している印象です。
「開発型の証券化」が大幅増加
令和6年度の傾向として、「開発型の証券化」が大きく伸びています。開発型不動産証券化は、既存の不動産ではなく、これから建設される不動産を対象にした証券化の手法です。将来の不動産開発プロジェクトを資金調達するための手法であり、開発プロジェクトの資金を調達し、将来的なリターンを得ることを目的としています。
不動産特定共同事業のうち、不動産の開発資金を証券化により調達する「開発型の証券化」について、令和6年度の実績は249件、約2,719億円でした。
図4:開発型証券化の実績
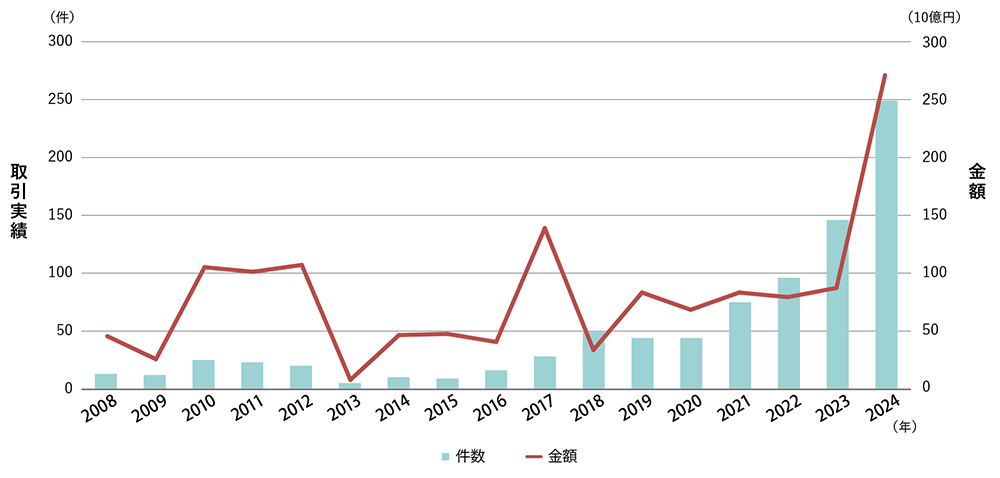
国土交通省「令和6年度 不動産証券化の実態調査」より作成
原所有者(オリジネーター)からすれば、こうした開発型の証券化こそが、市場の活性化や拡大に大きく影響を与えると考えられます。立地が大きな条件にはなりますが、開発型の証券化スキームは今後の不動産市場に大きな影響を与えそうです。