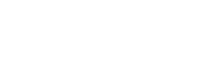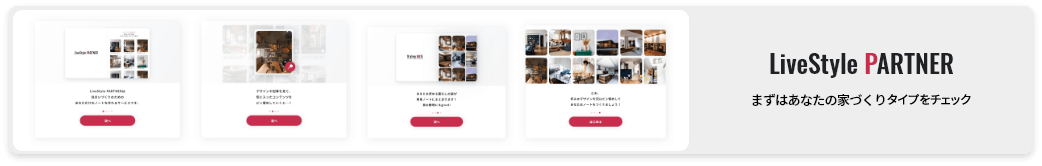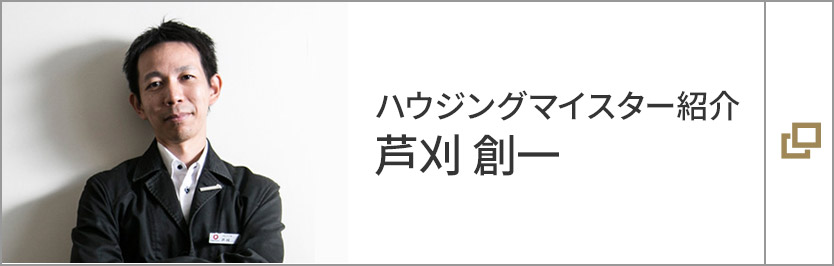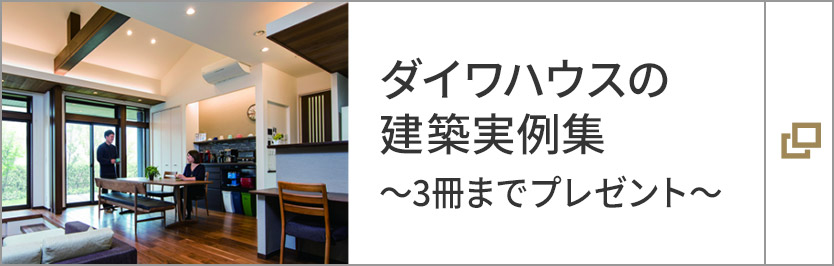せっかく家を建てるなら、家で過ごす時間や空間の心地よさを大切にし、
家具や照明などのインテリアにこだわりたいと思う方は多いはず。
けれど、設計の段階で家具を起点にプランニングする方はとても少ないようです。
今回はお気に入りの家具を中心とした空間づくりについて、
ダイワハウスの設計士・芦刈創一が提案します。
Profile

大和ハウス工業株式会社
一級建築士/インテリアプランナー/
インテリアコーディネーター
光を意識し、ガラスを用いた住まいづくりを得意とする自称「ガラスの魔術師」。ハウジングマイスター(社内認定)として積み重ねてきた経験とノウハウを生かし、現場での知識共有を通じた後輩指導にも力を注ぐ。大学時代は馬術部に所属。
住まいは「建物」と「家具」の両輪で完成するもの
ライフスタイルを大切にしている方は、建物だけでなくインテリア全体に思い入れがあるものです。ですが、実際に家を建てる際、ほとんどの方が建物と家具を切り離し、建物優先で計画を進めがちです。
けれどもし、新居に置く家具や照明がすでに決まっていたり、具体的なイメージを持っていたりするなら、その家具を前提に空間づくりを考えることをおすすめします。なぜなら、家具のサイズによって空間の使い方や動線が変わりますし、印象的な家具は家全体のテイストを左右するからです。
家具は、設計士とのイメージ共有をスムーズにする
重要な手掛かり

家具は設計士とのコミュニケーションにおいても、重要な役割をはたします。お客さまが家に置きたいと考える家具には、「こんな暮らしがしたい」という、プランニングするう上でのヒントが隠れているからです。
新居に置く予定の家具を伺った際、名品といわれるものであれば、私たちはまず、その家具の歴史を調べます。社会背景やデザイナーのコンセプトなども参考に、お客さまがその家具にどんな思いを投影しているのか想像することで、建物の設計のイメージがより鮮明になっていくのです。いわゆる名品家具でなくとも、その存在は重要です。お好みのテイストを伺う中で 「ジャパンディ」や「ナチュラル」といった表現をお使いになったとしても、その言葉に対して持つイメージは人それぞれ。そんなとき、具体的な家具のイメージがあれば、それが共通言語となって、理想とする暮らしを共有しやすくなります。

実は家を建てる際、多くの方は以前の家具を処分して新たに家具を購入されます。しかしそのような場合でも、「家具は入居が近づいてから考える」などと先延ばしにせず、家具も含めて設計士と一緒に検討するほうが、より全体的にバランスの取れた、快適な住まいに仕上がります。
こうした考えのもと、私たちは設計の提案とともに、家具のコーディネートについても提案しています。例えば制作するパースの中の家具は単なるイメージではなく、実際に入手や製作が可能な家具を用いて空間のトータルイメージを構成しています。
サイズ、色、素材、テイスト…
建物と家具の調和のために、意識すべき要素は?
1. ボリューム感
建物と家具の調和を考える上で私たちがまず考慮するのは “ボリューム感”です。「このサイズのソファならリビングはもう少し広く取ったほうがくつろぎ空間に広がりが生まれるだろう」「キッチンからリビングを見た景色でソファの占めるボリュームが大きいから、その先の壁面には収納や窓などを設けずシンプルにしよう」などと考え、調整を行います。
特に主役級の存在感のある家具であれば、“余白”を十分に取ることが重要になります。絵画でもキャンバスの中の余白や額縁によって、作品が生きるかどうかが決まりますよね。空間もこれと同じで、家具を単品の“点”で捉えるのでなく、壁や床や窓も含めた“面”の中で捉えることが大切です。

2. 素材
家具の質感も大切です。特に木製家具では、木材の種類が鍵となります。一室に複数種類の木材が混在すると互いの魅力を打ち消し合うため、床や柱、壁などと家具の木材は、できる限りそろえます。家具が先に決まっている場合は、建物で使う木材をそれに合わせます。床と異なる木材でつくられたテーブルが気に入っているなら、脚の素材をスチールなどに変えることもあります。
3. 照明
照明も建物との関係性が強いアイテムです。あるお客さまは、近代建築の巨匠であり照明デザイナーでもある、フランク・ロイド・ライトの名作スタンドライト「タリアセン」をお持ちでした。そこでブロックを重ね合わせたようなこの照明を生かすために、エントランスからリビングにかけて大谷石を 張り、建物と照明が呼応するようなデザインに仕上げました。
ダイニングなどに美しいペンダントライトを考えている方も多いですが、それだけでは生活に必要な照度に満たないので、補助灯が必要になります。間接照明をどこに設置するかなど、照明に合わせた空間・配電設計が不可欠です。

4. 重量
さらに、物理的な耐荷重の問題も考慮が必要です。重いシャンデリアやシーリングファンを設置する場合は天井に補強が、グランドピアノや大型の石製テーブル、ウォーターベッドなどを置くなら、床材に補強が必要になります。こうした補強工事は完成後に行うのが難しいため、家具は計画の早い段階で決めておくことが重要です。

普段通りのライフスタイルを伝えることが、
心地よい空間づくりの近道

お客さまにとって設計士に必要な情報を提示するのは難しいことです。そこで、私たちは最初のヒアリングの段階で、お客様のライフスタイルを詳しくお聞きします。「朝食は家族全員で食べますか?」といった質問から始まり、ご家族それぞれにとって大切な時間や場所を探ります。そして、会話から得たヒントをもとに、心地よい空間づくりを進めていきます。
その結果、リビングのソファを長時間使用したり、腰痛の方がいたりする場合には、ソファも硬めのものをご提案します。リビングにしっとり落ち着いたくつろぎ感を求めていらっしゃる場合は、照明も柔らかく低い位置に設置し、ソファも沈み込むようなソフトなタイプを提案します。また逆にお手持ちの家具からライフスタイルを想像して、設計に生かすこともあります。
一般に、「建築がマクロ」「家具がミクロ」という印象を持たれがちですが、実際は両者が調和して初めて心地よい空間が完成します。インテリアの話は建物とは無関係と考えず、ささいなことでもぜひ設計士に伝えてみてください。また私たちが一番知りたいのは、飾ることのない皆さんの「いつも通りのライフスタイル」です。それは家が建った後に始まる実際の生活そのものですから。

<Column>実例!家具から始める空間設計
今回は、設計士の芦刈に3つの家具写真を提示。それらを生かした空間設計について具体的な考え方を教えてもらいました。
実例A:モダンな木製ローテーブル
素敵なテーブルですが、注目すべき特徴は広い面積、背の高さ、チーク材のような色合いです。床に近い大きな木の面があるため、床材との調和が重要になります。モルタルやピータイルなどを選び、テーブルと床の相性を考慮します。存在感のあるテーブルなので、リビングは余裕を持った広さが必要です。またこの低さのテーブルの場合、日常的に使用するならソファの高さや硬さを厳選するか、サイドテーブルを追加すると実用的です。

実例B:レトロな黄色いL字ソファ
かなり個性の強いソファです。このソファを軸に考えるなら、ポイントは色、背の高さ、そしてL字の形。背が高く、色が強いので、部屋の真ん中に置くとかなり圧迫感が生まれます。コーナーに沿わせるように配置するのが良いでしょう。背もたれと座面が直角に上がっていて背が高く、硬さもありそうなので、リビングでのくつろぎ用というより、ダイニングテーブルに合わせるものとして想定してみます。そうするとこのソファを軸にLDKの配置を計画する必要がありそうです。レトロポップな雰囲気がお好みであれば、床材はヘリンボーンタイプの木目やモルタル調などにすると良いかもしれません。

実例C:青銅やクリアガラスを用いたペンダントライト
銅やガラスなどの無垢の素材はどんな素材とも比較的相性が良く、選択肢の多い照明です。キッチンやダイニングにアクセントとして取り入れることができます。また、トイレの照明に使えばぐっと空間の格を上げることもでき、来客の多い家にはおすすめです。リビングに落ち着きを出したいなら、ペンダントコードを長くして、重心を低くすると効果的。空間全体を照らす明るさがないので、機能面では別に照明を設ける必要があります。こうしたことも合わせて配線計画を立てます。

建物と、家具と、暮らす人が、共に育む「暮らしの空間」
心地よい住空間は、建物が完成した瞬間に生まれるのではありません。そこに家具が配置され、人が暮らし始めることで徐々に育まれていくものです。私たち設計士は、引き渡し時に記録として住まいの写真を撮りますが、お客さまの生活が始まってから再び拝見すると、暮らしの輪郭がくっきりとし、空間が気持ちよく呼吸し始めているなあと感じます。住まいとは、建物と家具、そして暮らす人が、共に育んでいくものといえるかもしれません。私たちは、お客さまの思いに寄り添いながら、新しい暮らしのスタートが良い形で切れるよう、お手伝いできればと思っています。
まとめ
インテリア選びと空間設計は切り離せないもの。建物と家具が調和することで、より心地よい空間が生まれます。設計の早い段階で家具のサイズや形、素材を考慮したり、家具についての思いを設計士に素直に伝えたり。建物、家具、暮らす人が一体となって育む住空間を目指すことが、理想の暮らしへの近道となるでしょう。