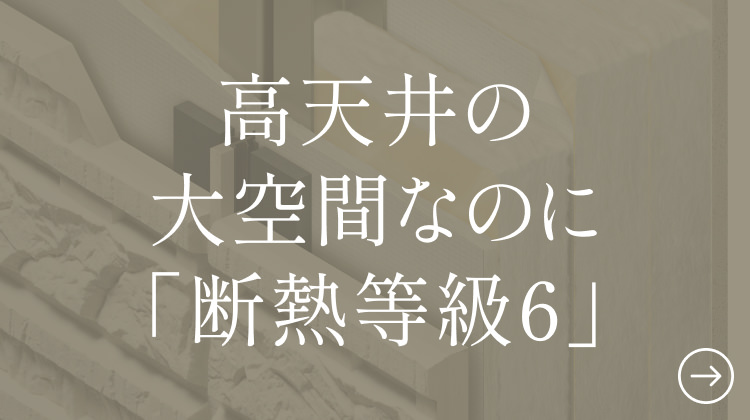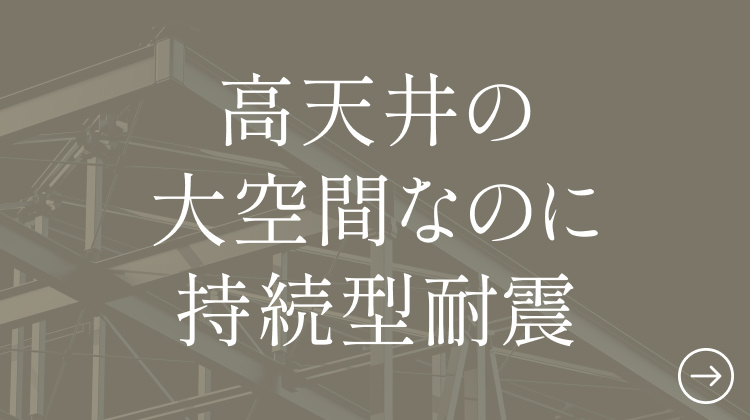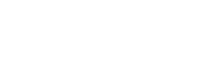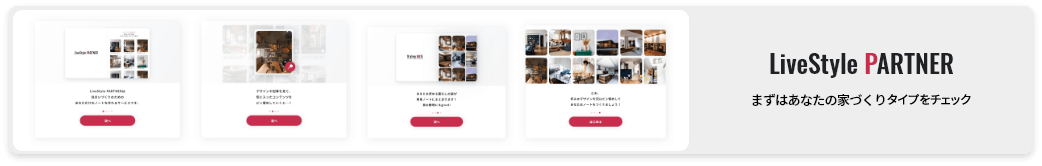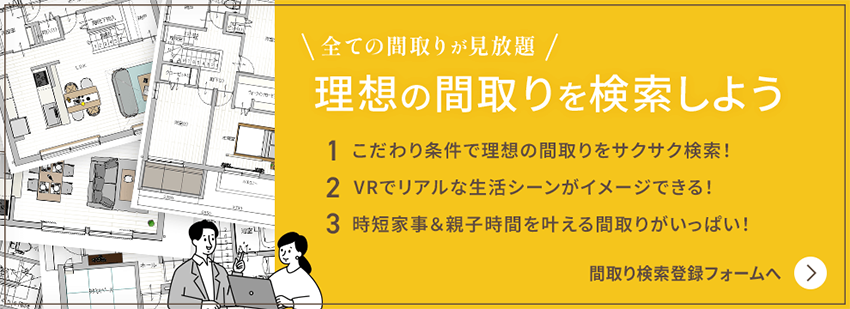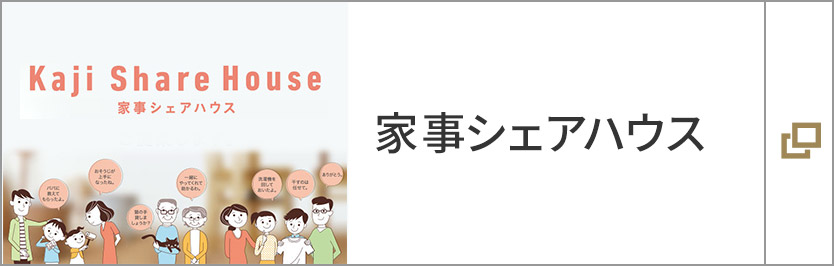「部屋干ししたいけど生乾きのニオイが気になる……」、そんな洗濯の悩みはありませんか?
洗濯家事を快適にするには、部屋干しと外干しの特徴を知り、
ライフスタイルに合わせて使い分けることが大切です。
このコラムでは、部屋干しと外干しのメリット・デメリットはもちろん、
日々の洗濯家事がラクになるコツ、
さらには理想の洗濯動線を実現する家づくりのアイデアもご紹介します。
Part1ライフスタイルや気候の変化で、
洗濯はますます大変な家事に!?
「洗う・干す・取り込む・たたむ・仕分ける・しまう」と、洗濯には多くの工程があり、とても手間がかかるものです。それに加えて、ライフスタイルや気候の変化によって、洗濯家事のストレスはさらに増えていると考えられます。どのようなことが洗濯家事のストレスを増やすのでしょうか。
共働きによる洗濯家事の制限
夫婦共働きで忙しいと、そもそも洗濯の時間を確保するのも大変です。そのため、洗濯は朝の忙しい時間帯を避けて夜に行う、休日にまとめて行うというご家庭も多いでしょう。ただそうなると、「部屋干しで生乾き臭が発生した」「休日に複数回洗濯機を回したり干したりするのが大変」といったストレスにつながる可能性があります。
子どもの成長に伴う洗濯回数の増加
お子さまがいるご家庭の場合、子どもが成長するにつれて洗濯の負担感はさらに増すことがあります。学校の通学服に加え、体操服や水着、塾・習い事の服など、服を着替える場面も増えると、その分洗濯回数も増えるからです。洗濯回数が増えると、洗った後に干す場所に持っていく手間が増えたり、洗濯物を干すスペースの確保が必要になったりします。そして、「ベランダが狭く洗濯物を干すスペースがない」といったストレスにつながります。

気候変化
予測しにくいゲリラ豪雨、衣類の傷みを早めてしまう紫外線量が多い猛暑など、近年の気候の変化により日中でも外干しがしづらい環境になっています。また外干しの場合は、大気中に含まれる花粉や黄砂、PM2.5、車の排出ガスなどによって洗濯物が汚れる心配もストレスになります。
このような変化が洗濯家事に影響を及ぼしていますが、特に「以前に比べて部屋干しが増えたけど生乾き臭が気になる」「外干し派だったけど部屋干しもうまく取り入れたい」というように、干し方が気になる方が多いのではないでしょうか。
そこで、この後のPartでは、部屋干しと外干しのメリット・デメリットを解説します。それぞれのポイントを理解した上で、自分たちのライフスタイル合う洗濯家事について考えていきましょう。
Part2部屋干しのメリット・デメリット

部屋干しのメリット
1. 天候に左右されない
雨や雪、洗濯物が飛ばされそうな強風など、天候にかかわらず干すことができます。外出中に天候が急変しても部屋干しなら安心です。
2. 時間帯を選ばない
共働き世帯など日中に洗濯ができず、帰宅後や早朝が洗濯の時間というご家庭も多いはず。部屋干しは「夜だから」「早朝だから」と心配することなく、生活パターンに合わせて干すことができます。
3. 花粉や黄砂、PM2.5などの付着を防げる
大気中を漂う花粉や黄砂、PM2.5のほか、排気ガスによる汚れ、排気ガスから生じる窒素酸化物などが洗濯物に付着することを防げます。特にアレルギー体質だと洗濯物に付着した物質で各種の症状が出る場合もあるため、季節によらず部屋干しをしたい方は多いでしょう。

4. 紫外線による衣類の傷みを防げる
太陽光に含まれる紫外線は殺菌効果が期待できる一方で、衣類の色あせや生地が傷む原因にもなります。一般的なガラス窓は紫外線が通過するため、サンルームなど日差しが当たる場所でも同様です。しかし、部屋の中で日差しが当たらない場所に干すなら、紫外線による色あせや傷みを抑えやすくなります。
5. 防犯対策になる
夜も洗濯物が干したままになっているなどで第三者に生活パターンを推測され、空き巣に入られたり衣類が盗まれたりするリスクを軽減できるのも部屋干しをするメリットの一つです。
6. 冬場の乾燥対策になる場合も
洗濯物に含まれていた水分が室内の湿度を上昇させるため、冬場の乾燥対策としてもある程度役立ちます。ただし、部屋の広さと洗濯物の量によって乾燥を防げる度合いは異なり、効果が続くのも洗濯物が乾くまでの間となります。
7. 洗濯動線がコンパクトになる
洗濯には洗濯物を仕分けて、洗濯機で洗濯と脱水を行い、終わったら干すという作業があります。洗濯機のある場所と外干しをするベランダやバルコニーが離れていると、濡れて重くなった洗濯物を抱えて室内を移動し、窓を開けて、外履きに履き替えて干すという作業が毎回必要になります。部屋干しの場合、洗濯機の近くに干す場所を設ければ外干しのときほど移動せずに済み、洗濯時の生活動線をコンパクトにしやすくなります。そのため外干しでも部屋干しでも動線が短くなるよう、洗濯機の置き場所や洗濯物を干す場所を近くに設けると便利です。

部屋干しのデメリット
1. 乾きにくい、時間がかかる
洗濯物が乾きやすい条件として、高い温度、低い湿度、風通しの良さがあげられます。からっと晴れた日の外干しに比べて、部屋干しの洗濯物が乾くまでに時間がかかるのは、そのままではこうした条件を満たしにくいから。逆に言えば曇って気温が低く、温度が高い日なら外干しでも乾くのが遅く、浴室乾燥機や衣類乾燥除湿機を使うなど、乾きやすい条件を整えれば部屋干しでも早く乾かせます。
2. 生乾き臭が発生しやすい
生乾き臭の原因となるモラクセラ菌などの雑菌の繁殖は、洗濯物を湿った状態で長時間放置することでも起こります。このため部屋干しで乾くまでに時間がかかると、湿ったままの時間が長くなり雑菌が繁殖しやすくなります。ただ、天気の良い日に部屋干しする場合、日当たりの良い部屋に洗濯物を干すことで、窓ガラス越しでも紫外線による菌やシミの除去を期待できます。
3. 部屋の見た目が悪くなる・場所を取る
部屋干し専用のスペースがない場合、家族が行き来する空間に洗濯物を干すことになります。そうなると室内が雑然と感じられ、スペースが圧迫されて洗濯物をよけて歩くことも起こります。

4. 室内に結露やカビが発生しやすくなることも
部屋干しは冬には室内の乾燥対策にもなりますが、閉めきった部屋で湿度の高い状態が日々続けば、梅雨の時期と同様に結露やカビの原因になることも考えられます。
5. 電気代がかかる場合がある
温度や湿度を調節し、洗濯物に風を当てるなどの工夫で乾燥を早めるには、衣類乾燥除湿機やサーキュレーター、浴室乾燥機などを併用することも多く、外干しのときよりも電気代が増えてしまいます。
Part3外干しのメリット・デメリット

外干しのメリット
1. 早く乾きやすい
晴れて乾燥し、ある程度の風が吹く日は、高い温度、低い湿度、風通しの良さという早く乾くための条件を満たすため、外干しをすると早く乾きます。加えて、太陽光の熱で洗濯物に含まれる水分の蒸発を早めるのも乾きやすいポイントです。
2. 日光による殺菌・消臭効果が期待できる
紫外線は殺菌効果があるとされ、洗濯物に直射日光を当てると付着している雑菌の繁殖を抑えやすくなります。雑菌は洗濯物がにおう原因の一つですから、雑菌の繁殖を抑制することでニオイを軽減する効果にも期待できます。

3. 電気代がかからない
部屋干しで早く乾かそうとすると、衣類乾燥除湿機やサーキュレーターなどを使ったり、浴室乾燥機で乾かしたりすることになります。それに比べて外干しは太陽光や自然の風が乾燥に利用できる分、電気代はかかりません。
4. 大物の洗濯物も干しやすい
シーツや毛布、布団、カーテンなど大きなサイズの洗濯物は、部屋干しできるスペースが見つからないこともあるでしょう。その点、外干しならベランダや庭などの広いスペースを活用して干すことができます。
外干しのデメリット
1. 天候に左右される
雨、雪、強風などの天候で外干しすることはまずありません。また日中に天気が急変しそうな予報のときに外干しするのは、乾いてないのに途中で取り込んだり、外出中に洗濯物が濡れてしまったりするリスクと隣り合わせです。
2. 花粉やPM2.5、ホコリ、虫などが付着する
洗濯物を外干しして太陽光や外気に当てることで、大気中の花粉や黄砂、PM2.5、排気ガスから生じる窒素酸化物などが付着する可能性が高まります。季節によってはカメムシやハチ、ハエなどが洗濯物にとまっていることもあるので、取り込むときに注意しましょう。
3. 衣類が紫外線で傷みやすい
長時間の外干しは、紫外線の影響で衣類が色あせたり生地が傷んだりすることがあります。特に色の濃い衣類は紫外線を吸収しやすく、白など明るい色の衣類より色あせや傷みが早いとされています。
4. 時間帯が限られる
洗濯物が乾きやすいのは日中とされ、外干しは朝に干して夕方までに取り込むなど干す時間帯が制限されるのが一般的です。さらに冬は日没が早まるため、気温が上がり始める9時頃から洗濯物を干し、14時〜15時頃には取り込んだ方が良いでしょう。

5. プライバシーや防犯上の懸念がある
夜になっても洗濯物が外干しのままだと誰も帰宅していないことが推測され、生活のパターンがわかって空き巣などのターゲットになる可能性もあります。また、衣類が盗まれるような被害も考えられます。
6. 風で洗濯物が飛ばされる可能性がある
風通しの良さが乾きやすい条件の一つといっても、あまりに風が強すぎると洗濯物が物干し竿から飛ばされ、ベランダや地面に落ちて汚れたり、紛失してしまったりする可能性があります。
Part4部屋干しも外干しも快適に!
洗濯家事のコツ&間取りや洗濯動線のアイデア
部屋干しと外干しそれぞれにメリット・デメリットがありますが、工夫を取り入れることで、洗濯家事はもっと快適になります。洗濯の「洗う→干す→取り込む・収納する」というプロセスに分けて、ストレス軽減の工夫をご紹介します。
1. 洗う
気になる生乾き臭は雑菌の繁殖で発生するため、汚れたものはすぐ洗うことがポイントです。また、雑菌を増やす原因になるタンパク質汚れはニオイの発生源にもなります。
- 洗濯物は洗濯表示マークに従って洗うことに加え、しっかりと汚れを落とす
- 汚れたり湿ったりした洗濯物は、雑菌が繁殖しないうちに早めに洗う
- 汚れを落とすために、洗濯機に洗濯物を入れ過ぎない、十分な水位・水流で洗う、適切な量の洗剤を使うといった点に注意して洗う
(体操服のように特に汚れがひどいもの、油や食べこぼしが付いた汚れなどは、予洗いやつけ置き洗いで事前に汚れを落としておくと効果的です) - しばらくたってから洗う場合は、洗濯機の中に入れたままにせず、湿気がこもりにくいランドリーボックスに入れる
- 洗濯が終わったら早く干す。梅雨時期や夏の時期など気温が高い季節は洗濯機の中に1時間以上放置しないように注意が必要です。もし1時間以上取り出すことができなかった場合は、上手に乾燥させてもにおう可能性が高まります。
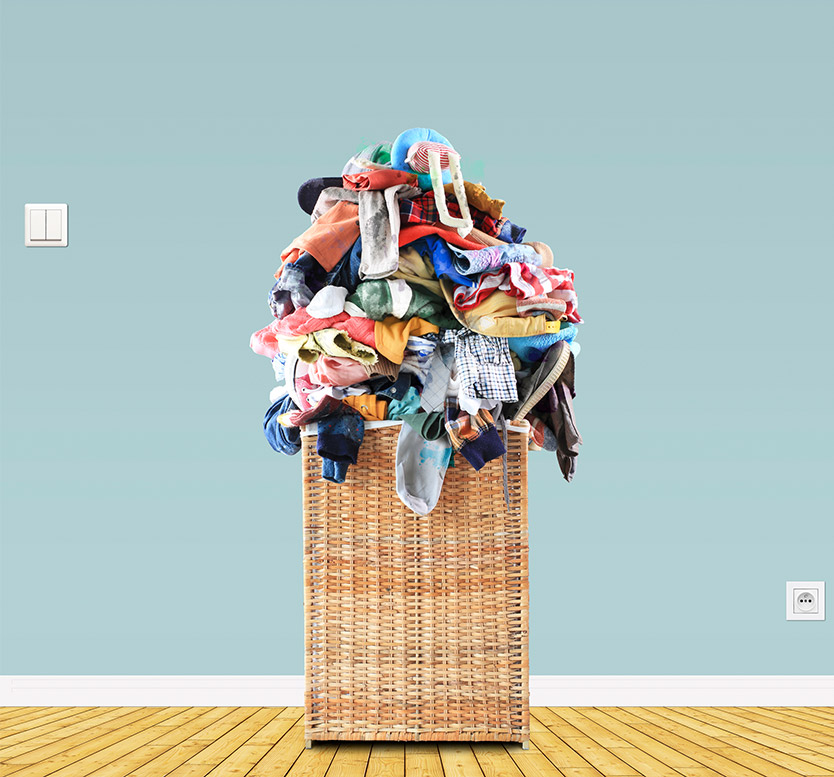
また、「脱ぎ散らかした衣類を集めてランドリーボックスに入れる」「裏返しに脱いだ衣類・丸まったままの靴下をひっくり返す」といった「名もなき家事」の手間も、毎回行っていれば大きなストレスに。家族一人ひとりが家事をシェアする意識もストレス軽減には重要です。
家づくりのアイデア
- 汚れたものをリビングなどに持ち込まず、洗濯機置き場のランドリーボックスに入れられるよう、玄関からすぐにアクセスできる場所に浴室・洗面所、洗濯機置き場を設ける
- 洗濯物の予洗いやつけ置き洗いに利用できるスロップシンクなどが洗濯機の近くにあると便利
2. 干す
部屋干しの場合
生乾き臭が気になる、見た目が良くない、結露やカビの発生など、部屋干しで感じるストレスの主な原因になるのは「乾くのが遅いこと」。早く乾燥させればこうしたストレスは軽減できます。高い温度、低い湿度、風通しの良さなどの条件を意識して干すようにしましょう。
- 室内用物干し竿などを使って洗濯物を干す間隔を十分に取る
- エアコンの冷房運転や除湿運転で湿度を下げる、扇風機やサーキュレーターで洗濯物に風を当てて周囲の湿気を発散させ空気を循環させるといった工夫のほか、衣類乾燥除湿機などを使う
- バスタオルなどは二つ折りにするより、ガウンのようにハンガーに掛ける
- 壁際や部屋のコーナーは避けて空気が流動しやすい部屋の中心部などの場所を選ぶ

また浴室乾燥機は光熱費がかかるものの効果的に乾燥でき、部屋干しをしても洗濯物がLDKなどから目に入らないというメリットも。光熱費を節約したいなら、最初は部屋干しである程度乾かして、最後に浴室乾燥機でしっかりと乾かしましょう。
カーテンレールにハンガーなどを掛けて洗濯物を干す方もいるとは思いますが、洗濯物の重さでカーテンレールが傷むことも考えられるため避けた方が良いでしょう。また、窓を開けていなければ部屋のコーナーや壁際と同じで風通しは悪く、洗濯物がカーテンについた状態だとカビも発生しやすくなります。
家づくりのアイデア
- リビングなどに干すと洗濯物に加えて扇風機やサーキュレーターなどが邪魔で、見た目も良くないため、洗濯・乾燥・片付けまでできるランドリールームがあると便利
- ランドリールームには換気扇に加え、扇風機・サーキュレーター、アイロンなどが使えるようコンセントも設置。それらの収納場所も設けると空間がスッキリする
- 気密性も高く、家の中は適度な温度、湿度に保たれている全館空調の家は、一般的な住宅よりも部屋干しで乾きやすいとされる
- 部屋干ししかしないご家庭、洗濯物は庭に干すというご家庭、または、バルコニーでガーデニングを楽しんだりリラックスしたりしないというご家庭は、バルコニーを設けないという選択肢も考えられる。バルコニー設置の費用が抑えられ、掃除の手間やメンテナンス費用もなくせる

外干しの場合
外干しはよく乾くことが多い半面、紫外線による衣類の色あせ・傷みが気になる人もいるでしょう。紫外線は直接当たった面にダメージを与えるため注意が必要です。
- 紫外線を吸収しやすい色の濃いものなどは裏返して干すことで、服の表側へのダメージを軽減できる
ただし、洗濯表示マークに陰干しの指示があればそれに従う。裏側にもダメージを与えたくない服も陰干しが適しています。 - 一般的に洗濯物が乾きやすい時間帯とされる9時~15時の間に干す
晴れた日なら気温が上がり、湿度が下がって、乾きやすい条件が整ってきます。ただし、秋冬は気温の低下が早く、せっかく乾いた洗濯物が湿りやすくなるので、15時よりも早く取り込む方が良いでしょう。
家づくりのアイデア
- 深い軒があると強い日差しを遮ってくれるので陰干しできるスペースが増える
- 庭に干すことが多いならウッドデッキを設けて、LDKからすぐ庭に出られるようにすると洗濯動線がスムーズになる
- 庭に外干しをする際、周囲の家や道路から洗濯物を見えにくくなるよう柵などを設置する。中庭を設けると近隣の目を気にせず外干しができる

3. 取り込む・収納する(しまう)
洗濯物を取り込んだ後にたたんで、それぞれの収納場所にしまうといった手間のかかる作業をなるべく簡略化するとストレス軽減に役立ちます。
- 例えば、シャツや上着などハンガーに掛けて干した衣類を、そのままクローゼットに収納する
- 服のシワなどを気にする必要がない下着、パジャマ、室内着などはたたまず、各自の収納ボックスに入れる

また、家事シェアの一環として、洗濯物の仕分けまでは取り込んだ人が行い、たたんで収納場所にしまうのは家族それぞれの作業にするのも良いでしょう。
家づくりのアイデア
- 洗濯機を干す場所の近くに置けるよう水回りを配置するなど、洗う→干す→取り込む・収納するが効率的に動けるよう間取りを工夫
- 洗濯のプロセスのほとんどが行えるランドリールームがあると便利。ランドリールームとバルコニーやウッドデッキを近くに配置すると、部屋干しと外干しの使い分けがしやすく、急な雨で洗濯物を取り込んだ後もすぐに部屋干しできる
- 和室や畳スペースを活用すると、広い場所で洗濯物をたたむ・仕分けるといった作業がしやすい
- 洗濯物を干す場所の近くに、家族全員用のファミリークローゼットを設けると効率的。家族の衣類をまとめてファミリークローゼットに一時置きして、各自が自分の部屋に衣類を持ち帰って収納する家事シェアのやり方も
Part5部屋干し派vs外干し派論争に終止符。
洗濯家事が快適な家とは?
ここまでご紹介したように、部屋干しでも外干しでも洗濯のストレスを減らし、より快適に家事をこなすには「洗濯がラクになる家づくり」と「家族全員で洗濯のプロセスをシェアすること」も大切です。しかも普段の生活では洗濯だけでなく、料理や掃除などさまざまな家事を同時並行で進めなくてはなりません。そうした家事全般に家族みんなが参加しやすくなるのが大和ハウスの「家事シェアハウス」です。
みんなの家事参加を促す家事シェアハウス
洗濯、掃除、料理など家事の分担は増えていますが、それだけでは「脱ぎっぱなしの靴や衣服、出しっぱなしのおもちゃを片付ける」「トイレットペーパーや洗剤などを交換、補充品を購入する」といった、事前に決めた役割分担ではカバーしにくい「名もなき家事」が誰か一人の負担になりがちです。
そこで生活に必要な家事全体を家族みんなでシェアするのが「家事シェアハウス」の考え方。そこで大切なのは誰でも家事ができるように家事の情報や進め方をシェアすることです。例えば、ランドリールームには「一般洗い」「おしゃれ着」「汚れがひどいもの」など洗濯物を分別して入れるランドリーボックスを設ければ、洗濯時の面倒な分別の手間が省けます。

家事シェアハウスの間取り例

【2階建ての1階部分の間取り】
延床面積 : 1階 18.85坪(62.32m2)、2階 16.04坪(53.04m2)、合計 34.89坪(115.36m2)
間取り:3LDK
①家事シェア動線/帰宅後すぐに上着や靴を「自分専用カタヅケローカー」にしまい、ファミリーユーティリティやLDKにアクセス
②来客動線/①の家事動線とすみ分けるようにまっすぐLDKにアクセス
家事が楽になる間取りも選べる規格住宅&セミオーダー住宅

大和ハウスでは注文住宅以外に、価格を抑えながら間取りや外装・内装、設備などを注文住宅品質で実現できる規格住宅・セミオーダー住宅「Smart Made Housing.」も用意しています。
「規格住宅」は、これまで大和ハウスがハウスメーカーとして手がけてきた何万件もの住宅によるデータベースの中から、家事が楽になる家をはじめ人気の間取り2,300通り以上の中から選べます。「セミオーダー住宅」は、規格住宅と同じ2,300通り以上の間取りからプランを選び、さらに自分好みカスタマイズ可能です。
人気の平屋プランのほか、ウッドデッキやファミリークローゼットを設けたプランなども選べます。「Smart Made Housing.」の間取りは簡単な登録をすればすべて見ることができます。洗濯をはじめ家事がラクになるプランを探してみてはいかがでしょうか。
お話を伺った方
神崎 健輔(かんざき けんすけ)さん
洗濯・シミ抜き職人。実家の老舗クリーニング店「白洋社」部長。株式会社クラスタス CTO。宅配クリーニング「Nexcy(ネクシー)」CTOとして、全国から集配可能なクリーニング店の運営も行う。またそれらの経験をもとに、「洗濯ハカセ」として、家庭でもできる洗濯・シミ抜き術を発信中。テレビ雑誌等、メディア出演多数。