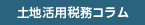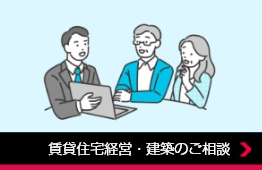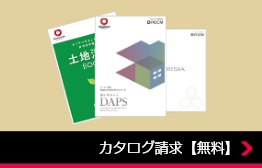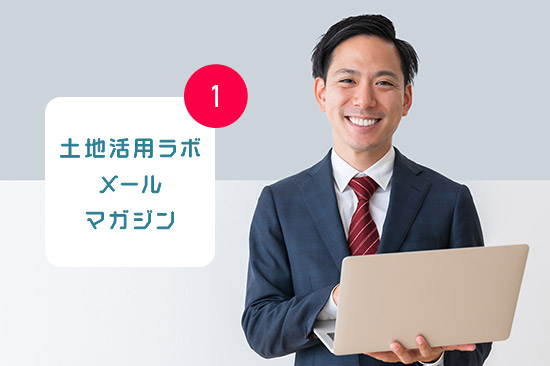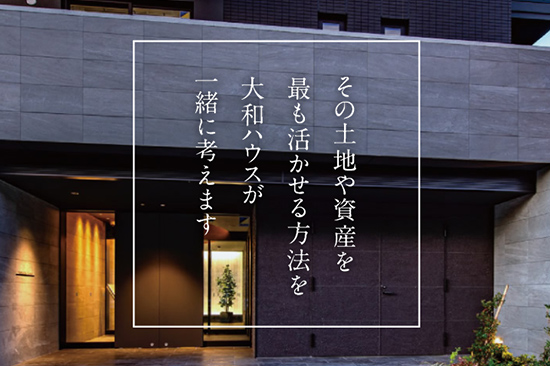コラム vol.471-19
コラム vol.471-19CASE19管理できない不動産を相続することになった
公開日:2025/07/31
一人で実家に暮らす父親も高齢となり、介護施設にお世話になることになりました。このままだと実家も空き家となり、自分もきょうだいもすでに家を持っており、使うつもりもありません。相続しても、管理できそうにもなく、どうすればいいのでしょうか。

相続した土地が遠隔地にあるなど、相続した土地を管理できないとして、昨今、管理されず放置されている土地や建物が増えています。実家を出た子どもたちがそれぞれ家を持つと、家が余ることになりますので、相続の時点で空き家が生じることになります。
使用用途のない空き家を相続した場合のリスク
遠隔地の不動産の場合、屋根や外壁の塗装・水回りの修理など定期的なメンテナンスに費用や手間がかかります。
実家を相続する際には、相続登記が必要になり登録免許税がかかるうえ、空き家になった場合でも固定資産税や都市計画税などの税金を払い続ける必要があります。
また、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税も発生します。(相続登記は2024年から義務化されました。自分で行うことが難しい場合は、司法書士に依頼することもできます。)
当然、空き家になった場合でも、外壁や外構の手入れ、設備(特に電気系統のチェック)の点検などの定期的なメンテナンスは必要です。メンテナンスの費用や手間をいやがり、長期間放置すると、雑草が茂ったり、ゴミが不法投棄されたりすることがあります。そうなると、近隣住民からのクレームや苦情となり、トラブルが起きたり、場合によっては、漏電による火災のリスク、不法侵入や犯罪のリスクもあります。
令和5年(2023年)12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」で、「管理不全空家」が新しい区分として定義されました。1年間を通して人の出入りや電気・ガスなどの利用状況を総合的に見て判断されるもので、空き家の中でも、壁や窓などの一部が破損・腐食していたり、ゴミが散乱していたりすると、適切に管理されていないと判断され、「管理不全空家」と認定されます。そうなると、市区町村は、管理不全空家として指導・勧告できます。つまり、所有している建物が管理不全空家に指定されてしまうと、自治体からの指導が入り、改善が見られなければ固定資産税を最大6分の1に減額する特例が解除されたり、管理コストが増大したりする可能性があります。
使用用途がなく、管理もできない土地の対処
使用用途がないということは、賃貸事業などの収益を生む方法も考えられないことが多いはずですから、対処方法とすれば、不動産事業者に売却するか、自治体やNPO法人等の支援を受け活用するなどが考えられます。売却してしまえば、管理の負担もコストもかかりません。売却により利益が出た場合には所得税がかかりますが、相続した空き家であれば利益から最大3000万円控除される制度もあります。
市区町村によっては「空家等活用促進区域」が指定され、前面道路の幅員の合理化や、用途地域で制限された建物への変更が認められるなど、用途変更や建て替えを促進しています。
空家等対策の推進に関する特別措置法の改正によって、空家等管理支援法人制度が創設されました。民間事業者の知見や経験を活用し、空き家管理の効率化を図るため、空き家問題の解決を促進することを目的とした制度です。認定されたNPO法人や社団法人が、空家等管理活用支援法人として、空家等の適切な管理を促進するための支援業務を実施し、所有者等からの相談に対応して助言を行いますので、こうした機関に相談するのも一つの方法です。
令和5年4月に創設された「相続土地国庫帰属制度」を活用することも可能です。令和5年4月より相続登記の義務化とともに、相続した土地を国に引き渡すことができる新たな制度が創設されました。
この制度は「相続土地国庫帰属制度」といい、令和5年4月27日から開始されています。申請できるのは相続や遺贈によって土地を取得した相続人で、この制度の開始より前に相続した土地でも申請することが可能です。複数人で相続した場合も申請することはできますが、共有者全員での申請が必要です。
ただし、全ての土地が国に引き渡すことができるわけではなく、法令で定められた却下事由と不承認事由のいずれにも当てはまらない土地のみが引き取りの対象となります。
- 申請できない土地
- ・建物のある土地
- ・担保権や使用収益権が設定されている土地
- ・他人の利用が予定されている土地(境内地、墓地内の土地、用悪水路として利用されている土地等)
- ・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
- ・境界が明らかでない土地、所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地
なお、申請の際は審査手数料が必要となり、承認された場合は負担金の納付が必要です。
相続を控えている人は、相続予定の不動産がどのような状態なのか、早い段階から確認しておく必要があります。もちろん、相続人が複数いる場合は、相続人の間で十分に話し合いの上、決定することが重要なのはいうまでもありません。ただし、トラブルを避けようと、安易に共同名義にして、結論を先延ばしにしてしまうと、リフォームしたり、売却したりする際に共有名義人全員の同意が必要となり、不動産の活用や処分が行いにくくなるリスクがありますので、注意が必要です。