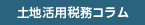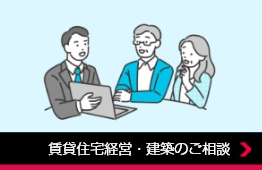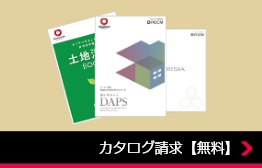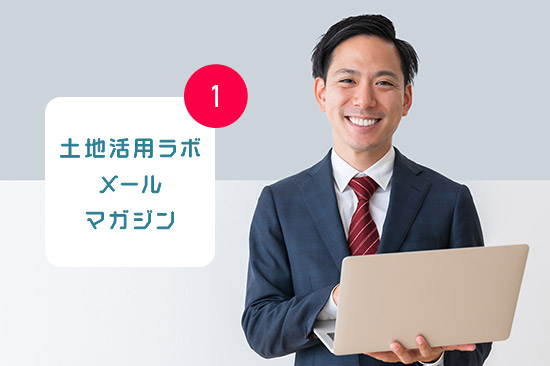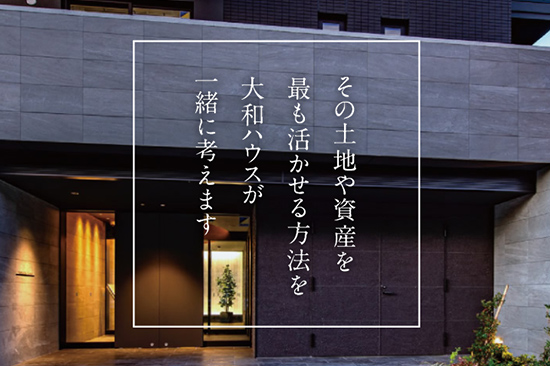コラム vol.562
コラム vol.562相続財産に債務(借金)あった場合の対策
公開日:2025/07/31
親が亡くなり、相続財産を確認したところ、債務(借金)があったということは少なくありません。親としても、できる限り迷惑をかけたくない気持ちから、なかなか言い出せなかった面もあるかもしれません。ここでは、相続財産に債務(借金)があった場合の注意点を紹介します。
被相続人(亡くなった方)が債務を残していたら、原則として相続人が引き継ぐことになります。民法896条では「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とあり、預貯金や不動産など、相続人にとって有益な財産もあれば、できることなら引き継ぎたくない、借金などの負の遺産もあります。
仮に、親が亡くなり相続人になった際、親に債務(借金)などあれば、それも含めて相続することになってしまいます。
相続税の債務控除
相続税を支払う際には、相続財産の価額から、被相続人が残した借金などの債務や葬式にかかった費用を差し引いて課税価格を計算します。つまり、マイナスの財産に関しては債務として、控除されます。この控除のことを「債務控除」といいます。 たとえば、プラスの財産として5000万円の預貯金、マイナスの財産として500万円の債務があった場合、相続財産(課税遺産)総額を算出する際、5000万円から500万円が控除されることになり、4500万円が相続税の課税対象となります。被相続人に債務があった場合には、この債務控除を活用することで相続税の軽減が可能となります。
「相続税の課税の対象となる純資産の総額」=「プラスの相続財産(不動産資産、現金、預貯金、有価証券、生命保険金ほか)」-「マイナスの財産(借入金などの債務、葬式費用など)」
債務控除の対象となるのは、銀行や消費者金融からの借入金に加えて、クレジットカード、カードローンの借金(一括払い、分割払い、リボ払い、ショッピング、キャッシングなど)、個人からの借り入れなどが対象となります。また、事業用のローンや融資残高、未払費用(家賃、水道光熱費、通信料、携帯電話費用、税金など)も債務控除の対象となります。亡くなった日現在の借入金の残高、未払利息は債務控除として差し引くことができます。
ただし、相続財産総額から債務控除するためには、以下のような条件がありますので、注意が必要です。
- ・亡くなった方が負っていた債務であること
- ・亡くなった時点での債務であること
- ・亡くなった方の死亡時に支払うことが確定していたこと
たとえば、香典返し費用、法事(法要)の費用、相続登記費用、遺言執行にかかる費用、相続税申告にかかる税理士費用などは、亡くなった人の債務ではなく、亡くなった時点での債務ではありませんので、債務控除の対象にはなりません。
保証債務・連帯債務
保証債務とは、債務者が債務を返済できない場合に、その債務を肩代わりすることであり、連帯債務とは、数人の債務者が同一の内容の債務について各自独立に全部の給付をなすべき債務を負担することですが、この保証債務・連帯債務は、原則として債務控除の対象とはなりません。
それは、保証債務といっても、債権者が請求をするかどうかは相続発生段階では不明であり、そもそも、主たる債務者に請求することも可能だからです。
ただし、保証債務に関しては、「主たる債務者が弁済不能の状態にあり、保証人がその債務を履行しなければならない場合」「主たる債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みのない場合」に関しては、債務控除ができるとされています。
連帯債務に関しては、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、その金額を債務控除でき、金額が明らかではない場合でも、連帯債務者に弁済不能の状態にある者があり、その弁済不能者の負担部分を負担しなければならないと認められる場合には、その部分の金額も債務控除可能となっています。
賃貸住宅経営者の場合の債務控除
賃貸住宅などの不動産賃貸業を営んでいる人が被相続人の場合は注意が必要です。ご入居者から預かっている敷金は、預かっているだけの現金ですから、ご入居者が退去するときは返却しなければなりません。敷金は債務控除の対象になります。ただし、管理会社が敷金を預かっている場合は、被相続人は現金を保有していませんので、債務控除することはできません。
被相続人が事業を行っていた場合などは、借入金は普通に存在しますし、保証人になっているケースもあるでしょう。親に借金があることは聞かされていても、保証人になっていたことはわからなかったというケースは少なくないようです。
相続放棄をすれば、債務を引き継ぐことはありませんが、プラスの財産もマイナスの財産も故人の人生の一部です。相続税の支払い期限は長くありませんので、亡くなったあとの対策に困らないように、生前のうちから被相続人を尊重し、遺産相続について率直な話し合いを持つのが最優先ではないでしょうか。