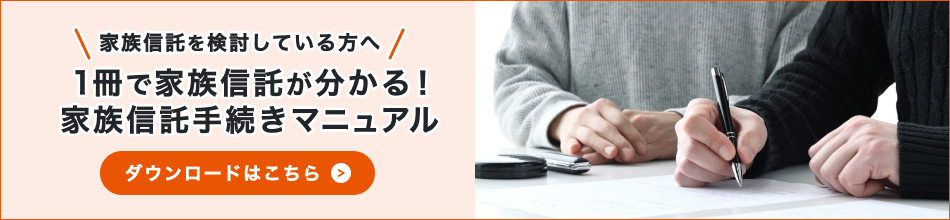- Livnessトップ
- くらし情報コラム
- 家族信託は任意後見制度とどう違う?財産を守る制度を比較
コラム<介護>
家族信託は任意後見制度とどう違う?
財産を守る制度を比較

認知症と診断されると、不動産や預貯金といった財産を本人が自由に管理・運用することができなくなります。そのような事態に備える制度として、「家族信託(民事信託)」の他にも「任意後見制度」があります。
いずれも親の財産を守るための法制度ですが、目的に応じて選択することが重要です。
前回に続き、司法書士・行政書士の山口里美先生に、制度の違いや使い分けのポイントを伺いました。
 家族信託は「財産の活用」、任意後見制度は「財産の保全」
家族信託は「財産の活用」、任意後見制度は「財産の保全」

家族信託と任意後見制度は、どちらも本人の財産管理を目的とした制度ですが、契約の効力発生のタイミングや活用の柔軟性に違いがあります。
家族信託は、将来の判断能力の低下を見据えて、本人が元気なうちに信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分の権限を託す制度です。判断能力がある段階から契約が効力を持ち、財産を「すぐに活用できる」ことが特徴です。
ただし、医療や介護に関わる契約などを本人の代わりに進める「身上監護(しんじょうかんご)」は対象外です。
一方、任意後見制度は、判断能力があるうちに備えることは家族信託と似ていますが、本人の判断能力が低下した時点で契約の効力が発生します。そのため「いざというときの保険」のような位置づけで、身上監護も可能です。
また、任意後見制度では家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、本人の財産保護を目的として、必要最小限の財産管理・処分しか行えないとされています。
その他、以下のような違いがあります。

家族信託と任意後見制度は、どちらか片方の制度が優れているということではありません。それぞれに異なる対応範囲があるので、「財産をすぐに活用したい」「取りあえずの安心を得たい」など、目的に応じて活用しましょう。
 制度を併用するという選択肢も
制度を併用するという選択肢も

2つの制度を併用することも可能です。たとえば、不動産の活用や売却は、すぐに効力が発生する家族信託で備えておき、医療・介護などに関する契約行為は任意後見制度でカバーするといった活用法もあります。
制度を活用するには、主に以下のような費用が発生します。具体的な金額は信託財産や依頼する専門家により異なるため、事前に確認しましょう。
家族信託
- ・契約書の作成費用、公正証書作成手数料
- ・不動産の信託登記に伴う登録免許税・司法書士報酬
- ・制度設計・契約書作成を専門家に依頼する際の報酬
- ・信託口口座の開設費
任意後見制度
- ・契約書の作成費用、公正証書作成手数料
- ・後見監督人の選任後は、月額15,000円前後の報酬が発生(裁判所の判断による)
契約書に不備があると、契約が無効となるリスクもあるため、専門家に依頼することをおすすめします。
まとめ

専門家に相談しながら最適な備えを
家族構成や財産状況などにより、将来への備え方は異なります。大切なのは家族の目的に沿った制度活用をすることです。認知症対策が不要な場合でも、相続時の財産配分について「遺言」を活用することで安心につながります。
親の思いを大切にしつつ、子ども世代の負担を軽減するには、実績のある専門家と早い段階から相談して準備を進めることが大切です。
家族信託について、詳しくは下記のコラムもご一読ください。
リブネスでできること。
「不動産売買」「相続」「資産運用」「賃貸管理」まで、大和ハウスグループのネットワークを生かし、お客さまのお住まいに関するお悩みの解決をお手伝いいたします。
教えてくれたのは…
山口里美(やまぐちさとみ) 先生
1993年司法書士資格を取得、旅行業から法律業へ転身。1997年に事務所を開設。司法書士法人・行政書士法人の経営に取り組みながら、株式会社グランサクシードの代表取締役を務める。
講演活動は年間70回以上(2024年実績)。相続などのテーマを中心に著書は15冊。
※掲載の情報は2025年8月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。
くらし情報コラムに関するアンケート
不動産に関する読んでみたいコラムのテーマなどございましたら、こちらのフォームからご送信ください。今後のコラム作成の参考とさせていただきます。
本アンケートへ頂いた内容へのご返信は行っておりません。
不動産に関するご相談、お問い合わせなどはこちらよりご連絡お願いいたします。
写真:Getty Images

![Livness [リブネス]](/stock/img/common/logo-livness.svg)