- Livnessトップ
- くらし情報コラム
- 不動産収益を活用した税務対策とは?法人化から注意点まで
コラム<投資/資産形成>
不動産収益を活用した税務対策とは?
法人化から注意点まで

不動産投資は、収益を上げながら所得税や住民税の軽減まで可能な投資方法です。今回は収益物件を活用した税務対策について解説します。
 不動産投資における3つの税務対策とは?
不動産投資における3つの税務対策とは?
会社員でも個人事業主でも、所得がある限り税金は発生します。所得が多くなるほど、税率は高くなり、納税額も大きくなります。ここでは、税務対策の一つにもなり得る「不動産投資」についてご説明します。①所得税と住民税、②贈与税、③相続税の順に見ていきましょう。
【POINT!】
日本では「申告納税制度」が税制の柱となっており、納税者自身が申告し、税金を納めます。そのため、申告者自身に正しい税の知識がなければ損をしてしまう場合があります。収入が増えても支払う税金ばかりが多くなり、手取りが減る……そのようなケースを避けるため、税金制度に対する知識を身につけ、賢く税務対策を行いましょう。
もし、あなたが不動産投資で手元にお金を残し、財産を築きたいと考えるのであれば、セミナーなどにも参加して自分自身で情報収集し、勉強するのも一つの方法です。また、不動産に関して頼れる相談相手を探すことも大切です。
 税務対策①所得税と住民税の税務対策とその仕組み
税務対策①所得税と住民税の税務対策とその仕組み
所得税と住民税における税務対策の基本は、課税対象となる「所得」の額を減らしていくことです。不動産投資とどう関わるのか、まずは所得税と住民税の基礎知識から見ていきましょう。
所得税と住民税とは
「所得税」は、1年間の所得に税率をかけて算出されます。なお、所得は「収入」と異なり、下記の式で計算します。
収入(年間の所得全体)- 必要経費 = 所得
収入は、会社員なら給料の全額、不動産オーナーなら家賃収入が該当します。さらに、ここから所得税の額を下記の式で計算します。
( 所得 - 所得控除 )× 税率 = 所得税
所得から適用されるすべての所得控除分を差し引いたものに税率をかけ、所得税を算出します。
「所得控除」には、「扶養控除」や「医療費控除」など、さまざまな種類があります。詳しくは国税庁の「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」をご覧ください。税率については、所得が高いほど税率が上がる「累進税率」となっています。
次に「住民税」についてです。住民税は地方自治体に納める税金であり、「都道府県民税」と「市町村民税」の合算です。所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず定額が課税される「均等割」があります。厳密に言うと税率は地方自治体によって異なるのですが、所得割の税率は10%、均等割の部分は5,000円程度と考えていただければ問題ありません。
所得税と住民税の税務対策の仕組み
所得税も住民税も、所得に税率をかけて算出します。所得が少ないほど支払う税金も少なくなります。
所得を減らすには、「収入を減らす」あるいは「必要経費を増やす」のいずれかが必要です。とはいえ、収入減は避けるべきですから、カギとなるのは必要経費でしょう。むやみに経費を増やすのではなく、経費にできるものは漏れることなく「必要経費」として計上することが賢い税務対策であると言えます。
なお、必要経費が収入よりも大きかった場合、所得はマイナスとなります。いわゆる「赤字」の状態ですが、この場合には給与所得や雑所得などから徴収されている税の還付を受けることができます。
■不動産投資で税務対策をするには確定申告が必須
収益物件を取得し、給与所得以外に不動産所得などで年間20万円以上の所得を得た場合には、「確定申告」をする義務があります。確定申告をしない場合には「脱税」にもなり得るため、注意が必要です。所得税の還付を受けるためにも、確定申告をしましょう。
■青色申告と白色申告
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。青色申告は白色申告よりも必要書類が多く手続きが複雑ですが、税務対策の効果が大きいと言える制度です。
青色申告と白色申告の主な制度の比較表
| 青色申告 | 白色申告 | |
| 特別控除の制度 | 10万円特別控除。条件を満たせば55万円特別控除または65万円特別控除 | 制度なし |
| 損失の繰越控除制度 | 赤字が出た翌年から3年はその損失を繰り越せる制度 | 制度なし |
| 生計一親族に支払う給与 | 青色事業専従者給与制度 | 事業専従者控除制度(事業的規模のみ) |
| 減価償却制度の各種特例 | 適用できる | 制度なし |
| 特別控除の制度 | |
|---|---|
| 青色申告 | 白色申告 |
| 10万円特別控除。条件を満たせば55万円特別控除または65万円特別控除 | 制度なし |
| 損失の繰越控除制度 | |
| 青色申告 | 白色申告 |
| 赤字が出た翌年から3年はその損失を繰り越せる制度 | 制度なし |
| 生計一親族に支払う給与 | |
| 青色申告 | 白色申告 |
| 青色事業専従者給与制度 | 事業専従者控除制度(事業的規模のみ) |
| 減価償却制度の各種特例 | |
| 青色申告 | 白色申告 |
| 適用できる | 制度なし |
■確定申告の税務対策のポイント「経費」
不動産投資の際の出費には、経費にできるものとできないものがあります。先ほどもお伝えしたように、「経費となる出費を漏れることなく計上すること」がカギです。次の表を参考にし、経費となるものを確認しましょう。また、確定申告する際には領収書などの「経費証拠書類」が必要です。きちんと保管するようにしてください。
【経費になるもの】
不動産管理費
修繕費
修繕積立金
管理会社への委託料
ローンの利息
必要経費になる税金
①事業物件にかかる不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税など
②事業にかかる個人事業税、法人事業税、自動車税、印紙税、利子税など)
減価償却費
専従者給与
損害保険料
仲介手数料
広告料
旅費交通費(物件の下見、打ち合せなど移動時)
新聞図書費(リサーチするための本や新聞など)
消耗品費(PC、携帯などで事業で使用する部分)
交際費(借主や業者など)
通信費(事業で使用する部分)
コンサルティング費用(税理士、コンサル会社などに依頼した場合)
【経費にならないもの】
ローンの元本返済部分
必要経費にならない税金(所得税、住民税、法人税、法人住民税、延滞税、加算税など)
社会保険料や生命保険料など
生活費など賃貸事業に関係のないもの
【POINT!】
個人の不動産賃貸業の場合、税務署による「経費として適切かどうか」の判断が厳しい傾向があります。日本においては「不労所得」の経費が認められにくく、不動産所得も不労所得のように考えられてしまうケースがあるからです。しかし、法人の場合は「必要経費とされるものの範囲」が広くなります。
経費は、不動産投資の収益に大きな影響を与える要素です。しかし、必要経費として認められるか否かの判断は複雑であり、高度な専門知識を要します。不動産に詳しい税理士に相談するなど、プロの力を借りることも重要です。
 税務対策②贈与税の税務対策とその仕組み
税務対策②贈与税の税務対策とその仕組み

贈与税についても、不動産を活用しての税務対策が可能です。ポイントはさまざまな非課税制度をきちんと把握・活用することと言えます。
贈与税とは
「贈与税」とは、贈与した財産にかかる税金のことです。財産には土地や建物などの不動産も含まれ、贈与を受けた人に支払う義務が発生します。
(不動産の評価額 ― 基礎控除110万円)× 税率(※価格と条件による)= 贈与税額
なお、一般的な贈与税には「暦年課税制度」が採用されており、その年の1月1日から12月31日に贈与を受けた財産の合計から算出します。
※暦年課税で計算されないケースもあります。後ほどご紹介します。
税率については国税庁の「贈与税の計算と税率(暦年課税)」をご確認ください。
注意点としては、贈与税の税率が相続税に比べて高めに設定されていることです。納税者にとって大きな負担となります。その上、不動産贈与に関しては「所有権移転登記」による登録免許税や不動産取得税も発生します。このように重なる税負担を少しでも減らすため、不動産贈与が発生する可能性があるとわかった時点で対策を講じる必要があります。
■贈与税の税務対策の仕組み
贈与ではその時点の時価で不動産を移転できるため、将来価値が上がる見込みのある収益物件をあらかじめ贈与しておくことができれば有効な税務対策となります。
なお、贈与においては「相続時精算課税制度」もあります。贈与される額が2,500万円以下の場合、贈与税を納めずに贈与を受けることができる制度です。ただし、贈与者の死亡時、相続税の対象として「贈与時の価額」と「相続財産の価額」を合計し、相続税額を計算します。一度この制度を利用した同一人物同士間では、暦年課税制度に戻ることができないため、慎重に検討する必要があります。詳しくは国税庁「相続時精算課税の選択」をご覧ください。条件を確認し、有利である場合には利用してもよいでしょう。
 税務対策③相続税の税務対策とその仕組み
税務対策③相続税の税務対策とその仕組み

収益物件を活用すれば、家賃収入などを得ながら相続税の負担を軽減できます。ここでは相続税の税務対策とその仕組みについてご説明します。
相続税とは
収益物件を所有している方が亡くなり、その不動産を相続する場合には「相続税」が発生します。現預金や株式など他の相続財産も含めて、下記の計算式となります。
相続財産の合計額 - 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) = 課税される額
基礎控除が大きいものの、千万円単位、億万円単位で相続税が課税されるケースもあるため、早い段階で税務対策を考えたほうがよいでしょう。また、売買や贈与と同様、「相続登記」による登録免許税がかかります。なお、相続の場合、不動産取得税は非課税です。
相続税の税務対策の仕組み
相続税を減らすためには、「財産を減らす」あるいは「財産評価を下げる」ことが必要です。特に土地は「一物五価」といわれ、1つの土地に対して5つの価格体系(①路線価、②実勢価格、③公示地価、④基準値標準価格、⑤固定資産税評価額)が存在します。この価格差を利用することで、効果的な税務対策ができるのです。
土地の価格は「①路線価」で計算されます。路線価とは、その道路に面している標準的な土地の価格です。2本の道路に面している土地であれば、高いほうの路線価だけを適用するのではなく、低いほうの路線価の影響も含めて計算します。
土地の評価額は「路線価×土地の面積」で計算しますが、土地の形状や利用状況によっては低く評価されることもあります。道路と面していない(無道路地)、土地の形がいびつである(不整形地)、斜面が含まれる(がけ地)などが該当し、評価が下がり相続税も安くなります。
また、「小規模宅地等の特例」など、非常に有利な減税制度も存在するため、「どんな特例があり、適用可能なものはどれか」などの確認が重要です。複雑な法律に関わるため、プロの力を頼るのも一つの方法です。
相続対策についてはくらし情報コラム「“相続”が“争族”に!?早めの相続対策が吉!不動産相続の基本とその方法」をご覧ください。
 事業とする場合、法人化におけるメリットとデメリットは?
事業とする場合、法人化におけるメリットとデメリットは?
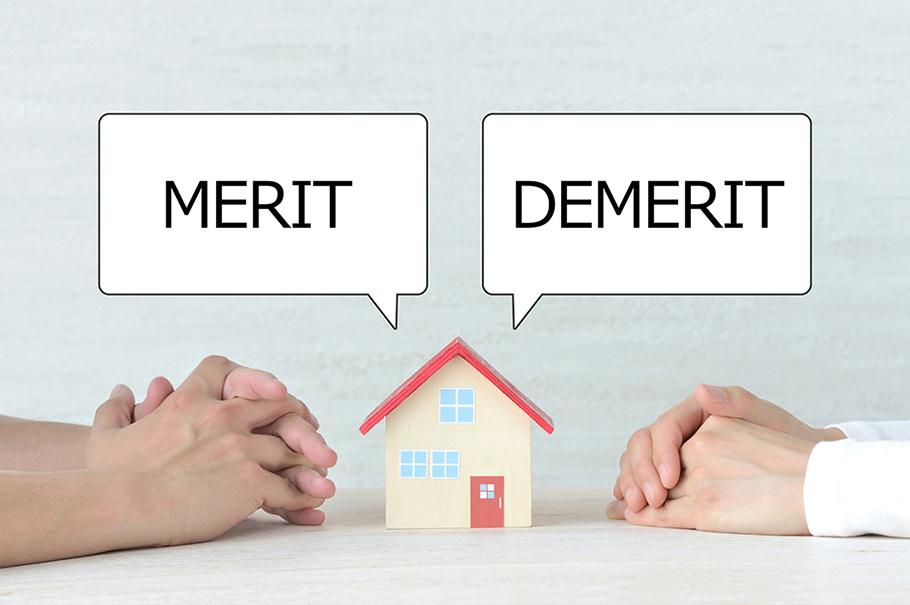
不動産経営の税務対策で切っても切り離せないのが「法人化」です。2006年(平成18年)には会社法が改正され、資本金1円でも株式会社を設立できるようになりました。誰でも簡単に法人を設立できますが、メリット・デメリットを把握することが大切です。
法人化におけるメリット
■1. 必要経費の範囲が個人事業の場合より広い
先ほども触れたように、個人の不動産投資に認められる必要経費の範囲は非常に限られたものとなっています。しかし、法人の場合はその範囲が個人より広く、役員報酬や生命保険料なども経費(法人の場合は「損金」)として計上できるのです。
■2. 役員報酬を必要経費にできる
法人であれば「役員報酬」が経費となります。自分や家族を役員とし、その報酬を経費計上することができるのです。なお、報酬を受け取る側としては「給与所得」となり、所得控除が適用されます。
■3. 法人の最高税率のほうが低い
個人の所得税の最高税率は、4,000万円を超えた場合の45%です。一方、資本金1億円以下の中小法人の場合、最高税率は800万円を超えても23.2%になります。つまり、所得が高くなるほど、法人化のメリットが大きいのです。なお、利益に対する税金には所得税・法人税のほか住民税、事業税などもありますので、税負担の比較は総合的に検討する必要があります。
■4. 退職金を積み立てながら税務対策ができる
「小規模企業共済」は国による事業主向けの退職金制度です。加入できるのは従業員が20名以下の個人事業主か会社役員のみとなりますが、毎月の掛け金が全額所得控除されるために効果的な税務対策が可能です。
支払う側にとっては将来のための積み立て金となり、事業をやめた際、あるいは満65歳になった際に退職金として受け取ることができます。また、掛け金の範囲内で貸し付けを受けることも可能で、資金不足に対するリスクヘッジにもなります。
■5. 出張で支払われる旅費日当が経費として計上できる
個人の場合は移動費や宿泊代などの実費のみが必要経費となりますが、法人の場合は旅費日当も経費となります(ただし、社内に「旅費規程」がある場合に限られます)。
■6. 物件売却時に売却損が出ても不動産所得と相殺できる
物件を売却し「売却損」が出た場合、法人であれば損金として計上し、賃貸収入と相殺することができます。個人事業主は分離課税と言って、総合課税の不動産所得とは別計算となるため、この相殺ができません。
■7. 自宅を社宅にして、賃料の一部を会社の必要経費にできる
法人の場合、居住専用の自宅の家賃も、一定の算式で計算した社宅料を役員から受け取ることで、家賃を損金として計上することができます。これを「借り上げ住宅」と言います。
【POINT!】
効果的な税務対策のため、不動産所得が多くなってきたらぜひ法人化を検討しましょう。
とはいえ、法人化にはメリットだけでなくデメリットもあります。また、法人化するタイミングも個人の状況によって異なるため、ご自身だけで判断するのは難しいものです。ご自身で勉強しつつ、不動産経営の専門知識を持つ税理士など、信頼できる相談相手を探してみてください。
法人化におけるデメリット
■1. 損金不算入がある
法人が行った賃貸業務やそれに付随する経済活動は、すべて法人が行ったものとして「損金」に影響を及ぼします。費用は「会計上の経費」であり、損金は「法人税法上、経費として扱えるもの」ですが、双方は別のものであると理解しましょう。法人税を計算する際には、必要経費として収入から差し引ける部分(損金算入)と差し引けない部分(損金不算入)があり、「費用を増やす」のではなく「損金を増やす」ことが重要なのです。
■2. 会社の維持に費用と手間がかかる
法人の場合、「法人住民税」が課税されます。法人住民税には「均等割」があり、これについては所得がない場合にも都道府県と市区町村のそれぞれに課税されます。税率は原則一律ですが、地方自治体により一定の範囲内で変えることが可能です。
また、その地域独自の条例で税制上優遇措置を講じている場合もあります。情報収集を怠ると、本来であれば受けられる優遇措置を逃してしまうことになるため、注意が必要です。
加えて、行政手続きが多いこともデメリットの一つです。法人化するためには、定款の作成、公証役場での定款の認証、法務局への登記申請など、手続きに手間がかかります。また、法人に関連する税金も多く、それぞれの手続きが必要です。司法書士や行政書士などに依頼することも可能ですが、専門家に対応してもらう限り費用が発生します。
■3. 確定申告が個人より手間がかかる
個人事業主の場合、確定申告での所得税の計算は比較的シンプルで、確定申告を行うことで住民税や事業税は役所の方で計算します。しかし、法人の場合にはこれと異なります。法人税、法人住民税、法人事業税など、すべてご自身で計算し、税務署や都道府県、市区町村にそれぞれ提出しなければなりません。
 税務対策の失敗例
税務対策の失敗例

次に、税務対策の失敗例について具体的に見ていきましょう。
相続税対策で不動産を購入したが利益を出せなかった
現金は金額そのままが評価額となり、相続税が課されます。一方、不動産であれば資産評価が下がるため、相続前に現金を不動産に換えておくことは有効な税務対策だと言えます。
そのため、中古物件を購入してみるのも有効な手段の一つと言えます。なぜなら、新築物件を購入した場合、中古になった瞬間に投資価格より大幅に値段が下がってしまいます。不動産を資産として保有することで、相続税の削減には成功しても、投資では投資価格に見合う利益を出せない危険性があるため注意が必要です。
土地活用して、投資用不動産を建てたが、需要がない地域だった
遊休地などの土地の場合、そのまま相続すると多額の相続税がかかる可能性があるため、その土地に投資用の不動産を建築し「貸家建付地」とするのも一つの方法です。これにより、評価額が大幅に下がります。建物自体も建築価格の6割ほどで評価される場合が多く、借家権割合として30%が控除されます。
また不動産賃貸経営では、たとえ赤字が出たとしても、他の黒字の所得から一定の順序に従って差し引くことができるため(損益通算)、有効な所得税対策にもなり得ます。
【POINT!】
相続税対策に限らず、過疎化が進む地域での不動産投資は、リスクが高いと考えましょう。特に「先祖代々の土地を守りたい」などの気持ちが強い地主さんは、需要がない地域に不動産を買い、相続税の削減はできても不動産投資で大きな損失を出してしまう傾向があります。不動産投資を行う前にまずリスクを学び、「このエリアにはどんな不動産の需要があるか」などについてもリサーチしてみてください。
不動産所得が多くなり所得税率が高くなった
日本の所得税の税率は、「超過累進税率」により決定されます。超過累進税率とは、課税所得が一定額以上になった場合、その「超過部分」に対する税率が高くなる仕組みです。当然、不動産所得が高くなれば所得税率も高くなり、税金の負担は大きくなります。
まとめ
今回は不動産投資を活用した税務対策について紹介しました。具体的な取り組みを行うためには、個人の状況に応じたプランを立てていく必要があります。不動産経営の税務対策について詳しく知りたい方は、専門家をお取次ぎさせていただきますので、リブネスまでお気軽にご相談ください。大和ハウスグループでは専門家とともに、あなたをサポートいたします。
※掲載の情報は2021年8月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。
くらし情報コラムに関するアンケート
不動産に関する読んでみたいコラムのテーマなどございましたら、こちらのフォームからご送信ください。今後のコラム作成の参考とさせていただきます。
本アンケートへ頂いた内容へのご返信は行っておりません。
不動産に関するご相談、お問い合わせなどはこちらよりご連絡お願いいたします。
写真:Getty Images

![Livness [リブネス]](/stock/img/common/logo-livness.svg)








