



「建築にいのちを吹き込む」
建築エンジニアとして、希代の建築家たちとのプロジェクトを次々と具現化する者がいる。
建築に“いのち”を宿らせる、その技術と情熱に迫る。
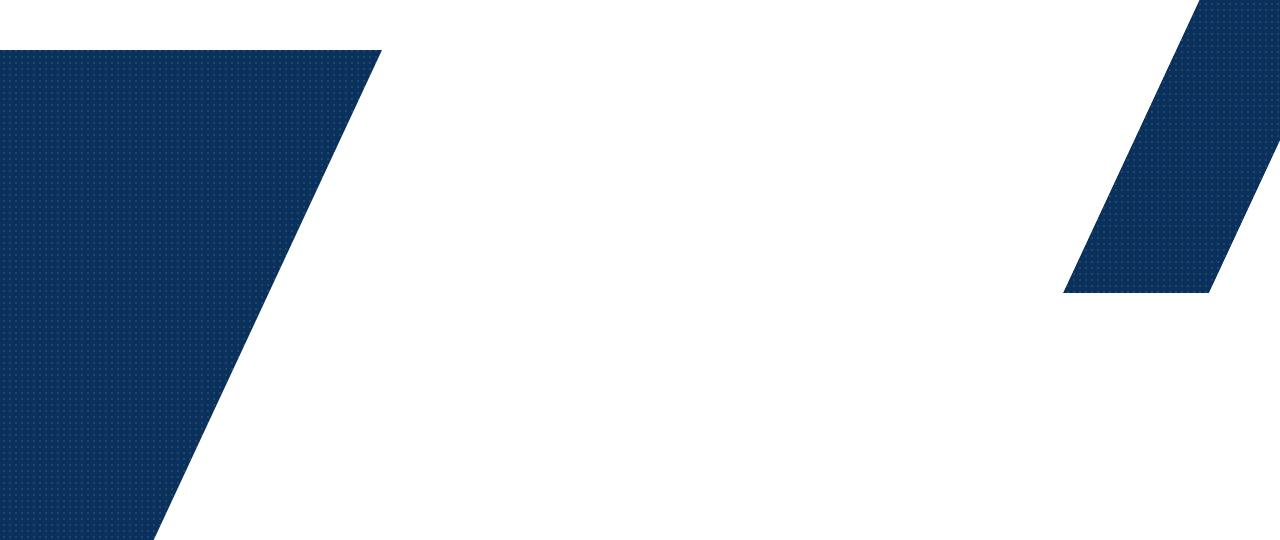


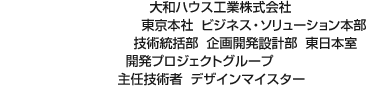

![]()
![]()
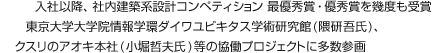



生き物のような有機的建築
大阪・関西万博の一角に、ふわりと漂うクラゲのようなパビリオンがある。その名は「いのちの遊び場 クラゲ館」。白い膜屋根の下には「創造の木」がそびえ立ち、鉄骨と木材がからみあいながら枝を広げ、木組みは膜の外へ触手のように伸びていく。
クラゲ館のプロデューサーは、音楽家・数学研究者・教育者の顔を持つ中島さち子氏。基本設計は、気鋭の建築家・小堀哲夫氏。そして建築工事の企画から施工までの全体監修を大和ハウス工業が担い、グループ会社のフジタも設計・施工に参加した。
大和ハウス工業の大野にとって、すべての始まりは、小堀氏からの一本の電話だった。過去にも仕事を共にした建築家は「万博で、また一緒にやりませんか」と大野を誘った。
大和ハウスグループの協賛が決まり、大野は中島氏に尋ねた。「どんなイメージのパビリオンですか?」。返ってきたのは予想外の答え。「もうね、グワッと!グワッと感!」。そして小堀氏から最初に渡されたのは、生き物のような手描きのスケッチだった。
天才的なプロデューサーと非凡な建築家から投げかけられた“抽象的な思考”と“感覚的なデザイン”。大野は頭を抱えるどころか、逆に胸が高鳴った。「課題があれば、フィジビリティ(実現可能性)を考え、ソリューションを見つける。それが建築エンジニアの仕事ですから」。
大野は建築エンジニアとして企画から設計、施工まで、多くの人と協力し、プロジェクトを動かしていく。かつて参加した「東京大学大学院情報学環ダイワユビキタス学術研究館」でも、その力を発揮した。
建築家・隈研吾氏が設計したのは、緩やかにうねるウロコ状の外観だった。当時はBIM※草創期。いち早くBIMを導入していた大和ハウス工業でも、生物的な意匠をBIMに落とし込み、施工するのは難しく、現場は苦戦。プロジェクトに後から加わった大野は、課題解決の糸口を次々と提案し、建築家の“思想”を“技術”によって現実の空間へ変換した。
クラゲ館でも、屋根の有機的なゆらぎを表現するため、上下3層のレイヤーを考案。最上層の鉄骨は、膜屋根を支えるために整然と組む。2層目の鉄骨と最下層の木材は、ジオメトリ(幾何学)デザインの専門家が粘菌アルゴリズムを用いて設計。各層をずらして配置することで、ゆらぎを生み、より有機的な見え方へと変換した。
「自由にできるところ、できないところを見極め、落とし所を見つけていく」。そこにエンジニアとしての役割がある、と考えている。
※ Building Information Modelingの略称。デジタルモデリングを使用して初期設計から建設、保守、廃棄まで、建築資産のライフサイクル全体にわたる情報管理の仕組み。

クラゲは皆の中にある創造性やいのちの象徴

大野と共にクラゲ館の建築に奔走した仲間

ウロコ状の壁がうねる東京大学の研究館



まちのストーリーを共有する
課題を見極め、ゴールへ導く大野の姿勢は、まちを再生するプロジェクトでも貫かれていた。
大和ハウス工業は、過去に開発した郊外型住宅団地を、地域の住まい手と共に再耕・再生する「リブネスタウンプロジェクト」を進めている。
始まりは横浜市の「上郷ネオポリス」。住民との対話を数年にわたり重ねる中、「みんなが気軽に立ち寄れる“お茶場”がほしい」という声が上がり、コミュニティ施設を整備することになった。
その企画・設計者として大野に声がかかった。プロジェクト推進部門の部長は、熱を帯びた口調で語りかけた。「40、50年前につくられた日本のニュータウンは、今やオールドタウンとなり、静かに衰退している。でも、そこに住んでいるのは、日本の高度経済成長を支えた人たちだ。彼らのまちやセカンドライフがこれでいいのか?君はどう思う?」。その問いが、大野の心に火をつけた。
ニュータウンの衰退は、日本の大きな問題だ。だが、高齢先進国の日本で解決策が見つかれば、きっと世界の道しるべになる。まちをつくった大和ハウス工業が誰よりも先に取り組むべきだし、取り組む価値がある。
大野は、コミュニティ施設の予定地に向かった。まちの中心にある空き地に立ち、直感した。「つくるのは東屋(あずまや)だ」。東屋とは屋根と柱だけの小さな建屋のこと。もちろん壁はつくるが、建物に表裏がなく、四方八方から人が集まり散っていく場所にしよう。名前には「テラス」を付けませんか、と提案した。
計画途中で、買い物難民問題を解消するコンビニエンスストアの併設が決定。他にも要望が次々と出る。だが、大勢の要望をパッチワークのように足していくと、どんどん肥大化し、何をしたかったのかが見えなくなる。そんな時、大野は「私たちは、ここを目指しているんですよね?」と大きなストーリーを見つけ、共有する。目的地が同じなら、道に迷うことはない。
建物には「可変性」と「拡張性」を持たせた。イートインスペースは、間仕切りの少ない設計や可動什器で、イベントなど多目的に使える場に。隣の自治会館や前のバス停などの周囲とつながるように動線や開口部を設け、建物の領域を外へシームレスに拡張した。みんなが“共感”できる場のストーリーを“技術”で形にしてみせた。

建物の内と外がシームレスにつながる

まちでは多世代の交流が息づいている



粘土の塊にルールを見いだす
上郷ネオポリスと並行して、大野はもう一つの大規模プロジェクトに関わっていた。大和ハウスグループ みらい価値共創センター「コトクリエ」。人や組織をつなぎ、未来の人財を育てる拠点だ。
プロジェクトでは、これまでにない発想を求めて外部建築家を招くことになり、大野に候補者選びが託された。頭に浮かんだのは、かねてより空間づくりに感銘を受けていた小堀氏だった。
小堀氏は基本計画・デザイン監修として参画。グループ会社社員とのワークショップから生まれた「エンドレスにつながる」「生命体のように進化・成長し続ける」というキーワードをもとに、建築の構想を膨らませていった。
ある日、突然、小堀氏が粘土でつくった大きな模型を持ってきた。何層にも重なった、いびつな塊。差し出された瞬間、その場が静まり返った。……粘土のようには、建築はつくれない。動揺、不安、沈黙。その中で大野だけが、ざわめく感覚を覚えていた。「これ、できるかもしれない」。
頭の中で即座に形を解析し、「線」の集合として読み取った。線を少しずつずらして重ねれば、なめらかな曲線を描ける。どんなに有機的な形でもルールを見出せば、建築として成立させられる。
粘土の塊には、DNAの二重らせんやメビウスの輪、かつてこの地にあった平城京の記憶が重ねられていた。塊はそれから3年後、土地が隆起したような有機的な建築物となって竣工を迎えた。
プロジェクトでは、3Dモデルで仕上がりを確認できるBIMを、企画から設計・生産・施工・施設管理まで一貫して活用。大和ハウスグループにとっても大きな財産となった。
こうして、いつのまにかビッグプロジェクトに名を連ねるようになった大野だが、本人には「次はこんな仕事がしたい」という欲がない。「ただ愚直に、好きなモノづくりを丁寧にやってきただけなんです」。
大学卒業後に入社したゼネコンでは、20代で現場監督を任され、年上ばかりの職場でリーダーとしての在り方を意識してきた。
その後、大和ハウス工業へ。30代後半、東京大学のプロジェクトに関わった頃からだろうか。「自分はリーダーのタイプじゃない」と思うように。これまで出会った希代の建築家は皆、「建築はこうあるべきだ」と哲学を持っていた。「私は、そのビジョンをキャッチアップし、いかに実現するか、という点に面白さを感じたのです」。
東京大学のプロジェクトでは、建築家や現場に寄り添い、課題を解決し、周囲を支えることに徹した。その頃からリーダーシップよりも「最良のフォロワーシップ」を発揮することに価値を感じるようになった。「どんな小さな物件でも、1人でやるより、チームで取り組んだ方が間違いなくいいものになる」と知ったからだ。

大地が隆起したような有機的な外観

雄大な奈良盆地を一望する丹生庵

緑やアロマに癒やされるカフェ



いい歳を重ね、愛される建物へ
2025年5月。大野は奈良のコトクリエにいた。この日は、奈良教育大学附属中学校の1年生たちが探究学習を行う日。大和ハウス工業の社員から講義を受け、「世界に一つだけのサステナブルスクール」をテーマに、グループでアイデアをまとめ、発表する。
大野の担当は「コトクリエから学ぶ共創空間」の講座。子どもたちと建物を巡りながら、空間コンセプトや設計意図、環境配慮の工夫をやさしい言葉で伝えていく。
例えば、ダイニングに隣接する中庭「風のパティオ」では、こんなふうに。「食堂って広さが限られてるよね。でも、この大きなガラス扉を開けると、中庭も部屋の一部になり、同じ機能で使えます。こうやって建物の中と外の境界線をなくして空間を広げているんです」。
子どもたちは熱心にメモを取り、グループワークでは大野から学んだことを他の講座の同級生に懸命に教える。「建築に一つも無駄がなく、照明も人の動きに合わせているのがすごい」、「日本や世界はCO2をいっぱい出しているけど、コトクリエは未来についてちゃんと考えている。そこが一番いい」と目を輝かせる。
教頭先生は「コトクリエのようなクリエイティブな空間に入ると、子どもたちの顔つきが変わるんです。設計者本人から聞く経験も、心に響く学びになっています」と喜んだ。
最後の発表会を見ながら、大野の胸はじんわりと温かくなった。「今日は私が意図した以上に、子どもたちが想像豊かに空間を使ってくれて、本当に感動しました」。
建物が“生きた場”として育ち、愛されていた。大野は建物を、一生を持つ“人格”として見る。人と同じように、建物も年を重ねるごとに味わいが増すように、時間軸を見据えた設計で“いい歳の取り方”まで考える。「建物は完成時が一番きれいかもしれないが、それはもっとも人工的な状態。コトクリエは、竣工から4年たった今の方が、ずっと美しい」。
大野は、これまでの仕事を振り返り、「私には建築家のような強い想いや自我がない」と謙遜する。しかし、形を持たないからこそ、どんな器にもなれる。建築家が投げたボールを受け止め、「この方法ならできる」「別の方法もある」と投げ返せる。
その姿は、まるで“水”のようだった。静かに流れながら、障害に逢うと激して勢力を倍加する。広く深い大洋のように、どんな声も受け止め、ときには蒸気となり、雲となり、雨となり、雪と変じ、霞と化す。大和ハウス工業の創業者が大切にした「水五訓」の教えを、大野は自然体で示していた。
これからも大野は建築エンジニアとして、周りを動かす水流となり、新たな地形を描くだろう。彼と、その背中を追う志ある者たちが大河となり、大和ハウス工業をまだ見ぬ大海へ連れていくのだ。

コトクリエ職員と連携して学習をサポート

コトクリエの空間を思い思いに活用

これからの未来の価値を創る子どもたち
※掲載の情報は2025年6月時点のものです。
-
 「建築にいのちを吹き込む」
「建築にいのちを吹き込む」
-
 「想いをつなぐリゾートホテル」
「想いをつなぐリゾートホテル」
-
 「自在に描く邸宅の新境地」
「自在に描く邸宅の新境地」
-
 「建築事業に次なる使命を」
「建築事業に次なる使命を」
-
 「アスリート、第二の人生が始まる」
「アスリート、第二の人生が始まる」
-
 「カーボンニュートラルに挑む」
「カーボンニュートラルに挑む」
-
 「お客さまと共に生きていく」
「お客さまと共に生きていく」
-
 「DXで建設業界を変えていく」
「DXで建設業界を変えていく」
-
 「日本の旅をもっと面白く」
「日本の旅をもっと面白く」
-
 「新築から『再生と循環』へ」
「新築から『再生と循環』へ」
-
 「おもてなしの心は続く」
「おもてなしの心は続く」
-
 「世界で活躍する16人のクリエイターと共に」
「世界で活躍する16人のクリエイターと共に」
-
 「再エネで故郷を次世代へ」
「再エネで故郷を次世代へ」
-
 「21世紀は風と太陽と水」
「21世紀は風と太陽と水」
-
 「設計革命の先駆者であれ」
「設計革命の先駆者であれ」
-
 「公民連携のまちをつくる」
「公民連携のまちをつくる」
-
 「国の礎を支える」
「国の礎を支える」
-
 「生涯現役で働く」
「生涯現役で働く」
-
 「復興支援に立ち上がる」
「復興支援に立ち上がる」
-
 「住宅工法の常識を変える」
「住宅工法の常識を変える」
-
 「アメリカを開拓せよ」
「アメリカを開拓せよ」
-
 「日本の工業団地を輸出する」
「日本の工業団地を輸出する」
-
 「農業を工業化する」
「農業を工業化する」

