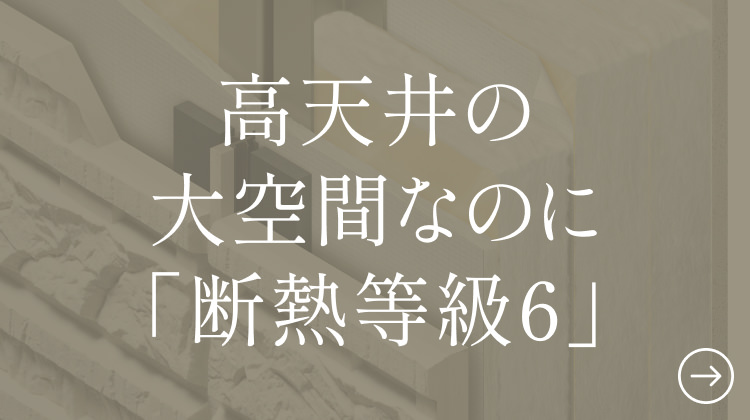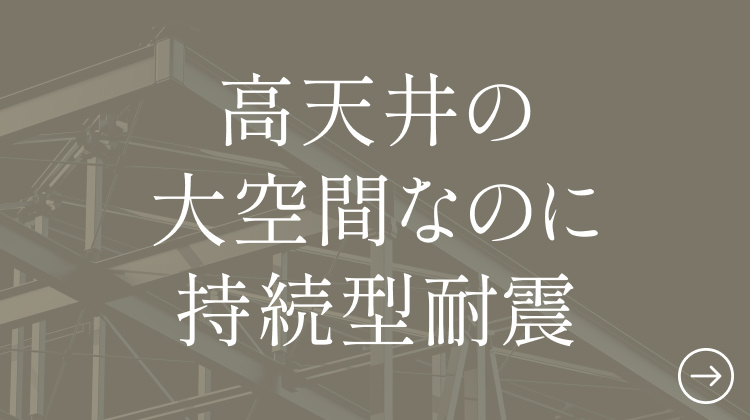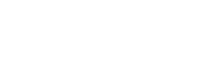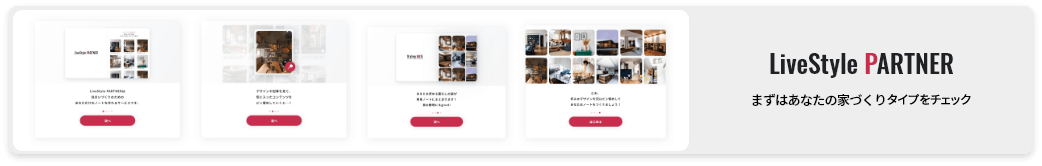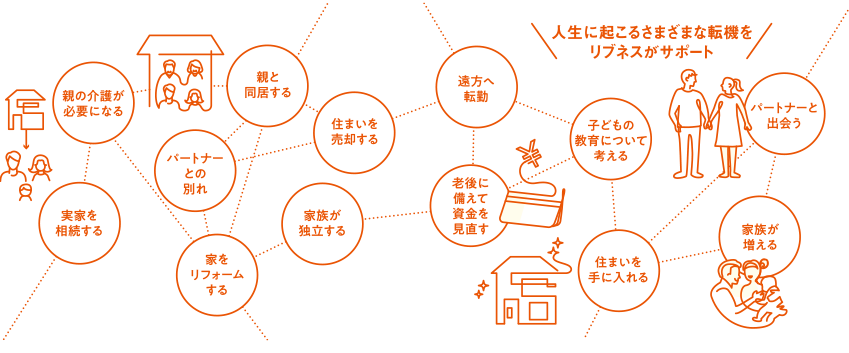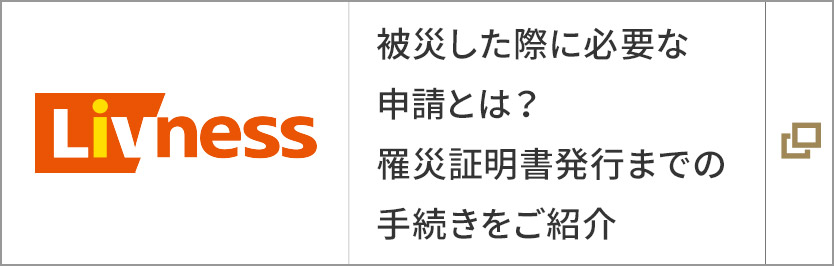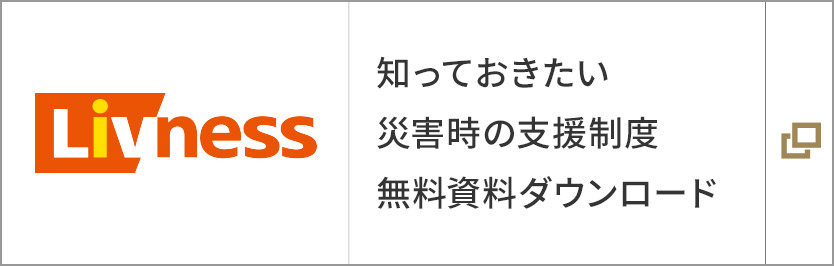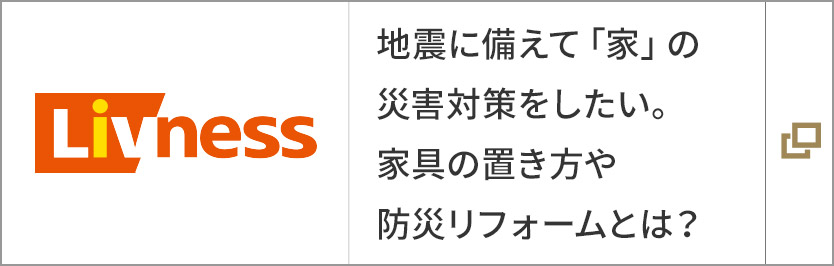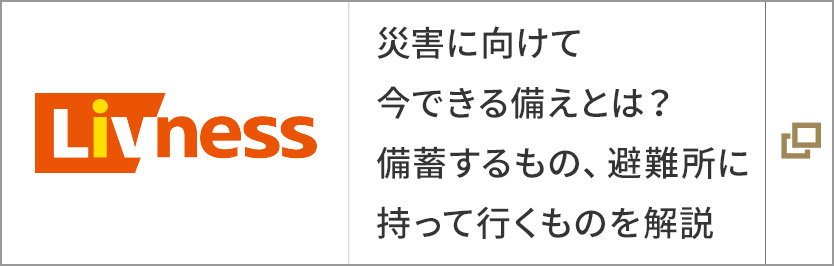地震や津波などの自然災害が発生し、住まいが損害を受けた場合
どのような支援制度を利用できるか知っていますか?
今回は、被災後の経済的負担を軽減する公的支援制度の概要をご紹介します。
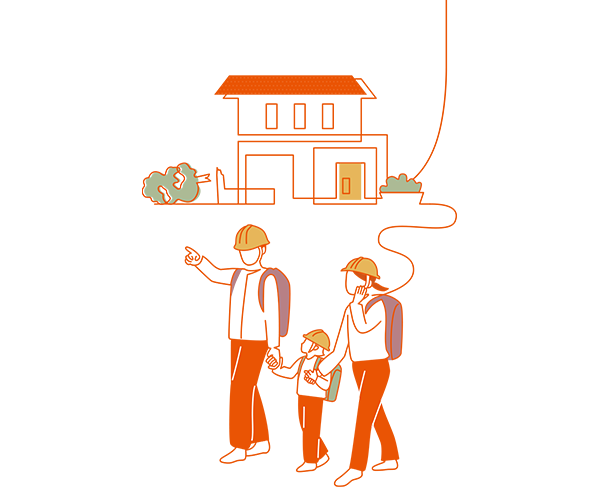
自然災害発生後は、住居の再建や生活の継続のために多くの資金が必要になります。国や自治体による公的支援制度を利用するには、被災者やその家族が申請手続きを行わなければなりません。万一の事態に備えて、制度の概要や申請時に求められる書類について知っておくことが大切です。
支援を受けるために必要なのが「罹災(りさい)証明書」。調査に基づき、住居の被害程度を「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの区分で認定します。各種支援制度への申請時や、税金の減免・猶予、融資の申請を行う際にも欠かせません。発行までには時間がかかることもあり、急を要する場合は即日発行が可能な「罹災届出証明書」を取得することをおすすめします。罹災届出証明書の提示で受けられる支援もあるため、自治体が発信する情報をよく確認しましょう。東日本大震災から14年を迎える今、災害への備えとして支援制度について理解を深めてみてはいかがでしょうか。
もし、わが家が被災したら?
公的支援制度について知る
災害時の公的支援制度について知り、自治体等への問い合わせや申請をスムーズに行うための心構えをしておきましょう。
住居が自然災害による損害を受けた場合、専門家の調査に基づき、その程度を認定し、証明するために作成される公的な書類のこと。支援金の支給、固定資産税の減免や猶予、学費減免措置など、さまざまな支援を受けるために必要な証明書です。
●申請の流れ
申請に必要な書類は次の3点です。
- 罹災証明交付申請書
- 自治体の役所かホームページからのダウンロードで入手できます。
- 身分証明書
- マイナンバーカード、運転免許証など。
- 建物の写真
- 片づけや修理をする前に、外観全体の写真、部屋全体の様子が分かる写真、損壊部分をアップにした写真を残しておきましょう。
提出物をそろえて、自治体の役所や出張所で申請します。委任状を持った第三者も代理で申請できます。
実際の被害状況を確認するため、調査員が現地調査を行います。屋根や外壁、柱などを確認する「外観調査」、建物内の損傷具合を確認する「内部調査」があります。
現状調査後に被害程度が認定されると、罹災証明書が発行されます。
国や自治体による支援金や弔慰金など、返還義務のない給付金を受け取れる支援制度があります。
被災者生活再建支援制度
10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等で、住宅が全壊・半壊した世帯のほか、補修が必要となる被災世帯を対象に支援金が給付されます。
支給額
被害の程度や住宅の再建方法に応じて、25万円~300万円
災害障害見舞金
対象となる災害により重度の障害が残った人に対して支払われる見舞金。
支給額
- ●生計維持者が障害を受けた場合・・・250万円
- ●それ以外の人の場合・・・125万円
被災者生活再建支援制度
自らで住宅の応急修理の費用を負担できない場合、屋根・台所・トイレなどの修理を自治体が業者に依頼し、支払いまでを行う制度があります。
災害弔慰金
対象となる災害において、市町村より遺族に支給される弔慰金です。
支給額
- ●生計維持者が死亡した場合・・・500万円
- ●それ以外の人の場合・・・250万円
加入している保険の種類と契約内容もこの機会にチェックを!
- 1火災保険
- 火災、落雷、風災、雪災、水災などによって建物に損害が生じた場合に、損害額が保険金として支払われます。地震が原因の火災は補償外です。
- 2地震保険
- 火災保険の補償範囲に入らない地震、噴火、津波などの自然災害による損害を補償する保険。火災保険とセットで加入します。損害の程度と保険金設定額に応じて、保険金が支払われます。
お問い合わせ
大和ハウス工業株式会社 リブネス事業推進部
フリーダイヤル 0120-413-109
大和ハウス工業株式会社 リブネス事業推進部
フリーダイヤル 0120-413-109
受付時間:10時~17時30分(土日祝定休)
2025年2月現在の情報です。