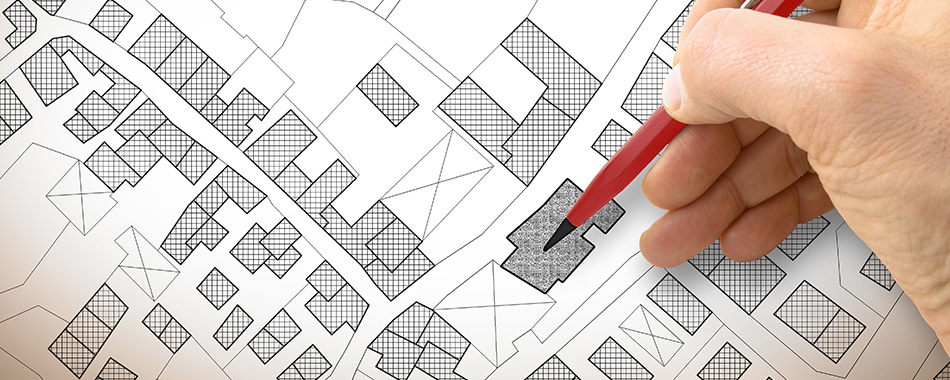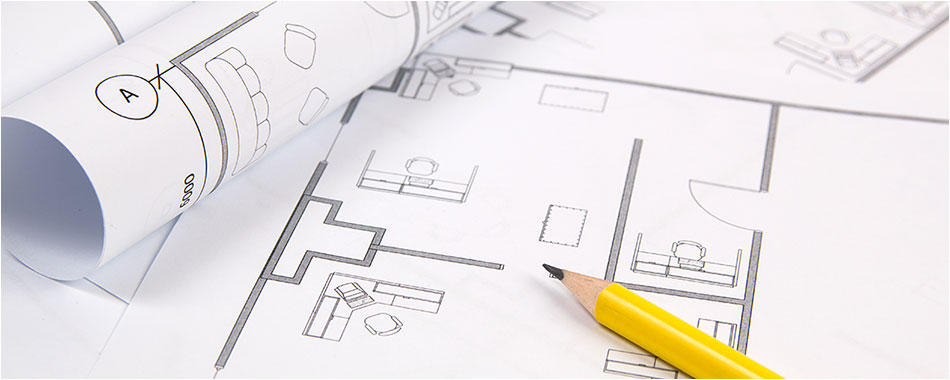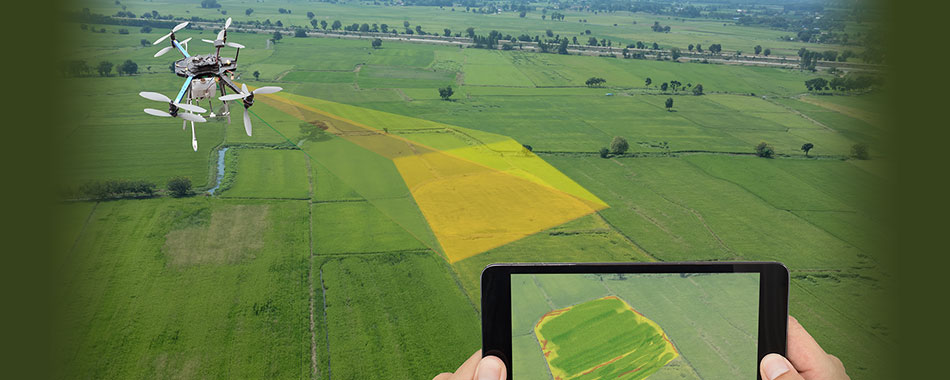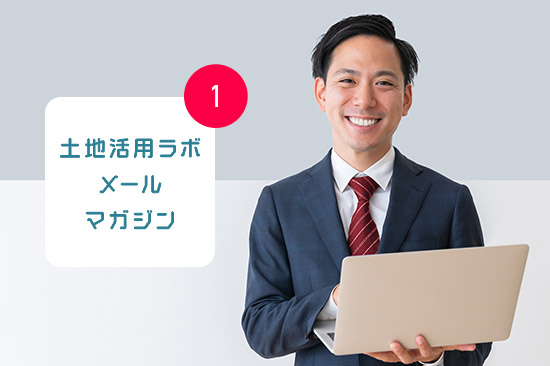コラム No.53-88
コラム No.53-88戦略的な地域活性化の取り組み(88)公民連携による国土強靭化の取り組み【50】地域資源の流動的活用による地方創生の推進
公開日:2025/08/29
2025年6月、新たな地方創生の基本構想(地方創生2.0)が閣議決定されました。地方創生2.0では、2014年からの過去10年間の地方創生(1.0)の成果と反省を踏まえ、新たに目指す姿として、「『強い』経済と『豊かな』生活環境の基盤に支えられる多様性の好循環が『新しい日本・楽しい日本』を創る」としています。一方、地方部では、遊休不動産の流動化制度等を活用して、自治体や民間事業者、金融機関、地域投資家等が連携して、地域再生の取り組みが活発化しています。
地方創生2.0が目指すもの
2014年に策定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」によって始動した地方創生構想(1.0)により、各地方公共団体が積極的に地方創生に取り組んだ結果として、企業の地方移転等による雇用創出、産官学連携の促進、移住者数の増加など一定の成果が見られます。
一方で、この10年を振り返ると、少子高齢化による人口減少傾向は続いており、総人口は約340万人減少、生産年齢人口(15~64歳人口)は約410万人減少、65歳以上の高齢者人口は約320万人増加し総人口に占める割合は28.3%となっています。また、東京圏一極集中、地方圏から東京圏への若者の流出傾向も継続しており、2024年における若者(10代及び20代)の東京圏への流入超過数は13万人を超えており、さらに、地方部から都市部への流入超過は全国的な傾向でもあります。とはいえ、国民総生産(GDP)の半分程度は地方部が占めているといわれており、地方創生は国全体の経済を支えるためにも、避けられない重要課題です。
今回策定された地方創生2.0においては、「やりっぱなしの行政、頼りっぱなしの民間、無関心の市民が三位一体になると地方創生はうまくいかない」(「第1回民主導による新たなまちづくり推進会議」における談話)とし、「従来の『縦』の連携、すなわち国・都道府県・市町村という行政機関の階層的な関係性だけではなく、地域間の『横』のつながりを再認識し、強化していくことが極めて重要」としています。つまり、地域の「産官学金労言士」等(金:金融機関、労:労働界、言:言論界、士:専門家)の公民が連携し、地域内外に埋もれている地域資源を有効活用することで、地方創生を単なる地域活性化策ではなく、日本の活力を取り戻す経済政策として位置づけることが強調されています。
(内閣官房「地方創生2.0基本構想」より)
そのような観点で地域を見渡すと、公民連携による再生・再開発が見込める不動産等の未利用資源が点在しています。以下では、地域における遊休不動産の活用に焦点を当てて、地域創生の取り組みを探ってみます。
遊休不動産の流動化による地域価値の向上
地方都市においては、空き家や空き店舗、古民家、未利用あるいは老朽化した公的不動産(PRE)など、遊休不動産が増加しており、地域課題でもあります。放置すれば、住宅地や商業地に点在することになり、地域自治や公的サービスの維持、地域の衛生面や安心安全の維持が困難となるなど地域環境の悪化が進み、ひいては地域の人口減少を引き起こし、いわゆる「都市のスポンジ化」という問題に発展しかねません。しかし一方で、見方を変えれば、雇用の創出や観光振興、子育て支援、福祉といった地域再生に活用可能な地域資源とも言えます。このような地域の遊休不動産に価値を吹き込む手法として、不動産特定共同事業(FTK)制度を活用した不動産の証券化による流動化、所有と利用・運用を分離する事例が地方都市で増えています。
例えば、ある事業者が特定した不動産を活用して新たな地域事業を起こす場合、事業者自らが資金を調達して物件を購入し事業を経営することで収益を確保するのが通常ですが、何らかの理由で資金調達能力・ノウハウが不足している場合には、開発会社が国や都道府県の許可を得てFTKとなり、地域金融機関や機関投資家、個人投資家から融資や出資を受け、事業化に必要な資金を調達、不動産の購入・建設・改修を行い、事業者に貸与します。FTKは、賃料やテナント料収益を元に投資家等へ返済・配当を行うことで償還するといったスキームです。
不動産特定共同事業制度を活用することで、地域事業開発への資金調達ハードルが低くなり、結果として遊休不動産の再生が促進され、地域創生の一躍を担うことができます。
不動産特定共同事業がもたらす地域メリット
不動産特定共同事業は、クラウドファンディングに対応するなど、様々なパターンや方式が制度化されており、廃校・古民家のリノベーションや老朽化した集合住宅の再生、保育所の新設、さらに公的不動産(PRE)を活用した地域再開発など、地域再生への活用範囲が広く、地域にも多くのメリットをもたらします。
(1)不動産開発・改修に係る資金調達難への対応が可能になる
小口で資金を募ることにより、リスクを回避したい機関投資家や個人投資家など、多様な投資家からの資金調達が可能となります。また、地域事業に共感を持つ、あるいは応援したいという投資家への意識づけにも有効な手段です。さらに、対象不動産による事業の収益性に着目した資金調達も可能となります。
(2)まちづくりの自分事化・関係人口の増加につながる
地域住民や地域に関心のある個人が投資家となり、投資家として継続的に対象不動産の運営状況を身近で確認することで、まちづくりの自分事化や関係人口増加が見込めます。また、保育所や福祉施設、宿泊施設など、投資家自身が利用者となることも想定されるため、対象不動産の稼働率の維持・向上による中長期的な安定した施設運営が期待できます。
(3)公的不動産運営に対する行政費用を抑制できる
不動産特定共同事業は、現物不動産を直接取扱うスキームであることから、事業コストが比較的小さい小規模物件でも事業対象となり得るものです。そのため、地域の様々な公的不動産に対して円滑な資金供給が可能であることから、不動産特定共同事業の活用で、行政費用を抑制することが期待できます。
日本の活力を取り戻す経済政策として、不動産特定共同事業制度は、地域に眠る不動産を「稼げる不動産」、「地域価値を高める不動産」に転換する有効な手法のひとつだといえるでしょう。