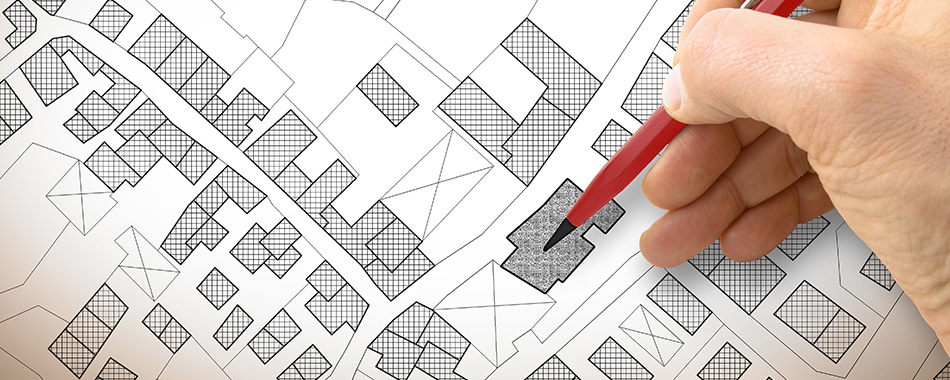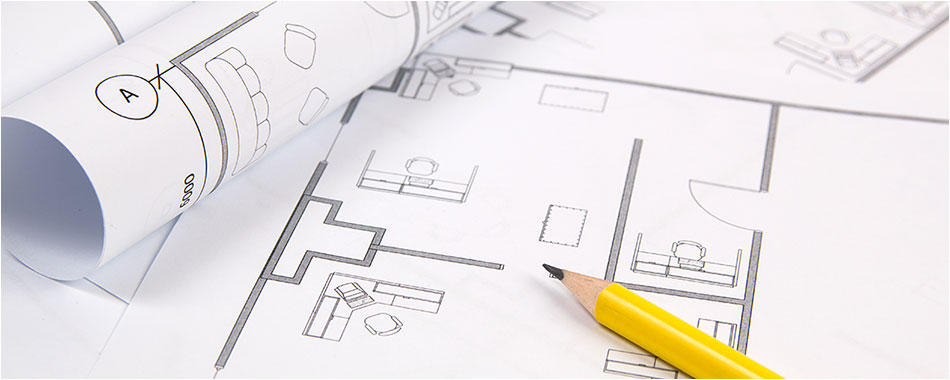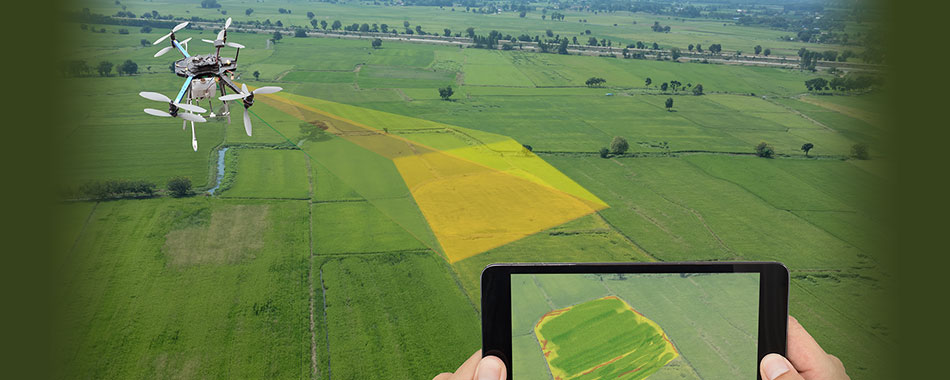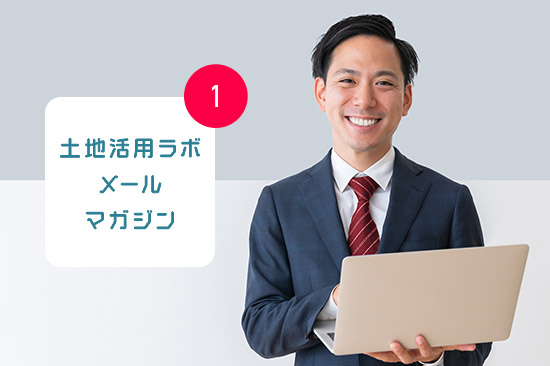コラム No.53-87
コラム No.53-87戦略的な地域活性化の取り組み(87)公民連携による国土強靭化の取り組み【49】官民連携による防災・減災のためのグリーンインフラ活用事例
公開日:2025/07/31
山地における土砂災害に対応する砂防ダム、高潮や高波等から海岸線を、あるいは河川の氾濫による内陸部への浸水に対応する護岸堤防、近年増加している内水氾濫による市街地への浸水対応など、これまで自然災害を防ぐ手法は人工構造物(グレーインフラ)による対策が主流でしたが、近年では加えて、グリーンインフラを併用し、持続可能な防災・減災基盤を整備する方向が主流となりつつあります。今回は、そのグリーンインフラの活用事例についてご紹介します。
大雨や地震による土砂災害に備える山林再生事業(六甲山系グリーンベルト整備事業)
長期にわたるグリーンインフラ整備事例として、兵庫県の「六甲山系グリーンベルト整備事業」がよく取り上げられます。
六甲山系は、中世より森林の伐採が進み、1868年に神戸港が開港したことで山麓部に人口が増加し都市化が進行するに伴って、特に明治維新後には乱伐が加速した結果、洪水や土砂災害による人的被害が大きな問題となっていました。そのため、1895年に兵庫県によって植林等による砂防事業が開始され(1938年からは国の直轄事業)、20世紀後半には森林の量的回復がほぼ達成されたとされています。
その間にも、1938年と1973年には記録的な大水害が発生、また1995年には阪神・淡路大震災が起こるなど、山麓部への自然災害による被害の懸念が消え去ったわけではありません。六甲山系には、そもそも断層帯があり、地質ももろい側面があるとされています。そのため国や県は、グリーンインフラの整備に加えて、地質の調査や砂防施設の整備、山間部への宅地開発制限など、重層的な施策を推進し、国際都市となった神戸地域を保全する取り組みが現在も続いています。
また、近隣の岡山県や広島県においても、同様な地形が連なっており、たびたび自然災害も発生していることから、六甲山系におけるグリーンインフラの取り組みが良き前例として活かされることが期待されます。
河川の氾濫を隣接する緑地帯に一時的に貯水し、地域災害を防ぐ事例(寝屋川治水緑地)
大阪府の寝屋川治水緑地(深北緑地)は、大東市深野北と寝屋川市河北にまたがる50.3haの地域に、治水機能を有した公園として、1974年から2002年にかけて建設されました。普段は運動広場や公園として住民の憩いの場となっていますが、大雨の時には河川からの洪水を計画的に一時貯留することによって、下流河川の水位低下と流量負担軽減を図るように設計されており、洪水による被害を防止する機能をもったグリーンインフラの好事例と言えます。
隣接する河川の堤の一部を意図的に通常の堤防よりも低い「越流堤」とすることで、寝屋川水系の増水時に水を緑地内へ誘導することにより、遊水地としての機能を果たします。緑地内は「Aゾーン:水辺のゾーン」「Bゾーン:ふれあいゾーン」「Cゾーン:スポーツゾーン」の3つのゾーンに区切られており、それぞれのゾーンに仕切堤により高低差を持たせることで、増水した水をAゾーン→Bゾーン→Cゾーンの順に貯留します。河川の水位が下がったところで、貯留水はポンプによってAゾーンに集められ、寝屋川排水門を開いて排水する仕組みとなっています。
図1

1982年以降、台風や梅雨前線により10回を超える河川氾濫が発生しましたが、市街地への浸水を防ぐことができており、寝屋川治水緑地の遊水地としての機能が実証されています。
寝屋川治水緑地事例は、住宅密集地における小規模河川の氾濫災害にグリーンインフラが有効な手法であることを示しています。
ゲリラ豪雨等による内水氾濫の軽減が期待できる市街地緑化(南町田グランベリーパーク)
近年、気候変動による都市部での短時間局地豪雨(いわゆるゲリラ豪雨)が多発しており、特にコンクリートやアスファルトで市中を覆われている首都圏では、毎年のように、下水道への排水能力を超えて市街地が冠水する内水氾濫を引き起こしています。その対応策として、自然界にある土の浸透能力を最大限に活用するグリーンインフラ手法が各所で採用されています。東京都町田市鶴間地域に再開発によって2019年に誕生した「南町田グランベリーパーク」は、その典型的な事例です。
南町田グランベリーパークは、「すべてが公園のようなまち」をコンセプトに、まちづくりの中に、みどりを基調としたグリーンインフラの仕組みを取り入れています。
(1)バイオスウェル(雨のみち)
この仕組みは、とてもシンプルなもので、70センチメートル程度の深さで帯状に側溝を掘り、そこに砂利を敷き詰め、敷地中に降った雨水を集めて、ゆっくりと時間をかけて土の中に浸透させる装置です。
図2

出典:町田市ホームページ
(2)レインガーデン(雨のにわ)
もう一つは、施設内の一角に小石を敷き詰めた窪み(池)と植栽帯を作ることで、施設内に降った雨水を集め、地中にゆっくりとしみ込ませる装置です。
図3

出典:町田市ホームページ
これらの装置により、大雨時にも施設が水浸しになるのを防ぎ、地中の雨水は時間をかけて近くの河川に流れ込むため、周辺地域の内水氾濫を緩和することが可能となります。南町田グランベリーパークの取り組みは、まちそのものの景観と生活空間の快適性を向上させ、地域活性化につなげるグリーンインフラ活用の好事例だと思います。
なお、この取り組みは、2021年に国土交通省の第1回グリーンインフラ大賞都市空間部門で優秀賞を受賞しています。
地球温暖化や気候変動が世界的な問題となる中、グリーンインフラは、自然界自体がもつ機能を活用し、防災・減災力を高め、都市の居住環境を向上させる新たな社会資本整備の考え方として、重要性が増しています。国も、2020年に「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」を設立し、産官学連携によるグリーンインフラの社会実装を推進しています。